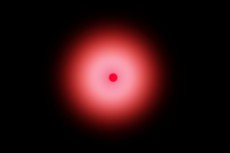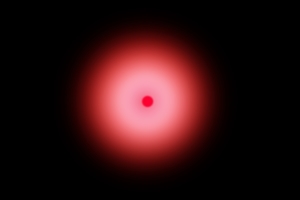見えない代わりに 前編 「視力と引き換えに彼が得てしまった能力とは」|川奈まり子の奇譚蒐集三〇
TABLO / 2019年8月18日 7時0分
大阪府在住の「怪談好きなすぅさん」こと佐々木澄夫さんは、約17年前、40歳のときに糖尿病の合併症が原因で視力を失った。
一縷の望みをかけて最後の手術を受けた日は澄夫さんの誕生日で、願掛けの意味がこめられていたのだが、残念な結果になってしまったのである。生まれつきの視覚障碍者ではなく、ほんの1年ほど前までは標準的な視力を持って、会社勤めをしていた。失ったものの大きさに呆然とするほかなく、澄夫さんは精神を病んで、退院後の3年間は実家に引き籠もっていたという。
すでに40歳。澄夫さんはまだ独身だった。闘病中に失業し、治療に費やして貯えも乏しい。さらにこうして急に真っ暗な虚空に放り出された。
絶望しか感じ得なかったのだ。
しかし、やがて彼は視力と引き換えに不思議な力を得たことに気がついた。奇しくも自分の誕生日に見える世界と別れることになったが、もしかするとそのとき、見えないものを感じる能力を備えた人として、澄夫さんは新しく生まれ直したのかもしれない。
そう、幽霊なのか妖怪なのか、それとも神と呼ばれる存在なのか定かではないが、常人には見ることが出来ない怪しい存在を感じ取る能力を、彼は視力と引き換えに得たのである。
そしてその力が、彼を再生への道へ導いた。
おすすめ記事:親黙り、子黙り「お兄ちゃんは木の間に入っていって見えなくなった」|川奈まり子の奇譚蒐集二五(上) | TABLO
手術直後からそれは始まった。
そのとき、両目の網膜に外科手術を施された後の措置として、澄夫さんはうつ伏せに寝るように指導されていた。この時点ではまだ、包帯が解かれたときには視力が戻っていることを彼は期待していたが、とりあえずは両目が塞がれて、何も見えない状態になった次第だ。麻酔が覚めるとほどなく、看護師や家族が運んでくる食事や会話によってしか今が何時かもわからないことに気がついた。
夕食が済み、自分を訪ねてくる者がいなくなると、まだ黄昏時なのか、すでに夜中なのかの見当もつかなくなった。
回復のためには早々に眠ってしまうべきなのだろうが、鎮痛剤を点滴で入れてもらっても尚、多少痛みがあり、頭が冴えて仕方がない。どうしても眠気が萌さないので、彼はこっそりとラジオを聴くことにした。昼間のうちに、両親がポータブルラジオとイヤホンを持ってきて、枕もとに置いていってくれた。コードを手繰り寄せてイヤホンを耳に挿し、手探りでラジオの電源を入れて、周波数を探る……と、どうだろう! たちまち、現在の時刻が明らかになった。
「午前1時ちょうどをお報せします」
こんななんでもないことが、今の澄夫さんには嬉しかった。彼はさっそく好きな音楽とディスクジョッキーのトークを楽しみはじめた。やがて、ラジオが午前2時ちょうどを報せた。
と、その瞬間、左の足首を何者かが両手で掴んで引っ張った。
「何? 誰?」
驚いて彼は大声で問うたが、足首が解放されただけで、返事はなかった。
「何や? 看護師さん? 違うんか? 誰や!」
やはり答えが返らない。しかし、ベッドの足もとの方に人の気配を感じた。
衣擦れの音。床の上で足を踏みかえる音。両目を閉じられてから無意識に緊張して耳をそばだてている彼は、どんな小さな音も聴きもらさなかったのだ。
そのとき、どういうわけか、ふと彼は、この棟の地下に霊安室があることを思い出した。
参考記事:阿蘇山の夜道 「夜中に寝ていると『窓の外を見ろ!』と叫ぶ何者かの声」|川奈まり子の奇譚蒐集二七 | TABLO
この病院は地域の拠点である大きな総合病院で、ましてや糖尿病の持病を抱えていたため、昔から幾度となく受診したことがあり、病棟の地理は知り尽くしていると言ってもよかった。
ここはメインとなる棟の6階にある個室で、自分は部屋の出入口に足を向けて寝かされており、そして出入り口は廊下を挟んでエレベーターと向かい合っているはずなのだ。手術前に、看護師から説明を受けていたから、それは確かだ。
……霊安室からエレベーターに乗って死者の魂がやってきたんじゃないかと想像してしまった。
しかし、まさか幽霊なんているわけがないのだから、入院患者に変な奴がいて、悪戯をしかけてきたのだろうと、すぐに考え直した。そこで「はよ自分の部屋に戻らんか! あっち行け」と、そこにいるはずの誰かに向かって叱りつけ、あとは無視してラジオに没頭した。そのうちようやく眠気が萌してきて、看護師に揺り起こされるまで目が覚めなかった。
日中は、目が見えない不自由さを除けば、何事もなく過ごした。そしてまた夜になった。睡魔の訪れを待ちながらラジオを聴いていると、やがて……。
「午前2時ちょうどをお報せします」
昨夜のことがあるので、彼は緊張して身構えた。が、何も起らず、ホッとした……と思ったら、おそらく2時の時報から3分ほど経って、左の太腿をポンポンと掌で軽く叩かれたのである。
小さな掌だった。
力も弱く、従って痛かったわけではないが、感触がひどく生々しかった。子どもだ、と、閃いた。入院中の小児患者が病院をうろついて遊んでいるのだ。
「コラ! こんな時間に人の部屋に来て何をしてるんや! 出歩いちゃ駄目やないか!」
「……」
返事をしないが、何かがベッドの足もとに立っている感じが伝わり、それが一向に去らない。
「あっちへ行きなさい」
「……」
ナースコールで看護師を呼ぼうかと迷ったが、相手は子ども。しかも健常者ではない。看護師に見つかればこの子は叱られて、今後は見張りがつくかもしれない。それに返事をしないのではなく、口がきけない状態なのかもしれない。自分が今、目が見えなくなっているのと同じように。そう思うと、哀れである。
「……見つかったら叱られてまうぞ。お兄さんは目の手術をしたばっかりやし、遊んでやれんのや」
澄夫さんは優しく諭して、あとは放っておいた。足もとの子どもは大人しく、ずっと沈黙していたので、しばらくすると彼は眠りに落ちてしまった。朝に起きたときには気配が去っていたので、自分の病室に帰ったのだろうと思った。
関連リンク:赤い樵 「樹齢60年ほどの銀杏の大木を伐採してから起きた恐怖体験」|川奈まり子の奇譚蒐集二八 | TABLO
その翌日の晩は、ラジオが午前2時の時報を告げたら、昨日の子どもがきっとまた来るに違いないと思って待ち受けていた。
「午前2時ちょうどをお知らせします」
途端に、足もとから小柄な人間がベッドに飛び乗ってきたのがわかった。予想外の登場の仕方で、澄夫さんは思わずウッと息を詰めて硬直した。するとそいつは彼の背中にまたがり、両手で肩にしがみついてきた。幼い子どもに乗っかられているような感じがした。なんとなく小学生を想像していたのだが、思ったより小さいようだ……4歳か5歳か……たぶん男の子……。
ありありと子どもの姿を思い浮かべることが出来るような気がした。
そのときだ。
なぜかふいに、頭の中で「ご不動さんの真言を唱えよ」としわがれた声が囁いた。特に信心深いわけではなかったが、幼い頃から浜松のある寺院と家族ぐるみの付き合いがあったので、不動明王の御真言ぐらいは記憶している。
しかし、今、囁いたのは何者なんだろうか? 老人の声だったが、聞き覚えはないしかも脳に直接、声が入ってきたような気がした。これはいったいどういうことだ?
驚き、混乱していると、再び、同じ声が頭の中で「ご不動さんの真言を唱えよ」と告げた。そこで澄夫さんは慌てた気持ちになって、大急ぎで不動明王の御真言を唱えだした。
「のーまく さんまんだー ばーざらだん せんだー まーかろしゃーだーそわたや うんたらたー かんまん!」
唱え終わると同時に、背中にはりついていた子どもが一瞬で消えた。
――幽霊だったんだ!
背筋が凍り、澄夫さんはその後も繰り返し御真言を唱えながら、朝になって看護師が訪れるまで、生きた心地もしなかった。
明くる日の夜は、悩んだ挙句に午前1時にナースコールを鳴らして、やってきた看護師に、頭がおかしいと思われるのを覚悟の上で、こんなふうに訴えた。
「バカみたいやと思われるでしょうが、毎晩深夜2時になると、子どもの幽霊がやってきて、眠るどころではあらへん! 足を引っ張ったり、叩いたり、昨夜はついに背中に乗っかってきましてん! 感触や気配はちっさな子どものようなんやけど、真言を唱えたらパッと消えたから幽霊ですわ! 怖くてたまりまへん!」
澄夫さんの訴えを聞くと、看護師は「ベッドのせいかしら」と呟いた。
「この病院ではベッドは病棟を限らず使いまわしとるんですわ。このベッドは、子どもが使こうとったものなのかもしれまへんね」
「では、その子が亡くなって、ベッドに取り憑いて……?」
「さあ……。よぉわかりまへんが、たまにあるんですわ。こないなことが」
そして特別に、彼を1階のロビーで夜明かしさせてくれた。ロビーでソファに座ってラジオを聴いていたが、午前2時を過ぎても何も起きなかった。その日、検査のために別室に行っている間にベッドが交換されていて、それからは退院するまで子どもの霊に悩まされなかった。
しかし澄夫さんは、あれが初めての心霊体験には違いないが、今にして思えば、当時、深夜に病室の外の廊下やロビーに人の気配を感じたり、足音を聞いたりすることが頻繁にあったのだと私に話した。子どもの幽霊が来なくなってから後も、入院中ずっと、である。
そのときは疑問に思わなかったが、よく考えてみたら、病院というところは、夜は消灯しており、夜遅くに入院患者が病室から出て歩き回ったり、大勢の人々がお見舞いに来たりしないものであった。
手術してから視覚を奪われて昼も夜もなくなっていたから、明かりが消える「消灯」のイメージが湧かなかったのだが、暗くなって人々が活動を停止する時間帯のはず。では、夜のしじまに蠢いていたあの人々の気配は何なのかというと、あれらも幽霊だったのではないかと思うしかないとのことだ。(川奈まり子の奇譚蒐集・連載【三〇】)
(後編に続く)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
「乳房」を手放した女性が直面、それぞれの事情 傷跡をカバーできる「ヨガウェア」を開発・販売
東洋経済オンライン / 2024年4月6日 11時40分
-
レーシック手術は「5分で済みます」に要注意…そんなに早く終わるはずがない【一生見える目をつくる】
日刊ゲンダイ ヘルスケア / 2024年4月4日 9時26分
-
病院勤務犬、看取り犬、盲導犬…“癒し”以上に“救い”を与える犬たち「人間との関係ではできないことを可能にする」
ORICON NEWS / 2024年3月25日 7時40分
-
視力や認知機能低下より怖い交通事故になる要因 交通事故率を下げる簡単トレーニングを紹介
東洋経済オンライン / 2024年3月24日 17時0分
-
【海外発!Breaking News】道路を走るバイクの前に飛び出した“顔のない”歩行者 「煙のように消えた」と運転手(フィリピン)<動画あり>
TechinsightJapan / 2024年3月21日 12時21分
ランキング
-
1「原稿がイメージと違った」 読売新聞主任が紅麹関連記事の談話を捏造、処分へ
産経ニュース / 2024年4月17日 20時41分
-
2愛媛県、高知県で最大震度6弱の強い地震 愛媛県・愛南町、高知県・宿毛市
TBS NEWS DIG Powered by JNN / 2024年4月17日 23時19分
-
3十数秒の横揺れ、地鳴り 道路に水、建物ガラス割れ
共同通信 / 2024年4月18日 0時40分
-
4「ママチャリの人」個人情報拡散に元刑事・佐々木成三氏が警鐘 ネットで「私刑」認めるべき行為ではない
よろず~ニュース / 2024年4月17日 19時10分
-
5愛媛と高知で震度6弱、複数けが 南海トラフ可能性高まらず
共同通信 / 2024年4月18日 10時59分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください