インドで「日本人お断り」のスタートアップが続出するワケ
プレジデントオンライン / 2020年3月19日 15時15分
※本稿は、繁田奈歩『ネクストシリコンバレー』(日経BP)の一部を再編集したものです。
■ニチレイは魚や肉のオンライン販売「リシャス」に出資
日本企業のインド展開は、さかのぼると100年ほど前の商社となるだろうか。80年代にはスズキやホンダが進出したが、その後は緩やかな進出状況だった。
近年では、2009年にNTTドコモがタタ財閥傘下の携帯電話会社に出資し、第一三共も約5000億円を投じてインド製薬大手のランバクシー・ラボラトリーズ(Ranbaxy Laboratories Limited)を子会社化するなど、「インド進出ブームか?」と思わせるような投資案件が複数あった。
だがその進出ブームは長くは続かず、「インドは難しい」という認識が定着していった。そんな日本がインドにまた目を向けつつある。
特に最近は、日本の大企業がインドの市場に参入してくる案件だけでなく、インドのスタートアップとの協業が一つのテーマになりつつある。
シリーズBやCなどのある程度大型の資金調達の時期になってくると、日本の大企業も出資を検討し、単なる資本参加だけではなく、インドのスタートアップを通じた市場アクセスや自社の事業強化などを図ろうとする動きが出てくる。
例えばニチレイがインドで魚や肉のオンライン販売をするサイト「リシャス(Licious)」を運営するスタートアップに出資したのも、中長期的なインド市場へのアクセスを狙ったものだろう。
■「ペイペイ」はインドのスタートアップの技術を活用
他にもインドのスタートアップと連携し、彼らの技術やサービスを日本で日本企業が活用する事例が少しずつ出はじめてきている。
その一つが、旧高額紙幣の廃止をきっかけに急成長を遂げたペイティーエムだ。ソフトバンクとヤフーが立ち上げ、2018年12月に利用客に100億円を還元するというキャンペーンを打って話題をさらった「PayPay(ペイペイ)」は、ペイティーエムのQRコードの仕組みを採用している。
日本は2018年以降、政府がキャッシュレスの旗を振ったことでLINEやメルカリなど複数の企業が一気にスマホ決済に参入した。そんな中、インドですでに成功しているペイティーエムの技術を使うことで、ソフトバンクやヤフーは自力で技術開発をせずにサービスを展開することができた。
小売企業もインドの技術に注目している。物流のシステム開発メーカー「グレイオレンジ(GreyOrange)」が手掛ける倉庫用のロボットは、AIを使って需要予測をして、ピッキングをする作業員の前まで商品が入った棚を必要なタイミングで移動させることができる。作業員が無駄な移動をしなくても済むため、省人化や作業の効率化につながるのだ。
深刻な人手不足解消につながるとして、日本では大和ハウス工業がグレイオレンジとタッグを組んで販売攻勢を掛けている。
大手の中にはインドに開発センターを設けている日本企業もあるが、必ずしも自力路線だけで考えるのではなく、最新の技術を追いかけるインドのスタートアップと連携することも一つの選択肢になる。AIをとってみても、マシンラーニングやディープラーニングといった新しい技術が次々と生まれる。めまぐるしく変わる新しい技術を身につけた技術者を全て自社内に抱えるのは至難の業だからだ。
■日本の「ただ乗り」に不満の声
徐々にコラボレーションの事例が出はじめたとはいえ、正直、インドでの日本企業の評判は芳しくない。
インドのスタートアップが特に嫌うのは「情報へのただ乗り」だ。
スタートアップと大企業といっても、当然立場は対等。相手からの情報を求めるなら、こちらからも提供する必要がある。ギブ&テイクの関係でなければ長続きするはずもない。なのに、情報を得るだけ得て、次のアクションについて何も方針を出さないという日本企業が少なくない。
しかも、アポイントを取る時に「目的」を伝えないことも多いようだ。時間を取らせるのだから、相手にとっても有意義なミーティングになるように気を配る必要があるのはいうまでもない。ほかにも、ミーティングばかりをやって実働につながらないとか、話は聞くが意思決定ができないというような不満の声もよく聞く。
日本の企業はこのままだと、インドのスタートアップから「自分たちにベネフィットがない」と判断され、どんどん敬遠されてしまうだろう。
■「仕事以外」の関係作りが苦手な日本人
インドのインナーサークルに入るためには、もっと心を開く必要があるとも感じている。日本人の多くは仕事以外のコミュニケーションが得意ではない。だが、インドで人脈を構築するためにはこの欠点を克服する必要がある。
今でこそ、インド人の友人がたくさんいる私も、最初は手探りだった。時間があれば現地の人とお茶を飲み、雑談をしながら相手の考えを知って、それが次第にビジネスにも結びついていった。
日本人は用がなければ人に会いに行かないが、インドでは「無駄なお茶を飲むこと」も意外と大事なのだ。
もともと、カースト制度があったことも影響していると思うが、インド人は上下関係を気にする人が多い。「自分の上司や取引相手が信用できるのか」「一緒に仕事をしてメリットはあるのか」といった人との関係性を大切にする。
スタートアップは経営者同士がつながっているということを考えても、彼らが人に紹介したいと思えるようなビジネスパートナーとなるためには、「人間的な魅力」を伝える必要があるだろう。
■「投資の目的」を明確にしてスピードアップ
インドへの注目度が徐々に高まるにつれ、インドに拠点を作る日本企業が増えてきているが、いくら拠点を作ってもそれだけでは意味がない。本社が本気でやる気になって、現地に意思決定の権限を与えるなど、決断のスピードを上げていく必要がある。
インドではスタートアップの資金調達の情報が入ってきてから、わずか3カ月で契約するケースも少なくない。日本企業が数年かけて信頼関係を作って契約をしようとすると、どうしても取り残されてしまうのだ。
「投資の目的」を明確にすることも重要だ。純投資なのか、それともインドで事業を共同で展開したいのか、第三国にビジネスモデルを輸出したいのか――。
インドのスタートアップには、決算の内容を見ればバリュエーション(企業価値評価)が高すぎると感じるものも少なくない。結局は需要と供給の問題としか言いようがないかもしれないが、それを受け入れて投資するかどうかは、目的に大きく左右される。
目的が曖昧なほど意思決定のスピードが遅くなるので、日本の企業はこの点に注意すべきだろう。
■投資先は聖地バンガロールだけでなく目的に応じた都市選定を
玉石混交のスタートアップからどう投資先を選べばいいのか。その一つの解が「どこが投資をしているか」に着目することだ。高成長を遂げたスタートアップには初期から有力な企業やベンチャーキャピタルがバックアップしているところが少なくない。
インドのさまざまな都市に目を向ける必要もあるだろう。かつて、インドのスタートアップの聖地と言えばバンガロールだったが、いまやインド各地で魅力的なスタートアップがいくつも生まれている。
ナスコムのリポートによると、2017年の都市別のスタートアップ数を見ると、最も多いのがバンガロールで約1400社。インド全体のスタートアップに占める割合は27%となっている。次いでデリーの約1300社(25%)、ムンバイの約830社(16%)が占める。
大都市が中心ではあるものの、人口400万人未満の「ティア2」「ティア3」と呼ばれる都市でも、多くのスタートアップが生まれている。
南西部のプネーには約260社、西部のアーメダバード、北部のジャイプールにもそれぞれ100社のスタートアップがある。
さらに2018年には上位3都市の占める比率は下がっており、2017年の68%に対し、2018年は60%となっている。
都市ごとにスタートアップの特徴も異なる。例えば、フィンテックであれば金融の中心地であるムンバイが強い。巨大ハイテク都市に成長中のハイデラバードもIT系のスタートアップの拠点になっている。
このような状況下でも、いまだに多くの日本企業はバンガロールにしか目が行っていないようだ。AIの開発など、IT系では依然としてバンガロールがリードしているやもしれないが、すでに投資マネーの流入はデリーの伸びが大きくなってきていたりもする。スタートアップはバンガロールという一元的な考えだけではなく、状況に応じてエリア選択を考えていく必要もある。
■新興国での展開に抜本的な見直しが必要
これまで、日本企業では海外の市場開拓をできる人材が少なく、同じようなメンバーが国や地域を順番に担当していくことが多かった。そのため、2015年以降の「第二次インドブーム」では2003年~2006年頃、私が中国でビジネスをしてきた時の知人とよくインドで遭遇した。
ただ、中国など、他地域で販売して好調だったものをインドに持って来れば成功するという2010年代前半くらいまでのやり方はもはや通用しない。
EC(電子商取引)の発達で流通の形態が激変するなど、デジタル化が急速に進んだため、数年のうちにビジネスモデルそのものを見直さざるを得なくなっている。
この変化に対応できている日本企業は少ないように感じている。時代に適したビジネスモデルへの転換が常に求められており、新興国での事業展開の仕方については抜本的な見直しが必要だろう。
■インドは都市ごとに経済圏がある
これまでの国や地域の捉え方も変えることが求められる。インドは、依然として人口のうち65%が農村に集中している。そのため1人当たりGDPなどの統計は農村の実態にどうしても引っ張られてしまう。
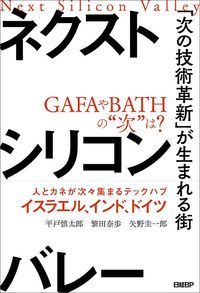
2019年現在のインドの1人当たりGDPは約2000ドルと他の新興国より低い。車などの耐久消費財の需要が急速に伸びる水準とされている3000ドルからは程遠いのだ。
だが、デリーに限っていえば1人当たりGDPは既に5000ドルを超えている。さらに、これまで見てきたようにハイデラバードのような巨大なハイテク都市が次々生まれ、2030年に1人当たりGDPが3000ドルを超えると推定される州の人口を合計すると5億人を超える。
インドは国全体を漠然と捉えるのではなく、都市ごとに経済圏があると考え、そことどう連携していくかを考えないと、実態を見誤る。つまり、それを意識することが成功へのカギとなる。
----------
インフォブリッジグループ代表
東京大学教育学部卒業。大学在学中にインド・ニューデリーで旅行会社を開始。1999年インフォプラント(現マクロミル)入社。2002年同社取締役、04年同社初の海外子会社の立ち上げなどを担当。2006年、インフォブリッジを設立して独立。現在はインド・デリー在住。インド市場を中心に日系企業の新興国進出支援やイノベーションエコシステム作り、スタートアップやテックコミュニティーと連携した新規市場開発などに携わる。
----------
(インフォブリッジグループ代表 繁田 奈歩)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
デロイト トーマツ ベンチャーサポート、インド ベンガルールに新たな拠点を設置
Digital PR Platform / 2024年4月15日 10時18分
-
躍進するインドの「本当の姿」がまるわかり!『決定版 インドのことがマンガで3時間でわかる本』4月12日発売
PR TIMES / 2024年4月12日 8時45分
-
日本は単なる下請けじゃない... 初任給「大卒で28万円」TSMC熊本工場の衝撃と日本進出の狙い【アニメで解説】
ニューズウィーク日本版 / 2024年4月3日 19時40分
-
欧州・米国拠点のグローバルVC、PULSARが本格的に日本進出。東欧のスタートアップ企業の日本進出を支援。SusHi Tech Tokyo 2024 GSPのオフィシャルアンバサダーにも就任。
PR TIMES / 2024年4月3日 13時40分
-
インドで関心高まる食の安全性。FreshToHome、新鮮食材の流通で食品eコマースを牽引
Techable / 2024年3月26日 18時0分
ランキング
-
1グリコ「チルド食品」出荷再開→再停止…システム障害で 乳製品・洋生菓子など、5月中旬の再開目指す【全文】
ORICON NEWS / 2024年4月19日 18時57分
-
2日本在留の外国人が日本で働きたくない理由 2位は「働く環境が悪い」、1位は?
ITmedia ビジネスオンライン / 2024年4月19日 17時15分
-
3東証、一時1300円安 大幅反落、2カ月ぶり安値水準
共同通信 / 2024年4月19日 12時5分
-
4東証大幅反落、終値1011円安 中東緊迫、3年2カ月ぶり下げ幅
共同通信 / 2024年4月19日 17時36分
-
5格安スマホの利用者は約4割 実際に支払っている月額利用料金の2位は「2000円台」、1位は?
ITmedia ビジネスオンライン / 2024年4月19日 17時15分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください










