軽い風邪でも病院に行く神経質なイタリア人がマスクを嫌がる深い理由
プレジデントオンライン / 2020年9月1日 11時15分
※本稿は、ヤマザキマリ『たちどまって考える』(中公新書ラクレ)の一部を再編集したものです。
■「イタリア人は何かとルーズ」はまったくの誤解
イタリアでは6月3日に国内の移動制限が解除されました。新規感染者の数は抑えられましたが、7月半ばの時点で累計感染者数は24万人を超え、死者数はアメリカ、ブラジル、イギリス、メキシコに続く世界5位となりました。
イタリアでの感染爆発のニュースに、「イタリア人は何かとルーズだから、感染症のこともそれほど深く考えずに暮らしているのでは?」と思った人もいるかもしれませんが、事実はまったくの逆です。彼らは感染症を含む病気に対して神経質な一面をもっていて、夫のベッピーノも「新型コロナは風邪やインフルエンザと同じ程度のもの」という認識が日本でまだあった時期から、このウイルスに危機感を示していました。
日頃から、うちの家族たちは病気全般に慎重です。たとえば「インフルエンザが流行る」という情報を報道などから知ると、姑はすぐに薬屋に行き、家族分のワクチンを買ってきて、全員にそれを接種させます。イタリアではワクチンは薬局で購入するものであり、自分たちで接種も管理もしなければなりません。子どもに必要なワクチンも同様です。
■「軽い風邪」でも病院を予約する危機管理意識
私の体調に少しでも病気の兆候が見られたりすると、イタリアの家族たちは神経質になります。「軽い風邪だから大丈夫」と本人が主張しても勝手に病院を予約し、無理矢理にでも医者に診せようとする。しかも夫の家族が特別ではなく、私が若い頃に付き合っていた詩人も、ほかの知人や友人も同様で、イタリア人は概して病気へ敏感に対応をする傾向が強い。そもそもホームドクター(かかりつけ医)のいる家が多いことも、関係しているのでしょう。
そうした危機管理意識が根付いているからか、今回の新型ウイルスにも「自分たちの命は自分たちで守っていかなければならない」という感覚が、イタリア家族たちのなかに当初からあったように思います。地方自治体や国といった、大きな組織のリーダーが先導して感染から守ってくれるだろうという希望的な観測は、もっていなかったですね。
日本人との感覚の違いは、マスクの扱いでも感じました。このコロナ以前、ほかの欧米諸国と同じく、イタリアでもマスクは普及していませんでした。わが家のケースで言えば、予防策といえば何よりワクチンがいちばんであり、体の内側から病気をブロックさえすれば、マスクのような表層的な対処は必要ない、というわけです。
■なぜ息子は「マスクを外せ」と先生に言われたのか
ポルトガルで息子のデルスが現地の小学校に通っていた頃のことです。彼が咳をしていたので、マスクをさせて学校に行かせたことがありました。ところが校門をくぐってまもなく、「大げさな疫病が流行っているように見えるから、直ぐに外しなさい」とそばにいた教師に言われたからと、マスクを外して帰ってきたのです。
しかし日本で育った私には、マスクをしないことで自分の風邪やインフルエンザをまわりにうつしてしまうという懸念が強くありました。そこで「マスクをするだけでもそのリスクは結構抑えられるはずなのに、なぜ普及しないのかわからない」という疑問を夫に投げかけてみたところ、夫の答えは「感染しても、それで抗体ができるんだから、いいんだよ」というものでした。
ワクチンの接種と同様に、体の内側に抗体をつくることのほうがマスクよりも意味があるらしい。そういった認識が私のまわりでは当たり前になっていたのですが、それと同時に、イタリアでもマスクが“大げさな疫病”を想起させるものだと知りました。
■色濃く残る「スペイン風邪」の記憶
おおよそ100年前、イタリアをはじめとするヨーロッパの国々で、マスクの着用を余儀なくされた時期があります。1918年から20年にかけて世界で推定5000万人以上が亡くなったともいわれ、その大半がヨーロッパの人々だったという「スペイン風邪」のパンデミックです。日本でも40万人近く犠牲になったとされますが、スペイン風邪はまさに、致死率の高い“大げさな疫病”だったのです。
現在のイタリアでも、スペイン風邪で親族を亡くした人が家族のなかに一人か二人はいるほど、そのパンデミックの記憶はまだリアルに残っています。身近なところでは、夫の母方の曾祖父も犠牲者ですが、その話はもう何度となく夫の祖母から聞かされたものでした。
当時イタリアで撮影された、とある家族の集合写真では、大人も子どもも全員マスクをつけて並んでいるのですが、その様子は尋常ではない、何か嫌なことが起こっているという不穏さに満ちていました。そのセピア色の写真を見て、マスクが欧州では即座に疫病を思い起こさせることをなんとなく理解できました。
■マスクは「自由が拘束されている感じがする」
イタリア国内の移動制限が緩和されて間もない頃、ニュースを見ていたら、北イタリアのどこかの海辺にたくさんの人がマスク姿に水着で繰り出している映像が出てきました。そこでインタビューを受けた女性はマスクをつけたまま、こう答えていました。
「海に来てまで本当はマスクなんてしたくありません。解放された気持ちになれないし、こんなもののせいで、自分のあらゆる自由が拘束されている感じがするんです」
自由の拘束。この女性の言葉はとても象徴的です。イタリア人にとってマスクは今や「自分たちの自由な判断では生きられなくなった」というパンデミックの状況を、端的に形象するものになっているのです。夫が「マスクは病気に屈服している感じがするから、つけたくないんだ」と言っていたのも、同じ心情が軸になっていると思います。
それと、やはり言語によるコミュニケーションが生活に根付いている彼らにとって、表情を遮るマスクは苛立ちの大きな要因ともなっているのでしょう。口を尖らせたりニヤリと笑うことも言語表現には欠かせないツールになっていますから、マスクで見えなくされてしまっては、うまく相手に言いたいことを伝えられない、というもどかしさをもたらしているはずです。ただそう考えると、やはり彼らにとって日常の言語の重要度は我々よりもはるかに大きく、それが感染拡大とは全くの無関係だった、とは言い切れないとも感じています。
■マスク一つとっても、日本とイタリアで違いがある
ちなみに、日本のニュース映像では、多くの政治家のマスク姿を見かけるようになりましたが、そのなかでも私がとりわけ気になっていたのは、小池百合子東京都知事です。緑のスーツには薄緑色のマスクを合わせたり、見るたびにお洋服とマスクが絶妙にマッチしている。彼女のマスクを見ているうちに、学校で決められた制服ではあっても、そこにわずかなアレンジを凝らして、自分なりの着こなしを演出していた学生時代をふと思い出しました。あれも、ある種の拘束からの解放だったのかもしれません。
片やファッション的な要素を加えて着用し、片や拘束具として嫌がる。マスク一つをとっても、日本とイタリアの間に感覚の違いがあるようで、興味深いです。
■「ソーシャルディスタンスは1メートル」
「ソーシャルディスタンス」という考え方がこのパンデミックによって定着しました。「互いの飛沫がかからないよう、人との距離を2メートル取りましょう」というものです。
ところがイタリアでは、「ソーシャルディスタンスは1メートルで」とされています。おそらく、その距離が彼らにとっての限界ギリギリの線なのだろうと思います。イタリア人たちは、相手の顔を見ながらそば近くでしゃべりたいのです。そうでなければ彼らのコミュニケーションは成立しません。それを精一杯我慢しての“1メートル”なわけです。
人との距離を詰めて話したいという気持ちは、電話からも伝わってきます。たとえばうちの姑。彼女から電話がかかってくると、受話器を耳から20センチほど離して聞くようにしないと、鼓膜が破れんばかりの迫力で向こうの声が迫ってくる。このご時世、電話を介していても飛沫感染の危険があるような気がしてしまうほどです。姑同様にイタリアの多くの人にとって、それぐらいの熱量でもって人と話すことが当然なのだと思います。
とはいえ、本人にその自覚はありません。私が家族に指摘しても「日本人の声の音量が抑え気味だからって、そちらに基準を置くな」と言われてしまいます。たしかに、言語や国民性によってしゃべり方や声のボリュームは違いますから、基準なんてない。ただ、今回のパンデミックでは大声で飛沫を飛ばしまくりながらしゃべる国民の国と、基本的に飛沫の飛ばないしゃべり方をする国民の国では、感染率にも差が出たのではないかと勘ぐらずにはいられないのです。
■日本人とは違う衛生管理の価値観
以前、ハンカチで鼻をかみ、それを畳んでポケットに入れ、しかもそのハンカチを人に貸すというイタリア家族たちの習性をエッセー漫画に描いたら、「そんなに私たちのことを不潔扱いしなくてもいいじゃないの!」と、家族からこっぴどく怒られました。
漫画に描いたのは、決して彼らをバカにしてのことではありません。日本人の私たちとは衛生管理の価値観が違うということを言いたかったのです。でもあれほど怒るということは、やっぱり後ろめたいところがあるんじゃないでしょうかね(笑)。おそらく、彼らにも少しは公衆衛生という面で腑に落ちないものがあったから、私の漫画にカチンときたのです。
だって、考えてもみてください。このコロナ禍の最中に同じことをしていたらどうなるか。万が一ウイルスがハンカチについていたら、ポケットの内側がウイルスの巣窟になり、そこから出した手で「チャオ!」と誰かを抱きしめ、肩を組み、ドアノブを握り、お金を触るわけですよ。それによるウイルスの拡散ぶりは想像するだけで恐ろしいものです。
■古代から続いている「ハグ」を簡単にやめられるのか
家族に怒られはしましたが、漫画家である私は、一般的な人の何倍も普段から人の動きを何気なく見ています。潜在意識下でどうしてもそうした観察眼のスイッチが入ってしまうのですが、そうやってイタリアや中国、アメリカや中東など、様々な文化圏のいろんな人たちのあらゆる習慣や特徴的な仕草などを見てきました。
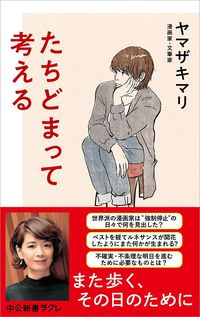
ウイルスの感染対策にも、人々の生活を観察する「日常風俗観察知識者」「人類の行動学者」のような専門家を加えるべきじゃないかという気もしますね。ウイルスの専門家が焦点を当てない人間の行動といった側面を知ることで、見えてくるヒントやアイデアが確実にあると思います。
感染症の専門家や歴史の記述を見ても、疫病には第2波、第3波が必ず起きるという指摘がなされています。この状況のなかで今後、イタリア人の人との距離の近さという習慣はどうなっていくのか。たぶん、完全に途絶えることはないでしょう。もちろん「1メートル」のソーシャルディスタンスのように、何らかの折り合いはつけていくと思いますが、人間の習性は抑えきれるものではありません。イタリア人にとってのハグ(抱擁)など体を触れ合う習慣は、古代から続いてきているわけですから、完全に控えるのは難しい気がしますね。
フラットな目線で観察したならば、至近距離でのコミュニケーションをそのまま貫いて、それでも生き延びた人たちが、ウイルスと共生しながら生きていくことになるのかもしれません。要するに、ウイルスによる人類の淘汰が起きる。ほかの生物の生態を踏まえても、それこそがウイルスの本質的な目的なのではないかという気がしてならないのです。
----------
漫画家・文筆家
東京造形大学客員教授。1967年東京生まれ。84年にイタリアに渡り、フィレンツェの国立アカデミア美術学院で美術史・油絵を専攻。2010年『テルマエ・ロマエ』で第3回マンガ大賞 受賞、第14回手塚治虫文化賞短編賞受賞。2015年度芸術選奨文部科学大臣賞受賞。著書に『プリニウス』(新潮社、とり・みきと共著)、『オリンピア・キュクロス』(集英社)、『国境のない生き方』(小学館新書)、『ヴィオラ母さん』(文藝春秋)など。
----------
(漫画家・文筆家 ヤマザキ マリ)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
ヤマザキマリ氏 大ヒット作「テルマエ・ロマエ」の制作秘話「読み切りで終わらせる漫画だと思って」
スポニチアネックス / 2024年4月21日 16時15分
-
日本でしかありえない企画展!? 「テルマエ展 お風呂でつながる古代ローマと日本」-ルシウスが案内する2つの国の入浴文化
マイナビニュース / 2024年4月8日 12時33分
-
感染が相次ぐ麻疹(はしか)とは? 感染リスクが高い「ワクチン空白世代」は要注意
ウェザーニュース / 2024年3月31日 5時10分
-
麻しん(はしか)の流行に備えるために(前編)
Japan In-depth / 2024年3月28日 12時7分
-
それって本当に花粉症!?自己判断が感染を広げる原因に 意外と多い目に症状が出る感染症が今年度も流行!その症状、花粉症ではないかも?!
@Press / 2024年3月27日 11時0分
ランキング
-
1埼玉県の治安「数字だけ見るといい状況でない」 さいたま地検の野下智之検事正が着任会見
産経ニュース / 2024年4月22日 21時44分
-
2中学1年の男子生徒(12)が川でおぼれ重体 川に落とした物を拾おうとしたか 三重・松阪市の愛宕川
CBCテレビ / 2024年4月22日 22時30分
-
3岸田首相の在職日数、戦後8位に 橋本氏超え、支持率低迷
共同通信 / 2024年4月23日 0時2分
-
4他県産を「鹿児島黒豚」「鹿児島黒毛和牛」と偽り納品 志布志市ふるさと納税返礼品 宮崎の業者「採算がとれなくて」
MBC南日本放送 / 2024年4月22日 16時11分
-
5ショートメールに届いた番号に電話すると「料金未納」と架空請求、新潟佐渡の男性が約600万円被害 佐渡署が捜査
新潟日報 / 2024年4月23日 7時55分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください










