脳科学者・中野信子衝撃自伝「セクハラなんて腐るほどあった」
プレジデントオンライン / 2020年11月7日 9時15分
※本稿は、中野信子『ペルソナ』(講談社現代新書)の一部を再編集したものです。
■やっぱり女は違う扱いをされるのだな
あたかも「名誉男性」であるかのように、自分の努力と才能とを男性原理社会の中であっても認めてもらえるよう、命を削るようにして必死で頑張る女性がたくさんいる。が、やっぱり女は違う扱いをされるのだなと、これまで、痛いほど思い知らされてきた。
たとえば鉄門(東京大学医学部医学科)には、女性の教授が当時からいなかった。いわば男性たちの“聖域”のようなものだ。
大学院でも、優秀な女性研究者がどれだけ論文を書いても、必ず下に見られるか、無意識に無視される。『ピーターラビット』を著したビアトリクス・ポターは、地衣類が菌類と藻類の共生であることをつきとめて、リンネ学会で発表したが、黙殺された。優れた業績であり、彼女が男であったなら認められたはずの論文だったが……。100年後、リンネ学会は性差別があったと公式に謝罪した。
■セクハラなんて腐るほどあった
21世紀の現在ですら、あの人は女を捨てているよねとか、あの教授とどこそこで夜一緒にいるところを見たとか、高い下駄履かされやがってとか言われるのを見て、心底うんざりした。

実力があっても、成果を上げてもじゃあ子どもは産んだのか、だったり、旦那さんはどんな人? なんていうことを聞かれる。男性研究者がそんなことを言われるだろうか?
セクハラなんて腐るほどあった。例えば先生から抱きつかれて、「やめてくださいよ」と邪険にすると、評価が下がって奨学金を受けるのに不利になるなんていうことはもうありふれ過ぎていて告発すらされなかった。
抱きつかれた時の賢い対処法は、「先生も疲れているんですね」などといってやんわりと腕をほどいてなだめる、というような方向になる。
女性に向ける目が、教授たちからして昭和なのだ。最先端のアカデミズムの中にいるはずの人たちが。
■失望と転換
こんなところで論文を書いて出世しても……という気持ちにならないほうが、おかしくないだろうか。21世紀になってもこれなら、私の生きているうちにはもう変わらないのではないかと失望した。謝罪があるとしても、また100年待たねばならないのか。
アカデミズムの世界で生きていこうという気はどんどんなくなっていった。どこでも浮いてしまった私だが、ここも私にはちょっと無理なのかもしれないな、と暗い気持ちが募った。
博士号を取って、フランスのニューロスピンで研究員になったはいいけれど、ポスドク(ポストドクトラルフェロー、日本語では、博士研究員)というのは任期が切れたら、次の就職先を考えないといけない。この先こんなことを何回繰り返せばいいのか、もっと頑張りを評価されてもいいんじゃないかという思いもあった。報酬が安すぎる上に、安定的でもない。
任期が切れるときにフランスでの次の就職先は見つけたけれど、一時帰国した時に今の夫と出会い、もう頑張らなくていいや、特に仕事にこだわらなければ何とか生きてはいけるだろうしなという考えにシフトした。男性原理の中でキャリアアップしなきゃと格闘していたのが馬鹿らしくなったのだ。
それで、日本に戻ってきて結婚した。
■パートタイムジョブからテレビの世界へ
ポスドクはパートタイムジョブで、例えばスーパーでレジ打ちするのと変わらないとも思った。
ただ、私たち二人ともそんなに体が頑健なほうではなかったこともあり、もう少し体力的に見合う仕事を、ということで文章を書くようになった。本を出すと、すぐにテレビ番組からオファーがあった。そのままテレビの仕事をつづけ、今に至る。
真面目な話、アカデミズムの資産を一般に還元する仕事は誰かがやらなくてはならない、と思ってはいた。
ほとんどの場合、日本の大学に在籍している研究者は、主として税金を元手に研究活動をしている。一方でその成果は広く知られていないことも多く、実用的な技術として使われているかといえば必ずしもそうではない。
科学技術立国、とずいぶん前に誇らしげにスローガンを掲げていた割には、残念ながら一般の人はウイルスと菌の違いもあまりわかっていないような感じだ。
■象牙の塔からの「ポルノみたいな扱い」
ただ、葛藤はあった。アカデミズムの中にずっといると、論文を書くことだけが正義で、一般向けにわかりやすく物を書く、なんていうことは、どぎつい言い方をすれば、象牙の塔で暮らす先生方からはポルノみたいな扱いをされてしまうのだ。メディアに出るのももちろん、同じ扱いである。あいつは悪魔に魂を売った、と後ろ指をさされる。
冷静に考えれば、不思議な現象だ。
むしろ教授陣に文字通り性を売りながら論文を書く方が普通にポルノだと思うけれど、昭和をひきずるアカデミックの基準では、そうではない。メディアに出る人に向けられる視線はさらに厳しいかもしれない。大衆向けの商業主義に加担するとは何事か、と眉を顰(ひそ)める先生方が今でもかなりの割合でいらっしゃることだろう。
けれど、「大衆向けの商業主義に加担してはならない合理的な理由」とは何だろう。先生たちに都合のいい考え方をすれば、私にも思いつくのだろうか?
科学の誤った理解を助長するのがけしからん、というなら、ご自身がもっと教育・啓蒙活動をすればいいだけではないかと思うが、「そんな時間はない」ようなのだ。つまり、優先順位は低いということになる。
それならば、私のことなど放っておけばいいようなものだが、情動の強さや攻撃の激しさを考えると、そうでもない、らしい。
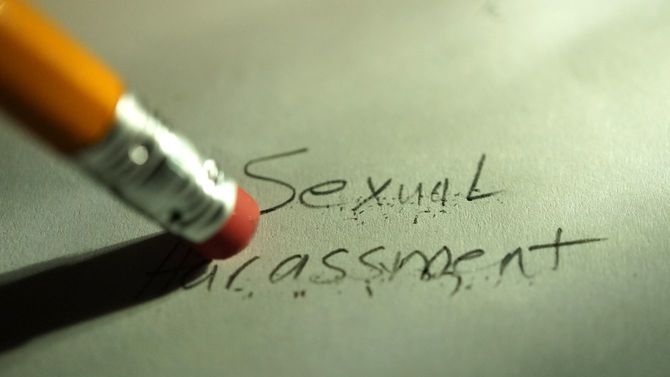
■時間とコストをかけて戦うなんて、どう考えてもバカバカしい
別に私からは、先生方がテレビに出ても、商業主義に加担した、資本主義の手先、などと古臭いコミュニストみたいなことを言ったりはしない。積極的に、お出になればいいと思う。
ただ、論文をどれほど書いていても、スタッフを自分の部下であるかのように扱ったために、コミュニケーションがうまくとれなくなってしまったり、説明の仕方が高尚過ぎていまいち伝わりにくかったりするようであれば、すぐに呼ばれなくなってしまう、そんな世界に、ナイーブな先生方は耐えられないかもしれない。
ともあれ、いつしかアカデミズムの世界は、単なる時代遅れの男性原理の象徴としか感じられなくなってしまった。もちろん、いまだ誠実に奮闘している人もいると思うし、全員を否定するつもりは毛頭ない。けれど、私自身は、生まれついての性別で、既にハンディキャップを持っている状態だ。
そんなもの跳ね返せ? いやいや、わざわざそんなアウェイの競技場で、一体何のために必死になってプレイする必要があるというのか? 給料も言うほどよくはなく、出世すればするほど女の魅力に乏しいねと揶揄(やゆ)される。自分の意地のため? そんなくだらないもののために、時間とコストをかけて戦うなんて、どう考えてもバカバカしい。
■「女としてはどうか」という愚問
時間は、ただの時の流れではなくて、寿命の一部である。一部とはいえ、こんな闘争に、命を懸けて取り組む価値など、欠片もない。過去のよく知りもしない人が勝手に作り上げてきた男性原理を覆すなんていうことのために、自分の、有限でしかない時間を、惜しみなく注ぐ気になど到底なれない。
そのうえ、たとえアウェイで勝ったとしても、そのインセンティブはたかが知れている。そこで業績をあげ、「勝負に勝った」としよう。その結果得られるものの乏しさときたら、むなしいものだ。女のくせによく頑張りましたね、と男性から苦々しげにまばらな拍手を送られるだけ。一般の理解を得られる可能性はほぼない。
たいていの男性研究者が取れないノーベル賞を、2度も受賞したキュリー夫人ですら、「妻として、女としてはどうだったのか」などという記事が今でも出てきたりする。剰(あまつさ)え、業績でなく容姿で評価されたりもする。受賞から100年以上たった今ですら、女としてはどうか、などと言われるのである。
■アウェイはアウェイ
いずれにしても、その苦闘とその成果がそのまま受け入れられることはない。つまり、勝負を受けて立ってもそれに勝っても、アウェイはアウェイなのだ。
勝ったところで、後続の女性陣に対して「あなたたちも頑張れば名誉男性になれるのよ」といわんばかりの姿を恣意的に強調され、その努力を搾取して成立している男性原理のプロパガンダとして、いいように使われるのがオチだろう。
驚くべきことに、「こんなに活躍されて、ご主人はかわいそうですね」と面と向かって私に言ってくる男性がまだいる。この人の話は面白いので何度でも口にしてしまうし、どこにでも書いてしまう。実名をさらされたらいやだろうからそれは礼を重んじて黙っておくが、“ご主人”の珍しい性格を知りも調べもしないような人がよくいうな、と思う。
この方は妻が自分よりも不出来でなければたちまち自信喪失してイライラし始めるような「かわいそうなご主人」なのだろう。自分の不幸の原因に自ら気づくことができないのは、それ自体が不幸なことだ。
■第三の生き方を選ぶ女子たちにエールを
女は若いうちしか売れないよと呪いのように言われ続け、自分の価値がどんどん下がるという価値観を埋め込まれて育ってくる。私は異質ではあったけれど、それでも、そうだ。
そんな中で、本当に自分のやり方で大丈夫なのか、自分より以前には誰も歩いたことのないような、この細い暗い道を行って、のたれ死なないかなという気になったこともないではない。

だが、もはや世間から見た成功と人生の満足度とは違うと、自らの満足度の方に重きを置く生き方を模索できる時代に今はなってきている。女性は、「モテ」を狙うか、男性原理の中でキャリアアップを狙うかの二択しかないように思わされて育ってくるが、「第三の道」を私は選びたいと思っている。
第三の生き方を選ぼうとひとたび決めれば、かなりのことが楽に捌けるようになる。自分の中の基準に自信を持つことが難しかった学生時代より、中年になってからの方がずっと私は心地よい。
他の、キャリアを持った/持とうとしている女子たちにも、もう男性が決めたヒエラルキーの中、アウェイのフィールドでの勝ちを目指すのは無意味だと、気づき始めた人が出てきているのではないだろうか。
彼女たちに私は、エールを送りたいと思う。
----------
脳科学者、医学博士、認知科学者
1975年、東京都生まれ。東京大学工学部卒業後、同大学大学院医学系研究科脳神経医学専攻博士課程修了、脳神経医学博士号取得。フランス国立研究所ニューロスピンに博士研究員として勤務後、帰国。東日本国際大学教授として教鞭を執るほか、脳科学や心理学の知見を生かし、マスメディアにおいても社会現象や事件に対する解説やコメント活動を行っている。著書には『サイコパス』『不倫』(以上、文春新書)、『空気を読む脳』(講談社+α新書)、『ペルソナ』(講談社現代新書)、『引き寄せる脳 遠ざける脳』(プレジデント社)、共著書に『脳から見るミュージアム』(講談社現代新書)、『「超」勉強力』(プレジデント社)などがある。
----------
(脳科学者、医学博士、認知科学者 中野 信子)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
【泥沼不倫】「家に誰かいる」…36歳妻が出くわした“いるはずのない人物” 妊娠中から続いていた裏切りと結末
オトナンサー / 2024年4月21日 8時10分
-
「運がいい人」も不安に襲われることはあるけれど…脳科学者・中野信子がおすすめする4つの〈不安の対処法〉
THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年4月8日 7時30分
-
よい人間関係を築くための〈配慮範囲〉とは? 他人のための〈利他行動〉をとると脳にポジティブな変化が起こるワケ【脳科学者・中野信子が解説】
THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年4月1日 12時15分
-
世界各地に存在する「男女に区別されない性」が当たり前にある民族
PHPオンライン衆知 / 2024年4月1日 11時50分
-
起こった出来事は同じでも…〈運がいい人〉と〈運が悪い人〉の決定的な「思い込み」の違い【脳科学者が解説】
THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年3月26日 12時0分
ランキング
-
1愛知・東郷町長が辞職願 第三者委、パワハラ認定
共同通信 / 2024年4月24日 22時55分
-
2エアコン清掃やるなら今!?家庭でできる簡単フィルター掃除をプロが伝授 そして業者に頼むなら時期に注意…GWから依頼急増
MBSニュース / 2024年4月24日 18時43分
-
3袴田さん再審、5月22日結審 姉「巌の気持ち伝える」
共同通信 / 2024年4月24日 20時7分
-
4【速報】全日空71便が新千歳空港に着陸後、大量の煙を出して滑走路上に停止…油圧系に不具合の可能性 乗客202人にけがなし
北海道放送 / 2024年4月24日 18時26分
-
5岸田首相、補選は自身への評価=規正法改正「強い覚悟」―参院予算委
時事通信 / 2024年4月24日 19時2分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください










