「民主主義」を後回しにしたシンガポールが経済立国に成功したのは偶然ではない
プレジデントオンライン / 2021年5月12日 11時15分
※本稿は、姫田小夏『ポストコロナと中国の世界観 覇道を行く中国に揺れる世界と日本』(集広舎)の一部を再編集したものです。
■コロナ禍の中国人を救った「家族主義」
コロナ禍で大陸の中国人が命拾いしたとしたら、その理由の一つは「家族」にあるといわれている。職を失い住むところを失っても、家族のもとに転がり込んで当座をしのぐことができた、というのだ。中国人の家族主義はよく耳にするところだが、これはとりわけ東アジアや東南アジア(以下、東洋とする)などの中国語を話す人々の間で共有される思想でもある。
シンガポールの初代首相を務めた故リー・クアンユー(李光耀、1923-2015)氏の論文「李光耀論東西方文化与現代化」(2004年)には、欧米先進諸国(以下西洋とする)の価値観である「個人の自由」と東洋の価値観のコントラストが描かれている。同氏は、工業化、都市化、グローバル化が進む中で、シンガポールは核心的価値観を保持する必要があるとして、次のように主張している。
「最も重要な核心的価値観とは、君臣、父子、夫婦、兄弟、友人が負わなければならない権利と義務を規定する五倫関係(仁・義・礼・智・信)である。これは、子どもの世話と教育の責任を説き、親孝行、家族や友人への忠誠、質素で謙虚になること、一所懸命に学び、働き、成人したときには紳士になることを教えるものであり、これらの価値観は中国の文明を存続させ、他の古代文明が衰退する運命から中国文明を救うものである」
■発展したシンガポールと中国の共通点
リー・クアンユー氏は1976年を皮切りに計33回も中国を訪問しているが、1980年代のシンガポールと中国の共通点を「(当時の中国の)人の動作や姿、話し方のトーンは東南アジアの華人と同じではないが、社会利益を家庭の利益に優先させ、家庭の利益を個人の利益より優先するという考えや、高齢者を尊重するという点で、互いの価値観は同じだった」と振り返っている。
同氏はこの論文で、家庭を社会の中核単位にし、社会的結束を強めることが東洋の文化の特徴であると主張しているが、他方、「五倫関係」については、例えば、国際社会では男女平等が進んでいるように、伝統的な価値観も現代社会に合うように調整することが必要だという柔軟な考え方も示している。確かに、こうした価値観も行き過ぎれば、支配・被支配の関係を強めてしまう欠点もあるため、常にバランスを取る努力が必要だ。
紀元前の中国で孔子は人倫の道を説き、武力を否定し、徳で以て世の中を治める徳治主義を広めた。のちに孔子の儒家思想を受け継いだ孟子が五倫関係を提唱する。四書五経は儒教の文献の中でも特に重要とされるもので、その中の『礼記(らいき)』は、周から漢の時代にかけて儒学者によって編纂された「礼」に関する書物だといわれている。そこには「まずは家を治めることだ」と書かれている。
■先に経済、後から民主主義
「先ず其の家を斉(ととの)う。其の家を斉えんと欲する者は、先ず其の身を修(おさ)む。其の身を修めんと欲する者は、先ず其の心を正しくす。其の心を正しくせんと欲する者は、先ず其の意を誠にす。其の意を誠にせんと欲する者は、先ず其の知を致す。知を致すは物に格(いた)るに在り」
家を治めることができれば、国を治めることもできる、そのためには個人の心のありようを正す必要があるという思想である。社会の秩序を維持するには、家が最小の単位となり、最小の単位である家庭の中の個人がそれぞれに道徳的義務を果たせば、国家もまた平和的に治めることができる、ということなのだろう。
シンガポールは、多くの国がモデルとして注目している国家だといわれている。リー・クアンユー公共政策大学院研究員で、ブルッキングス研究所研究員でもあるパラグ・カンナ氏は著書『アジアの世紀』で「ロシア、オマーン、ドバイ、中国を含め、こんにちアジア中の政府がシンガポール政府を詳しく研究している」と記している。
そのシンガポールでは、「民主主義より先に、広い範囲での教育や研修を通じて高度な技術を身につけた専門家が運営するテクノクラシー制度を導入したが、後に民主的な長所を結び付けるようになった」(同)という。先に自由や民主を輸入するのではなく、その土地にあった政治制度を培いながら、そこに民主を取り入れるという発想だ。アジアには、異なる文化を受け入れ、風土に合ったものに調和させる力があるということの示唆でもある。

■「民主主義」を掲げる西洋中心社会の課題
現代社会では、民主主義が普遍的な価値を持つ制度だと考えられている。個人は平等であり、差別を受けることなく自らの幸福を自由に追求できる権利が尊重されている。人は平等だとする価値観は、それこそ西洋文化が与えてくれた人類普遍の崇高な価値観だといえる。
一方、この西洋の価値観が負っている課題を提起する人物がいる。シンガポール国立大学リー・クアンユー公共政策学院の院長でもあり、前国連駐シンガポール代表のキショール・マブバニ氏だ。マブバニ氏はインド系シンガポール人としてシンガポールで生まれた。シンガポールはアジアの多民族国家であり、英語を公用語とすることで国民が西洋の文化を吸収した東西文化が融合する国家でもある。
米国国務省や中国外交部のエリートたちと数年にわたり仕事をし、両国の長所短所を熟知した同氏のユニークな視点は、少なくとも米国と中国の2つの世界で注目されている。
マブバニ氏は著書『The New Asian Hemisphere』(2008年)の中で、「インターナショナル・コミュニティとはあくまで西洋の価値観をシェアすることである」と、西洋偏重の国際社会の在り方に疑問を呈している。
同著では、世界人口の12%に相当する西洋諸国の9億人が、残り56億人の運命を決定していること、世界人口の55%を占める東洋人がIMF(国際通貨基金)や世界銀行のボードメンバーにおいて不在であることが指摘されており、マブバニ氏は「21世紀の逆説は、世界で最も民主的な国々によって非民主的な世界秩序が続いていることだ」と述べている。
■完全な民主主義の国は12%しかない
ここに面白い調査結果がある。英エコノミスト誌傘下のエコノミスト・インテリジェンス・ユニットの「民主主義指数」(2019年)によると、167の国とエリアのうち、「完全な民主主義」は20、「欠陥のある民主主義」は55、「混合政治体制」は39、「独裁政治体制」は53だという。
興味深いのは、「完全な民主主義」は167カ国のうちわずか12%にとどまっているということだ。欧州諸国のほか、ニュージーランド、オーストラリア、カナダなど西洋の国々が占めているが、「完全な民主主義」のもとで生活する人口はわずか4.5%足らずだ。他方、中国に強く民主化を働きかけるその筆頭の米国は「欠陥のある民主主義」に分類されている。「欠陥のある民主主義」は韓国、日本、米国の順でランキングされている。
シンガポールは「混合政治体制」に属しているが、同国以外にもタイ、インドネシア、フィリピンがこれに属している。そして中国は「独裁政治体制」に属しており、ベトナム、ラオス、カンボジアもここに分類されている。いずれも私たち日本人が経済的結びつきを強くし、日頃から親しくしている国々だ。
■白か黒ではなく、変化をとらえるべき
この調査結果が示唆するのは、確かに民主主義は「人類共通の理想」だとはいえ、その国の政治体制を一気に転換させることはできないということだ。歴史や風土、社会や経済の影響を受けながら、長期的に変化を遂げていくのだろう。一方、マブバニ氏は著書で次のように指摘している。
「西洋のマインドは不自由な中国の人々が幸福である可能性を考えることができない。西洋は自由をイデオロギー的に理解し、また自由は絶対的な美徳だと認識しており、“半自由”などとは馬鹿げていると思っている。自由は相対的であり、実際に多くの形態を取り得るという考えは、彼らにとって異質なのである。しかし、こんにちの中国人の生活を20~30年前と比較すると、彼らははるかに大きい自由に到達した」
中国を白か黒かでとらえるのではなく、時々刻々と変化するその変化のありようをとらえるべきだ――そんな示唆ではないだろうか。ちなみに、マブバニ氏はポストコロナの世界動向について、2020年3月20日発行の米外交専門誌「フォーリン・ポリシー」でこう述べている。
「新型コロナは、米国中心のグローバル化から中国中心のグローバル化という、すでに始まっている変化を加速させるだけである」
■台湾を訪問して驚いたこと
古代中国には目上への敬意や若輩へのいたわりなど、人の道徳的義務を語る思想があった。個人の権利を声高に主張するのではなく「礼」を重んじるのは、「礼」がなくなれば人と人の間に保たれていた秩序が失われ、世の中が乱れるからだ。
人としての道徳的義務は現代の東アジア、東南アジアだけにとどまるものではない。インドやバングラデシュも同じだった。筆者は、コルカタ出身で東京に在住するインド人ファミリーと親交があったが、彼らが重んじるのも目上への敬意であり、若輩へのいたわりだった。イスラム教を信じるダッカ在住の若い世代にも、こうした観念は共通していた。
「礼譲(れいじょう)」という言葉がある。日本語でも中国語(北京語)でもほぼ同じで、「礼儀正しくへりくだった態度」(大辞泉)を意味するが、簡単に言えば、「相手に譲る」ということだ。共産主義の影響を受けなかった台湾では、人々が生活の中で「礼儀正しさ」や「譲り合い」の礼譲文化を実践している。
筆者は、2019年に台湾を訪問した際にこんな経験をした。台北市の新光三越百貨店の地下飲食街を訪れたとき、満席のフードコートで、空席を探す筆者に席を譲ってくれたのは、なんと小学校低学年の兄弟だった。食事を終え、夢中でゲームを楽しんでいた兄弟が、背後に人の気配を察したのか、サッと立ち上がって席を譲ってくれたのである。小さな子どもに席を譲ってもらうなどは、人生で初めての経験だった。

■目上への敬愛、真心のこもった接客…
翌朝、ホテルの部屋でテレビをつけると、3組の母娘がそれぞれに自慢話を競い合う番組を目にした。その中の1組の母親が、「うちは儒教や仏教の思想で子どもを育てました」と自慢げにコメントしたのには驚かされた。
台湾では「三字経」や「弟子規」を子育てのバイブルにするお母さんは少なくないという。「弟子規」は、難解といわれる中国の古典「四書五経」を子ども向けに要約し編集したもので、人としての徳目や、親や祖先など目上の人への敬愛を説いている。
高雄市の新幹線駅のインフォメーションセンターでは、若い男女2人の担当者が同時に起立して迎えてくれた。無料案内所なのに席を立って迎えてくれる、この「礼」には感動した。台北に戻る列車では、車内販売のワゴン車を押す女性の対応が心にしみた。期待していた名物のお弁当は品切れだったが、「申し訳ございません」と謝る彼女の表情から伝わってきたのは、「がっかりさせてごめんなさい」という相手へのいたわりの気持ちだった。
■中国から日本へ、日本から台湾へ
台北の友人は、「自分を低くして相手を立てる、自分が我慢することで相手を喜ばせる――これを生活の中で実践することで、『今日はいいことをやった』という幸せな気持ちになれるのです」と話していた。
台湾の政治家を祖父に持ち、自ら儒学的研鑽を積む法律家の高居宏文氏はこう語っている。
「台湾での『儒学の精神』は、1949年の国共内戦を経て蒋介石とともに台湾に渡りました、儒学を学んだエリートたちがもたらしたといわれています」
台湾は、1895年に日清戦争の講和条約(下関条約)により清国から日本に割譲され、1945年の敗戦まで半世紀にわたり日本が統治したが、当時の台湾では日本の民間人を通して「生活の中の儒学の実践」を吸収したとも言われている。高居氏は「日本が台湾を統治した時代、『自分はへりくだり、相手を立てる』という社会秩序を維持するために最も必要な在り方を、日本人が無意識にも生活の中で示してくれたのです」と話している。
日本では、江戸時代を通して武家を中心に学問としての儒学が取り入れられ、その後、明治時代には儒学の忠孝思想が取り入れられた教育勅語が1890年に公布された。中国で生まれた儒学が日本に伝わり、日本で受容された儒学はさらに台湾に渡り、今なお人々の生活や行動規範に影響しているのは大変興味深いものがある。
■伝統思想は失われると思ったが…
毛沢東が推し進めた文化大革命(1966~76年)によって、中国の伝統的な思想や価値観は破壊されてしまった。儒学思想もまた破壊の対象となった。しかしその後、1978年から始まった改革開放を経て、中国の価値観も大きく変わった。
中国の改革開放後に提唱された「中国の特色ある社会主義」は、マルクスレーニン主義、毛沢東思想に西側の資本主義的な市場経済概念を取り入れた中国共産党の公式思想だが、ここには政治、経済、思想文化、社会建設など多岐に及ぶ内容が、概念に基づき定義づけられている。
『中国特色社会主義綱要』(上海人民出版社、2013年)には、「文化大革命の中で伝統文化は前代未聞の危機に遭遇したが、伝統文化の価値の方向性、行動モデル、思惟方式は中国の政治構造と国家制度を形成するうえで重要な役割を果たした。<中略>我々は、孔子から孫中山(孫文)に至るこの貴重な遺産を継承しなくてはならない」とあり、現代の中国共産党が、儒学に見る伝統的価値観を肯定していることがわかる。
■近隣諸国は中国を慕うのか
一方で、一定の警戒心も見せている。同著は「権力の膨張をもたらし、越権現象がもたらされる」と指摘し、「トップの力が強すぎると、民主を推し進めることが不十分になる」ことが権力の行使と政府の統治にもたらす問題だと捉え、政治体制改革を経て徐々にこれを解決するべきだとしている。
図らずもここに書かれているように、中国は決して「民主化」を断念したわけではないことが見て取れ、また、上に立つ者に都合のいい解釈をさせないよう、バランスを取りながら、古代思想を取り入れようとしていることが伺えるのだ。
また、「西側においては権力に対する疑念の態度が、分権化された競争力ある政治システムの文化的基盤を築いた」と西洋の価値観についても言及する半面、「中国の伝統政治文化はこれとは異なり、信頼を基礎にしており、リーダーと導かれる者との間の信頼関係が、中国の民主集中制の政治制度モデルの文化的要素を作り出している」と主張している。
中国では、生活に余裕を持つ人が増えた2000年代以降に儒学思想や仏教思想への関心が高まった。現在もテレビやインターネットで、わかりやすく市民に解説する専門番組が普及しており、多くの国民がこれに関心を向けている。習近平国家主席ですら「弟子規」を勉強するよう呼び掛けた時期があった。
だが、現政権の昨今の対外政策に目を向ければ、香港問題、南シナ海問題、中印国境問題など、世界をざわつかせている。これでは「徳目」による政治という中国思想の原点から大きく軸足がズレているのではないかと、ハラハラさせられる日々だ。
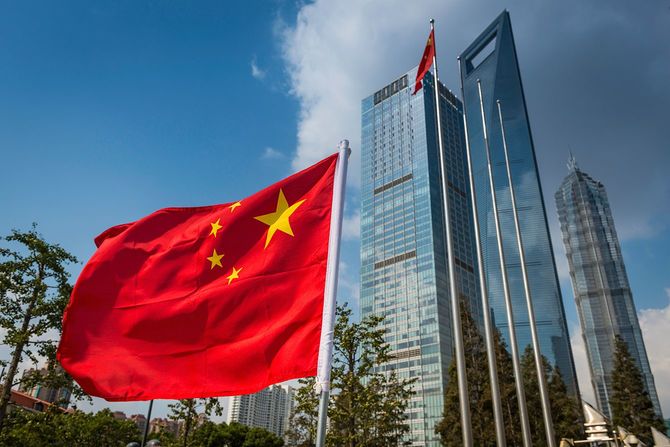
■「徳を以て民を治める」からは程遠い
孔子が発した言葉に「近き者説(よろこ)び、遠き者来たる」という一句がある。小説家の井上靖氏が描いた『孔子』には、「近い者が喜び懐き、その噂を聞いて遠くの者が自然にやって来る。そのような政治ができたらそれが一番いい」――とある。周の武王、文王は人徳があったため、周りの人々が自然に近寄ってきたというが、その政治を「王道政治」とするならば、中国に身構える周辺諸国さえ存在する今の中国を見れば、それは「王道政治」ではなく、「覇道政治」だといえる。
ましてや中国の現政権は、インターネット上の庶民の日常会話ですらあまりに敏感で、少しでも政権に不都合な発言でもあればただちに封じ込めてしまう。徳を以て民を治めるといった度量のある政治からは程遠い。
ちなみに、前出のリー・クアンユー公共政策学院院長のキショール・マブバニ氏は2020年6月8日、米国の雑誌「The National Interest」のWEB版で、「中国共産党の主な目的は、世界規模で共産主義を復活させることではなく、世界最古の文明を復活させることだ」とコメントしている。
■内向きな愛国主義で終わるべきではない
中国の文明といえば漢字がある。「仁」という字は、人偏(にんべん)に「二」と書くが、『孔子』(井上靖著)には、孔子の言葉としてこう書かれている。

「親子であれ、主従であれ、旅で出会った未知の間柄であれ、人間が二人、顔を合わせればその二人の間にはお互い守らなければならぬ規約とでもいったものが生まれてくる。それが仁というものである」
「信」については、人偏に「言」と書くが、「人間の口から出す言葉(言)は、真実でなければならない」という意味だ。
世界の四大文明の中の一つである中国文明だが、紀元前の周の時代には、のちに東アジア各国に大きな影響をもたらす思想哲学が生まれた。「礼」や「仁」、また「信」という漢字に込められたのは、これを失えば世の中が乱れ、逆にこれを重んじれば社会秩序は維持できるという儒学思想である。紀元前に生まれた古い思想ではあるが、今なお東アジアに共通する価値観であり続けているのだ。
中国の現政権が目指している「中華民族の復興」は、単なる内向きな愛国主義で終わるべきではない。西洋の価値観がフィットしないというならば、中国が行うべきは、中国古代の思想の中に、哲学的な深み、あるいは人類の普遍的価値を探求することではないだろうか。少なくとも、中国共産党の性格が時代とともに変化し、「人倫」と「ルール」を以て国を治める価値観を生み出せば、世界平和の維持に大きな貢献をもたらすはずだ。
----------
フリージャーナリスト
東京都出身。フリージャーナリスト。アジア・ビズ・フォーラム主宰。上海財経大学公共経済管理学院・公共経営修士(MPA)。1990年代初頭から中国との往来を開始。上海と北京で日本人向けビジネス情報誌を創刊し、10年にわたり初代編集長を務める。約15年を上海で過ごしたのち帰国、現在は日中のビジネス環境の変化や中国とアジア周辺国の関わりを独自の視点で取材、著書に『インバウンドの罠』(時事出版)『バングラデシュ成長企業』(共著、カナリアコミュニケーションズ)など、近著に『ポストコロナと中国の世界観』(集広舎)がある。
----------
(フリージャーナリスト 姫田 小夏)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
先進国が掲げる「法の支配」のダブルスタンダード 西洋基準たる「万国公法」の呪縛から脱する時だ
東洋経済オンライン / 2024年4月16日 9時0分
-
ロシアに無知だったEUはソ連のように自壊する ロシアを民主主義の反面教師としてきた欧州のツケ
東洋経済オンライン / 2024年4月11日 8時0分
-
三浦瑠麗氏の「メディア復帰」問題なしか 関係者も舌を巻いたパネルディスカッションの仕切りぶり
東スポWEB / 2024年3月25日 6時18分
-
三浦瑠麗氏 安全保障ディスカッションに登場「世代を超えてもっと話し合って」
東スポWEB / 2024年3月24日 17時32分
-
民度があり、豊かな国でなければ「民主主義」はできない 「民主主義サミット」が韓国で開幕
ニッポン放送 NEWS ONLINE / 2024年3月21日 17時50分
ランキング
-
1【速報】堀江容疑者の自宅に家宅捜索 日本橋高島屋“1000万円超の純金茶わん”窃盗事件 警視庁
TBS NEWS DIG Powered by JNN / 2024年4月15日 23時6分
-
2新NISAで50~60代が“やってはいけない”投資の失敗例。「年利3%で安定的に運用できる」おすすめの投資信託も
日刊SPA! / 2024年4月15日 8時51分
-
3コロナワクチン心筋炎注意 厚労省、子どもで2例報告
共同通信 / 2024年4月16日 0時37分
-
4盗まれた“純金の茶わん”見つかる 事件後の様子は…容疑者の父親が語る
日テレNEWS NNN / 2024年4月15日 20時21分
-
5またも発生したメガソーラー火災 メンテナンス人手不足などリスクも浮き彫りに
産経ニュース / 2024年4月15日 19時18分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください









