月収600万円でも手元にはほとんど残らない…NHK大河の舞台「日本三大遊廓・吉原」で働く花魁の"懐事情"
プレジデントオンライン / 2024年12月14日 18時15分
※本稿は、河合敦『蔦屋重三郎と吉原 蔦重と不屈の男たち、そして吉原遊廓の真実』(朝日新聞出版)の一部を再編集したものです。
■江戸時代の男性たちのパラダイス
江戸幕府が公認していた遊廓の代表は、江戸の吉原、京都の島原、大坂の新地である。これらを俗に三大遊廓と呼んだ。
遊廓の周囲は、堀や塀でしっかり囲まれていた。つまり、お城の廓(くるわ)(曲輪)と同じだから遊廓というのだ。ただ、遊女が集まっている場所なので、遊廓という名称が付いたらしい。別名を色里、くるわ、遊里などともいい、男たちにとっては日常では味わうことのできない最高の快楽が堪能できる、まさにパラダイスそのものだった。
しかも一歩、遊廓内へ足を踏み入れると、江戸時代の厳しい身分の上下関係が消え失せたのである。色里では、大名だろうと商人だろうと関係ない。どれだけ気前よく金銭をばらまくか、通や粋といわれるように、その言動や振る舞いがいかに洗練されているかが客の価値すべてを決めたという。非常に特殊な世界だったわけだ。
■遊廓開設にあたって幕府が求めた三条件
戦国時代末期、京都や大坂などには、集まる男たちをあてこんで遊女屋が林立し、勝手に客を取って遊ばせるようになった。風紀が乱れるということで、豊臣政権は遊女屋を一カ所に集めたが、その方針を江戸幕府も踏襲したのである。
天正18年(1590)、小田原北条氏を倒した豊臣秀吉は、その旧領を徳川家康に与え、江戸を拠点にしろと命じた。秀吉の死後、関ヶ原合戦で覇権を握った家康は、慶長8年(1603)、朝廷から征夷大将軍に任じられて江戸に幕府を開いた。
家康は江戸城と城下を天下普請(諸大名に命じる土木工事)によって大改修をはじめたので、各地から労働者たちが江戸に集まりはじめた。そんな男たちを当てにして、慶長17年(1612)(異説あり)、日本橋の葺屋(ふきや)町に初めて遊廓が誕生したといわれる。それが吉原である。
遊廓の設置を申請したのは、遊女屋の代表・庄司甚右衛門であった。幕府は、甚右衛門に遊廓の開設を認める代わりに「客の逗留は一昼夜に限る。人身売買の不法行為を防止する。犯罪者の逮捕に協力する」という三条件をつけたといわれる。
■明暦の大火を機に、浅草へお引越し
江戸はその後もますます発展して人口も爆発的に増加したので、吉原遊廓も大繁盛となった。ところが、である。明暦3年(1657)の明暦の大火により、江戸の市街地の大半が焼失し、このとき吉原も焼けてしまったのだ。

日本橋界隈は江戸城の大手に近く、水陸の交通の要衝であった。そのため魚河岸、金座・銀座があり、大店(おおだな)も集中していた。そんな江戸の中心地だったので、幕府はさらなる発展をはかるため、大火を機に市街地の整備に乗り出した。
そうしたなか、売買春を行う一大歓楽街たる遊廓が日本橋地域に位置するのは、風紀を乱す原因になると判断したのだろう。江戸郊外の浅草へ移されることに決まったのである。
当時の浅草一帯は江戸の郊外で田園も多かった。そんな2万坪に及ぶ地域を四角に区切り、田圃を埋め立てて新たに遊廓を造成したのだ。以後、葺屋町の吉原跡を元吉原といい、浅草のほうは新吉原と呼ぶようになった。
■1年間で67人の僧侶が「女犯」で捕まった
新吉原は江戸の中心部から外れたが、遊びに行くには徒歩や乗り物(馬や駕籠)以外に、舟を使う場合も多かった。大川(隅田川)沿いの船宿(休憩所のある船の貸し出し業者)に入り、そこで小舟(猪牙舟(ちょきぶね))をチャーターして川をさかのぼり、山谷堀(さんやぼり)から陸へ上がって日本堤を通って新吉原へ向かうのだ。
日本堤で歩いていると知人に会うこともあったが、そこはそれ、互いに知らないフリをしたのだった。なかには本人とバレぬよう変装する者もいたそうだ。とくに僧侶などは、坊主頭だから「俺は医者だ」と身分を偽ったり、カツラをかぶったりして吉原通いに精を出したという。しかしときたま町奉行所の一斉摘発が入り、のんびり妓楼に泊まっていると、逮捕されることもあった。
寛政8年(1796)には67人、天保12年(1841)には58人の僧侶が、吉原で女犯(にょぼん)の罪で捕まり、江戸の日本橋で晒されている。
■全盛期には7千人以上の遊女が働いていた
さて、いよいよ新吉原に到着する。ただ、遊廓の周りはぐるりとお歯黒溝と称する堀がとりまいていて、とても飛び越えることができない幅(一説には9メートル)がある。しかも出入り口は、大門と呼ぶ一カ所のみであった。
いうまでもなくこれは、遊女の逃亡を防ぐための措置であり、同時に犯罪者の侵入を防止する目的もあった。大門を入ると、すぐ左手に面番所が設置されている。番所内には町奉行所から出張してきた役人たちがおり、客の出入りに目を光らせている。槍や長刀などの武器は持ち込むことはできなかったし、一般の女性も客として原則入ることはできない(花見の時期などは見物が許された。また、許可証があれば特別に入れた)。
大門から真っ直ぐに大きな通り(仲之町)が中央を貫き、左右には引手茶屋がずらりと並んでいる。吉原全体は、江戸町・京町・角町・揚屋町・伏見町などいくつかの区画に分けられ、大通りから一歩横道に入ると、今度は妓楼がずらりとならび、一階の張見世(はりみせ)では格子越しに遊女たちが座っている。全盛期(19世紀前半)には、遊女が6、7千人以上おり、遊女以外の労働者たちも5千人以上いたという。
■高級遊女になるためには教養もマナーも必須
なお、遊女と一口にいっても多くの階級に分かれていた。最高ランクの太夫、その下に格子、そして散茶、切見世など、しかも時代によって呼び方や階級数は変化する。たとえば最高級の太夫は、享保期は3800人の遊女の中でわずか4人だけだったが、重三郎の時代の明和年間(1764〜1772)になると消滅し、散茶が最高位となる。
ちなみに花魁と呼ばれるのは太夫だけだったが、吉原から消えたこともあり、やがて高級な遊女一般をさす言葉になった。
花魁のような高級遊女を相手にできるのは「上客」と呼ばれる金持ちだけだった。豪商や大名とその重臣が大半だったから、教養があり芸事にも詳しい必要があった。だから遊女も格が高くなると、歌や踊りだけでなく、和歌や俳句、茶道や花道にまで通じていた。また、儒学や絵画、囲碁や将棋にいたるまで豊富な知識を有していた。
花魁は客を不快にさせないよう、体臭には気を遣い、悪臭の源になる生ものや臭い野菜は一切食べず、香料の入った湯船に長時間入り、常に匂い袋を身につけた。顔に汗をかくこともタブーとされ、暑い夏に打掛を重ね着しても、汗をかかない鍛錬をしたといわれる。だからこそ、どんな客も満足させることができたのである。
■吉原で遊ぶにはいくら必要だったのか
さて、そんな花魁と遊ぶためには、客は揚げ代として一両二分払う必要があった。
それがどれくらいの価値になるのかということだが、じつは現代の金額に換算するのはほとんど不可能なのだ。江戸時代は260年以上続いた。同じ一両小判でも、時期によって金銀の含有量が大きく違う。また、何を換算の指標にするかでも、大きく変わってくる。たとえば、大工や職人の賃銀を例にとって考えて見よう。
江戸時代、一両(=四分)で23人の大工を一日雇えたという。いまの大工の日当は2万円ぐらいなので一両二分は70万円ちかくになる。ところが米の値段で換算すると、10万円ほどなのだ。同じ一両二分なのに70万円と10万円では、あまりにかけ離れている。それを理解してもらったうえで、米の値段に換算して話を進めていこう。
さて、初日は揚げ代として10万円を支払った。なのに、その日は花魁と床入り(性行為)することはできない。それはいくら金を積んでも無理。規則で少なくとも三度は足を運ばなくては床入りできないのだ。
■現代のぼったくりバーも驚くチップ相場
吉原では模擬的に夫婦のちぎりを結ぶという過程をとる。男と女が出会い、親しみ、恋に落ち、性愛関係になるという手順を踏む必要があるのだ。さらに意外なことは、客が支払った揚げ代は、花魁の懐には一銭も入らないことだ。すべて店の収益になってしまうのだ。
花魁たちの収入は、床入りした際に客から貰う「床花(とこばな)」だった。これは、いまでいうチップだ。つまり、三回目からようやくお金が入ってくる。これを俗に「三会目」といい、客と馴染みになるのだ。
もちろんそれからも花魁たちは客がずっと訪れてくれるよう、あの手この手を考える。思わせぶりな言葉や別れの涙は当たり前、ラブレターもありふれた手段。場合によっては自分の体に刺青で相手の名前を刻んだり、愛している印に小指を切り落として贈ったりする。生活がかかっているので必死だ。

さて、こうして花魁がもらう床花だが、その額はなんと揚げ代の4〜5倍。米の金額に換算しても一晩に40万〜50万円だ。大工の手間賃換算なら280万〜350万円になる。いまの高級クラブや風俗店、いやぼったくりバーでも、さすがにここまではぶん取られないだろう。ただし、明確な規定はないから、上客はもっと気前よく金を出したようだ。
■月収600万円でも、出費で消えてしまう
とはいえ、床花すべてが花魁本人の懐に入るわけではない。2割は店(妓楼)へ差し出し、もう2割は店のスタッフたちに渡す決まりになっていた。実質的に手にできるのは6割程度。つまり、いまの金額(米に換算)にして30万円ほどが実収入だったわけだ。
しかも花魁は日に一人しか客をとらず、しかも毎回床入りするわけではないので、その月収はおよそ米換算で600万円程度と考えてよい。ものすごい高収入のように思えるが、じつは花魁の手元に金はほとんど残らなかった。というのは、とにかく出費が多いのだ。きらびやかな衣裳、髪飾り、所有する座敷の家具や布団にチリ紙まで、すべて自前だったのである。
さらにお付の新造(しんぞう)や禿(かむろ)<といった若い娘の小遣い、客への贈り物代などがかかったのだ。
■売られた女性たちが生涯過ごす「苦界」
ただ吉原の遊女は花魁ばかりではない。むしろ下級遊女のほうが圧倒的に多く、客をふったり選んだりすることはせず、わずかな金銭で身をまかせた。一晩で複数の客をとる遊女もいた。花魁も重三郎の時代には、初会で床入りすることも珍しくなかったらしい。
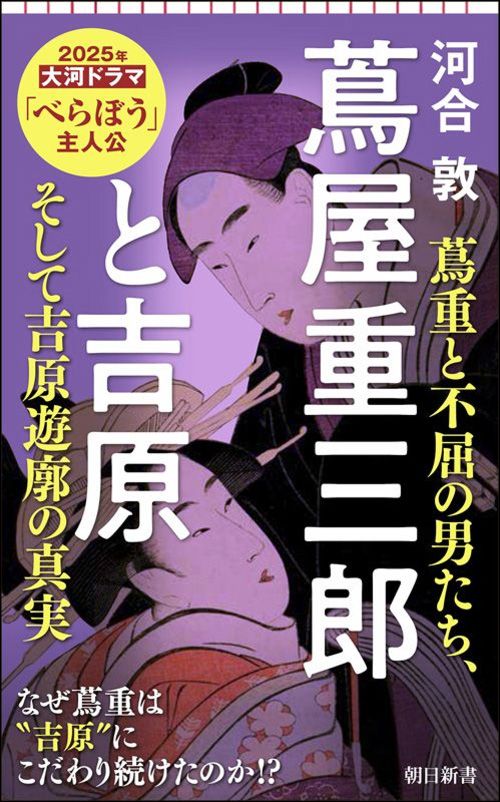
ところで吉原の遊女たちはみな、共通の話し方をした。いわゆる「ありんす」言葉だ。これはお国なまりを隠すためだといわれる。彼女たちの多くは、子供のとき親に売られた地方農民の娘である。
27歳になった正月、年季が明けて晴れて自由の身になれたが、その多くは性病や感染症でそれ以前に亡くなってしまい、そうした病死者は近くの浄閑寺へ葬られた。同寺で弔われた遊女の数は、一説には1万5千、あるいは2万人にのぼると推定されている。一生、廓の中で生きていくのが定めだったのだ。
男にとっては憧れのパラダイスだったかもしれないが、遊女たちにとって新吉原はまさに苦界だったのである。
----------
歴史作家
1965年生まれ。東京都出身。青山学院大学文学部史学科卒業。早稲田大学大学院博士課程単位取得満期退学。多摩大学客員教授、早稲田大学非常勤講師。歴史書籍の執筆、監修のほか、講演やテレビ出演も精力的にこなす。著書に、『逆転した日本史』『禁断の江戸史』『教科書に載せたい日本史、載らない日本史』(扶桑社新書)、『渋沢栄一と岩崎弥太郎』(幻冬舎新書)、『絵画と写真で掘り起こす「オトナの日本史講座」』(祥伝社)、『最強の教訓! 日本史』(PHP文庫)、『最新の日本史』(青春新書)、『窮鼠の一矢』(新泉社)など多数
----------
(歴史作家 河合 敦)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
中村勘九郎、父・勘三郎さんが演じた蔦重に挑む 『きらら浮世伝』が歌舞伎座に
ORICON NEWS / 2024年12月12日 11時43分
-
江戸時代の遊女にまつわる“間違ったイメージ”とは? 悲劇だけではなかった/『禁断の江戸史』より
日刊SPA! / 2024年12月11日 8時47分
-
遊女は「人参10本分の値段」だが、美少年なら30万円…次のNHK大河の見どころ「江戸の風俗街」の驚きの階級社会
プレジデントオンライン / 2024年12月1日 18時15分
-
NHKは「吉原の闇」をどこまで描くのか…次の大河の舞台「江戸の風俗街」で働く遊女4800人の知られざる生活
プレジデントオンライン / 2024年11月30日 18時15分
-
『NHK大河ドラマ 歴史ハンドブック べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~ 蔦屋重三郎とその時代』11月29日発売
PR TIMES / 2024年11月29日 12時15分
ランキング
-
1知人が結婚 「私も!」と意欲が高まる人と「先越された」とプレッシャーを感じる人 独身男女543人の本音
まいどなニュース / 2024年12月14日 11時45分
-
2飛行機代0円、無料宿泊……旅のプロに聞いてみたら、旅費「節約」テクがこんなにもあって驚いた
オールアバウト / 2024年12月14日 18時30分
-
3「スタッドレスタイヤ」溝が残ってるのに“使用NG”なことがある!? 寿命は何年? 覚えておきたい「危険なタイヤ」の見分け方とは?
くるまのニュース / 2024年12月13日 21時10分
-
4許せない!嫁の実家近くに「30年・月15万円返済」で新築戸建てを購入した〈月収45万円・40歳のサラリーマン家族〉に、67歳の姑の怒り爆発の「トンデモ理由」
THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年12月14日 8時15分
-
5「写真どおりの髪型じゃない!」美容師に“無料にしろ”と主張する女性客が沈黙したまさかの理由
日刊SPA! / 2024年12月13日 8時53分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください











