ボイコットが意味したもの――NBA選手たちが人種差別と闘い続ける理由【大西玲央コラム vol.2】
NBA Rakuten / 2020年9月19日 12時0分
シーズン再開後、一時的にボイコットが決行されたNBA。選手たちが戦っている”相手”とは、そして声を上げる理由とは――
イースタン・カンファレンス準決勝でマイアミ・ヒートに敗退し、ミルウォーキー・バックスがプレイオフから姿を消した。レギュラーシーズンをトップで駆け抜け、優勝候補として考えられていただけに、驚きも大きかっただろう。予想外の早期敗退とはなったものの、バックスがリーグに、ひいてはスポーツ界に大きな足跡を残したことには変わらない。現地8月26日のボイコットだ。
バックス対オーランド・マジックの第5戦開始直前に、バックスの選手たちはボイコットを決断。結果、その日に行なわれるはずだったプレイオフの3試合が延期となった。その波はNBA全体、さらにはWNBA、MLB、MLS、NFL、NHLにも波及。日本でもテニスの大坂なおみ選手のボイコットによって、その賛否と共に大きく取り上げられた。
NBAでのボイコットは今回が初めてではない。1959年に、当時ミネアポリス・レイカーズのエルジン・ベイラーら3人の黒人選手が、試合を行なうウェストバージニア州のレストランで入店拒否されたことを受けて、出場を辞退している。さらに1961年には、ボストン・セルティックスの黒人選手数人がケンタッキー州のコーヒーショップへの入店を拒否されたことで、リーグMVPのビル・ラッセルを筆頭に黒人選手が試合をボイコット、白人のチームメイトだけがプレイをした過去がある。
いずれも、それぞれの身に降りかかったことを受けてのボイコットだったが、今回のように社会問題に対する抗議が目的で試合が取りやめとなり、リーグが停止状態に持ち込まれたのはリーグ史上初めてだった。
その後、3日間の停止期間を経てNBAは再開。大坂選手も、大会側が彼女の主張に寄り添うように「人種差別や社会的な不公平に抗議するため」として当日の試合実施を見合わせたことで、ボイコットを撤回、翌日に出場する運びになった。そして、今でも選手たちによる主張は続いている。プレイオフ再開の条件には、黒人に対する差別や警察による暴力といった社会問題に対する、リーグやチームオーナーの積極的な反対活動が掲げられている。そして大坂選手がその後優勝した全米オープンで、警察による暴力の被害者となった名前を掲出した7枚の黒いマスクを着用していたのも大きな話題となった。
アスリートが声を上げ続けるワケ
「スポーツに政治を持ち込むな」
今回の件で度々目にする反対意見だ。これは日本だけではなく、アメリカでも変わらない。2018年2月、レブロン・ジェームズがドナルド・トランプ大統領に関して否定的な発言をしたことを受けて、FOXニュースのキャスターを務めるローラ・イングラムは自身のニュース番組で件の発言を取り上げ、「ボールをつくだけで1億ドルもらえる人に政治的なアドバイスを受けたくない」と述べ、「黙ってドリブルしてろ」という言葉で締めている。スポーツ界を超越した影響力を持つと言われるレブロンほどの存在でも、こうした意見を投げかけられるのだ。
今の世代の選手たちは、確かにこれまでと比べて政治的な発言が多くなっている印象はある。ジョージ・フロイド氏の暴行死から発展したデモ活動にも、多くのNBA選手が参加した。ではなぜ選手たちは「スポーツに政治を持ち込む」のか。なぜ声を上げ続けるのか。平たく言えば、「できるから」なのだが、それがどういうことなのか、紐解いてみよう。
まずは今回のボイコットに至った経緯を振り返っておきたい。現地8月23日夕方に、ウィスコンシン州ケノーシャの警官が、黒人男性のジェイコブ・ブレイク氏に向けて背中から7発の銃弾を撃ち込む事件が発生。「BLACK LIVES MATTER」という文字をコート上に大きく掲出し、ジャージーにも社会正義のメッセージを背負うなど、一種の使命感を持ってNBAの再会に臨んでいた選手たちは、この事件を重く受け止めていた。
翌日24日のメディア対応でバックスのジョージ・ヒルがこの件を憂い、25日の試合後にはロサンゼルス・クリッパーズのドック・リバースHCが涙ながらにこの現状を訴えるなど、選手やコーチたちが動揺していたのは明らかだった。

25日の夜、ケノーシャでは事件に対する抗議活動が行なわれていた。その最中、自警団を名乗るカイル・リッテンハウスという17歳の白人少年が、自身が持ち込んだアサルトライフルのAR-15で2人を殺害、1人に重傷を負わせた。SNSに拡散された動画では、殺したあとも彼は平然と歩き回り、ライフルを持った状態で警官の横を通り過ぎるのが映し出されていた。彼がイリノイ州の自宅近くで第1級殺人容疑で拘束されたのは翌日のことだった。
そして26日、この一連の事件を重く見たヒルは、第5戦の出場を辞退するとチームに申し出る。当初ヒルは単独でボイコットを行なうつもりだったが、ヒルの決意を試合開始直前に知ったチームメイトたちはロッカールームで話し合った結果、チームとしてボイコットすることを決断。3勝1敗とリードしていたバックスは、この試合の不戦敗を受け入れるつもりだったのだ。バブルの中で抗議活動に参加ができない今、試合を捨ててでも抗議をしたいという一心で。
しかしバックスの「自分たちは不戦敗でいい」という申し出をマジックが受け入れず、むしろ「気持ちは一緒」とバックスとともにボイコットを選択し、試合そのものが延期された。その日開催される予定だった残りの2試合も延期となり、ついには選手全体によるボイコットへと発展した。
選手間でも意見が分かれたボイコット
バックスがボイコットを行なったのは、偶然彼らがその日の1試合目だったからではない。事件が起きたケノーシャとミルウォーキーがあるのは、同じウィスコンシン州――アメリカ合衆国で最も人種的な分離が大きい州という研究発表がある――なのだ。2年前には、現在もバックスでプレイするスターリング・ブラウンが駐車違反を理由に、複数人の警官に囲まれ暴行を受けた。その数年前にも、選手が黒人であることを理由に宝石店で警察を呼ばれている。
バックスにとって、今回の事件は決して他人事ではなかったのだ。次は自分の家族・友人や自分自身がターゲットになるかもしれない。多くの黒人が感じている“恐怖”に近い感情と最も近しいところにいるのが、バックスの選手たちだったのだ。だからこそ、今回のボイコットは計画的なものではなく、その場の感情で突発的に生まれた。
試合のボイコットは、選手たちからすれば最終手段のようなものでもある。出口の見えないままボイコットに突入したことに、怒りを表す選手もいた。バブル内の選手ミーティングでは、再開への基準を作らないまま始めたことを問題視し、リーグで一番影響力のあるレブロンを筆頭に反発があり、一時は選手同士での分断が生じていた。
その後、選手たちはそれぞれが夜通しで話し合いを行ない、翌27日朝の全体ミーティングでプレイを再開させる方向で合意。そして28日にはNBAとNBA選手会による共同声明で、プレイオフを再開させることが発表された。早期決着できたのは、両者の間で「選手、コーチ、チーム代表とともに、リーグが投票行動の向上、市民関与促進、有意義な警察・刑事司法改革などを含む幅広い問題に取り組む」、「リーグのチームが本拠地として使用するアリーナを、投票所として使用するために、それぞれの地元当局と連携する」、「プレイオフの放送を通して、投票に関する知識を深め、市民関与を促進する」という、リーグとチームが選手たちに寄り添った合意がなされたことが大きい。

これらの中に多く組み込まれた“投票”というキーワードは、極めて重要なものだ。投票できる権利なんて、日本人からしてみれば当然のものだ。しかしアメリカでは、投票したくてもできないという問題が存在する。黒人の多い貧困地域などでは、そもそも投票所がまともに運営されていないのだ。「現場に不満なら投票して変化を勝ち取れ」とよく言われるが、そのスタートラインにすら立てていない人が無数にいる。しかもそれが、投票させないために作為的に行なわれている地域も多々ある。まずそこから変えていかなければならない。NBA選手たちの主張は、そこを基軸に作られている。
「プレイを続けながら抗議をすべき」という意見
そこで出てくるのが、先述の「スポーツに政治を持ち込むな」だ。
スポーツは多くの人にとって日常からの逃避であり、楽しむためにあるというのがその主な主張だ。「バスケットボールが見たいだけ、政治的主張など見させられたくない」という声は大きい。しかし、選手たちからすればこれは政治的主張などではない。生きるか死ぬかの問題なのだ。「バスケットボールが見たいだけ、お前らが殺されようが知ったことではない」と言われているようなものだ。
なお、日本でのNBAのボイコットに対する受け止めは、大方が「よくわからないし自分たちにはあまり関係のない問題なので首は突っ込まないけど、残念だ」というものが多かったように感じる。もちろん、日本では黒人に一度も会うことなく一生涯を終える人も多くいるだろうし、どういった仕打ちを受けているのかは想像し難いところがあるだろう。そんな人たちでも、人権を無視され、日本では困った時に頼れる存在の警察に怯えて生きるという毎日を想像すれば、イメージが湧くのではないか。本来自分の味方であるべき存在が、自分を守るどころか攻撃する敵だった時の絶望感を想像してみて欲しい。
大坂なおみ選手への一部の反発を見る限り、「自分たちにはあまり関係のない問題」ではもはや無いと私は感じている。「黒人としての主張ばかりで、日本人としての主張が無い」、「日本のためには何をやった」という声を見るが、大坂選手は黒人の日本人だ。本来なら分けて考える必要性が全くないことに対して、憤慨している意見が多く散見される。ワシントン・ウィザーズの八村塁がBLMの抗議活動に参加した時も同様だった。

「プレイを続けながら抗議をすべき」という意見も多い。ボイコットなど意味はなく、プレイする姿勢で世間に訴える方が心に刺さるというものだ。当初、レブロンもこの想いでシーズン再開に臨んでいたわけだが、結果は見ての通りだ。プレイをしながらの抗議は、今までも常にしてきた。世間がそこに目を向けていなかっただけである。だからこそ、今回のボイコットでは、プレイを止めてまで抗議をする必要があった。結果的に世界中がこの話題を取り上げ、意見の衝突はあるものの話し合いが行なわれている。それだけのためだとしても、ボイコットは必要なものだったと言えるのでは無いだろうか。
なぜ選手たちは「スポーツに政治を持ち込む」のか。なぜ声を上げ続けるのか。それは、単にできるようになったからだ。400年近く、黒人差別に対する抗議は続いている。少しずつ、権利を勝ち取っているのだが、その度に反発が起きている。今回は警察組織という絶対的な正義に切り込んでいるため、その反発も大きい。
NBA選手だからこそ届けられる声がある
しかし、それでも選手たちは声を上げ続ける。「大金を貰ってる金持ちが差別だと主張しても意味がない」とよく言われるが、むしろ逆だ。NBA選手の多くは、幼少期を貧しい黒人地域で過ごしている。ドラッグ、ギャング、殺人などを日常的に見る世界だ。そこで挙がる声など、どこにも届かない。バスケットボールに打ち込み、必死に上を目指し、世界で450人しか入れないNBAにようやく辿り着き、世界中の子どもたちの憧れの存在となって、ようやく自分の声を聞いてもらえる権利を手に入れたのだ。かと思えば、声を発すれば「アスリートは黙っていろ」と押し潰される。こんな理不尽、選手たちが納得するはずがない。だからこそ、彼らは声を上げ続けてきたのだ。
大坂なおみ選手も繰り返し言っていることだが、これは政治ではなく人権問題だ。疑問を持つべきは、黒人差別や警察による暴力が「政治」として一括りにされることだろう。今回のボイコットは、ジェイコブ・ブレイク氏の銃撃事件に対するものではない。事件はあくまできっかけで、抗議の本質は、選手たちが何年も声を上げ続けてきたことの延長にある。20代、30代の若いアスリートたちが、声を上げ続けないと注目されないというこの状況は、決して良いものではない。なぜ彼らがその重荷を背負わなければならないのか。少しでも、彼らの肩の荷を下ろすことができないだろうか。
日本にいる人にとって、選手の活動に募金をするなど直接的な手法はあるにしても、できることは少ないかもしれない。ただひとつ、確実にできるのが、この問題をしっかりと認知すること。「関係ない、興味がない」と遠ざけるのではなく、本質を理解しようとすることだ。「スポーツを見るためにそこまでしたくない」と言われればそれまでだが、もはや黒人の差別問題はスポーツだけではなく、自分たちの生活レベルでも理解すべき時代なのである。
大西玲央:アメリカ・ニュージャージー州生まれ。『NBA.com Japan』『ダブドリ』「NBA Rakuten」などにライターとして寄稿。NBA解説、翻訳、同時通訳なども行なっている。訳書に『コービー・ブライアント 失う勇気』『レイ・アレン自伝』など。近年は、NBA選手来日時の通訳をNBA Asiaより任され、ダニー・グリーン、ドレイモンド・グリーン、レイ・アレン、ケンバ・ウォーカー、トニー・パーカーといった数々の選手をアテンド。
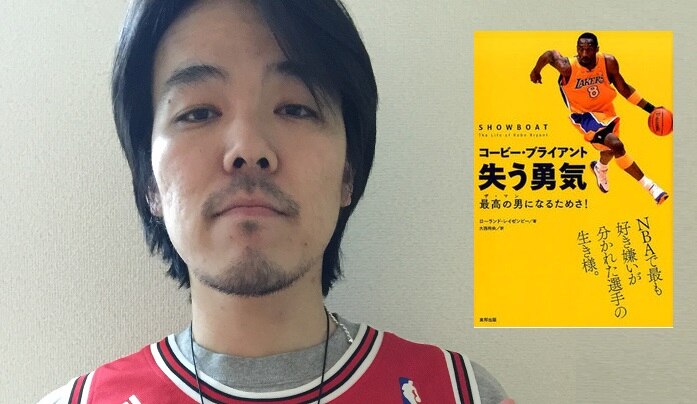
(C)2020 NBA Entertainment/Getty Images. All Rights Reserved.
この記事に関連するニュース
-
【無料配信】“ダブルエース”vs“プレイオフ・ジミー”、東の第7シードを懸けて激突!【4/18(木)午前8時 ヒート対76ers】
NBA Rakuten / 2024年4月17日 12時0分
-
殿堂入り選手シャキール・オニールはプレイオフで”古巣”推し「ヒートとジミー・バトラー抜きには語れない」
NBA Rakuten / 2024年4月13日 9時37分
-
フェネルバフチェ巡る騒動が頻発のトルコ、残りシーズンは重要な試合のVARに外国人審判員を採用へ
超ワールドサッカー / 2024年4月12日 22時15分
-
アンソニー・デイビスが約52分プレイ レブロン・ジェームズ不在のレイカーズを勝利に導く
NBA Rakuten / 2024年3月28日 1時0分
-
レイカーズのレブロン・ジェームズが次戦のバックス戦を欠場か
NBA Rakuten / 2024年3月26日 9時39分
ランキング
-
1引退発表の長谷部誠 日本のファンに向けて動画でメッセージ「まだありがとうとは言いません」
スポニチアネックス / 2024年4月17日 21時42分
-
2イチロー先生 おこづかいUPの交渉術は「キラーフレーズ」 現役時代「給料10倍になりました」
スポニチアネックス / 2024年4月17日 18時40分
-
3大谷翔平がリーグ最多安打に 3安打固め打ちでベッツに並ぶ、イチロー以来の快挙も
Full-Count / 2024年4月18日 7時18分
-
4【引退会見内容】長谷部「いつかその瞬間が来るに違いないと…」「まだ思い出に浸りたくない」
スポニチアネックス / 2024年4月17日 21時36分
-
5内田篤人氏、現役引退を表明した長谷部誠から連絡受けたことを明かす「内田と違い怠けずに…」冗談を交えねぎらう
スポーツ報知 / 2024年4月17日 22時57分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください









