「これからは個の時代」そう言って会社を辞めた人に待ち構える悲惨な末路
プレジデントオンライン / 2020年12月14日 11時15分
■会社は「儲けさせてくれる社員」しかいらない
コロナ禍で景気が急速に減退する中、大企業においても人員整理、リストラの動きが活発になってきた。
電通では、11月に40代以上の社員を対象に、正社員を業務委託契約に切り替える制度が導入された。タニタでも従前より正社員の一部を業務委託に切り替える制度が導入されている。
会社にとって、正規雇用の社員を解雇するのは極めてハードルが高いが、業務委託契約を解除するのは極めて簡単なのである。この制度の目的が「会社に利益をもたらしてくれる=儲けさせてくれる社員しかいらない」という点にあることは明白であろう。
経団連も、従前から、「メンバーシップ型雇用からジョブ型雇用への転換」をメッセージしている他、トヨタの豊田章男社長も「終身雇用を守っていくのは難しい」というかなり踏み込んだ発言をしている。
コロナ禍において、このトレンドがますます加速していくことは、もはや疑いようがない。これからは社員の中でも「黒字社員」と「赤字社員」、「儲けさせてくれる社員」と「損をさせられる社員」に仕分けられていくであろう。
■会社よりもインフルエンサーに依存するほうが危険
前述のような状況下で、いわゆるビジネスインフルエンサーが「個の時代」などといったキャッチフレーズを掲げ、「任意のスキル(YouTube、プログラミング、ブログなど任意のバズワード)を学べば個人で食っていける」「企業に依存する生き方はむしろ危険」というような主張を行っている。
そのような主張につられてオンラインサロンや高額なスクール費用に課金を行い、安定したキャリアを投げ出す人も後を絶たない状況である。
しかし、少し考えてみると、その業界の収益性というのは、基本的に需給によって決まるので、インフルエンサーが「Xは儲かる」と言って煽った瞬間に人が殺到し、一気に儲からないビジネスになってしまうのが基本である。
従って、会社に依存するのも危険だが、インフルエンサーに依存するのはより危険であるとすら言える。
■インフルエンサーからは「信者ビジネス」を学べ
では、インフルエンサーから学ぶべきものが無いかというと、全くそんなことはない。

インフルエンサーの掲げる「個人のスキルで食っていく」という主張を真に受けるのではなく、逆に、その事業構造自体を解析して、自分の仕事に活かすなり、あるいはそのままパクるのも一つの手だろう。
インフルエンサーが、「Xを学べば儲かる」という主張をするのは、基本的にその「Xを学ぶ」ための情報商材なり、スクールなりに誘導するためである。そのため、「X」は、ブログ、YouTuber、プログラミングなど、(突き詰めると奥は深いのだが)誰にでもとりあえず取り組むことができる、誰にでもチャンスがあるように感じられるものであることが多い。
要は、情弱と言われる層を引っ掛けるためには、始めるハードルが低く、一攫千金の可能性を提示するのが、ベストの方法なのである。
このように、情弱を集めて「儲ける手段」を売りつけるのが、インフルエンサーが得意とする「信者ビジネス」の本質なのだ。
■信者ビジネスはなぜ儲かるか
「信者ビジネス」というネーミングからも分かるように、ビジネスモデルの原型は宗教にある。
日本においても海外においても、寺社仏閣や教会が有名な観光地足りうるのは、それが豪華で、金のかかった建物だからである。
逆に言うと、そのような建物を建立することが可能な宗教は、ビジネスとして見ると、基本的に極めて収益性が高いということである。
その大きな理由としては、通常のビジネスにおいては、誰かに働いて貰う場合、給与なり業務委託費なりを払わないといけないが、信者ビジネスの場合は、「修業」ということにして、タダ働きさせることが可能だからである。
実際、かつて、凄惨(せいさん)な犯罪を引き起こした新興宗教である、オウム真理教がその手法を巧みに使っていた。彼らが展開した「うまかろう安かろう亭(飲食店)」「オウムのお弁当屋さん」「マハーポーシャ(パソコンショップ)」などは、信者がタダ働きしているため、コストが極めて安く、そのため価格の割に品質がいいことで有名であった。
もちろん、このことはオウム真理教を擁護する性質の話ではなく、純粋にビジネスモデルについて考えた場合の話である。
実は、ビジネスインフルエンサーが展開するオンラインサロンも似たような構造になっており、サロンの宣伝や運営の手伝いを無償でさせられ、それによってスキルが身につく、という理由で対価が支払われないことも多い。
多くのオンラインサロンは、新興宗教を現代風にしたビジネスであり、宗教の基本フォーマットである「修業、労働、布施、勧誘」を信者に行わせることによって利益を得るビジネスモデルなのである。
■「これは何で儲かっているのか」という視点を持つことが重要
このように、誰か影響力を持っている人の言うことを鵜呑みにするのではなく、むしろ、「その人がどうやって金を儲けているのか」を着眼点にすることで、真の狙いが見えてくるのである。
真実が現れるのは「その人が何を言っているか」ではなく、むしろ、「その人が誰から、どうやって金をもらっているか」なのである。
そして、この「金儲け視点」を持つか持たないかが、「儲けさせてくれる社員」と「損をさせられる社員」の差である。
つまり、自分が勤めている会社が、「何を、誰に、どのように」売って、どのくらい儲けているのか、その儲けの源泉を把握し、どのようにその金儲けに対して貢献できるかを考え、行動している社員が「会社を儲けさせてくれる社員」だと言える。
逆に、自社の儲けの構造を全く考えていなかったり、その考えが浅いがために真に理解できずに見当違いのことをしてしまったり、ただ単に目の前の与えられた業務をこなすだけのような社員はいずれ、コストカットの対象となり、「損をさせられる社員」として切り捨てられてしまうのである。
■生き残るために、騙されないために必要な「金儲けリテラシー」
コロナ禍による不況、さらに不況対策のための金融緩和により、今後はますます「持てる者と、持てない者」「儲ける者と、儲けられない者」の二極化が進んでいくと考えられる。
そのような中で必要なのは、いま、大きな組織にいるのであれば、その中で、組織に「金を儲けさせること」により、自分が組織に守ってもらう側、必要とされる側に立つことである。
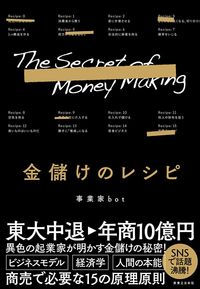
そして、いま、自分が弱い立場にいるのであれば、「弱者から金を儲けようとする人がどう引っ掛けようとしてくるか」を知り、自分を守ること、そして、正しい金儲けの方法を知って、自分が強者の側に立つことである。
私はかつて、東大在学中に起業した際、「金儲けのノウハウ」がまとまった本がないことに非常に困ったという体験がある。
この度、上梓した『金儲けのレシピ』(実業之日本社)はそんな「金儲けのノウハウ」をまとめ、搾取から身を守り、また真摯に金儲けに取り組もうとする人のための本である。
コロナ以降の社会を生き残るために不可欠な、「金儲けリテラシー」をぜひ本書で身につけて欲しい。
----------
経営者
東京大学在学中に起業、のち中退。フランチャイズチェーン企業に事業売却後、売却先企業にて、新規事業及び経営企画管掌の役員を務める。再度起業し、現在年商10億円以上の企業を経営。起業しビジネスを作っていくプロセスの中で、「金儲け」のノウハウが確立していないこと、既存のビジネス書があまり当てにならないことを痛感し、「金儲けのノウハウ」をまとめることを決意。著書に『金儲けのレシピ』(実業之日本社)などがある。
----------
(経営者 事業家bot)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
918人が集団自殺…「カルト」の文字が初めて新聞に踊った1978年人民寺院事件…日本では“金余り”90年代に「オウム、統一教会、幸福の科学」らが躍進
集英社オンライン / 2024年6月4日 19時0分
-
なぜオウム真理教は殺人テロ集団になったのか…ヨガ道場が「カルト教団」に変質した根本原因
プレジデントオンライン / 2024年5月31日 17時15分
-
「東大生の就職」コンサル選ぶ"身も蓋もない"理由 今と昔で違ってきた「賢い」ということの基準
東洋経済オンライン / 2024年5月30日 16時30分
-
「顧客にどれだけ損をさせ」「何人部下を辞めさせたか」を自慢するかつての野村證券の営業マン…新人研修の担当部長は「法令違反を犯して表営業できなくなった社員」
集英社オンライン / 2024年5月21日 8時0分
-
Z世代を不安にさせるビジネスがなぜ流行るのか 不安に動かされる「われわれ」の社会の病理
東洋経済オンライン / 2024年5月17日 10時40分
ランキング
-
1物流TOB合戦、佐川の「異次元の高値買収」で決着へ 株式市場は厳しい評価、問われる巨額買収の果実
東洋経済オンライン / 2024年6月3日 17時30分
-
2中小の瓶飲料がピンチ 資材・原材料の値上げラッシュも価格転嫁しにくく板挟み 悲鳴を上げる業界団体の長
食品新聞 / 2024年6月4日 9時30分
-
3これまで「1kg数円」で処分していたが…マグロの希少部位「血合い」に水産業界の注目が集まっている理由
プレジデントオンライン / 2024年6月4日 10時15分
-
4【検索急上昇ワード】全国の人気温泉地ランキング…2024年4月に最も注目されたのは、長い歴史を持つあの温泉!【第1位~第5位】
THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年6月4日 11時30分
-
5データ転用・独自解釈・書き換え…5社に広がった型式不正、揺らぐ自動車業界の信頼
読売新聞 / 2024年6月4日 0時1分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください











