得をするのは富裕層と仲介業者だけ…ふるさとが潤わない「ふるさと納税」の歪んだ構図
プレジデントオンライン / 2023年11月28日 15時15分
■浮き彫りになった「ふるさと納税」の問題点
「官製ネット通販」と揶揄され、1兆円規模にまで膨れ上がった「ふるさと納税」。年末のかきいれ時を迎え、1000万人近くにまで広がった利用者が「おとくな返礼品」を探し求めて、あまたの「ふるさと納税サイト」をはしごしている。
地方自治体も、地場産業も、寄付者も、「三方一両得」の制度として始まったふるさと納税だが、市場の拡大とともに本来の趣旨が忘れ去られ、さまざまな問題点が浮き彫りになってきた。
今、利用者が寄付した税金のうち1500億円規模にも上る巨額のマネーが、全国の自治体とは無縁の東京の仲介サイト業者などに掠め取られている実態をご存知だろうか。善意の寄付が制度につけ込んだ民間業者の懐に入ってしまっているのだ。
もう一つ。高額所得者ほど寄付額の上限が高くなる仕組みを使って合法的な節税対策として利用されていることを承知しているだろうか。納めるべき所得税や住民税が肉や魚の返礼品にすり替わり、住んでいる自治体に納付されず住民サービスに支障をきたしているのである。
ほかにも、制度の矛盾が、有識者にとどまらず当事者の自治体からも次々に指摘されるようになった。
ふるさと納税を主唱した菅義偉前首相は「2兆円」を目標に掲げたが、規模が大きくなることは弊害も大きくなることにつながる。
ふるさと納税が健全な制度として持続的に発展するためには、小手先の手直しではなく、原点に立ち戻る抜本的な改革を行わねばならないタイミングを迎えている。
「ふるさと納税は、だれのためにあるのか」が問い直されなければならない。
■返礼は「礼状」を出す程度…はじめは「善意の寄付」だった
ふるさと納税は、「自分のふるさとや縁のある地域に寄付(納税)して、元気になってもらおう」という趣旨の寄附金税制の一つで、2008年にスタートした。
政策的に言えば、地方と大都市の格差是正や人口減地域における税収減対策を、自治体と庶民の間で進めようというもので、個人が納める税の一部移転ということになる。税法上は、寄付額を住民税から控除する仕組みで、当初の上限は住民税のおおむね1割、現在はおおむね2割。所得税も、税率に応じて一部控除される。ただ、寄付しようとすれば2000円の自己負担金が持ち出しになる。
税収の少ない地方自治体が自由に使える寄付金で少し財源が潤い、販路が限られていた地場産業は返礼品需要で少し活性化し、ふるさとに貢献したくてもなかなかできなかった利用者が少し満足感を味わい返礼品まで受け取って少し得した気分になるという、「三方よし」の制度といえた。
もともと「善意の寄付」を想定していたので、当初は、利用者も寄付額もささやかで、寄付を受けた自治体も礼状を出す程度のほのぼのとしたものだった。
知る人ぞ知る制度で、11年に東日本大震災で被災自治体への寄付が急増したものの、しばらくの間は、寄付者は10万人余り、総額も100億円余りで推移していた。
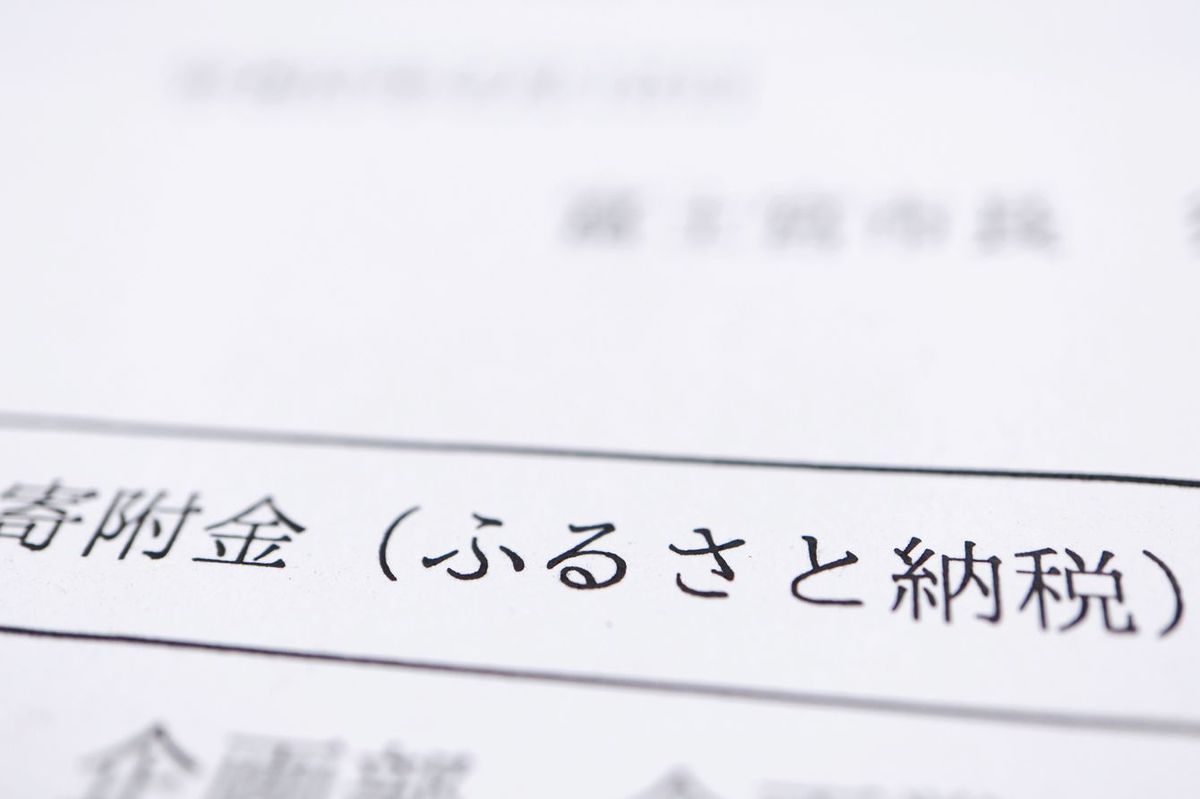
■寄付金の獲得競争が全国に広がった
ところが、地場の特産品を返礼品としてふるさと納税を募る自治体が現れるようになり、その動きはやがて全国に広がって寄付金獲得の競争が始まった。
いつのまにか、寄付金を集めること自体が目的化し、もともとの狙いが変質していったのである。
そして2015年。寄付できる金額の上限が倍増(住民税控除額の上限を1割から2割に引き上げ)し、確定申告が不要となるワンストップ特例の導入で手続きが簡略化されると、事情が一変する。
ふるさと納税がにわかに注目を集め、利用者の意識も様変わり。返礼品が税金の還元策になることがわかると、自らのふるさとへの貢献など置き忘れ、ネットに並ぶ返礼品の品定めに血眼になった。高額返礼品を受け取り実質的な節税にいそしむ高額所得者の姿も目立つようになった。
寄付者は100万人を超え、寄付総額は一気に1500億円規模にまで膨れ上がった。
そうなると、利用者の関心を誘うためには地場の特産品だけでは足りず、地場産業以外の返礼品や地場産業とは関係のない商品券や金券まで提供する自治体も現れ、「寄付金争奪戦」はますますエスカレートした。
■仲介サイト業者が続々と参入
とはいえ、ビジネスとは無縁の地方公務員が、十分な実務のノウハウを持ち合わせているわけもない。
そんな事情に目をつけたのが、ネット通販などに長けている中央の民間業者だった。最初に仕掛けたのはベンチャーの「ふるさとチョイス」で、IT企業アイモバイル系の「ふるなび」、ソフトバンク系の「さとふる」、「楽天ふるさと納税」の楽天など、大手業者が続々と「ふるさと納税サイト(仲介サイト)」事業に参入した。本来、自治体が行わなければならない実務を、業務委託として請け負い、仲介手数料を得るなど、さまざまな形で全国の自治体に関与していったのである。
どの仲介サイトも、自治体ごとの返礼品はもちろん、肉・魚・果物・民芸品などにジャンル分けされ寄付額に応じて整理された全国の返礼品が一目でわかる「ふるさと納税サイト」を展開し、利用者を寄付に誘った。
自治体にしてみれば、独力では限界のあった返礼品の情報発信が、仲介サイトに情報を提供するだけで全国津々浦々に行き渡るようになったのである。さらに、返礼品の選定や評価まで助言してくれるうえに、面倒な決済まで肩代わりしてくれるようにもなった。
こうして、どの自治体にとっても、仲介サイト業者はなくてはならない、ありがたい存在になったのである。
■利用者は300倍、寄付総額は約120倍に急拡大
ふるさと納税の22年度の利用者は891万人で、スタートした08年度の3万人余りに比べると実に約300倍。寄付件数は5184万件と14年連続で過去最多を更新し、寄付総額は9654億円にまで膨れ上がった。08年は81億円だったから約120倍に膨張、この3年間に限っても倍増している。

寄付受入額トップの自治体は、宮崎県都城市で約196億円。北海道紋別市約194億円、同根室市約176億円、同白糠町約148億円、大阪府泉佐野市約138億円、佐賀県上峰町約109億円と、「100億円自治体」が続く。
昨今は過大に集まった寄付金の使い道に苦慮する「うれしい悲鳴」を上げる自治体も出ているという。
一方、利用者の大半を抱える大都市圏では、本来入ってくるはずだった多額の住民税が地方の自治体に流失し、住民サービスに支障が出始めるようになった。寄付に伴う23年度の住民税の減収総額(いわゆる「赤字」)は全国で6798億円となり、もっとも多い横浜市は272億円に達する。名古屋市、大阪市、川崎市も軒並み100億円を超える。こちらは、本当の悲鳴だ。
「ふるさと納税狂騒曲」が全国に響き渡り、悲喜こもごもの自治体の姿が映し出されている。
■自治体に入るのは寄付金の半分にも満たず
こうなると、話は違ってくる。
当初は静観していた総務省だが、各方面からさまざまな問題点が指摘されるようになって、規制策を打ち出さざるを得なくなった。
まず19年に、「返礼品は地場産品に限り調達費は寄付額の3割以下」(3割ルール)、「返礼品+経費の総額は寄付額の5割以下」(5割ルール)という「御触れ」を出し、ルールを遵守した自治体のみがふるさと納税を実施できる制度(指定制度)を導入した。
たとえば、寄付金が10万円の場合、返礼品の調達費は3万円以下、送料や仲介サイトに支払う手数料、広告費などを含めた総経費は5万円以下に抑えなければならなくなった。寄付額のせめて半分は自治体に入るよう指導したのである。
ところが、仲介サイトのPR合戦にもあおられて、返礼品競争はヒートアップ。「御触れ」を無視するかのように、高額の返礼品を提供したり、多額の経費をつぎ込む自治体が続出。読売新聞の調べによると、21年度に「5割ルール」を超えた自治体は138市町村に上ったという。
さらに、新たな問題が露見する。仲介サイトが、「5割ルール」の枠外として、システム管理費や顧客情報管理費など「募集外(ボガイ)」と称するさまざまな手数料を、自治体から広く徴収していたことが判明したのだ。
■小手先の対策では不十分
また、これまで「5割ルール」の対象外だった、自治体が発行する寄付金受領証やワンストップ特例に関わる事務費も、無視できない額になってきた。
こうした「隠れ経費」を含めると、多くの自治体が「返礼品+経費」が5割を超えてしまうという。
このため、総務省は10月から、経費の算定基準を厳格化して「隠れ経費」をすべて加え、地場産品の基準も厳しくした「新5割ルール」の実施に踏み切った。
しかし、いずれも小手先の対策に過ぎず、とても抜本的な見直しとは言い難い。
あらためて、ふるさと納税の問題点を整理してみる。
①巨額の税金が仲介サイト業者に流出している
②業者に支払う経費の算定基準や内容が不透明
③高額所得者ほど実質的な節税効果が大きい
④返礼品や経費のコストが重く、寄付額の半分程度しか自治体に入らない
⑤地場産品の人気度によって寄付金受け入れの自治体間格差が大きい
⑥大都市圏の自治体は流出額が大きく、住民サービスに支障が出ている
⑦利用者の大半は返礼品目当てで、ふるさとへの貢献という理念がかすんでいる
⑧ふるさと納税に絡んだ不祥事が続発し、贈収賄のような刑事事件まで起きている
など、枚挙に暇がない。
ふるさと納税の寄付総額が100億円前後の10年前ならともかく、今や市場は1兆円規模となり、さらに拡大が見込まれるだけに、どれをとってももはや看過できなくなった。
■寄付額の15%抜き取られる…仲介業者に逆らえなくなった地方自治体
とくに、重要な問題点を深掘りしてみる。
まず①と②について。
「5割ルール」では、返礼品の調達額は3000億円程度、経費は2000億円程度になるが、経費のうちかなりの額が仲介手数料や決済手数料、顧客リスト管理費、販売促進費、広告宣伝費などの名目で、仲介サイトの運営業者に支払われている。
寄付金受け入れ額ランキングに名を連ねる九州のある自治体の担当者によると、あれやこれやで仲介サイト業者に支払う金額は寄付額の15%程度に上り、しかも手数料などの料率は仲介サイト業者から一方的に提示され、不満を感じても交渉の余地はほとんどないという。
担当者に言わせれば「無垢(むく)な自治体を食い物にするハゲタカ業者が巨額の税金をかすめとっている」となる。つまり、全国では1500億円にも上る税金が、ふるさととは無縁の仲介サイト業者の懐に収まってしまっているのだ。ふるさとへ寄付したつもりの利用者にすれば、実に不快で由々しき問題と言わざるを得ない。
仲介サイト業者への巨額流出は、当初の制度設計では想定していなかったとみられるが、制度の抜け穴であり、放置しておいていいはずがない。
■「金持ちが得をする制度」は欠陥
次に③について。
ふるさと納税における住民税の控除の上限(寄付金の実質的な上限)は、2割の定率のため、高額所得者ほど寄付の上限額が飛躍的に大きくなる。
ちなみに、22年の世帯平均年収546万円(厚生労働省・国民生活基礎調査)の場合、上限額は概算で6万円(夫婦の場合、家族構成により異なる、以下同じ)になる。
もっとも多いのは年収200万~300万円世帯だが、300万円世帯の上限額は概算で1万8000円だ。
これに対し、年収が1000万円なら約17万円、1500万円で約40万円、2000万円で約56万円、3000万円は100万円余り、5000万円になると200万円を超す寄付ができてしまう。寄付額の3割は返礼品となって戻ってくるので、その分が実質的な節税となる。
逆進性がきわめて高く、税の公平原則からみれば極端な不均衡が生じている。つまり、「金持ちほど得をする制度」なのである。当初から指摘されていた制度上の欠陥で、素直に受け入れられる利用者がどれほどいるだろうか。
④以下は、寄付金目当ての返礼品競争が招いた結果であり、自治体が税収を奪い合う構図は歪んでいるとしかいいようがない。

■富裕層の節税に歯止めをかけるべきだ
では、どうするか。
制度上の欠陥や抜け穴は、根本的に是正しなくてはならない。
まず、手がけやすいところでは、寄付額の上限(税額控除の上限)を「定率」に加えて新たに「定額」を設けることだろう。
約1000万人の利用者が約1兆円を寄付している現状から計算すると、1人当たりの平均寄付額はざっくり10万円。これは、年収約700万円の世帯の上限額に相当する。2割の上限率はそのままで、上限額としてたとえば10万円を設定すれば、全世帯の7割を占める年収700万円未満の世帯には影響がなく、一方で、節税にいそしむ高額所得者の多額寄付に歯止めをかけることができる。そうすれば、庶民の怨嗟の声も少しは鎮められるかもしれない。
寄付総額は一時的に減るだろうが、だからといって高額所得者に配慮する必要はまったくない。利用者のすそ野は広がっており、伸びしろもたっぷりあるだけに、数年単位でみれば、ふるさと納税市場は活性化していくだろう。
■最大の問題は、仲介サイト業者への税金流出
次に着手できるのが、経費の抜本的見直しだ。
総務省は、自治体に入る寄付金を寄付額の半分程度を目安にしているが、少なすぎる。経費などを差し引いて、少なくとも7割、できれば8割は残らないと、本旨に反するのではないか。「返礼品+経費」を「3割以下」に抑えるようにすべきだ。
仲介サイト業者への税金の巨額流出は、現在の最大の問題ともいえる。
民間の仲介サイト業者を規制することは容易ではないが、自治体の経費の使い方に厳しいガイドラインを設けることは難しくないだろう。
一つの方策として、地場以外の業者に支払う経費に上限を設けてはどうだろうか。たとえば、仲介サイトの大手業者に10%以上も支払っている仲介手数料の上限をクレジットカード並みの3%程度に抑えることが考えられる。
その結果、不満をもった仲介サイト業者が手を引いたとしても、ふるさと納税の仕組みが崩壊するわけではない。もっとも、仲介サイト業者がふるさと納税を起点にして自社の経済圏に利用者を引き込むことを狙っているとしたら、すんなり撤退するとは考えにくい。
そして、できることなら、経費の支出先は地元の業者(自治体レベルにとどまらず県レベルも含む)に限るべきだろう。それは、地域が潤うことと同義語だ。
■ふるさと納税サイトは「カタログ通販」になっている
仮に大手業者の仲介サイトがなくなった場合、総務省は、県や有力自治体が主導して県レベルのささやかな仲介サイトを地元業者に委託する代替策を推奨してはどうだろうか。
利用者には不便になるかもしれないが、「カタログ通販」化した「ふるさと納税サイト」を眺めて、ショッピング感覚で寄付している現状を見つめ直す契機になるのではないか。
「税金が肉や魚に変わるのが当たり前」という風潮をおかしいと捉えなければならない。そもそも縁のある自治体に寄付することが本旨だったのだから、ささやかな返礼品が贈られてくればよしとすべきだろう。
寄付額に上限を設け、地元業者以外への経費支出を抑えれば、ふるさと納税を取り巻く景色も変わってくるに違いない。
そうなれば、さまざまな問題点を抜本的に解決するための知恵も出てこよう。
爆発的に拡大しているふるさと納税だが、あるべき姿は、「寄付金争奪戦」でもなければ、「官製ネット通販」でもない。
スタートから15年経った今、創設の趣旨に立ち戻る「勇気」が求められている。
----------
メディア激動研究所 代表
1955年生まれ。名古屋市出身。早稲田大学政治経済学部政治学科卒。中日新聞社に入社し、東京新聞(中日新聞社東京本社)で、政治部、経済部、編集委員を通じ、主に政治、メディア、情報通信を担当。2005年愛知万博で博覧会協会情報通信部門総編集長を務める。日本大学大学院新聞学研究科でウェブジャーナリズム論の講師。新聞、放送、ネットなどのメディアや、情報通信政策を幅広く研究している。著書に『「ニュース」は生き残るか』(早稲田大学メディア文化研究所編、共著)など。 ■メディア激動研究所:https://www.mgins.jp/
----------
(メディア激動研究所 代表 水野 泰志)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
アマゾン参入で「ふるさと納税」に起こる大変化 税金を喰い荒らすふるさと納税ビジネス「前編」
東洋経済オンライン / 2024年5月7日 8時0分
-
初任給「26万円」で入社→手取り「20万円」だった…!なぜ「6万円」も引かれたのでしょうか?
ファイナンシャルフィールド / 2024年5月1日 21時10分
-
寄付の際の税金について
楽天お金の総合案内 みんなのマネ活 / 2024年4月26日 10時0分
-
ママ友が「ふるさと納税の返礼品」で「100万円」の高級腕時計を受け取ったそうですが、”高収入世帯”と思ってよいのでしょうか?
ファイナンシャルフィールド / 2024年4月25日 2時10分
-
ふるさと納税は「高年収」じゃないと意味がない?「年収1000万円」と「年収400万円」の返戻品の差について解説
ファイナンシャルフィールド / 2024年4月11日 2時30分
ランキング
-
1〈速報・那須2遺体〉“全身刺青”の宝島さん娘の内縁の夫が逮捕「何見てんだよ」とポルシェのオープンカーでライバル店に横づけ挑発…「彼はチンピラでした」「ほとんど亡くなった奥さんの命令で動いてた」
集英社オンライン / 2024年5月7日 1時17分
-
23か月後に再び来店“万引き犯”…店はマークしていた 札幌の53歳女逮捕「やっていません」
STVニュース北海道 / 2024年5月7日 9時17分
-
3立て続けに自宅被災の珠洲市民、6割が再建の意欲低下…仮設住宅の女性「また被災するかも」
読売新聞 / 2024年5月7日 8時25分
-
4【中継】娘の内縁の夫が“首謀者”か 知人ら2人を死体損壊疑いで逮捕 那須夫婦遺体
TBS NEWS DIG Powered by JNN / 2024年5月7日 11時42分
-
5自民議席減へ立民と調整 国民・玉木氏、次期衆院選で
共同通信 / 2024年5月6日 21時46分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください










