選挙を動かすネット動画、偽情報や中傷にどう向き合えばいいのか 「広告収入の透明化必要」「規制、監視はプライバシー犠牲」
47NEWS / 2025年2月2日 9時0分
交流サイト(SNS)に多くの動画コンテンツが投稿され、選挙運動での存在感が増す。偽情報の拡散や候補者への中傷に、どう向き合えばいいのか。インターネット選挙を経験した候補者と、SNS規制の議論に詳しい専門家に聞いた。(共同通信=米津柊哉、大根怜)
▽ネット選挙、公費負担の枠組み検討を―衆院選に出馬した原田謙介さん

原田謙介さん
2012年春から、インターネットでの選挙運動解禁を求めて同世代の仲間と活動してきた。スマートフォンがだいぶ身近になっていたのに、社会の未来を決める大事なタイミングでネットが使えないのは時代に合わないと思っていた。
当時は成り済まし対策が焦点だったが、2013年の解禁後、問題が顕在化することはなかった。もう一つの課題だった誹謗(ひぼう)中傷対策は解決されないどころか悪化している。異論を述べる人を政治家自身が敵視し、悪意の応酬で分断を生もうとする事態が散見される。選挙中は平常心でいられないから気持ちは分かるが、慎まなければならない。
2024年の衆院選に岡山1区で2度目の出馬をした。「友人が原田さんのインスタグラムをシェアしていた」と話してくれる人もいて、3年前の選挙よりもSNSの反応は多いと感じた。影響力は間違いなく増しているし、双方向のやりとりができるのは良いことだ。
ただ、動画配信で収益を得られる仕組みができて、第三者による演説などの「切り抜き動画」が広まったのは十数年前に想定していなかった。先鋭化した動画ばかりが視聴されると、候補者の主張と異なる話が独り歩きする恐れがある。
選挙中はボランティアの手を借りてSNSを運用した。もっと力を入れようにも、選挙の時にSNSのプロを雇うことはできない。現行制度では公費負担の対象がポスターなどに限られており、一定の枠内でSNSを含め配分を自由に決められる仕組みを検討すべきだ。
× ×
はらだ・けんすけ 1986年岡山県生まれ。東大卒業後、若者と政治をつなぐNPO法人を設立。2024年衆院選に立憲民主党から出馬し落選。
▽お金の流れ、透明化が必要―湯浅墾道明治大教授

インタビューに答える明治大の湯浅墾道教授
選挙運動でSNSが活用され、有権者は従来のメディアだけでは行き渡らない情報に触れることができるようになった。中でも動画コンテンツは圧倒的に力がある。自分で身近なものを撮ってアップしている人は、流れてくる動画も信頼できると感じているのではないか。
背景には、注目のテーマを取り上げて再生回数を増やし、広告収入を追求する「アテンションエコノミー」がある。候補者の応援動画を作ったり、逆に落選させるための動画を流したりすることは選挙運動の一環かもしれないが、陣営と金銭のやりとりがあるのなら規制の余地は大いにある。
現状、陣営による有料広告は禁じられているが、第三者が流す動画には何の規制もない。まずはSNSを通じたお金の流れを透明化し、検証していく必要がある。
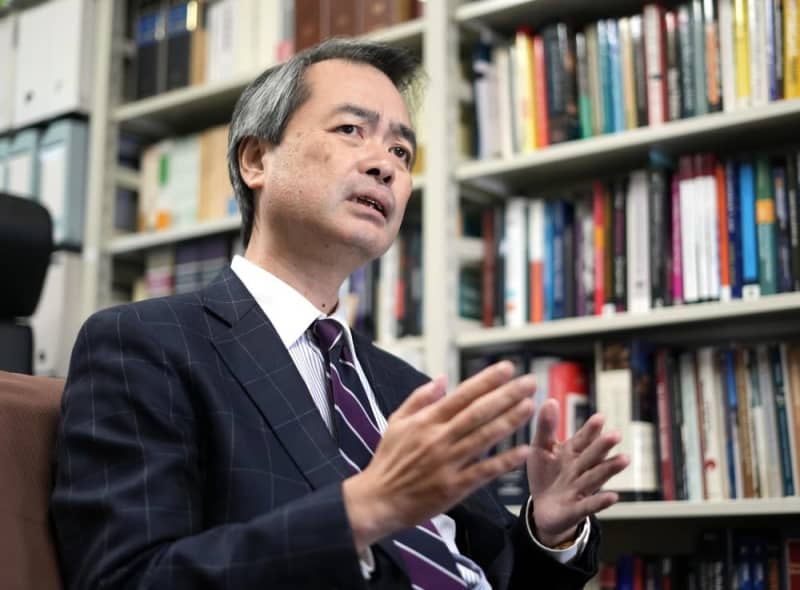
湯浅墾道教授
偽情報、特に生成人工知能(AI)を悪用した「ディープフェイク」が選挙結果をゆがめる懸念も生じている。政治家の話し方や顔をAIに学習させ、簡単にフェイク動画を作ることができる。動画を流すAI利用者に規制をかけるか、あるいはプラットフォーマーと呼ばれる企業側に政治的な内容のものを流させないよう規制するか、各国とも試行錯誤している。
インターネット選挙の取り締まりを従来通り市区町村の選管に任せるのはもはや不可能だ。韓国では中央選管が他の行政機関から独立して強力な権限を持っており、選挙のたびに24時間態勢でSNSを監視する。日本もこれにならい、中央に強力な選管組織を置く方策が考えられるだろう。
× ×
ゆあさ・はるみち 1970年生まれ。東京都出身。情報セキュリティ大学院大教授などを経て2021年から明治大教授。専門は情報法。
▽SNS規制は民主主義存立のジレンマに―山本達也清泉女子大教授

インタビューに答える清泉女子大の山本達也教授
2011年ごろに起きた中東の民主化運動「アラブの春」ではSNSが大きな役割を果たした。エジプトでは一部の人たちが当時のムバラク政権打倒を目指し、SNSで声を上げた。最初は仮想空間だけの出来事だったが爆発的に広がって一線を越え、政権の崩壊につながった。
今回の兵庫県知事選もSNSからうねりが広がり、現実の投票行動に結びついたという点が共通している。選挙でますます無視できないツールとなるだろう。
一方でSNSを重視すればするほど、選挙結果に影響力を行使したいと考える他国の勢力に付け入る隙を与える懸念が高まる。2022年の台湾の統一地方選では、SNSを介して中国からさまざまなフェイクニュースが流された。2016年の米大統領選や、英国がEU離脱を決めた国民投票でも真偽不明の情報が飛び交っていた。

山本達也教授
こうした外部からの攻撃を防ぐには、国がSNS規制や監視を強化せざるを得ない。つまり政治制度の根幹である選挙を公正に実施するために、民主主義的な価値である国民のプライバシーを犠牲にするというジレンマに陥ることになる。選挙の信頼性維持に大きな難題が課される時代となった。
最後のとりでは既存のメディアだ。深く取材し、裏を取った正確な情報こそ信頼性が高い。もし政府がSNSへの規制や監視を強める状況になった場合、メディアは権力行使が抑制されたものかどうかをチェックし続ける必要がある。そのバランスが崩れれば、いよいよ民主主義が危うくなる。
× ×
やまもと・たつや 1975年東京都生まれ。専門は公共政策論、民主主義論、情報社会論。
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
大統領も信じた選挙不正陰謀論 フェイクが分断する韓国保守の深層 麗澤大学・西岡力氏
産経ニュース / 2025年1月31日 7時0分
-
今年は“選挙サマー”7月に行われる見通しの参院選へ、動き出した各党&候補予定者たち 宮本融教授「政界再編、ガラガラポンという形も…」
北海道放送 / 2025年1月20日 21時45分
-
選挙時のSNS規制で意見分かれる 石破首相「一致した見解を」維新・吉村代表「SNS=誤情報は違う」
東スポWEB / 2025年1月19日 15時7分
-
街頭演説妨害、車で追尾。「荒れる選挙」に警戒続く 相次ぐ社会福祉法人乗っ取り。法改正も、資金流出
47NEWS / 2025年1月10日 9時0分
-
2025年「オールドメディアの衰退」は現実となるか 転換期の1年、起こりうることを未来予測しよう
東洋経済オンライン / 2025年1月4日 7時30分
ランキング
-
1男子高校生(18)を殺人などの疑いで逮捕 保育士殺人事件 徳之島・伊仙町
KYTニュース / 2025年2月2日 0時30分
-
2「ドクターイエロー」ねぎらい 約200人の親子ら 車体を清掃
TBS NEWS DIG Powered by JNN / 2025年2月1日 23時41分
-
3東京など首都圏に雪の予想 JR青梅線の一部区間で始発~午後3時頃まで運休 中央本線や一部在来線で大幅な遅れや運休の可能性も
TBS NEWS DIG Powered by JNN / 2025年2月2日 0時34分
-
4「殺すつもりだった」…母親の首を絞めて殺そうとした男子高校生を逮捕 北海道岩見沢市
北海道放送 / 2025年2月2日 6時50分
-
5《新橋グループ窃盗事件》「都庁勤務だと聞いていたのに…」 澤藤翔容疑者(28)が“トクリュウ”に堕ちたワケ「ヤバい奴と揉めた」
NEWSポストセブン / 2025年2月2日 7時15分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください










