水分補給は昼コーヒー、夜ビール… 「熱中症になりやすい人」の特徴と対策
ananweb / 2024年6月29日 20時10分
最高気温が30度を超える真夏日が続出し、猛暑を予感させる今日このごろ。早くも夏バテ気味、という人も多いのではないでしょうか。熱中症対策も今から始めることが大切です。そこで今回は、中医学士で漢方薬剤師の大久保愛先生が、夏バテ・熱中症対策となる食薬習慣と、NG習慣を教えてくれます!
夏バテ・熱中症対策は万全ですか?

【カラダとメンタル整えます 愛先生の今週食べるとよい食材!】vol. 272
全国的に暑い日が続きますが、今年は例年よりも猛暑になるようです。毎年、夏の気候に負けてしまう人は、早くも疲れを感じているのではないでしょうか。気温が上がると気をつけなければならないのは、水分を欠乏させないことです。私たちの体は、暑い気候の中でも体温を一定に保とうとする機能があります。自律神経の働きにより発汗が促され、その汗が蒸発するときに体温調節されるのです。
ですが、エアコンや紫外線など様々な要因で自律神経が乱されると、だるさや食欲不振などの夏バテの症状を引き起こします。発汗量と水分摂取の内容や量のバランスにより、脱水ぎみになり、体に熱がたまると、熱中症となり、夏バテよりも深刻な状態となります。
酷暑が続く近年の夏には自律神経対策、脱水対策に気をつけなければなりませんね。ということで今週は、夏バテ・熱中症対策となる食薬習慣を紹介していきます。
今週は、夏バテ・熱中症対策となる食薬習慣
夏バテも熱中症も、夏の不調の代表格です。また、夏バテをしている人は、熱中症にもかかりやすいとも言われています。そこで、まずは夏バテをしないように栄養バランスや睡眠の質、空調の管理、紫外線対策、入浴習慣、腸内環境などの見直しを行うことで自律神経を整えることが大切になります。
さらに、熱中症対策として脱水にならないように水分補給の内容やタイミング、量などの調整も必要になります。近年の夏は、異常に気温が高くなっているので、何も対策をしないで元気を保つことは難しくなっています。漢方医学では、自律神経が乱れないように栄養バランスや睡眠の質を整えて『補気血』をし、体にこもった熱を『清熱』したり、消耗する潤いを補うために『補陰』することが必要と考えます。
そこで今週は、『気血水』を補い、『清熱』もできる食薬を紹介します。今週食べるとよい食材は、【鯛茶漬け】です。逆にNG習慣は、【打ち合わせ中のコーヒー、夜のビール】です。
食薬ごはん【鯛茶漬け】
タウリンが豊富で『気血』を補うことのできる鯛でお茶漬けを作りましょう。タウリンには、深部体温を下げる働きがあるため、蒸し暑い時期に食べると『清熱』に役立ちます。また、梅干しを加えることで、汗で失われるミネラルの補充もでき『補陰』効果も高まります。
<材料>
梅干し 1個(包丁で叩く)
大葉 3枚(千切り)
ごはん 1杯
醤油やわさび お好みで
鯛など刺し身 お好みで
熱い緑茶 お好みで
<作り方>
材料を茶碗に入れて、お茶をかけたり、混ぜたりしてお召し上がり下さい。
NG行動【打ち合わせ中のコーヒー、夜のビール】
朝起きた時、打ち合わせ中、眠気がでてきたとき、ランチの後、おやつの時間に…とあっという間に何杯もコーヒーを飲んでいる人は多いと思います。コーヒーも水分ですが、利尿作用が働くため、大量に汗をかくこの時期の水分補給には向いていません。
また、一日の終わりにビールやハイボールなどキンキンに冷えた炭酸のお酒で、涼みながら、癒される習慣をスタートさせるかたも増えていることだと思います。アルコールにも利尿作用があり、アルコールの分解にも水分が消耗されます。暑苦しく、汗をかく量が増えるシーズンです。水分補給の内容がコーヒーとお酒に偏ってはいないでしょうか? 脱水症状になり熱中症のリスクを高めないように、飲み物の種類の見直しもしてみましょうね。
ジメジメとした毎日ですが、だるさを解消したり、スッキリするためにコーヒーやお酒を飲みたくなりますよね。ですが、夏バテしたくない、熱中症対策をしたいと考える人は、一瞬で終わる至福のときよりも、長期的に快適な状態をキープすることを考えた、食事や水分補給をしていきたいですね。そのほかにも心と体を強くするレシピは、『不調がどんどん消えてゆく 食薬ごはん便利帖』(世界文化社)や新刊『だる抜け ズボラ腎活(ワニブックス)』でも紹介しています。もっと詳しく知りたい方はぜひご覧ください。
※食薬とは…
『食薬』は、『漢方×腸活×栄養学×遺伝子』という古代と近代の予防医学が融合して出来た古くて新しい理論。経験則から成り立つ漢方医学は、現代の大きく変わる環境や学術レベルの向上など現代の経験も融合し進化し続ける必要があります。
近年急成長する予防医学の分野は漢方医学と非常に親和性が高く、漢方医学の発展に大きく寄与します。漢方医学の良いところは、効果的だけどエビデンスに欠ける部分の可能性も完全否定せずに受け継がれているところです。
ですが、古代とは違い現代ではさまざまな研究が進み明らかになっていることが増えています。『点』としてわかってきていることを『線』とするのが漢方医学だと考えることができます。そうすることで、より具体的な健康管理のためのアドバイスができるようになります。とくに日々選択肢が生じる食事としてアウトプットすることに特化したのが『食薬』です。
Information
<筆者情報>
大久保 愛 先生
漢方薬剤師、国際中医師。アイカ製薬株式会社代表取締役。秋田で薬草を採りながら育ち、漢方や薬膳に興味を持つ。薬剤師になり、北京中医薬大学で漢方・薬膳・美容を学び、日本人初の国際中医美容師を取得。漢方薬局、調剤薬局、エステなどの経営を経て、未病を治す専門家として活躍。年間2000人以上の漢方相談に応えてきた実績をもとにAIを活用したオンライン漢方・食薬相談システム『クラウドサロン®』の開発運営や『食薬アドバイザー』資格養成、食薬を手軽に楽しめる「あいかこまち®」シリーズの展開などを行う。著書『心がバテない食薬習慣(ディスカヴァー・トゥエンティワン)』は発売1か月で7万部突破のベストセラーに。『心と体が強くなる!食薬ごはん(宝島社)』、『食薬事典(KADOKAWA)』、「食薬ごはん便利帖(世界文化社)」、「組み合わせ食薬(WAVE出版)」、「食薬スープ(PHP)」など著書多数。
公式LINEアカウント@aika
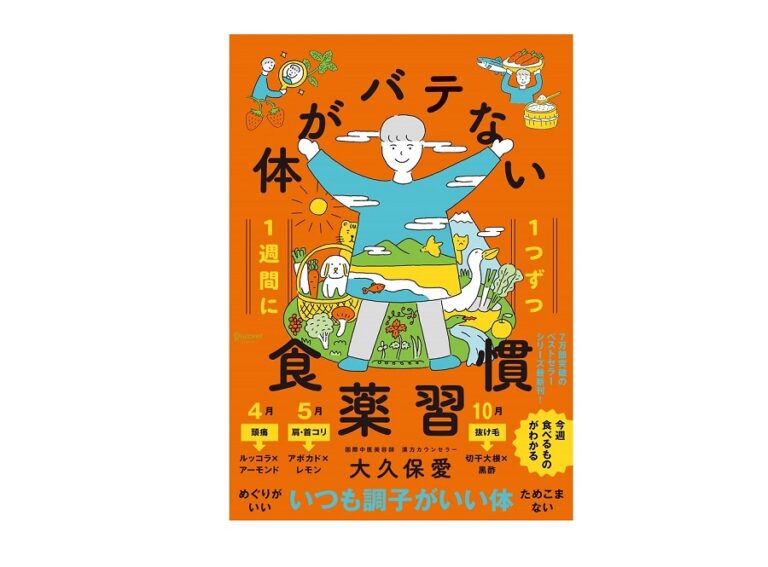
『1週間に一つずつ 心がバテない食薬習慣』(ディスカヴァー)。
『女性の「なんとなく不調」に効く食薬事典』(KADOKAWA)
体質改善したい人、PMS、更年期など女性特有の悩みを抱える人へ。漢方×栄養学×腸活を使った「食薬」を“五感”を刺激しつつ楽しく取り入れられる。自分の不調や基礎体温から自分の悩みを検索して、自分にあった今食べるべき食薬がわかる。55の不調解消メソッドを大公開。
©SKIMP Art/Adobe Stock
文・大久保愛
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
冷えは万病のもと!免疫力を高めて感染症に負けない体をつくる3つの「温活習慣」
ハルメク365 / 2024年11月20日 18時50分
-
「立ちくらみ」の原因はコレだった!更年期や貧血以外の意外な原因、よくあることなの?
OTONA SALONE / 2024年11月16日 22時0分
-
「今年は10月まで暑くてツラかった!」猛暑疲れで、げっそり「老け見え」してる!? リセット&回復に役立つ栄養サプリって?
OTONA SALONE / 2024年11月5日 11時0分
-
「見た目はキレイなのに、口臭きつい」は最悪! 40・50代女性はホルモン変化で「口臭リスク」がアップ!! どうすれば!?
OTONA SALONE / 2024年11月1日 21時1分
-
人気漢方薬店で不調のセルフチェック方法と漢方の考え方を教わりました
CREA WEB / 2024年10月31日 17時0分
ランキング
-
1「運転する夫に『間違えてばっかり!』と怒鳴ったら、路肩に急停止。怖くて大ゲンカしましたが、私が悪いんですか?」投稿に回答殺到!?「お前が運転しろ」「料理してる時に言われたらどうする」の声も
くるまのニュース / 2024年11月26日 12時10分
-
2風邪の初期症状の正しい理解と市販薬の使い方を知る…「ひき始めに服用する」わずか4%
日刊ゲンダイDIGITAL / 2024年11月26日 9時26分
-
3ダイソーで販売「グミ」に回収命令……「深くお詫び」 使用不認可の着色料を使用、5万7000袋を回収
ねとらぼ / 2024年11月26日 18時1分
-
4究極に美味しい「たらこスパゲティ」の作り方。コツは1つだけ:11月に読みたい記事
女子SPA! / 2024年11月26日 8時44分
-
5「50代でモテている男性」3つの特徴。見た目が渋くてカッコいい「イケオジ」じゃなくてOK
日刊SPA! / 2024年11月26日 15時52分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください










