「人生詰んでる」女子のヤバい課外活動、男子バレー髙橋藍大推薦の青春部活小説、眩しすぎる修学旅行の「ある一日」。令和の高校生が主人公、「Z世代」を体感する傑作小説6選(後編)
文春オンライン / 2024年6月28日 6時0分
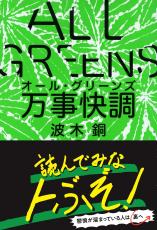
『万事快調 オール・グリーンズ』
〈 直木賞候補作も!「ウーバーイーツ配達員のくせに!」「まだ人生に本気になってるんですか?」「いつまでも弱くて可愛いままでいてね」令和の若者=「Z世代」を体感する傑作小説6選(前編) 〉から続く
親ガチャ、スクールカーストといった令和のバズワードから見え隠れするのは、可視化されすぎてしまったさまざまな「格差」への諦めと、日々を大過なくやり過ごそうとする若者たちの防衛心理なのもしれません。
そしてそんな心理は、確実に令和に生まれる物語の原動力となります。ただ現状を描くのではなく、その先に光が見えるような、前向きな小説が令和の今、続々と生まれています。
今回は、そんな「令和を生きる若者たち」を感じる小説を「本の話」編集部が厳選。
確たる輪郭を持って彼らと「今」を提示する6作品をご紹介。今回はいずれも高校生が主人公の3冊です(前編は こちら )。
『万事快調 オール・グリーンズ』波木銅 著
前編で紹介した3冊は、いずれも東京がメインの舞台となっていますが、本書は地方、古びたボウリング場が残る北関東の片田舎です。そこから抜け出せない若者のリアルを極限まで活写しながら、創造力の翼を目一杯広げて描かれた、第28回松本清張賞受賞作です。
「人生詰んでる」北関東の女子高生が選んだありえない「ビジネス」
主人公は、地元の工業高校に通う3人の女子高生。
居心地の悪い家から抜け出し、駅近公園でのフリースタイルラップに打ち込む朴秀美。露悪的で常に何かに毒づいている図書委員の岩隈真子。陸上部のエースで成績優秀、一見してスクールカーストの最上位にいそうだが、心に闇を抱えた矢口美流紅(みるく)。
それぞれに何かが欠けていて、何かが過剰。いずれにしても「人生詰んでる」ような日々を送っていた3人の日常は少しずつ既定路線を外れていき、「最悪の出来事」を経て秀美が手に入れた「あるもの」であまりにもエクストリームな方向へ――。
〈「大麻、マリファナ! 私、種を手に入れたんだ。たまたま。だから、それを育てて……売り捌く」
「酔っ払ってんのか。ヒップホップかぶれが」
「マジだって!」〉
膨大なカルチャー情報サンプリング、「万事休す」なのに、なぜだか愉快!
ままならない日常を一足飛び、二足飛びで振り切るかのように、3人は校舎の屋上にあるビニールハウスで大麻を育て、ビジネスを始めることに。そして物語は急加速、卒業式の日に繰り広げられるクライマックスへと爆走していきます。
――と、ここまで物語を紹介すると、よくある「ヤバめで治安悪そうな犯罪小説」と思われがちですが、本書はそれだけではありません。
3人はそれぞれに膨大な古今東西の文学、映画、音楽などのカルチャーを愛していて、会話のはしばしに膨大なサンプリングがちりばめられています。たとえば、こんなアーティストや作品名が。
バスタ・ライムズ、パブリック・エネミー、たま、ドアーズ、ジョイ・ディヴィジョン、中島みゆき、ニルヴァーナ、ビリー・アイリッシュ、ヴィヴァルディ、ワーグナー、『綿の国星』、『時計じかけのオレンジ』『悪魔のいけにえ』、『アンチクライスト』、『ブルー・ベルベット』、『ドラッグストア・カウボーイ』、『レイジング・ブル』、『ゆきゆきて、神軍』、『リバース・エッジ』『ユービック』『 銀河ヒッチハイク・ガイド』『コインロッカー・ベイビーズ』『侍女の物語』、フランシス・ベーコン、「芝浜」、そしてジャン=リュック・ゴダール――。
人類がこれまで作り上げてきた文化的な営みへの、深遠なるリスペクトの表明。デッドエンドにいる3人は、過去との連なりの中で自らを救う欠片を見つけ、そこから力を得て「今」を生き抜こうとしています。そしてその姿はなぜか、この物語に「ヤバい」だけでない、カラッとした心地よい風を吹かせているのです。
「おもしろかった。タイトルが秀逸。『八方ふさがり』とか『万事休す』といったような状況なのに、この愉快さ。もちろん、ラストには大麻の煙が充満しているのだから、快調以外の何物でもないのだ」(松本清張賞の選考委員の1人、中島京子さんの選評より)
破滅的なのにこの上なく爽快。ちなみに今、書店では若手営業部員が考えた新しい帯が巻かれています。
「読んでみな、トぶぞ!」
『八秒で跳べ』坪田侑也 著
一方、こちらの作品の「トブ」は、『万事快調』と比べたらきわめて健全。全国大会をめざす高校のバレーボール部が舞台で、「青春部活小説」と帯にもあります。しかしながら、いわゆる少年ジャンプ系の「努力・友情・勝利(→もっと強い敵登場→もっと努力して勝利、の無限ループ)」とは一線を画す読み味。小説だからこそ描きうる、きわめて繊細な心情描写が胸に刺さる作品です。
「努力・友情・勝利」とは一線を画す青春部活小説
少し熱量が低めだがバレー部のレギュラーだった高校2年の宮下景は、突発的な事故で足首を怪我し、コートをしばらく離れることに。一方、事故の「原因」を作った同級生の女子・真島綾は、中学時代に漫画新人賞で佳作を受賞して漫画家を目指しているが、今は創作に行き詰まり「暗い海の底」に。
〈「......好きで始めたはずなのに、いつの間にか、どうして描いてるのかとか全部、わけわからなくなってるんだね」〉
控えに甘んじ、退部するつもりだったチームメイトにレギュラーを奪われ、心がざわざわとし始めた景は、綾にバレー部のポスターを描いてもらうことに。この何気ない依頼が青春真っ只中、道に惑う2人の日々にさざなみのような変化をもたらすことになります。
現役大学生作家の才能を感じる一冊。「八秒」には2つの意味がある?
作者の坪田さんは、現役の慶應義塾大学医学部生。15歳で小説新人賞を獲得して作家デビューを果たすと同時に、学生時代はバレー部でスポーツにも打ち込んでいました。その2つの経験で得た喜びや苦しみなどのさまざまな感情を、的確に言語化する作家・坪田さん底力が、本作には惜しげもなく注ぎ込まれています。
たとえば、バレーボールの試合の、こんなシーン。
〈 僕は助走距離を確保する。塩野のトスがふわりと上がってきた。
地面を蹴る。跳ねる。太腿の筋肉、肩の筋肉、前腕の筋肉。繊維の一本一本が滑って、細胞が燃えた。筋肉に直接記憶されている動作が、自然と再現されていく。ジャンプの最高到達点の視界にブロックが入ってくる。
一瞬の出来事だった。手のひらで、熱が爆(は)ぜた。〉
パリ五輪での活躍が期待されるバレーボール男子日本代表の髙橋藍選手も、本書を読んで「多感な高校生だからこそ、一つひとつの出来事が大きく心に刻まれる。苦しんだ先に喜びがあることを、この小説は教えてくれる」と大推薦。
タイトルにある「八秒」とは、試合中、主審が笛を鳴らしてから八秒以内にサーブを打たなければ反則となる、というルールを指したもの(相手に1点が入る)。ただ、物語の終盤、景はもうひとつの「八秒」の意味を知ることになります。クライマックス、景はそのもうひとつの「八秒」の意味を心の真ん中に置きながら「跳ぶ」のです。
もうひとつの「八秒」の意味は、是非本書を読んで知っていただけたら。
『それは誠』 乗代雄介 著
主人公は地方に住む高校2年生の佐田誠。『それは誠』は、誠が東京への修学旅行の自由行動の一日に、先生たちには知らせずに行った小さな冒険を描いた物語です。
平易な言葉の積み重ねなのに、圧倒的な描写力
作者の乗代さんはインタビューで、本作の創作手法についてこう語っています。
「目当ての場所を決めたら、そこに一カ月くらい泊まり込んで、あらゆる時間帯にいろんな行き方で同じ場所を歩き回って、見たものをその場で書き留めていくんです。『それは誠』の場合は日野市でした。たとえば、公園にやって来た保育園児たちが落ち葉で遊ぶシーンがあるのですが、あれも実際に目にしたことです。すると、この時間帯に園児たちが散歩に来るとか、きれいな乾いた落ち葉が冬になってもたくさんあるとか、舞台の状況が把握できてくる。そうやって集めた風景から当然起こるべきこととして小説が立ち上がってきます。ストーリーは自分でコントロールしている意識はなくて、見たものを小説につなげるというより“つながる”という感じなんです。その場所で人がなにかしているイメージが見えてくる」
(好書好日 乗代雄介インタビューより)
誠は修学旅行の自由行動の日に「日野に住むおじさんに、1人で会いに行きたい」と、集団行動でともに動く予定の班員たちに告げます。誠は男子4人女子3人、人気者と余り者で構成された班員に(誠が気になる女子・小川楓が含まれている)、おじさんに会いたい理由を告白。最終的に男子3人は誠と行動することになります。
そして女子は学校から支給された男子のGPSを持って、学校に提出したコース通りに行動することで男子の「アリバイ工作」に協力。男子4人は密かに日野に向かい、おじさんの家を訪ねることに――。
平易な言葉の組み合わせなのに、高校生7名が交わす会話やシーンの描写がこの上もなくみずみずしくて、眩しい。一人一人の個性や背景がページを繰るごとに色彩を帯び、それぞれの心が近づいたり、離れたりしていきます。
たとえば教室で、ふとした瞬間に同級生女子とじゃれ合う小川楓に向けられた、こんな視線の描写。
〈 小川楓は顔を下げたまま机を離れて、隣の井上の背中に腕を回し、鳩尾(みぞおち)のあたりにすがりついた。乱されてアーチを浮かせた色素の薄い細い髪が、窓から斜めに差す午後の光を透かしている。僕はそこから目を離せないでいた。
その時、勢いよく開いた教室の引き戸が枠を叩くすごい音がした。クラス中が一斉にそっちを向くと、半分顔を出した名取の元に、戸がゆっくり返っていくところだ。タブレットの入ったカゴを持ってたんで停められなかったらしく、そのあとずっと平謝りしてた。
向き直ると、小川楓は井上の懐にもぐりこんだままだった。横髪のわずかな隙間から何回か、瞬(まばた)きともいえない緩慢な目の閉じたり開いたりが見えた。その瞳は、セーターに睫毛が触れるほどの間近で、潤むような光をはなっていた。宿っている情を読み取るのは簡単だった――退屈。喜びや怒り、哀しみにふれた時と何ら変わりなく、退屈を漲(みなぎ)らせてさえ小川楓の瞳は輝いていた。〉
織田作之助賞受賞作にして、著者は本作で芸術選奨も受賞
令和に描かれた小説ですが、普遍的な文学が持つ言葉の力、時代を超えた輝きが、この作品にはあります。それは、先に引いた作者の創作スタンスにもあるように、今この世界をとことん目に焼き付け、書き留めようとしているから。
作者は小学生から高校生までが通う、小さくてアットホームな塾で、長年講師をしていました。その時の子どもたちとのコミュニケーションの記憶が、のびのびとした高校生たちの描写に生かされているのでしょう。
また宮沢賢治やつげ義春、児童文学者の長崎源之助や漫画家・アーティストのタイガー立石、ミュージシャンの奥田民生など、さまざまなジャンルの表現者たちの作品が誠たちの心の中で生きていて、そのことも作品全体の土壌と物語の説得力に奥行きを与えています。
本作は第169回芥川賞の候補作となり、第40回織田作之助賞を受賞し、乗代さんは本作で令和5年度(第74回)の芸術選奨文部科学大臣賞にも選ばれています。
「彼らの冒険は小さいけれど切実さがある。ウエルメードな(筋書きがよい)物語に見えるが、苦闘して書いている乗代さんの姿勢にも感動した」(織田作之助賞選考委員・古川日出男さんのコメント)
「小説の面白さを知ってもらうためにも、是非多くの若い読者に読んでもらいたい作品」(芸術選奨・贈賞理由より)
――――ー
三者三様ならぬ三作三様の高校生活。つねに万事快調とはいかないし、道に惑うこともあるけれど、次に進むためにどうしても必要なことから目を背けず、小さな冒険を積み重ねていく中で、人生は進んでいきます。
高校時代のみならず、大人になっても、あるいは老境に達しつつあったとしても、人生において大切な「スタンス」のようなものが、この三作にはしっかりと刻まれています。
(「本の話」編集部/本の話)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
「宮藤官九郎作品は不適切」と言う人に欠けた視点 「ホモソーシャル作家」という評価は正しくない
東洋経済オンライン / 2024年6月21日 15時0分
-
「第5回京都文学賞」作品・読者選考委員の募集、新たな最終選考委員の就任、新規協力出版社及びHAPSと連携した募集リーフレット等の発行
PR TIMES / 2024年6月21日 11時45分
-
◆2024年度織田作之助青春賞募集を開始◆関西大学が全国の若者の小説創作を応援~24歳以下の書いた短編小説が対象、昨年の応募は336点~
Digital PR Platform / 2024年6月7日 20時5分
-
◆2024年度織田作之助青春賞募集を開始◆関西大学が全国の若者の小説創作を応援
PR TIMES / 2024年6月7日 16時45分
-
「第三回松花堂昭乗イラストコンテスト」【幸せ】をテーマに全国の小・中・高校生から募集します
共同通信PRワイヤー / 2024年6月3日 12時0分
ランキング
-
1すき家、7月から“大人気商品”の復活が話題に 「この時期が来たか」「年中食いたい」
Sirabee / 2024年6月29日 4時0分
-
2水分補給は昼コーヒー、夜ビール… 「熱中症になりやすい人」の特徴と対策
ananweb / 2024年6月29日 20時10分
-
3若々しい人・老け込む人「休日の過ごし方」の違い 不安定な社会、「休養」が注目される納得理由
東洋経済オンライン / 2024年6月30日 9時0分
-
4忙しい現代人が“おにぎり”で野菜不足を解消する方法。野菜たっぷりおにぎりレシピ3選
日刊SPA! / 2024年6月30日 15時53分
-
5Appleのカメラアプリ「Final Cut Camera」はもう使った?なめらかズーム&手ぶれ防止でプロ級動画が完成
isuta / 2024年6月29日 18時0分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください











