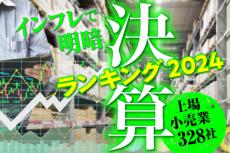インフレ、経済正常化で明暗!小売業の上場小売業2023年度決算と24年度展望
ダイヤモンド・チェーンストア オンライン / 2024年6月24日 19時55分

小売業の2023年度決算は、一部の業態で巣ごもりの反動減や耐久消費財の販売不振などのマイナス影響が見られたものの、インフレによる単価上昇、経済正常化に伴う人流の回復、インバウンドの復活などが追い風となり、全体でみれば好業績となった企業が多かった。本稿では、『ダイヤモンド・チェーンストア』2024年7月1日号特集「決算2024ランキング」からデータの一部を抜粋し、営業収益上位企業の動向を見ていく。
※営業収益は売上高+営業収入。売上高は主に商品の売買に伴うもので、営業収入は卸売上や不動産収入の合計。売上高として全額計上する企業もあれば、営業収入を多く計上する企業もあるため、基準を同じにするために営業収益を使用している
ランキングトップは今年もあの企業!
『ダイヤモンド・チェーンストア』誌では、毎年7月1日号の「決算ランキング」特集で、上場小売業(外食を除く)の営業収益ランキングを掲載している。
今年度のランキングを見ると(図表)、上位3社の顔ぶれは前年度から変わらず、首位はセブン&アイ・ホールディングス(東京都:以下、セブン&アイ)だった。営業収益全体の約75%を海外CVS事業が占めるなど、近年はグローバルリテーラーとしてのポジションを確立しつつある同社。23年度の決算は減収となったものの、営業収益は11兆円超と2位イオン(千葉県)に2兆円近い差をつけている。
図表●上場小売業営業収益ランキングトップ10
単位:百万円、%
※CVSの営業収益はチェーン全店売上高を使用
※ファミリーマートは単体のチェーン全体売上高
※ファミリーマート、ファーストリテイリング、J.フロント リテイリングはIFRS
PPIH=パン・パシフィック・インターナショナル・ホールディングス
| 順位 | 社名 | 営業収益 | 増減 | 営業利益 | 増減 | 決算期 | 業態 |
| 1 | セブン&アイ・HD | 11,471,753 | ▲ 2.9 | 534,248 | 5.5 | 24/2 | ― |
| 2 | イオン | 9,553,557 | 4.8 | 250,822 | 19.6 | 24/2 | ― |
| 3 | ファミリーマート | 3,069,290 | 3.8 | 83,763 | 30.8 | 24/2 | CVS |
| 4 | ファーストリテイリング | 2,766,557 | 20.2 | 381,090 | 28.2 | 23/8 | SP |
| 5 | ローソン | 2,750,984 | 7.2 | 94,090 | 46.3 | 24/2 | CVS |
| 6 | PPIH | 1,936,783 | 5.8 | 105,259 | 18.7 | 23/6 | SP |
| 7 | ヤマダHD | 1,592,009 | ▲ 0.5 | 41,489 | ▲ 5.8 | 24/3 | CE |
| 8 | マツキヨココカラ&カンパニー | 1,022,531 | 7.5 | 75,705 | 21.6 | 24/3 | DgS |
| 9 | ツルハHD | 970,079 | 5.9 | 45,572 | 12.3 | 23/5 | DgS |
| 10 | ニトリホールディングス | 895,799 | ▲ 5.5 | 127,725 | ▲ 8.8 | 24/3 | SP |
次点のファミリーマート(東京都)は23年度決算でチェーン全店売上高(CVSは営業収益ではなくチェーン全店売上高で比較)が初めて3兆円を突破。前年度に続きランキング3位を堅持している。
4位以下は順位に変動があり、昨年5位だったファーストリテイリング(山口県)がローソン(東京都)を抜いて4位に浮上。6位パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス(東京都)、7位ヤマダホールディングス(群馬県)、8位マツキヨココカラ&カンパニー(東京都)は変わらず、昨年10位のツルハホールディングス(北海道)がニトリホールディングス(北海道)を抜いて9位に浮上している。
国内小売2トップの最新動向
ランキング上位企業の動向をみていくと、首位のセブン&アイの24年2月期の連結業績は、営業収益が同2.9%減の11兆4717億円、営業利益が同5.5%増の5342億円だった。
23年2月期業績で米スピードウェイ(Speedway)の業績がフル加算され、海外CVS事業の業績が大きく伸長した同社。24年2月期における同事業の営業収益は同3.7%減の8兆5169億円、営業利益は同4.1%増の3016億円の減収・営業増益だった。中核事業である米セブン-イレブン(7-Eleven,Inc.)がガソリン価格下落と販売量減少で苦戦したのが減収の要因で、これにより連結営業収益も前期を下回っている。
セブン&アイは今後も海外CVS事業を成長させる考えを打ち出しており、24年1月に米Sunoco LPからテキサス州西部、ニューメキシコ州およびオクラホマ州の204店舗を追加取得。北米以外でも24年4月に、豪州のエリアライセンシーとして「7-Eleven」を約750店展開する事業会社を持つConvenience GroupHoldingsの全株式を取得している。これら海外CVSのM&A効果が業績にどう影響するかが注視される。
一方、国内事業会社では、セブン-イレブン・ジャパン(東京都:以下、セブン-イレブン)とSMのヨークベニマル(福島県)が増収・営業増益、GMSのイトーヨーカ堂(東京都)は増収・営業赤字だった。ちなみに、セブン&アイは24年2月期の決算発表時、さらなる成長に向け、イトーヨーカ堂とヨークベニマルからなる「SST(スーパー・ストア)事業」のIPO(新規株式公開)の検討を開始したことを明らかにしている。
注目集めるイオングループによる再編
2位イオンの24年2月期の連結業績は、営業収益が同4.8%増の9兆5535億円、営業利益が同19.6%増の2508億円の増収・営業増益だった。主要事業会社の業績を見ていくと、中核事業会社のイオンリテール(千葉県)は増収・営業増益、本誌区分ではGMS業態としているイオン北海道(北海道)も増収・営業増益を果たした。イオン九州(福岡県)は連結決算移行のため、対前期増減率はないものの、単体業績では営業収益、各段階利益ともに過去最高を更新している。
近年グループの稼ぎ頭の1つとなっているウエルシアホールディングス(東京都:以下、ウエルシアHD)は増収・営業減益。コロナ関連需要の反動減の影響で売上総利益が計画を下回り、営業利益が前期実績を下回った。
イオングループで注目されるのは再編の行方だ。イオンは23年11月に、SMのいなげや(東京都)の持分保有比率を17.01%から51.0%に引き上げ、連結子会社化している。今後は24年11月をめどに傘下のユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(東京都:以下、U.S.M.H)といなげやを経営統合するとしており、統合が実現すれば、いなげやはマルエツ(東京都)、カスミ(茨城県)、マックスバリュ関東(東京都)に並ぶU.S.M.Hの4つ目のSM事業会社となる見通しだ。
さらにイオンは24年2月、ウエルシアHDとツルハホールディングスとの経営統合に向けた協議を開始することで合意したと発表した。この経営統合が実現すれば国内初の2兆円規模のDgS連合が誕生することになる。すでに上位集中が進んでいるDgS業界だが、今回の発表がまた新たな再編の呼び水となる可能性もありそうだ。
インフレで競争に変化? どうなる2024年度決算
小売業の24年度決算はどのような結果になるのだろうか。各社が公表している23年度の業績予想を見ると、好業績を見込んでいる企業が多いようだ。23年度は苦戦が目立ったHC、百貨店も24年度の業績予想では増収・増益を計画している企業が多い。
22年3月頃から続く円安は出口が見えず、水道光熱費をはじめ各種コストは依然高止まりしているものの、足下ではインフレに対する消費者の受容が広がっており、「価格以外」の価値を訴求しやすい局面に入っているととらえることもできる。ここ数年は低価格訴求を強みとする企業がパイを奪うかたちで成長を続けてきたものの、この先はこれまでとは違う競争が見られる可能性も高そうだ。
本誌毎年恒例の「決算ランキング」特集では営業収益だけでなく、ROAやROE、総資産回転率、売上総利益率、在庫回転率、時価総額といった経営指標のほか、既存店売上高や期末店舗数といった小売経営において重要なデータを主要業態別にまとめている。各業態各社の業績指標を読み解けば、強さの理由が浮かび上がってくるはずだ。
インフレに人流回復、インバウンドとさまざまな要因が絡まり、業態間だけでなく、企業間の格差も鮮明にあらわれた23年度決算。勝ち組、負け組を分けた要因は何だったのか。各業態各社の業績指標から読み解いていただきたい。
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
いよぎんHDの24年度中間決算「増収増益」で過去最高を更新
南海放送NEWS / 2024年11月8日 16時20分
-
【決算深読み】パナソニックHD決算 2024年度上期は予想覆す改善、AI関連で好調目立つ
マイナビニュース / 2024年11月1日 16時2分
-
相鉄HD、純利益70%増の152億円 9月中間決算、不動産分譲業が好調
カナロコ by 神奈川新聞 / 2024年11月1日 5時0分
-
富士通、24年上期の決算発表 - 売上収益が減収、通期の営業利益を下方修正
マイナビニュース / 2024年10月31日 18時4分
-
NECが24年上期決算を発表 - 森田社長がNECネッツエスアイのTOBに対して言及
マイナビニュース / 2024年10月29日 19時38分
ランキング
-
1相鉄かしわ台駅、地元民は知っている「2つの顔」 東口はホームから300m以上ある通路の先に駅舎
東洋経済オンライン / 2024年11月22日 6時30分
-
2「築浅のマイホームの床が突然抜け落ちた」間違った断熱で壁内と床下をボロボロに腐らせた驚きの正体
プレジデントオンライン / 2024年11月22日 17時15分
-
3三菱UFJ銀行の貸金庫から十数億円抜き取り、管理職だった行員を懲戒解雇…60人分の資産から
読売新聞 / 2024年11月22日 17時55分
-
4ジャパネット2代目に聞く「地方企業の生きる道」 通販に次ぐ柱としてスポーツ・地域創生に注力
東洋経済オンライン / 2024年11月22日 8時0分
-
5会社員が考える“テレワークのデメリット” 「会話不足」「公私の切り替えが曖昧」を超えた1位は?
ITmedia ビジネスオンライン / 2024年11月22日 7時0分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください