資生堂は1500人、オムロンは2000人…なぜ今、日本の大企業は「人員削減」を行い、多くの場合で「中高年」が対象なのか
Finasee / 2024年5月22日 20時0分
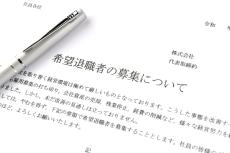
Finasee(フィナシー)
大企業に入社できれば一生安泰?
2024年3月期決算を発表するタイミングに合わせ、大企業の多くが人員削減を発表しています。一例を挙げると……
資生堂・・・国内で早期退職1500人を募集。45歳以上かつ勤続年数20年以上の社員を対象。
オムロン・・・国内外で2000人の削減。国内においては1000人の希望退職を募集。勤続年数3年以上かつ年齢40歳以上の社員が対象。
東芝・・・間接部門を中心に、早期退職優遇制度で最大4000人を削減。
コニカミノルタ・・・国内外で2400人の人員削減。事務機などの海外生産拠点や、各国の販売子会社などの正規社員と非正規社員を対象。
ワコール・・・150人の希望退職者を募集。勤続年数が15年以上の販売職を除く従業員のうち、満45歳以上の正社員および契約社員、満50歳以上の管理職と定年後再雇用者が対象。
住友化学・・・国内外で4000人の人員削減。事業売却や再編、合理化などを通じて削減する。
東京商工リサーチが5月17日に発表した「2024年上場企業『早期・希望退職募集』状況」によると、5月16日までに「早期・希望退職募集」が判明した上場企業は27社で、前年同時期の20社に比べて増加しました。上場区分では東証プライム市場上場企業が17社を占め、募集を開始した企業の直近通期最終損益は17社が黒字でした。
ちなみに前回調査では、募集企業21社のうち、黒字企業は12社だったので、黒字決算でもリストラを進める企業が増えていることが分かります。また、上記に挙げた5社のうち、東芝は非上場になっているので、東京商工リサーチの数字には含まれていません。
整理解雇、希望退職、早期退職…どう違う?ところで、ニュースなどでは単純に「人員削減」という言葉が用いられますが、人員削減にもさまざまな種類があります。
「整理解雇」は、企業経営が悪化している時に人件費を削減するために行われるものですが、解雇の原因が社員ではなく企業側にあるため、それを行える要件が厳しくなります。具体的には「役員報酬の減額」、「賞与の不支給」、「希望退職者の募集」を行ったうえで、それでも経営が厳しいという場合にのみ、整理解雇が認められます。
「希望退職」は、企業が一定の期間や範囲を定めて退職希望者を募り、その期間内に退職希望を出した社員に対して、割増退職金や有休休暇の買取、再就職の斡旋といった優遇措置を取ります。一般的に「早期希望退職」という言い方をするケースもありますが、厳密には早期退職と希望退職は異なります。
希望退職はリストラ策の一環で、企業の経営が厳しい時などに行われますが、早期退職は希望退職と同じく、手を挙げた社員に対して優遇措置を講じるものの、その目的は、組織の若返りやキャリア支援など福利厚生的な意味合いがあります。
「退職勧奨」は、企業側から社員に退職を推奨し、双方が合意したうえで退職してもらうというものです。希望退職とどう違うのかという点ですが、希望退職は退職を希望する人たちが自ら手を挙げるのを待っているのに対し、退職勧奨は企業が特定の社員に退職を勧めます。一般的には職務怠慢や問題行為がある社員に対して、無用のトラブルが生じるのを回避しつつ、円満に退社してもらいたい時に行われます。
「派遣社員の削減」は文字通り、契約期間が満了した時点で更新をせず、人員を削減するというものです。
この4つが人員削減の主だったものです。
また人員削減というと、「レイオフ」という言葉を思い浮かべる方もいらっしゃるでしょう。レイオフとは、イギリスやアメリカにおいて、企業の業績悪化などを理由に行われる解雇のことですが、もともとは一時解雇を意味し、業績が回復したら再雇用することを条件にしていました。
しかし最近のレイオフは、再雇用条件なしの恒久的な解雇であるのが一般的になっており、一時解雇に関しては「テンポラリー・レイオフ」と称しているようです。総じて、再雇用条件のないレイオフが多くを占めているということです。
多くの人員削減で、なぜ「中高年」が対象になるのかこの手の人員削減は、中高年をターゲットにしたものが大半を占めています。これは、企業として中高年社員に辞めてもらいたいと思っているからに他なりません。
独立行政法人労働政策研究・研修機構の「各年齢階級における正規、非正規の内訳」というデータを見てみましょう。
ここでは正規社員の人数を参考にします。1988年と2023年の年齢階級別従業員数を比較してみましょう。
25~34歳・・・878万人→818万人(▲6.8%)
35~44歳・・・927万人→843万人(▲9.1%)
45~54歳・・・717万人→984万人(+37.2%)
55~64歳・・・307万人→571万人(+86.0%)
65歳以上・・・36万人→126万人(+250.0%)
1988年から2023年までの35年間で、日本企業が超高齢社会になっていることが分かる数字です。
そして、組織の高齢化が何をもたらすのかを考えてみて下さい。一番の問題点は、特に年功序列的な色合いの濃い日本企業の場合、年齢が上がるほど給与が増えていきますから、企業側からすればコストがアップすることになります。
国税庁の「年齢階層別の給与額」を見てみましょう。あくまでも平均値ですが、従業員が5000人以上の大企業の場合、年収ベースでは以下のようになります。
20~24歳・・・233万1000円
25~29歳・・・414万2000円
30~34歳・・・488万円
35~39歳・・・540万5000円
40~44歳・・・587万5000円
45~49歳・・・606万円
50~54歳・・・610万円
55~59歳・・・633万3000円
60~64歳・・・387万5000円
65~69歳・・・265万3000円
70歳以上・・・233万円
このように、平均給与のボリュームゾーンを見ると、45歳から59歳までの年齢階層が最も高額になっています。高給なうえに社員数も多いため、企業にとってはこの層のコスト負担が非常に重くなっているのです。
そのうえ、今は65歳定年が当たり前になり、ゆくゆくは70歳定年も視野に入りつつあります。
企業としては、これだけの人数を占めている中高年社員を、さらに65歳、70歳まで雇い続けていけるだけの余裕が無くなっているとも言えます。そのため、少しでも早い段階で、中高年社員の人員削減に着手し始めているのです。黒字であるにも関わらず人員削減を行っている企業が多いのは、これから先の人件費負担増を出来るだけ軽減したいと考えているからです。
1980年代半ばから1990年代にかけて社会人になった人たちが、まさに人員削減のターゲットになっています。この年齢層の人たちはかつて、「大企業に入れたら一生安泰」などと言われたものですが、30余年という時間の流れは、この程度に当時の常識を覆すだけの力があるということです。
鈴木 雅光/金融ジャーナリスト
有限会社JOYnt代表。1989年、岡三証券に入社後、公社債新聞社の記者に転じ、投資信託業界を中心に取材。1992年に金融データシステムに入社。投資信託のデータベースを駆使し、マネー雑誌などで執筆活動を展開。2004年に独立。出版プロデュースを中心に、映像コンテンツや音声コンテンツの制作に関わる。
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
「早期・希望退職」募集が続出する2つの理由…3年ぶり1万人超えへ
日刊ゲンダイDIGITAL / 2024年6月11日 9時26分
-
上場企業27社が「早期・希望退職」を募集 3年ぶりに1万人超えの可能性
ITmedia ビジネスオンライン / 2024年5月24日 17時50分
-
勤続18年、退職金が「1000万円」ほど出るので早期退職を考えていますが、周囲から「早期退職だと税金が高い」と言われます。実際、そんなに大きな差があるのでしょうか?
ファイナンシャルフィールド / 2024年5月22日 2時30分
-
上場企業「早期・希望退職募集」は27社、対象は4000人超 - 年齢制限ない募集も
マイナビニュース / 2024年5月21日 10時3分
-
テスラの人員削減が韓国を襲う―韓国メディア
Record China / 2024年5月20日 14時0分
ランキング
-
1中国の過剰生産「有害」=雇用保護へAI行動計画―G7首脳声明
時事通信 / 2024年6月15日 16時44分
-
2バーガー店打撃…日銀「国債買い入れ減額」で “歴史的円安”に歯止め?
日テレNEWS NNN / 2024年6月15日 13時57分
-
3「阿武隈急行」の赤字穴埋めする2県5市町の補助金、宮城・柴田町が2358万円の支払い拒否
読売新聞 / 2024年6月15日 20時24分
-
4アップルにEUが制裁金、世界売上高10%の可能性…デジタル市場法違反に初認定か
読売新聞 / 2024年6月15日 15時19分
-
5「南高梅」が全国で記録的不作、価格は例年の3〜4倍に…「こんなことは初めて」
読売新聞 / 2024年6月15日 12時4分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください











