「30代は保守的?」企業型DCの資産配分、65万人のデータからわかった意外な事実
Finasee / 2024年6月28日 11時0分
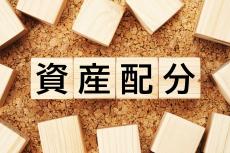
Finasee(フィナシー)
リーマンショックから15年超、アベノミクスによる株価上昇トレンドへの転換から10年超が経過しました。2024年になってから、日経平均株価は史上最高値を更新し、確定拠出年金(DC)の資産残高が大きく増えている方が多いことと思います。そんななか、企業型DCの実施事業主が気にされていることがあります。30代加入者の動向です。
掛金の配分割合は、元本確保のみ派と投信派に分かれる傾向企業型DC実施事業主の危惧は、次のようなものです。
「最近、入社した20代は投資にアレルギーがないが、少し上の世代の30代は保守的で、運用結果も出ていないのではないか」
特定の企業をピックアップしてみると、そうした傾向もみられましたが、全体としてはどうでしょうか。そこで、野村證券が受託している企業型DC加入者約65万人分の傾向をデータから検証してみました。
毎月の掛金の資産配分に着目し、元本確保型商品(定期預金・保険商品)への配分を100%から0%(つまり投資信託100%)まで10%きざみで集計しました。その結果として、100%と0%の両端に人数が集中します(以降、元本確保型100%を元本確保のみ派、0%を投信派と呼称します)。
これは以前からみられる傾向で、投資信託を選ぶ人は全額を投資信託に配分し、そうでない人は元本確保型のみを選ぶことが多いといえます。
DC制度では、配分指定を1%単位で行えるので、元本確保型と投資信託の組み合わせも可能ですが、組み合わせる人は多くありません。棒グラフにすると、100%と0%に大きな山が存在し、間には少しだけ棒がある、というイメージです。このグラフの形状について、加入者全体と30代では、「違いがある」といえるほどの差は見られませんでした。
年代による差よりも、資格取得年による違いが顕著年代による差があまりないのであれば、次は市場動向などの環境要因が考えられます。そこで、企業型DCの資格取得年(企業型DCで加入者になった年)で区切ってみると、明確な違いが浮き彫りになりました。
2010年代までに資格取得した場合、元本確保のみ派の人数が2割前後、投信派の人数は5~6割という傾向がみられました。残り2割の人が元本確保型と投資信託を組み合わせていて、中央(半々のところ)に少しだけ山がある、というイメージです。これは、どの年代でもほとんど変わりません。
それが2020年代の資格取得者から、変化がみられるようになります。
元本確保のみ派の人数が1割、投信派の人数が7~8割となり、元本確保型と投資信託を組み合わせた人は1割程度に減少しました。とくに20代では元本確保のみ派の人数は1割を切り、投信派の人数が8割を超えています。
最近の新卒入社者に投信派が多いことは認識していましたが、上の年代であっても同じ傾向である、ということがはっきりとわかりました。市場環境の好転やつみたてNISAの定着などが影響しているものと思われます。
「考える機会」が運用見直しにつながる可能性上記で活用したデータは、2024年4月時点の掛金の配分割合です。にもかかわらず、資格取得年と現在の年齢で区切って明確な違いがみられることが企業型DC実施事業主の悩みにつながってきます。
30代はリーマンショック後から2010年代に入社した人が多く、20代と比較すると保守的な配分の人が占める割合が高いといえます。さらに、運用商品の変更はいつでもできるのに、資格取得時の配分のまま放置している人が大層という影響もあります。
一方で、2020年代に資格取得した人は、40代・50代でも投信派が多くなっています。つまり他の企業からの離転職者が、新たな企業でのDC資格取得を機に運用見直しを実施しているとも考えられます。このことは、「考える機会」があれば運用見直しにつながる可能性がある、ともいえるでしょう。
配分指定書の配布・回収で「考える機会」をつくる離転職といった個人の事情ではなく、企業として「考える機会」を提供するためには、退職給付制度の見直しや運用商品の除外が想定されます。しかし、双方ともに、簡単にできることではありません。
そこで、比較的実施しやすいのが、配分指定書の配布と回収です。定期的に拠出される掛金の資産配分を変更することで、少しずつリスク量を増やしたり減らしたりすることが可能になります。するべきことが明確なため、行動を促しやすいという面もあります。その際、判断基準になるような情報も伝える必要があります。たとえば、次のような内容です。
・配分する運用商品で運用結果が大きく異なる
・毎月の掛金の配分変更は、金額が大きくないので実施しやすい(スイッチングはむずかしいが掛金の変更は取り組みやすい)
・過去のデータではあるが、バランス型投資信託を10年間保有した場合、マイナスになる確率はとても低い
・タイミングを考えるのではなく、今から実施する
ペーパーレス化の流れに逆行する施策ですが、企業型DCを通じて投資に向き合う機会は重要です。また、DCの活用はもっとも税優遇のメリットが大きくなります。「資産運用立国」で投資やDC制度が注目されている今だからこそ、企業型DCの活性化を実現していただきたいと思います。
津田 弘美/野村證券株式会社 確定拠出年金部
社会保険の専門出版社において、企業年金分野の編集記者として厚生労働省記者クラブ等に所属。厚生年金基金の隆盛期から企業年金2法の成立等を取材。その後、野村年金サポート&サービス(現在は野村證券に合併)に入社。確定拠出年金の運営管理業務に10年以上にわたり従事し、投資教育の企画立案、事業主サポート等を担当。業務の傍ら、横浜国立大学大学院において、理論と実務の両面から企業年金制度についての考察を行う。横浜国立大学大学院国際社会科学研究科博士課程後期課程修了(経営学博士)。
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
企業型確定拠出年金のことがよく分からないまま運用しています…利益を出すにはまず何から始めるべきですか?
Finasee / 2024年11月19日 11時0分
-
野村證券で売れ筋になった新ファンド「野村ブラックロック世界優良企業厳選ファンド」はS&P500を超えるのか?
Finasee / 2024年11月15日 6時0分
-
シリーズ オルタナティブ投資 発展の歴史 第5回 最近のオルタナティブ投資事情(後編)
Finasee / 2024年11月8日 7時0分
-
「なんで今まで教えてくれなかったんだ!」確定拠出年金に無関心だった同僚が目覚めた“資産残高の差”が生まれる理由
Finasee / 2024年10月31日 12時0分
-
シリーズ オルタナティブ投資 発展の歴史 第4回 どうやって投資するのか?(前編)
Finasee / 2024年10月30日 7時0分
ランキング
-
1「バナナカレー」だと…? LCCピーチ、5年ぶりに「温かい機内食」提供…メニューは? 「ピーチ機内食の代名詞」も復活
乗りものニュース / 2024年11月24日 12時32分
-
2冬の味覚ハタハタ、海水温上昇で今季の漁獲量は過去最低か…産卵場所に卵ほとんど見つからず
読売新聞 / 2024年11月24日 11時52分
-
312月に権利確定「株主優待」長期保有が嬉しい銘柄6選
THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年11月24日 9時15分
-
4年収壁見直し、企業の9割賛成 撤廃や社保改革要請も
共同通信 / 2024年11月24日 16時22分
-
5「ワークマン 着るコタツ」新モデルが登場 累計43万着を突破、人気の秘密は?
ITmedia ビジネスオンライン / 2024年11月22日 11時24分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください









