バブル世代の「豪華すぎる内定争奪戦」とは? その後の〈就職氷河期世代〉が背負わされたバブル時代の大きすぎたツケ<br />
THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2025年2月4日 8時15分
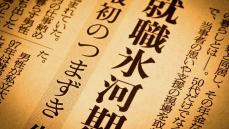
「就職氷河期」という言葉がメディアに初めて登場したのは、1992年秋のことです。当時、リクルートが発行していた就職情報誌『就職ジャーナル』に登場した造語であり、94年には新語・流行語大賞の「審査員特選造語賞」を受賞しています。本記事では、第一生命経済研究所の首席エコノミストである永濱利廣氏による書籍『就職氷河期世代の経済学』(日本能率協会マネジメントセンター)より一部を抜粋・再編集して、「就職氷河期」はなぜ生まれたのか、その前後の時代背景からわかりやすく解説します。
「就職氷河期」当時の採用市場とは?前後の世代と比較した違い
「就職氷河期」という言葉がメディアに初めて登場したのは、1992年秋のことです。当時、リクルートが発行していた就職情報誌『就職ジャーナル』に登場した造語であり、94年には新語・流行語大賞の「審査員特選造語賞」を受賞しています。
景気には波がありますので、日本でもたびたび就職難の時代は訪れています。1929年に公開された映画『大学は出たけれど』(小津安二郎監督)は流行語にもなっており、それからしばらくして起こった昭和恐慌では、大学や高専を卒業した学生でさえ就職が難しく、特に大卒文系の学生は就職率が4割を切ったと言われるほどの就職難に見舞われています。
くわえて、以後もたびたび就職難の時代は訪れています。しかし、1990年代にそれまでの「就職難」ではなく、「就職氷河期」という言葉が生まれたのは、その直前までの就職事情が「バブル景気」を背景とした「超売り手市場」であったことと関係しています。
バブル景気というのは、内閣府の景気動向指数上で1986年12月から1991年2月までの期間を指しています。そして、バブル景気の発端となったのは、1985年9月の「プラザ合意」です。プラザ合意というのは、先進5か国(日米英独仏)の蔵相(日本の場合。現在は財務大臣)と中央銀行総裁による過度なドル高を是正するための合意です。
ドル高による巨額の貿易赤字に苦しんでいたアメリカの呼びかけで開催されて合意に至ったわけですが、当時の円安によって輸出産業が好調だった日本ではプラザ合意以後、急速なスピードで円高が進行し、円高不況に直面します。
その打開策として、日銀が低金利政策に踏み切ったことで企業は融資を受けやすくなり、設備投資だけでなく、土地や株式の購入にも資金が流れ込み、地価や株価が高騰し始めたことによって始まったのがバブル景気です。
なかでも地価の高騰は凄まじく、バブル景気の最盛期には「土地の価格は絶対に下がらず上がり続ける」という「土地神話」を多くの企業や人が信じ込み、不動産関係の企業だけでなく、一般の企業も本業とは関係のない土地の購入やリゾート開発などに乗り出すなど、空前の不動産ブームが巻き起こりました。
そして土地さえ持っていれば、金融機関から多額の融資を受けることができ、そのお金でさらに土地を手に入れるという、まさに土地が巨額のお金をもたらす時代でした。土地の購入は日本国内だけにとどまらず、海外の不動産取得を進める企業も多く、企業経営者の中には不動産や株への投資で本業の何倍もの利益を上げ、その戦果を誇らしげに語る人もいたほどです。
反対に、この時期に株や不動産への投資を積極的に行わなかった企業は「変わり者」扱いされるほどで、日本ではまさに空前の不動産ブームが起こった時代と言えます。
企業や個人が株や不動産で巨額の利益を手にしたことで、今では考えられないことですが、高級車や高級住宅地、高額なブランド品なども飛ぶように売れ、社会全体がそれまでにない好景気を実感したのがバブル景気の時代でした。
バブル景気を取り上げた各種作品などで、タクシーを止めるために1万円札を手に持ってひらひらさせた、クリスマスには高級ホテルがカップルで満室になった、彼女にプレゼントするために高級ブランドショップに人が殺到した、といったさまざまなエピソードが披露されていますが、たしかにバブル景気の時代には、比較的多くの人が好景気を実感していたと言えます。
超売り手市場から就職氷河期へ
こうした好景気を背景に繰り広げられたのが、就職活動の「超売り手市場」です。当時は大卒男子の半数近くが上場企業に就職できた時代であり、銀行や保険、証券といった当時人気のあった金融業界や、勢いのあった不動産業界などに多くの学生が応募し、多くが採用された時代です。
この時代、上場企業といえども、人気のない企業が優秀な学生を採用することはとても難しく、企業説明会に出席した学生たちに交通費を支給したり、テレホンカードなどを配布したりすることはなかば常識になっており、学生の中には何社もの説明会を掛け持ちすることでかなりの金額を手にする人もいたほどです。
なかでも熾烈(しれつ)を極めたのが、内定者をいかに正式採用にまで持って行くかです。なかには資料請求のはがきを出したら返信ハガキが内定通知だったとか、説明会に参加しただけで内定が出た、といった今では考えられないほど簡単に内定(表向きは内定解禁日前の内定のため「内々定」)が出たため、学生の中には複数の内定は当たり前で、なかには二けたにのぼる内定を手にする人も珍しくなかったほどです。
もちろん、簡単に内定が出るからと言って、誰もが希望する大企業に就職できるわけではありませんでした。しかし、就職氷河期のような「そもそもスタートラインにさえ立てない」ということはなく、多くの学生が大手企業の説明会に参加し、面接などに進むことができた時代でもありました。
反面、学生が多くの内定を手にすればするほど、その選択権は学生が握ることになります。結果、企業の採用担当者は「多すぎる採用人数」を確保するために一定の辞退者を見越した多めの内定を出すわけですが、次には内定辞退を防ぎながら採用目標を達成することが求められます。
そこで繰り広げられたのが、内定者を「囲い込む」ための頻繁な食事会や、内定解禁日に他社に行かれるのを防ぐための温泉旅行や海外旅行です。当然、膨大な経費がかかりますが、バブル期には各企業とも驚くほど多くの人を採用していただけに、その人数を確保するためには、学生のレベルを落としてでも内定を出すほかありませんし、内定辞退を防ぐためには他社に負けないだけの「接待」をするほかなかったというのが実情でした。
学生はまさに「金の卵」であり、「大切なお客さま」でした。実際、私も学生時代、先輩たちがあまりにも簡単に内定を手にする話を聞いて、「就職活動ってこんなに簡単なんだ」と高を括っていました。
しかし、いざ自分が就職活動をする際には就職氷河期と重なったことで、「話が違う」と慌てたことを覚えています。
こうした今では考えられないような「超売り手市場」で就職活動をした世代が、いわゆる「バブル世代」です。バブル世代は好景気の時代を経験し、好景気の時に恵まれた就職活動を行い、好景気の時に社会に出るわけですが、ほどなくしてバブルが崩壊したことで長く続く景気低迷の時代を生きることになります。
バブルの崩壊によって大きな痛手を受けたのは、バブル景気の中で業容を拡大し、不動産投資や株式投資に多額の資金を投じ、必要以上に多くの人員を採用した企業です。要因としては、行き過ぎたバブルを抑えるための借り過ぎや貸し過ぎを防ぐために設けられた融資限度額に対する総量規制や地価税の導入、公定歩合の引き上げなどを挙げることができます。
資金を断たれた上に、融資の担保にしていた不動産の価格が急落、担保割れを起こして倒産に追い込まれる企業も少なくありませんでした。結果、バブル崩壊によって過剰設備や過剰債務、過剰人員の問題を抱えることになった企業は、こうした負の遺産の解消に取り組むほかはなく、その1つとして「採用数の極端な抑制」に取り組むこととなったのです。
その意味では、就職氷河期世代はバブル期のあまりに大きすぎるツケを払わされることになったと言えるでしょう。
永濱利廣
第一生命経済研究所
主席エコノミスト
この記事に関連するニュース
-
「最終面接落ちた」で他社からスカウトも…売り手市場続く大学生の就職活動 人材確保のため採用方法が多様化
東海テレビ / 2025年2月3日 21時53分
-
国民、就職氷河期世代支援に着手 参院選へ新看板政策
共同通信 / 2025年2月2日 16時3分
-
氷河期世代の暗黒「正規で働きたいのに…」→「年金をもらうのすら厳しい」老後破産の現実味
THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2025年1月16日 17時15分
-
〈手取り月24万円〉〈家賃4万5,000円〉47歳の非正規男性、年金機構から届いた「警告文」に臨戦態勢の構え「もう我慢の限界です」
THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2025年1月16日 7時15分
-
「円高で苦しく、円安でラクになる」が常識だったが…ここまで変わった「戦後から現在まで」日本経済の実情【経済評論家が解説】
THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2025年1月11日 9時15分
ランキング
-
1函館のラブホテル社長が語る“ラブホ経営”の難しさ。「2日間部屋が使用できない」困った用途とは
日刊SPA! / 2025年2月3日 15時51分
-
2《昭和生まれのお菓子ランキング》ベビースター抑えた1位は昭和39年発のメガセラー商品
週刊女性PRIME / 2025年2月3日 21時0分
-
3タイヤの謎の暗号!?「赤い丸」「黄色の丸」の意味は 無視すると「危険」ですか…? 2種類の「メッセージ」はドライバーに何を伝えているのか
くるまのニュース / 2025年2月4日 6時50分
-
4タイに移住した36歳男性が明かす、“食費だけで10万円近い”リアルな生活費「屋台飯はあまり食べなくなった」
日刊SPA! / 2025年2月3日 15時53分
-
5飲まない夫が「お酒やめたら?」と言い出した。理由は「女性としてキレイに見えない」から
オールアバウト / 2025年2月3日 22時5分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください









