難聴で認知症リスク5倍!?耳の不調を遠ざける3つのケア
ハルメク365 / 2024年6月4日 11時50分

前回は耳の聞こえの悪さが認知症のリスクを高めることを解説しました。そこで今回は、耳の聞こえをよくするために今日からできるセルフケアを紹介。川越耳科学クリニック院長の坂田英明さんの解説とともに、難聴&認知症予防につながる生活習慣を紹介します。
体をサビつかせる活性酸素の発生を抑えることが大切

認知症の原因ともいわれる老人性難聴は、なぜ起こるのでしょうか。前回説明したように、耳から入った音の振動は、蝸牛(かぎゅう)で電気信号に変換され、脳へと伝わります。
蝸牛には、特殊な線毛が生えた有毛細胞があり、この有毛細胞が揺れることで振動は電気信号に変わるのです。
「しかしながら、この有毛細胞は、年を取るにつれてダメージを受けて数が減少していき、一度壊れると再生することのない、人体で最も弱い細胞の一つなのです」と坂田さん。
有毛細胞がダメージを受けると、振動を電気信号に変換する力が衰え、脳に伝わる情報量も減ってしまいます。
「実は最近の研究で、有毛細胞のダメージには遺伝子が関与していることがわかってきました。Bak遺伝子という細胞死(アポトーシス)を引き起こす遺伝子によって有毛細胞が壊され、難聴になってしまうというわけです」(坂田さん)
「このBak遺伝子は、体をサビつかせる活性酸素が増えると活発に動き出すことがわかっています。よって基本は規則正しい生活と、栄養バランスのとれた食事などで活性酸素の発生を抑えることが大切です」と坂田さんは言います。
メタボ予防は難聴予防にもつながるさらに、内臓肥満に高血圧・高血糖・脂質代謝異常が組み合わさり、動脈硬化を招きやすいメタボリックシンドロームも、難聴を引き起こす原因の一つです。
「動脈硬化により血流が悪くなると、クモの糸のように細い内耳の血管は、ささいなことで詰まりやすくなったり、血流が途絶えたりと影響を受けてしまいます」と坂田さん。メタボ予防は難聴予防にもなる、と覚えておきましょう。

また、ゆらゆら揺らいでいる有毛細胞が、騒音や突然の大音量によって激しく揺れることで、倒れたり絡まってしまうこともあるといいます。「イヤホンで音楽を聴き続けたり、携帯電話を長時間耳に当てて話した後に耳が聞こえにくくなったケースもあります」と坂田さん。耳に負担をかけないよう心掛けましょう。
今日から取り入れたい!耳にいい9の生活習慣
それでは、耳の若さを保つ生活習慣を紹介していきます。今日から取り入れられることばかりなので、ぜひチェックしてください。
1:2倍の速さで音を再生する2倍速で音楽や朗読を流し、意識を集中して聞く力を鍛えるトレーニングは、聴覚とともに脳を活性化する効果が期待できます。3~4人による井戸端会議も、多方向から会話を聞き取ることで耳を鍛えるよい訓練になります。
2:香りと音を同時に楽しむ
難聴と認知症を同時に予防する方法としておすすめなのが、聴覚と嗅覚を一緒に働かせるトレーニング。アロマオイルやお香などの香りをかぎながら音楽を聴くことで、聴覚と嗅覚が同時に刺激され、脳全体が活性化します。
3:長時間の座りっぱなしを避ける長時間座りっぱなしでいると耳の中もむくみます。内耳はリンパで満たされているため、リンパの流れが悪くなると内耳も悪影響を受け、慢性化すると難聴に進むので、ご注意を。
4:コーヒーは1日1~2杯程度に
コーヒーに含まれるカフェインは、目覚まし効果などのメリットもありますが、取り過ぎると内耳を興奮させ、耳の健康によくありません。コーヒーは1日1~2杯程度が適量です。
5:紫外線を避ける紫外線を浴びると体内では活性酸素がつくられます。日傘や日焼け止めクリームなどで対策を。これからの季節、紫外線量の多い午前10時~午後2時は極力、紫外線を避けましょう。
6:ビタミンB12をしっかり取るビタミンB12には、内耳の血流を増やし、傷ついた神経を修復する作用があります。レバーや貝類、サンマやアジの干物、卵、焼きのりなどに含まれるので積極的に取りましょう。
7:ヘアカラーの溶剤に気を付ける
髪を染めるヘアカラーの溶剤には、有機溶剤アニリン色素の誘導体という神経毒性の強い化学物質が含まれているものがあります。染め剤を選ぶときには注意しましょう。
8:動脈硬化や血圧をコントロールする血流障害は難聴を引き起こす原因となります。健康診断などで動脈硬化や高血圧を指摘されている人は、きちんと治療してコントロールすることが、難聴予防にもつながります。
9:質のよい睡眠をしっかり取る睡眠不足による自律神経の乱れから難聴になることがあります。就寝前にぬるめのお湯にゆっくりつかって自律神経を整え、質のよい睡眠を取りましょう。
補聴器を活用するのも一つの手
国内の大規模調査「Japan Trak2022」によると、日本では、補聴器を着ける必要がある人のうち、実際に着けている人はわずか約15%。これは先進国の中で一番低い数字です。
前回説明したように、難聴は認知症のリスクを高めるので、耳の聞こえが悪ければ耳鼻科で相談して補聴器を活用しましょう。購入するときは、耳鼻科か、認定補聴器技能者という資格を持った補聴器のプロがいる販売店が安心です。
補聴器の種類耳かけ型
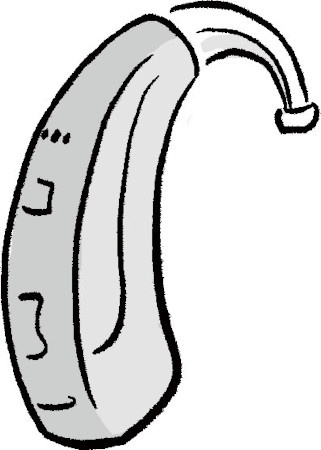
耳の後ろにかけて使うタイプ。本体が耳や髪で隠れるのであまり目立たず、小さくて軽いのがメリット。耳穴型より操作がしやすく、種類豊富です。ただし、汗で故障しやすく、メガネをかけている人は着けにくいのが難点。
耳穴型
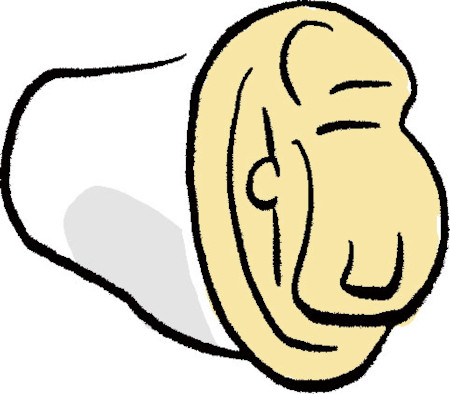
耳の穴にそのまま入れるタイプ。一般に難聴レベルの低い人向き。目立ちにくいため人気の形状ですが、汗や耳だれに弱く、小型化しているぶん操作しにくい、耳の形に合っていない、ハウリングを起こしやすいといった難点も。価格は高めですが、耳の形や聴力に合わせてオーダーメイドもできます。
箱型
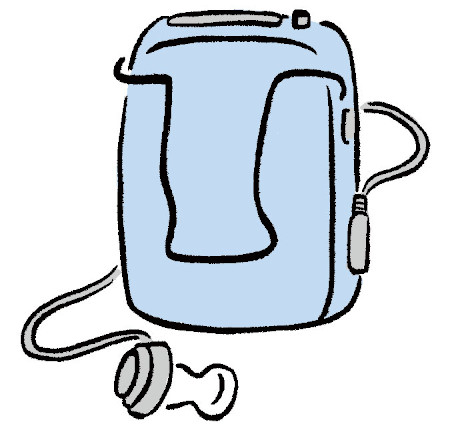
本体とイヤホンがコードでつながれていて、本体を胸ポケットなどに入れて使用する、昔からあるタイプ。価格が安く、本体は大きいぶん操作しやすいというメリットも。両耳に補聴器が必要な人や、よく動く人には不向き。本体のマイクが服にこすれる音がイヤホンに入りやすいのが難点です。
目と耳のケアをすすめる特集全5回、いかがでしたか?何事も早めの対処が吉。ぜひ今回紹介した耳にいい生活習慣や、目の疲れを改善&予防する生活習慣を取り入れてみてくださいね。
坂田英明(さかた・ひであき)さんのプロフィール

川越耳科学クリニック院長。1988年、埼玉医科大学卒業。91年、帝京大学医学部附属病院耳鼻咽喉科助手。ドイツ・マグデブルグ大学耳鼻咽喉科研究員、埼玉県立小児医療センター耳鼻咽喉科副部長を経て、2008年より目白大学保健医療学部言語聴覚学科教授。16年より現職。18年より埼玉医科大学客員教授、昭和女子大学客員教授。日本耳科学会代議員。日本聴覚医学会代議員。
取材・文=五十嵐香奈(編集部) イラストレーション=田上千晶
※この記事は雑誌「ハルメク」2021年5月号を再編集、掲載しています。
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
「もしかして難聴? それとも更年期?」と思ったら試してみて。セルフチェック方法【医師が解説】
OTONA SALONE / 2024年6月26日 16時31分
-
40代から難聴は始まる?「最近、聞こえづらくなってきた…」更年期にひそむ難聴リスク【医師が解説】
OTONA SALONE / 2024年6月26日 16時30分
-
ACジャパン支援のもと近藤真彦さん出演の難聴啓発キャンペーンを開始します!
PR TIMES / 2024年6月25日 16時45分
-
耳の奥の「キーン」を放置しないで!更年期以降の人に急増する、危険な梅雨シーズンの“耳鳴り”
週刊女性PRIME / 2024年6月22日 13時0分
-
毎日耳掃除をやってはいけない…耳鼻科医が解説「耳掃除は2週間に1回"手前だけ"で十分」な理由
プレジデントオンライン / 2024年6月5日 8時15分
ランキング
-
1Q. 納豆をより健康的に食べるには、どのような食べ合わせがおすすめですか? 【管理栄養士が解説】
オールアバウト / 2024年7月2日 20時45分
-
2藤井聡太“八冠再独占”への道 最大の難関は伊藤匠・新叡王への挑戦権獲得、トーナメントでの4連勝が必須
NEWSポストセブン / 2024年7月3日 7時15分
-
318÷0=?物議を醸した小3の宿題に東大生が反応。「教員の力不足」「思考力を磨く良問」などの声
日刊SPA! / 2024年6月30日 15時52分
-
4洗濯用洗剤、計量せず詰め替えパウチから注ぐ人がいるって本当!? メーカー「目分量はNG、原液こぼすと洗濯機が傷むことも」
まいどなニュース / 2024年7月1日 11時44分
-
5"ホワイト化"する企業で急増中…産業医が聞いた過剰なストレスを抱えてメンタル不調に陥る中間管理職の悲鳴
プレジデントオンライン / 2024年7月3日 9時15分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください











