アニメ、コロナの影響は製作だけでなく「宣伝」も 困難の先にある未来を予測する【この業界の片隅で】
マグミクス / 2020年5月18日 19時40分
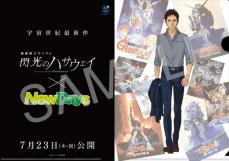
■オタクならではの「利用されたくない」心理
アニメ制作やアニメビジネスの現場における、「ちょっと知りたい話」「さまざまな裏話」を紹介します。今回は、アニメの宣伝についてのお話。業界の片隅で活動する「おふとん犬」さんが解説します。
* * *
アニメや関連コンテンツの企画書を読んでいると、やたらと目にするのが「イノベーター理論」です。かく言う私も、内心では無理があると分かっている企画をやむなくプレゼンすることになった時、少しでも説得力を持たせるために援用したことがあります。もちろん、理論の詳細までは理解しているわけがありません。
それでも簡単に説明させてもらうと、1962年に提唱された古典的なマーケティング分析だそうで、革新的な新商品を受け入れるユーザーを5つに分類するというものです。そのうちの16%を占める「イノベーター(革新者)」と「アーリーアダプター(初期採用者)」が重要で、残りの84%は彼らの動きに追随していくのだとか。ものすごく乱暴に言うと、「新しくて尖ったものがオタクの心に刺さらないと、広めようとしても広まらないよね」といったところでしょうか。
こういう話を聞くと、私のように短絡的で性格の悪い人間は、「じゃあ、影響力の大きいインフルエンサーをイノベーターとして雇えばいいじゃん」などと言い出します。実際、インフルエンサーマーケティングを事業主体としているPR会社はごまんとあります。
それ自体を否定するつもりはないのですが、私自身は、インフルエンサーマーケティングに積極的にはなれません。ファン心理を考えると、ターゲットに受け入れられなかった場合のリスクが大きすぎるからです。とりわけアニメや声優のオタクは、自らの意志で対象を好きになったという事実そのものに、強い誇りを抱いています。「誰かの商売の手段として好きにならされた」と後から明らかにされるのは、その誇りを傷つけられることに他ならず、「金儲け目当てのやつに利用された」「バカにされた」と感じるものなのです。
つい最近も、ネットで爆発的に話題を呼んだコンテンツが、実は「広告代理店案件」だったなどと大騒ぎになりました。冷静に考えれば、「広告代理店案件」でないコンテンツの方が少ないと思うのですが、そういうマイナスイメージがいったん広まり始めたが最後、リカバリーする手段を見つけるのが極めて困難になるのがネットの怖さです。
インフルエンサーを雇うより、誇り高きオタクたち自身にインフルエンサーになってもらう方が、宣伝としてはベターな手段と考えるべきでしょう。その呼び水とする、分かりやすいノウハウもいくつかありました。
新型コロナウイルス感染症による自粛が始まる前までは。
■コロナ禍で損なわれた宣伝ノウハウ
 コロナ禍で握手会などの接触イベントは中止に
コロナ禍で握手会などの接触イベントは中止に
身も蓋もない言い方をしてしまいますと、より多くの人が飛びつくのは、その時に流行しているものです。何をもって流行っていると判断するのか? シンプルに、目にしたり耳にしたりする機会の多さでしょう。だから宣伝には、物量や継続性=接触機会の多さが、ある程度は必要になってくるのです。とある有名コンテンツの関係者には、「作品の勝敗を左右するのは広告量です」と断言している方さえいます。いち早く流行に乗って、それを誰より深く極めて自慢したいというのは、普遍的なオタク心理でしょう。
ブランディングも重要です。ひと頃の有力なアニメ番組で、全国紙に全面(全15段1ページ)広告を掲載するという手法が取られていたことがあります。実はあの全面広告、目安の料金はネットで調べられるのですが、目の玉が飛び出るほど高額なのです。それでも行われていたのは、全国紙にこれだけ大きく載っているのだから、とてつもなく凄い作品に違いないと感じさせられるからです。本当に凄いかどうか自分で確かめてやろうと思うのも、オタク心理としてはありそうです。「オタク」という言葉が引きこもりを連想させるせいか、いまだに誤解されている向きがありますが、イノベーターやアーリーアダプターとなる彼らは、本来極めてアクティブな層です。
そのアクティブなオタクが、最も熱を入れるのが、ライブやお渡し会や舞台挨拶付き先行試写会といった、リアルイベントでしょう。イベントに参加したオタクたちは、「推し」が目の前に降臨した熱狂を、ネットを通して共有し、現場でグッズを購入し、信者となって布教に務めてくれます。客観的に見た完成度に首をひねらざるを得ない部分があっても、イベント参加者の間では大いに点が甘くなる傾向もあります。悪口を言っているのではありません。「モノ消費からコト消費へ」のような言い方を、耳にされたことはないでしょうか? 企業がオタクに「好き」を与えるのではなく、オタク自身の「好き」が企業を巻き込み動かしていく、そんな時代になっていたのです。
ここまで書くと、自粛で宣伝の何が損なわれたか、お分かりになっていただけるかと思います。街にどれだけ広告を出しても、肝心の人が歩いていなければ無意味です。かつてのようなリアルイベントも、当面は実施が難しいでしょう。そんな状況でブランディングに努めても、どれだけ効果があるでしょうか。
■それでも「好き」がある限り、未来は再び築かれる
 『VOCALOID2 HATSUNE MIKU』(クリプトン・フューチャー・メディア)
『VOCALOID2 HATSUNE MIKU』(クリプトン・フューチャー・メディア)
アニメに限らず全てのエンターテイメントが、これからしばらくの間、かつて経験したことのない事態に直面するでしょう。たとえば映画館は、すべての劇場で上映が再開できたとしても、興行収入は最大でも従来の30%~50%程度で推移するはずです。ソーシャルディスタンスを取るために1~2席開けの着席ということになれば、必然的にそうなるからです。
宣伝面に限っても、そもそもお金が掛けられなくなってきます。これまでのノウハウがどこまで通じるのかも、今はまだ、世界中の誰にもはっきりしたことは分かりません。それでも言い切れるのは、アニメをはじめとしたエンターテイメント自体が滅びることは決してないということです。
かつて結核が国民病と呼ばれていた時代、発症しているかどうかに関わらず、実に国民の約50%が感染していたという説があるそうです。そんな時代を経ても、さまざまな文化はさまざまに形を変えて、今に至るまで連綿と続いています。『文豪ストレイドッグス』のファンの方であれば、サナトリウム文学という、結核時代だからこそ花開いたジャンルさえあったことを、ご存知かもしれません。
サナトリウム文学のようなものとは言いませんが、アニメや声優の世界にも、時代の要請を受けて、新しいジャンルが芽生えて育つ可能性さえあります。そのジャンルを開拓するのも、おそらく企業ではなく、心からアニメが好きで、与えられるのでなく自分自身で「好き」を見つけようとするオタクでしょう。たとえどんな時代になっても、愛し続け、推し続け、自分自身でも絵を描いてみようと思う、あるいはステージに立ちたいと願う気持ちがある限り、エンターテイメントがウイルスに屈することはないのです。
予想を外すことに定評のある私が、「これは時代を変える可能性がある」と、いち早く明言して的中させたのが初音ミクです。長くなるので根拠の詳細は述べませんが、初音ミクを最初に見た時、作り手と受け手の区別のなさと広がりが、宣伝の力を凌駕するかもしれないと思ったのです。オタクの「好き」を取り込み続けることで、コンテンツ自らが意志を持つようにしてネットを通して発展していくのであれば、宣伝自体がもはや最小限のものしか必要なくなります。
新型コロナウイルス感染症による危機を乗り越えた後のアニメは、もしかすると、そんなふうになっていくのかもしれません。
(おふとん犬)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
身長182cmコスプレ美女、圧倒的スタイルに衝撃 “初音ミク”コスが話題
クランクイン! / 2024年11月12日 18時0分
-
コスプレ大好き海外インフルエンサー、「持っている服の半数以上は…」好きな日本のブランドとは?
オールアバウト / 2024年11月8日 21時25分
-
「身長差が凄い!」 身長182cm美人モデル、コス2ショットが衝撃的 スタイル抜群で連日話題に
クランクイン! / 2024年11月5日 18時0分
-
『ねんどろいど 初音ミク』限定の「ねんどろいど」フォトコンテスト開催決定!
PR TIMES / 2024年11月1日 18時15分
-
『キャラクター・ボーカル・シリーズ01 初音ミク』より、「初音ミク」がハロウィンにピッタリな小悪魔風の姿のねんどろいどが再登場!
PR TIMES / 2024年10月31日 14時45分
ランキング
-
1柳葉敏郎「暴れまくっていた」ドラマロケ地で謝罪「ぐちゃぐちゃにして帰ってしまいまして」
スポニチアネックス / 2024年11月24日 16時14分
-
2篠原涼子・市村正親の長男が警察ザタ!三田佳子の二男ら“お騒がせ2世”化を危ぶむ声も
女子SPA! / 2024年11月24日 15時47分
-
3上沼恵美子 PayPayの衝撃のチャージ額明かす スタジオ驚がく「30万でドキドキします!?」
スポニチアネックス / 2024年11月24日 15時57分
-
4水卜ちゃんも神田愛花も、小室瑛莉子も…情報番組MC女子アナ次々ダウンの複雑事情
日刊ゲンダイDIGITAL / 2024年11月24日 9時26分
-
5黒木メイサ 薄すぎる?メイクで新たな魅力発見「吸い込まれそうな瞳」「10歳は若く見える」と変化に驚きの声続々
スポーツ報知 / 2024年11月24日 19時29分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください









