キャピタルゲインとは|投資で得られる利益に対する確定申告や税金についても解説
楽天お金の総合案内 みんなのマネ活 / 2022年9月1日 10時0分

キャピタルゲインとは|投資で得られる利益に対する確定申告や税金についても解説
株式や債券、投資信託などに投資する目的の多くは、利益を得るためでしょう。投資から得られる利益は、「キャピタルゲイン」「インカムゲイン」という2つの種類に区別することができます。この2つの利益は性質が異なるため、どちらの利益を狙うかによって投資戦略も変わってきます。また投資で得た利益にかかる税金も、利益の種類によって課税方法などに違いが出てくるので確認が必要です。ここでは投資による利益と税金について、わかりやすく整理していきます。
キャピタルゲインとは
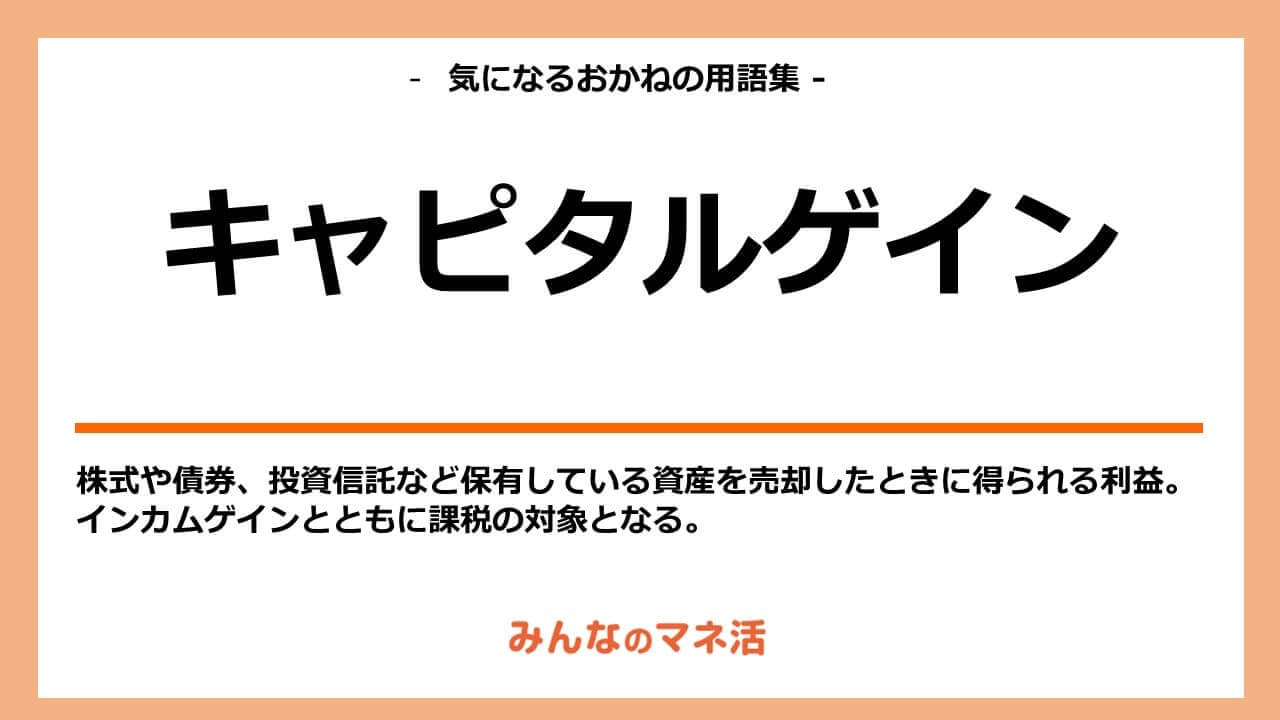
キャピタルゲインとは、保有している資産の価値が上昇し、それを売却した際に得られる利益のことです。資産には株式や債券、投資信託のほか、不動産なども含まれます。例えば、証券会社に口座を開設すると株式を購入できます。株式を購入した後、しばらくたって株価が値上がりしたとしましょう。値上がりした株式を売却すると、利益が得られます。そのときに得た利益を「キャピタルゲイン」と呼ぶのです。逆に値下がりしてから売却すると損をしますが、その損失は「キャピタルロス」といいます。
不動産でのキャピタルゲインについて、具体的な数字で確認してみましょう。例えば自分が住むための土地と家を3,000万円で購入したとします。しばらく住んだあと、引っ越しのために現在の土地と家は売却することになりました。その際、周辺の開発が進むなど人気の地域となっていれば土地の値段が上がっている可能性があります。土地と家を売ったときに5,000万円となっていれば、2,000万円のキャピタルゲインがあったということになります。
株式の場合「空売り」という信用取引が可能です。空売りでは、高値で売って安く買い戻すことで利益が出ます。このケースでは、売った資産を値下がりしたときに買い戻すことで利益が出ていることになります。最初の定義とは少し違うと感じるかもしれません。しかし、このときに得た利益についても、キャピタルゲインと呼んでいます。株や債券、不動産などの資産は、価格が変動します。資産を売買したときの、価格変動による利益と考えるとわかりやすいかもしれません。
キャピタルゲインの特徴

キャピタルゲインと対になる言葉に「インカムゲイン」があります。キャピタルゲインが保有する資産を売却したときに得られる利益である一方、インカムゲインは資産を保有している間に得られる利益のことです。例えば株式であれば「配当」、債券であれば「利子」、不動産であれば「賃貸収入」などがインカムゲインとなります。
キャピタルゲインはインカムゲインと比べて、1度に得られる利益が大きくなる可能性があります。例えば株式の場合だと、株式の保有で得られる配当金がインカムゲインに当たります。企業によって異なりますが、年間の配当は株価の数%というのが一般的です。では、株式の売買で得られるキャピタルゲインの場合はどうでしょうか。市場の環境も良く、企業利益が大きく増えると、株価が短期間に数十%上昇することはよくあります。年間では数倍になることもあり得るでしょう。
ただし、気を付けておきたいのは値下がりの可能性です。キャピタルゲインを狙って株式を購入したものの、大きく値下がりしてしまうことがあります。売却による利益は必ず出るものではなく、値下がりによるキャピタルロスとなるリスクについても、よく理解しておかなければなりません。
インカムゲインの特徴

為替レートの状況も、株価に影響を与えます。影響を受けるのは、輸出や輸入を行う企業の業績です。為替レートの状況は、円高ドル安・円安ドル高のように、円とドルの関係で表現することが多くなっています。
輸出企業の場合を見てみましょう。例えば1ドル100円の状況だと、1万ドルの商品を海外で販売し、売り上げを円に戻すと100万円になります。これが1ドル130円、つまり円安ドル高になると、同じ1万ドルの商品を売っても、円に戻すと130万円と30万円増えるのです。つまり円安ドル高の状況は、輸出企業の業績をあげる要因となり、株価を押し上げる可能性があるということです。海外で値下げをして、シェアを伸ばすという戦略も取れるかもしれません。
一方で、円安ドル高は、輸入企業にとっては不利な条件となります。1ドル100円の時、1万ドルの商品を輸入するには、100万円を1万ドルに変えて代金を支払います。これが1ドル130円になると、同じ1万ドルの商品を購入するためには、130万円が必要となります。円建てでの支払い代金が増えるため、業績にはマイナスに働き、株価を下げる要因となる可能性があります。逆に円高ドル安だと輸出企業にとっては不利に、輸入企業にとっては有利となり、業績への影響を通して株価に影響を与えます。
キャピタルゲイン、インカムゲインにはどのような税金がかかる?

資産の売却や保有で得られるキャピタルゲインとインカムゲインですが、どのように税金がかかるのでしょうか。証券会社で取引可能な株式と債券、投資信託について確認していきます。
日本の税制において、これらの資産を売却して得た利益(キャピタルゲイン)は所得税の対象となっています。また保有している間に得られる利子や配当(インカムゲイン)も所得税の対象です。所得の種類や課税方法などに違いがあるので、詳しく見てみましょう。
・譲渡所得(キャピタルゲイン)
株式等を譲渡して得た利益は、譲渡所得として課税対象となります。課税の方式は申告分離課税と呼ばれる、ほかの種類の所得とは区分して税額を計算する方式です。ここでいう「株式等」には、株式や公社債、投資信託などが含まれます。上場株式の場合、譲渡所得は次のように計算されます。
「総収入金額(譲渡価額)-必要経費(取得費+委託手数料等)=上場株式等に係る譲渡所得等の金額」
わかりやすくいえば、売却して得た金額から購入時にかかった金額と手数料などを差し引いた金額です。税率は20%(所得税15%、住民税5%)で、平成25年~令和19年の間は、ここに復興特別所得税(所得税の2.1%相当額)が加わります。これがキャピタルゲインにかかる税金です。
・利子所得(インカムゲイン)
利子所得とは、預貯金や公社債からの利子、公社債投資信託の分配で得た利益などのことです。税率は所得税と住民税、これに復興特別所得税が加わり20.315%となります。
銀行の預金には利子が付きますが、実はこれも利子所得です。預貯金の利子については、所得税が源泉徴収されて納税が完結するため申告は必要ありません。源泉徴収とは、天引きのことです。源泉分離課税と呼ばれる方式です。公社債からの利子、公社債投資信託の分配金については源泉徴収されますが、申告分離課税として確定申告もできます。また源泉徴収されたまま、申告不要とすることも可能です。
・配当所得(インカムゲイン)
株式から得た配当や、投資信託からの分配金などが配当所得にあたります。上場株式や公募株式投資信託から得た配当所得にかかる税率は、所得税・住民税などで20.315%となり、これが源泉徴収されます。源泉徴収したまま申告不要とすることもできますが、確定申告をすることも可能です。確定申告する場合は、総合課税(配当控除が適用できる)と申告分離課税が選択できるようになっています。
上場株式等の配当所得に関する課税方式については、2022年度の税制改正により、制度の変更が予定されています。これまでは「申告しない」「申告分離課税」「総合課税」の選択を、所得税と住民税で別々に行うことが可能でした。しかし、今回の改正により、2024年(令和6年)度分からは、所得税と住民税で同じ課税方式を選択しなければならなくなります。税金や社会保険料に影響することもあるため、確認しておきたいところです。
確定申告は必要?

確定申告は、所得税を申告して納税するために行います。会社員の方は源泉徴収と年末調整だけで完結しているという場合も多いと思いますが、自営業やフリーランスの方だと、毎年申告しているため、慣れている制度かもしれません。株式や債券、投資信託などから得られるキャピタルゲインやインカムゲインは、譲渡所得・利子所得・配当所得など所得税の課税対象です。基本的には確定申告により納税するものですが、証券会社で利用する口座の種類などによっては、申告が不要となる場合もあります。

・NISA口座
例えばNISA口座。NISA制度を利用できる口座です。NISA制度では、一定の投資額と期間において、配当金・分配金・売却益が非課税となります。税金がかからないので、確定申告も必要ありません。ただし年間の投資額には上限があります。
・特定口座
特定口座を利用し「源泉徴収あり」を選択した場合、基本的に確定申告の必要がありません。株式等の譲渡益にかかる税金は、証券会社が天引きして納税してくれます。しかし確定申告をしたほうが有利になる場合もあります。例えば複数の特定口座間での損益通算を行ったり、過去の損失について繰越控除を受けたりしたい場合は、確定申告をすれば納税額を減らしたり、還付を受けたりできる可能性があります。
特定口座では「源泉徴収なし」も選択できます。こちらを選択した場合は確定申告が必要ですが、証券会社が作成する年間取引報告書を使うのが便利です。1年間の譲渡損益を計算してあり、活用できます。
・一般口座
一般口座であれば、自分で年間の損益を計算して確定申告を行います。最近では、パソコンやスマートフォンから確定申告できるe-Tax(イータックス)も普及してきました。以前と比べ手軽になっているので、投資を始めたとしても確定申告で悩むことは少ないでしょう。

キャピタルゲイン・インカムゲインと、さまざまな種類の利益を得ることができる投資。株式・債券・投資信託への投資は、証券会社に口座を開くことでスタートできます。特定口座を作れば納税が簡単になり、NISA口座を開設すれば非課税制度の利用も可能です。老後資金などの長期的な資産形成では、投資が有利と考えられるでしょう。これまで資産が預貯金に偏っていたという方は、インフレ対策も兼ねて、証券口座を開設してはいかがでしょうか。これから口座開設を検討される方には、楽天証券の口座開設がおすすめです。楽天証券では、口座管理手数料が無料で使え、最低水準の手数料で資産形成を始めることができます。またチャットサービスなどのサポートも充実しており、投資初心者でも安心です。ぜひこの機会に楽天証券での資産形成を検討してみましょう。
この記事に関連するニュース
-
会社に勤めており、先月「年末調整」を行いました。所得には複数の種類がありますが、会社員にとってどのような関わりがあるのでしょうか?
ファイナンシャルフィールド / 2024年12月26日 22時20分
-
JTG証券、税金解説コンテンツ「債券の税金」に、確定申告の準備に役立つ「確定申告編」を追加!
PR TIMES / 2024年12月26日 9時0分
-
株で得た利益や損失の税金の申告方法について、説明が正しいのはどれ?【トウシルクイズ・税金】
トウシル / 2024年12月24日 7時30分
-
“塩漬け”になっている株式や投資信託を売って、NISAでの投資を考えています。損をした場合に何かできることはありますか?
ファイナンシャルフィールド / 2024年12月23日 23時0分
-
【事業売却】「税引後の売却対価」はいくら?個人・法人の「株式の譲渡所得」にかかる税金を計算
THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年12月19日 8時15分
ランキング
-
1今年流行った「大人の学び」が明らかに! 2025年に"注目すべきスキル"とは?
マイナビニュース / 2024年12月26日 17時3分
-
265歳以上で働くなら知っておきたい「シニアが得する制度」って?
オールアバウト / 2024年12月26日 20時30分
-
3トースターでお餅を焼くと中がかたいまま…上手に焼くコツをタイガーが伝授!「予熱」より「余熱」がおすすめ
まいどなニュース / 2024年12月25日 17時45分
-
4【10年に一度レベルの年末寒波】エアコン暖房の無駄を防ぐ部屋づくりのポイントは? - 節電の基本をダイキンが解説
マイナビニュース / 2024年12月26日 9時31分
-
5【MEGA地震予測・2025最新版】「能登半島地震以上の大きな地震が起きる可能性」を指摘 北海道・青森、九州・四国、首都圏も要警戒ゾーン
NEWSポストセブン / 2024年12月26日 11時15分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください










