谷川じゅんじ(JTQ) × 齋藤精一(Rhizomatiks)「MEDIA AMBITION TOKYO」対談インタビュー
NeoL / 2016年3月11日 20時3分

谷川じゅんじ(JTQ) × 齋藤精一(Rhizomatiks)「MEDIA AMBITION TOKYO」対談インタビュー
今年で4回目を迎える、最先端のテクノロジーカルチャーを実験的なアプローチで都市実装するリアルショーケース、MEDIA AMBITION TOKYO [MAT]が開催中。都内各所を舞台に最先端のアートや映像、音楽、パフォーマンス、ハッカソンやトークショーなどが集結し、都市の未来を創造するテクノロジーの可能性を東京から世界へ提示するこのテクノロジーアートの祭典は、回を追う毎に国内外で注目を集めている。主催であるMAT実行委員会の谷川じゅんじと齋藤精一に、MATの始まりから、コンセプト、可能性、導かれる未来図までを聞いた。
――まず、それぞれのお仕事の紹介をお願いできますか。
谷川「僕の仕事は空間を題材にしながら、コンセプト、空間、体験という3つのデザインを切り口として、これらを繋ぎ合わせることで、ブランディングという領域に様々な施策を押し上げていくことです。そのセンターにあるのは人で、体験によって人の記憶を作る仕事とも言えるかもしれません。食であれば食べておいしい、一緒にいた人と話して楽しい、あるいは展覧会で電気が流れるようなショックや感銘を受けたとか、そういう様々な経験ですね。直接的な体験も大切ですが、副次的に知ったり、関わってくれることも大切で、どういう風に記憶が繋げていくかというところでアウトプットのバリエーションが多いので、全体観は僕もわからないです(笑)」
――(笑)。ユニクロやマークジェイコブスなどの展示ブース、虎ノ門ヒルズのオープニングなど、谷川さんが手がけられたお仕事は幅広いですが、中心は“人”なんですね。ライゾマティクスはテクノロジーの最先端というイメージが大きいと思うんですが、ボディハックという思想があったり、実際は同じく“人”というところにフィーチャーされているのかなと。
齋藤「ライゾマというのは、テクノロジーがあまり表層に出すぎず、だけど裏ではたくさんすごいことをやってもらっていることが当たり前になっていくような、社会なのか街なのか、人なのか、もしくは人が身に着けているものなのか、そういうものに関わっていけたらなと思っている集団だと思っています。
うちが作っているものは、コンピューターやモーター、ギアだったりで、すごくハイテクなことをやっているけどどこかアナログ感があるんですよね。人肌の温度のあるような、そういうテクノロジーの使い方をしちゃってる。できてるんじゃなく、しちゃってるんです。この数年、携帯電話などいろんなものがスマート化しましたが、テクノロジーが出すぎるモノは消えていっている。だから、使う人間も、社会の中も含めて、テクノロジーがあまり前にでてこないものが普通になっていく気がしていて。今の社会はいい意味でやっと人間にフィーチャーされてきているから、その波と合っているのかなと。
今回、ライゾマティクスはアーキテクチャ部門(Rhizomatiks Architecture)を設立したんですが、なぜ建築かというと、やっぱり具体的に人に触れるところ、要はヒューマンスケールがあるからなんです。ウェブサイトにそれがあるかと言ったら、やっぱり二次元を通して、もしくは1.5次元を通してでしかなくて。そういう意味でも、10年やってみて、場所やモノを作ると最終的に“人”に行き着くんだなとつくづく思います」
谷川「そうですよ。ファッションに例えたら、いいブランドというのは、結局そのブランドを誰がいいと言っているかがメイン。受け止めてもらいたい層とコミュニケーションができているかがブランドのポテンシャルだと思うんです。受け止める人達が全部の価値を決めていくので、そういった意味では全ては人が中心に行く気がするんですね。そこがもしないならば、あってもなくてもいいものだというのも言える。人は結局全て人のために生み出すと思っています」

――そこがお二方の共通のコアなんですね。空間と建築というところでは出会いは必然なのかなと思いますが、知り合われた経緯は?
齋藤「某携帯会社さんが新しいブランドを作った時に、うちがそのデジタルコンテンツを作ることになって、初めてJTQのオフィスに伺ったときに初めてお会いしました。今でも忘れないのが、多人数がうごめいている中、谷川さんが大きな紙にぶわーっと絵を描いて提案したら、それで即決まっていったこと。その時に具体化できる力はすごいという勉強になった。イニシアチヴをとっていけるんだなと」
谷川「2008年の秋口ですね。みんなでその携帯電話を体験できるブースを作ったんですよ。空間はシンプルだったけど、中ではウェブとリンクするとかやたら難しいことやってて。全部のソリューションを使って、1個のブランドの体験を全方位的に形にするという走りだったんだよね」
齋藤「すごかったですよね。面白かった」
――お付き合いができて、お仕事だけじゃなくアイデア交換されたりする時間もあったんですか?
谷川「いや、とにかく現場主義だったので、全てプロジェクトベースでしたね」
――お仕事のマッチングがうまくいった要因は?
齋藤「僕が惹かれた部分は、谷川さんの具現化する能力。一番優れている人って全体のプランのミクロとマクロの行き来が早い人だと思うんです。要は万里の長城でレンガ1個1個を積み上げながら、これは全体的に何になるんだということが同時に見える人。そういう人はなかなかいないし、訓練しないと絶対できない。僕もその訓練をしようと思いました」
谷川「最初はものすごい数の人がいたので、特段齋藤さんの印象はないんです。テクノロジー系の人は特に多かったですしね。ただ、ちょうどメディア芸術祭という文化庁のイベントも空間構成の仕事でお手伝いをしていた時期で、仕事で関わった死にものぐるいで働いている人達がそちらでは受賞者なんですよ。それが僕にしてみればものすごくライヴ感とリアリティがあって面白かったんです。
テクノロジーと呼ばれるものの解釈や定義というのはすごくいろんな種類があるんだけども、1つ乱暴な括り方をするならば、結局持っている技ですよね。その技をどう主体たる人たちの目的に合わせて、活かしながら、期待しているような目的に辿り着くか。受け止めた人の中に感情などを巻き起こせるものに加工できるか。僕が見る限り、そこがテクノロジーを使っていろんなことをやってる人たちに共通する面白さ。
僕らが作るものはインテリアや建築とは違い、一定の時間が経つとなくなることが多い。だから記憶に残らないと作った意味がない。直接的なものに加えて副次的な広がりを生み出すきっかけとして、どこかで匂いを出すことがとても大事なんです。その匂いを出すときに2つ大切なことがあって、1つは時代を作っていること、もう1つは時代を飛び越えてヘリテイジになっていくこと。これは今でもありだよねというムードを持ったものにいかに近づけていくかという時に、あまり目に見えるものにフォーカスするよりも、目に見えにくい領域にフォーカスして膨らませる方が時間が経っても色あせない傾向にあると気が付いて、そこから特に僕の領域は、あまりその時代のトレンドを追いかけるような床天井を作る仕事じゃなくて、ある種どうやって“コト化”するかを考えるようになったんです。そこにテクノロジーというのは大事な役割を果たしてくれるわけです」
――なるほど。
谷川「床壁天井の進化というのは、どこまでいってもサーフェスなので限界がある。あまりすごいことして歩けなくなったら床の意味がないんです。役割が明確なものは比較的限界値があるんだけど、そこがヴィジュアル化されたら空間の役割や位置付けが変わる。そういう組み合わせは無限だなと思って、テクノロジー系の方たちと積極的にいろんなことをやっていきたいと考えました。その中でも、アーティスティックで、みんなの共感軸を強度に持っていながらも、ちゃんと形として作ることができる職人的なスキルをもった人たちと仕事をしたいと。そこにライゾマティクスがいたという流れです」

――それがMEDIA AMBITION TOKYO(MAT)を始められたきっかけにも繋がったんでしょうか。
谷川「そうです。テクノロジーにおけるつくり手たちとの関係が生まれ、可能性を感じたことがやりたいと思った一番の理由です。あと、僕は海外でも仕事をするケースがあんですが、海外では日本で作れないようなスケールのものもルールが違うので実現できることがある。それを東京で自分の周りにいるみんなに見てもらいたいというシンプルな気持ちがそもそもの種です。同時に、僕らが世界に評価されるために海外に行くことは多いけれど、世界に評価されるために日本に呼ぶという仕組みが極めて少ないとも思っていて。そこで海外メディアも含めて多くの人たちを日本に呼ぶことをできないかと考えた時に、毎年4月にミラノで開催されるミラノサローネが浮かんだんです。そこには想像できないほど多くのプレス関係者が集まるんですが、そういったことは東京では出来ないのだろうか。なにか手立てはないのだろうか。それで今から3年前に小さなスケールでMATをスタートさせたんです。
結果思った以上に手応えがあった。そこから年々規模を拡大し、今年はこうなればいいねと思い描いていた1つの形——東京全体を使ったイベントのフォーマットと言えるものが初めて形になったんだと思います。六本木ヒルズの52階にテーマ展のようなものがありつつも、周辺の様々な場所で、いろんなアーティストが領域にあったやり方で自分たちなりの発信をしている。これからはそういう人たちの活動や存在を、投資や援助してくれる領域の人たちのところにまで届かせる。かつ、青田買いまでできる会場づくりもするべきだと思っています。発信力も含め、世界と戦えるポテンシャルをもったマーケットなのだから、みんなの力で形にすることに協力してほしい。そういうことを考えていると最初に声をかけたのが齋藤さんだったんですよね」
――齋藤さんが初めてお話をお聞きになった時の感想は?
齋藤「そのお話を聞いたのは3年前ですね。既にメディア芸術祭は日本でも認知もあったし、海外からの評価が高かったんですが、やはり行政主導だと固さがある。最近のメディアアート作品は良くも悪くも文脈化されていないシームレスなものも増えたから、行政の固さでは受け入れが難しい部分もあるんです。見に来る人たちがお酒を飲んだりして楽しめる場がないのも気になっていました。これはよく日本にありがちな、すごくいい道を作ったのに、小さいトラップがあって結局ストップするというものの1つかなと。ミラノサローネのいいところは、役所みたいな固いところもフリーでお酒を振る舞って街中でパーティをやるし、便乗していろんなところが商売をするんです。家具屋がホットドッグを売るみたいな。それは本当に大事なことだと思うんですね。メディア芸術祭に来る人は数万人いるので、その時に裏チャンネルとしてMATをやって、2月の初旬もしくは中旬のあたりにその2つが中軸として東京を盛り上げていくと、他のところも色々便乗して盛り上げてくれるんじゃないかと。お話を聞いたとき、そういう全体像が谷川さんには見えていたので、僕もそういう場所があるというのはすごくいいなと。若い人たちが作品を発表する中でパーティがあるとか、いいじゃないですか」
谷川「ミラノサローネはすごくシンプルなんですよ。いろんな催事がこと細かに書かれているガイドブックが街中に配ってあるんです。メゾンの名前、展示日数、レセプションの日。グラスマークがついている日に行けば酒が飲めるし、エントランスフリーで入れるのか、インビテーションオンリーなのかもわかるんです。ミラノはブランドが来年度以降のプロトタイプを発表してたり、あるいはアーティストが自分でエキシビションやってメゾンにアイデアを売っていたりという、これからのことがわかる領域。同じ時期に、国際家具見本市がロー・フィエラミラノという巨大な展示場で開催されているんですが、そこはバイヤー向けの展示会があって、メゾンも出店しています。この2つのドメインをもって、まさに今年、そしてこれからというのものをみんなが占うという構造を時間をかけて確立されたんです。最初は家具だけだったのが、いまでは自動車、電気製品、コンピュータや通信機器など今となってはライフスタイルと呼ばれる全般に関わる巨大なイベントになった。みんながこの時期はミラノに行くんだと決めてスケジュールをずっと空けているわけです。
そうすると、ミラノなんて小さい街なので誰かに会うんですよ。ライブリーなハプニングに溢れてる。ギャザリングがあることでエキシビションも活きてくるし、海外はそういうフォーマットを作るのが上手。そういうセレンディピティな関係とか、偶発性みたいなことをもっと作っていかないと、予定調和だけでは面白いものは絶対に生まれてこない。
そういう意味では、東京にはすごくポテンシャルがある。東京のように24時間コンビニエンスで、夜通しアートイベントを盛り場でやって大丈夫な国は世界中どこにもないんです。アートな女子たちが夜中の盛り場を歩いていて何もトラブルが起きないという、そのシチュエーションはすごく特殊。そんなセキュアだったり、ピースフルな感じは日本の魅力だし、2月は和食もおいしい。春を間近に控えて気分がちょっとずつほころんでくる時に、東京をプラットフォームにして、テクノロジーカルチャー、ゲームやアート、もちろん商業も含めていろんな可能性がダイバーシティとして混在している実験的なショーケースが作れたら、充分に世界に通用するものになると思うんです。東京は街によって空気やキャラクターが全然違うので、これが全体にどんどん広がっていけば、今後すごく有力な場になる。銀座はこれから新しい施設ができるのでこういったことを積極的にやりたい人も出てくるだろうし、虎ノ門や品川の周辺も新しい街ができる。そういうところにはパブリックアートや様々な表現が出てくるはず。そういったものをたくさん見せた方がいいと思うし、体験は文脈性を伴っているので、周辺も必ず変わっていくだろうと。MATでは、みんなで知恵を絞って、そういったことを実験したいですね」
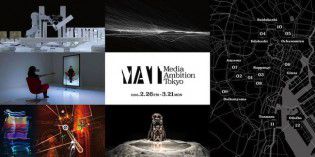
――今年、ライゾマティクスはどのようなプレゼンテーションを予定されているんですか?
齋藤「僕たちは六本木ヒルズのMATラボで展示をするんですが、せっかくラボという名目の場所でやるので、身体と空間が直結するとどうなるかという空間実験をやります。『SPACE EXPERIMENT #001, 002, 003』は、52階から見える素晴らしい景色を活かして、もしも脳波によって景色が変わるとどうなるかという試みです。以前MATで脳波によってモノを作るとどうなるか(作品名)という作品をつくりましたが、それに近い実験的な感じで。あと、関わってるのはボディスーツ(Rez Infinite -Synesthesia Suit)ですね。どれも実験的な、他のギャラリーではできないようなことをやります。僕は東京は意外と実験する場所がないと思っているんです。商業が絡むと失敗はNGじゃないですか。MATの良さは、型が決まっていないのでその実験が思い切りやれるところ。今回も拠点がたくさんありますけど、その中で色々実験をして、いいと思ったものは街にインストールすればいいし、ダメだと思ったものは来年違うものを作ろうとか、どちらかというとキャンバスに近いようなことをしている。参加アーティストも、文脈はしっかり作っていきたいので大先輩も若手も入り混じった構成にしていますが、がっちりキュレーションはしていない。そこがすごくいいところだと思ってます」
谷川「インバイト制で、みんなが面白いよと連れてきた人をそのまま受け入れる感じです。でもそこで中途半端に参加すると比べられた時に辛い思いをするので、ポテンシャルはあったほうがいいとは思います。ノミネーションされながらも参加できなかった人もいるし、想像してないところから飛び込んできた人もいる。でも結果的には収まる。これはラボで実験だから、この文脈性に評価はなくてもいいと思ってるんです。ただみんなが各々で面白い発信をして、競いあうことが大事。サローネは、面白いという評価を得るためにアーティストが命がけでプレゼンテーションをやっていて、そこに対するエネルギーがイベント全体をものすごく盛り上げている。わざわざ見にいく価値があると言わしめるモノは激しい競争の中から生まれてきているので、MATもそうしたアウトプットやパフォーマンスが見せられる状況ができれば、必ず遠くからでも人を呼ぶことができるようになると思う。そして来てみれば街も面白いし食事も最高だったよとなるはず。この想像を超えた巨大な都市の中に点在しているコミュニティの持つ多様性をポジティブに感じてもらえればいいかなと。テクノロジーだけじゃなくて日本という文脈も感じてほしいし、次世代に渡すべきイケてる領域を創造すること。これってオトナの責任だと思うんですよ」
――そういう想いを形にしていると。
谷川「第1回の時に披露したリリースがあるんですが、民間の民間による民間のためのということを掲げていて、土地を持っている人は土地を提供する。メーカーはプレイスメントでモノを貸し出して、作家はそれによって作品を作り、自分の知恵を出す。みんなでドネイトしながらすごい表現を作ろう、それを核にして新しいビジネスモデルや集客のプロトタイプなど全部を実験という名のもとに目に見える形にしていこうと。
東京をプラットフォームとしてヴィジョンを打ち出したいと思います。技術は瞬時に追い越される可能性があるけれど、ヴィジョンは簡単には凌駕できない。なぜなら技術はそのヴィジョンを形作るために日々進化するものなので、アウトプットされた瞬間から経年化されていくものだから。だからみんながMATをきっかけに集まり、利用してほしい。いろんなところから接点が生まれ、テックフェスのような感じで楽しくヴィジョンや可能性を見いだせれば素晴らしいことだとおもうんです。やっぱり何事も楽しくないとダメですから」
齋藤「うん、楽しくないと何も続かないですよね」
撮影 中野修也/photo Shuya Nakano
企画編集・取材・文/edit & interview Ryoko Kuwahara

MEDIA AMBITION TOKYO 2016(メディアアンビショントーキョー2016)”
主催:MAT実行委員会(六本木ヒルズ/ CG-ARTS協会/ JTQ Inc. / Rhizomatiks)
会期:開催中-3月21日(月)
会場:
01. 六本木ヒルズ(六本木)
02. INTERSECT BY LEXUS ‒ TOKYO(青山)
03. IMA CONCEPT STORE(六本木)
04. アンスティチュ・フランセ東京(飯田橋)
05. デジタルハリウッド大学(御茶ノ水)
06. Apple Store, Ginza(銀座)
07. Apple Store, Omotesando(表参道)
08. TSUTAYA TOKYO ROPPONGI(六本木)
09. 代官山 蔦屋書店(代官山)
10. チームラボ(水道橋)
11. 寺田倉庫(天王洲)
12. 日本科学未来館(お台場)
http://www.mediaambitiontokyo.jp/
谷川じゅんじ
スペースコンポーザー/JTQ 株式会社代表。
1965年生まれ。2002年、空間クリエイティブカンパニー・JTQを設立。 「空間をメディアにしたメッセージの伝達」をテーマにイベント、エキシビジョン、インスタレーション、商空間開発など目的にあわせたコミュニケーションコンテクストを構築、デザインと機能の二面からクリエイティブ・ディレクションを行う。
http://jtq.jp/
齋藤精一
株式会社ライゾマティクス代表取締役。東京理科大学理工学部建築学科非常勤講師。1975年神奈川生まれ。建築デザインをコロンビア大学建築学科(MSAAD)で学び、2000年からNYで活動を開始。その後ArnellGroupにてクリエティブとして活動し、2003年の越後妻有トリエンナーレでアーティストに選出されたのをきっかけに帰国。2006年にライゾマティクスを設立。2009年-2014年国内外の広告賞にて多数受賞。2013年D&AD Digital Design部門審査員、2014年カンヌ国際広告賞Branded Content and Entertainment部門審査員。2015年ミラノエキスポ日本館シアターコンテンツディレクター、六本木アートナイト2015にてメディアアートディレクターを務める。
http://rhizomatiks.com
関連記事のまとめはこちら
http://www.neol.jp/culture/
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
『クイズタイムリープ』劇団ひとりが感じる“テレビの面白い可能性” 最新技術×企画力で「どんなことが起きるんだろう」
マイナビニュース / 2024年12月29日 6時0分
-
旅を分解して味わい尽くす――仲野太賀×上出遼平×阿部裕介が放つ“かつてない”旅行記「すごくシンプルで良い遊び」
マイナビニュース / 2024年12月28日 7時0分
-
BREIMENの高木祥太、hamaibaが語る「山一」の歴史
Rolling Stone Japan / 2024年12月25日 15時0分
-
野田クリスタル、根底にあるのはインディーズ愛「小屋感がすごく好き」 新作『野田ゲー』でも実感
ORICON NEWS / 2024年12月17日 17時36分
-
野田クリスタル、新作『野田ゲーMAKER』も自信作 自分で作れる楽しさを熱弁も悩む「伝え方がわからない」
ORICON NEWS / 2024年12月17日 17時28分
ランキング
-
1賞味期限「2年前」のゼリーを販売か…… 人気スーパーが謝罪「深くお詫び」 回収に協力呼びかけ
ねとらぼ / 2025年1月15日 7時30分
-
2「室内寒暖差がつらい…」その要因と対策が明らかに! - 三菱電機が紹介
マイナビニュース / 2025年1月14日 16時10分
-
3芸能人なぜ呼び捨て?「日本語呼び方ルール」の謎 日鉄会長の「バイデン呼び」は実際に失礼なのか
東洋経済オンライン / 2025年1月15日 9時20分
-
4バイトをしているコンビニでは廃棄商品の持ち帰りは禁止されています。もう捨てる商品なのになぜダメなのでしょうか? 捨てるほうがもったいない気がします。
ファイナンシャルフィールド / 2025年1月14日 5時0分
-
5靴下真っ黒で徘徊…87歳老母が冷凍庫に隠していた「うなぎパック50個」の賞味期限を知った50代娘の切なさ
プレジデントオンライン / 2025年1月15日 10時15分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください









