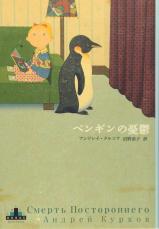母国のためクルコフは書き続ける【沼野恭子✕リアルワールド】
OVO [オーヴォ] / 2024年6月30日 8時0分
最近、ひと頃に比べてウクライナ関連のニュースがめっきり減った。「支援疲れ」などという言葉が飛びかい、それが日本人のウクライナへの関心をそいでしまっているような気がする。
しかし、言うまでもなくウクライナは相変わらず戦時下にあり、日常生活は破壊され続けている。だからウクライナの人々は、世界に向けて過酷な現実を「持続的に」訴えていかなければならない。その使命を自ら引き受け、文字通り世界中を飛び回っているのが、作家アンドレイ・クルコフだ。
国際的なベストセラーとなった1996年の「ペンギンの憂鬱(ゆううつ)」(新潮社)は、駆け出しの物書きが新聞社の依頼に応じて有名人の追悼文を書いているうちに胡散(うさん)くさい事件に巻き込まれていくという、ソ連崩壊後の独立まもないウクライナのキーウを舞台にしたサスペンスタッチのちょっとシュールな小説だった。主人公の分身のようなペンギンが名脇役で愛らしい。
この作品は日本でも比較的よく読まれているし、著者のクルコフ自身も時々、日本のメディアに登場しているので、その名はそれなりに知られているかもしれない。でも先日、メールのやりとりをしていて、彼が「8歳の時からキーウのサボテン・クラブに入っていて、当時日本で作られた『緋牡丹錦(ひぼたんにしき)』というサボテンを見たことが、日本に関心を抱くきっかけになった」と送ってきたので驚いた。その後、日本の詩歌や浮世絵の他、大江健三郎、川端康成、安部公房を読むようになり、4年間キーウの学校で日本語を勉強したというから、クルコフは日本との縁が深いのである。
彼には、小説の他に「ウクライナ日記」(吉岡ゆき訳)、「侵略日記」(福間恵訳、ともにホーム社)というドキュメンタリー作品がある。前者は2013〜14年のマイダン革命の推移を見守った著者の貴重な証言、後者は22年のロシア軍の全面侵攻に際し避難民となって西部リヴィウに逃れた彼自身の生々しい記録が綴(つづ)られている。
イギリスの「ガーディアン」紙に最近載ったインタビューでクルコフは、「戦時下の今は小説を書くことがやましく感じられ、どうしても書けない」と語っている。でも、日記形式で書かれた彼のノンフィクションはもちろん重要だとは思うものの、彼の小説には圧倒的な魅力がある。長編「灰色のミツバチ」(2018年)の主人公は、今まさに注目されているウクライナ東部のドンバス地方から南部クリミアまで、ミツバチとともに旅をする。特に後半、ハラハラする物語展開なのだ。面白くないはずがない。
この作品は、フランスのメディシス賞、アメリカの全米批評家協会賞などいくつもの国際的な文学賞を受賞している。8月末に日本の読者に翻訳をお届けすべく今、鋭意準備中だ。乞うご期待!
【KyodoWeekly(株式会社共同通信社発行)No. 26からの転載】

沼野恭子(ぬまの・きょうこ)/1957年東京都生まれ。東京外国語大学名誉教授、ロシア文学研究者、翻訳家。著書に「ロシア万華鏡」「ロシア文学の食卓」など。
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
復讐、愛、死、孤独、時代に翻弄される青年の壮絶な物語 映画『フィリップ』ミハウ・クフィェチンスキ監督インタビュー
ガジェット通信 / 2024年6月30日 21時0分
-
大沢在昌さん タフで美しい夢のヒロイン
読売新聞 / 2024年6月28日 15時15分
-
NHK「100分de名著」関連書が3冊同時発売! 宗教・戦争・文学を理解するための名著読み解きが勢ぞろい。
PR TIMES / 2024年6月25日 12時45分
-
北方謙三氏『黄昏のために』インタビュー「その場面で選ぶべき1つしかない言葉を選ぶことが小説を書く行為の根源にある」
NEWSポストセブン / 2024年6月23日 7時15分
-
「本のない家庭」で育った、ポール・オースター...ジャンルを超越し、人間を見つめた「文学の天才」の人生とは?
ニューズウィーク日本版 / 2024年6月7日 14時50分
ランキング
-
1すき家、7月から“大人気商品”の復活が話題に 「この時期が来たか」「年中食いたい」
Sirabee / 2024年6月29日 4時0分
-
2若々しい人・老け込む人「休日の過ごし方」の違い 不安定な社会、「休養」が注目される納得理由
東洋経済オンライン / 2024年6月30日 9時0分
-
3水分補給は昼コーヒー、夜ビール… 「熱中症になりやすい人」の特徴と対策
ananweb / 2024年6月29日 20時10分
-
4忙しい現代人が“おにぎり”で野菜不足を解消する方法。野菜たっぷりおにぎりレシピ3選
日刊SPA! / 2024年6月30日 15時53分
-
51年切った「大阪・関西万博」現地で感じた温度差 街中では賛否両論の声、産業界の受け止め方
東洋経済オンライン / 2024年6月30日 14時0分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください