柳井正「若者よ、自分で自分の希望をつくれ」【2】
プレジデントオンライン / 2013年10月8日 10時15分
若い頃はフリーター、縁故入社の会社もすぐ辞めた。そんな柳井氏を育てたのは「仕事」だった──。日本一注目される経営者が語る「希望の人生論」とは。
■大切なのは作業を割り当てること
――(『柳井正の希望を持とう』のなかで)私がいちばん感銘を受けたのはユニクロの商品についての個所です。私も含めて、世の中のほとんどは、ユニクロの商品はファストファッションの範疇にあるものと勘違いしていました。ですが、柳井さんが考えたユニクロの商品とは、「洋服業界の常識」を打ち破ったものなんですね。
【柳井】少なくとも、ユニクロの商品はファストファッションとはまったく違うものだとわかってもらえたのではないでしょうか。
ZARA、H&M、フォーエバー21の各社はファストファッションの代表です。彼らが売っているのは「流行」という情報。先んじて流行する服をいかに作るか、作ったものをいかに早く消費者に届けるかを計画し、緻密に進めていく。そのためのシステムを持っています。毎シーズン、流行の商品を揃え、売り切っていく。売り切ったら、そこでおしまい。そういったシステムは私たちは持っていません。真似しても、簡単にできるものではない。
一方、私たちが売っている商品はベーシックカジュアルです。流行に左右されない美的な服のことで、お客様が選んで、好きなように着こなすことができる。そして、そういった服ならば国境も問わないし、年齢にも左右されることはない。あらゆる人が買うことができる。私たちが対象にしているマーケットは流行の服よりもはるかに大きなものです。
――ここには柳井さんの熱いメッセージだけでなく、若い人に向けた仕事への取り組み方が具体的に書かれている。いわば「仕事の教科書」ともいえるのでは。
【柳井】私は店長たちに、つねづね「店長の仕事でいちばん大切なのは作業を割り当てることだ」と言っています。
たとえば、できる店長とできない店長がいる。できない店長は自分ひとりで頑張る。自分ひとりの理想の店をつくろうとする。それに対して、できる店長は全従業員と一緒になって仕事をする。従業員のそれぞれの立場を考えて、仕事を割り振っている。
うちのような小売りではパートの従業員が大勢、働いています。彼女たちは子どもを育てたり、食事の用意をしたり……、家事は彼女たちにとって大切なものです。ところが、できない店長はそういうパートの従業員の立場を無視して、機械的に作業を割り振る。それでは、働く人のモチベーションは上がらない。
作業を割り振るには、やる人の立場を推し量ることです。子どもを迎えにいく必要がある人には、そういったシフトを組む。熱がある人がいたら、早めに帰ってもらって、代わりの人に作業を頼む。それぞれの人の事情を聞いて、できるだけ働く人の希望に沿うようにする。むろん、すべての人の希望を100%かなえることはできません。しかし、事情を聞かずに自分の思い通りに仕事を進めても、うまくいかないでしょう。これは店長だけのことではなく、部下を持つ人すべてに当てはまる話です。
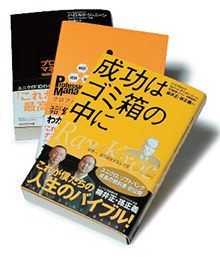
――本書では柳井さんの本の読み方も紹介されています。若い学生、ビジネスマンに、もう1度、本の読み方、選び方を教えてください。
【柳井】本を読むことはビジネスマンに限らず、誰もがやらなくてはならないことでしょう。そして、本を読むうえで大切なことは、頭でっかちにならないこと。ビジネスマンならば読書を通して知識を増やすことよりも、仮説を頭に描きながら、考えながら読むこと。
本書には私が勉強になった本をいくつか挙げてあります。いずれも読むには時間がかかるし、他の著作も参考にしながら読み進めていかなくてはならない。しかし、本来、読書とはそういうものでしょう。脳から汗を流して、読むこと。
■仕事はつらくて苦しい。それでこそ正しい
――さて、先ほどは、まえがきについて、ややほめすぎてしまいましたが、実はあとがきも今の時代にみんなが知りたいことです(笑)。危機の時代の経営者の行動について、ここまで具体的に話す人はあまりいません。
【柳井】詳しくは本を読んでいただいて(笑)。ただ、大震災のとき、政府も東電も、まったくダメな大人の典型のような行動だった。それに対するいきどおりがあって、あとがきを書かなくてはいけないと感じたのです。
経営者として先頭に立つ。従業員、社会に向けて、第一声を発する。現実を直視して、受け止める。自分たちに過酷な現実であっても、受け止めて、何らかの言葉を出す。従業員を意気消沈させないように「今は厳しい状況かもしれないが、いずれはこうしていく」と伝える。
危機、災害は必ずやってきます。平時のうちに準備をして、パニックを起こさず、淡々とやっていく。危機の時代に必要なのは平時における準備です。
――この本は確かに若い人が読んだほうがいいような……。ほかの経営者や年寄りのビジネスマンは「なんだ、こいつは。洋服でちょっと当てたからといって、いい気になるな」みたいなことを感じるかもしれない。

柳井正氏
【柳井】はは、そうでしょう。僕は若い頃からストレートにモノを言いすぎる。生意気だと評されてましたから。今でも、まだ言われるけれど……。
私は若い人に対して説教をするつもりはない。希望を持て、自分で自分の希望をつくれと言っているのです。私だって、若い頃はフリーターだったし、縁故入社で入った会社をすぐに辞めてしまって、ダメなやつと思われていた。将来のことなんて何も考えていなかった。他人に説教する資格なんてありません。ただ、仕事を通して研鑽を積んでいくうちに、仕事が面白くなって、一人前の社会人になることができた。私を育ててくれたのは仕事であり、社会です。大学生でも、若いビジネスマンでもいい。今、困っている人、将来、こういうことをやりたいけれど、果たして、どうしていいかわからないという人に読んでほしい。
今、若い人のなかで、「頑張らない生き方」が流行っているとも聞きます。しかし、本当ですか? 頑張らないで、いったいどうするんですか?
私は「生きる」ことはすなわち頑張ることだと思うし、仕事とはつらいことだと信じている。確かに、仕事はつらくて苦しい。しかし、それでこそ正しいのです。楽に生きていきたい、楽しく仕事をしたいと言っている人は現実を見つめていない。いい仕事をしようと思ったら、せいいっぱい頑張らないといけない。
若い人って自信を持っていないんじゃないでしょうか。それは謙虚なこともあって、自信を持つことに遠慮しているんだ。もっと自分自身に期待していいんですよ。遠慮しないで自分に期待して、世の中を渡っていってほしい。
日本を復興するのは年寄りじゃない。政治家でも財界人でもない。復興の主役は若い人ですよ。まちがいなく。
(ファーストリテイリング代表取締役会長兼社長 柳井 正、ノンフィクション作家 野地 秩嘉 野地秩嘉=インタビュー・構成 岡倉禎志=撮影)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
先行き不透明な時代に、経営トップたちの言葉に勇気づけられる【私の雑記帳】
財界オンライン / 2024年12月22日 11時30分
-
あなたはいくつ備える?AI時代に生き残るビジネスパーソン3つの条件とは
ダイヤモンド・チェーンストア オンライン / 2024年12月16日 20時54分
-
なぜユニクロの柳井氏は「ウイグル綿花問題」を語ったのか 中国で炎上しても、“あえて”発言した理由
ITmedia ビジネスオンライン / 2024年12月4日 7時26分
-
「ユニクロが脱新疆なら、中国人は脱ユニクロ」=柳井正氏の「新疆綿使ってない」発言が中国で物議
Record China / 2024年11月29日 11時0分
-
ユニクロ・柳井正氏はやっている…ユーモアでも声量でもない「聞き手の心をグッとつかむ話し方のコツ」
プレジデントオンライン / 2024年11月28日 7時15分
ランキング
-
112月末まで!今年の「ふるさと納税」注意したい点 定額減税の影響は? 申し込む前に要チェック
東洋経済オンライン / 2024年12月26日 13時0分
-
2女川原発、営業運転を再開=福島第1と同型で初―東北電力
時事通信 / 2024年12月26日 18時46分
-
3なぜスターバックスの「急激な拡大」は失敗に終わったのか…成長を一直線に目指した企業の末路
プレジデントオンライン / 2024年12月26日 15時15分
-
4昭和的「日本企業」は人事改革で解体される? 若手社員への配慮と、シニアの活性化が注目される背景
ITmedia ビジネスオンライン / 2024年12月26日 5時55分
-
5焦点:日産との統合、ホンダから漏れる本音 幾重のハードル
ロイター / 2024年12月26日 14時46分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください











