無情にも"法"にこだわる大名ほど弱かった
プレジデントオンライン / 2018年9月27日 9時15分
■教科書では説明できない「分国法のパラドックス」
高校の日本史の教科書には、「分国法」という言葉がかろうじて掲載されています。そこでは、それが戦国大名の必要条件だったとされています。独立国家を作る上で大名は法を必要とした、と説明されているわけです。
これは歴史学者の石母田正(1911-86)の学説によるものです。石母田説によれば、戦国大名の権力は、独立した「国家権力の歴史的一類型」と位置づけられます。そしてその権力は、倫理的体系や自己神格化などの宗教的イデオロギーによる支配の正当化を行わない「裸の権力」であるため、「『法』という客観的な非人格的な規範」がほとんど唯一の正当性の役割を担ったとされています。
しかし、それではなぜ、現在にはわずか10点ほどの分国法しか伝わっていないのかという疑問が湧いてきます。独立国家にとっての必須条件であれば、天下を取った織田家を筆頭に、もっと多くの分国法が伝わっていてもおかしくないと思うのが普通でしょう。
分国法について調べていて気が付くのは、実は教科書のそうした記述とは裏腹に、分国法を作った大名は全て滅びていることです。一方で織田信長のように勝ち残った者が作った法律は、今に至るまで見つかっていない。
■法に縛られなかった者の方が勝ち残った
そうなると、歴史教科書の従来の説明は少し転倒していると言わざるを得ません。私はこのことを「分国法のパラドックス」として本に書きました。では、なぜ分国法を定めた大名たちは、みな滅んでしまったのでしょうか。
法律とはそれを作った権力側をも縛るものです。法を作ると領国において恣意的な処断――「俺がルールブックだ」というような支配はやりにくくなるはずです。例えば、見せしめ的に一人だけを重い罪にして、周りを震え上がらせて言うことを聞かせる、といったことはできなくなる。
戦国時代という乱世の中では、他人の領土をぶんどった者が生き残りました。その意味で分国法を作った大名は真面目というか、線の細い人物が多い印象があります。そのようにして、法に縛られなかった者の方が勝ち残ったのは歴史の皮肉でしょう。本では次のように書きました。
ただし、分国法は歴史的にまったく無意味なものだったわけではありません。日本の法制史学の基礎を築いた中田薫(1877-1967)は、かつて分国法の意義を「従来法律的に対立していた公家法・武家法・民間慣習の三者を綜合して一となした点にある」と語っています。ここでいう「民間慣習」とは、「先例」や「古法」といった有形無形の法慣習や習俗のことです。
■「分国法」は時代を先取りしすぎていた
権力側の定める「中央の法」と、これら「田舎の法」との出会いは、早くは鎌倉後期には見られました。戦国大名たちの分国法は、これらをより本格的に法のなかに採り入れたものでした。彼らは民間の法慣習を「下から上」に汲み上げて、試行錯誤をしながら法律を自ら作ろうとしたわけですね。
たとえば江戸時代の藩は藩法を必ず持つようになりました。他人の領土を取ってナンボだった戦国時代が終われば、そうした分国法の理念は後の時代にも受け継がれた。その意味で彼らは時代を先取りしすぎていたのかもしれません。
それに織田信長でも法を作らなかったのは、庶民の慣習法に丸投げをしていたからだとも考えられます。庶民が日々の生活の中で作ってきたルールを吸い上げ、ボトムアップして成文化したものが分国法だったと考えると、「戦国大名」の苦悩や試行錯誤の先に、「戦国社会」そのものの姿が浮かび上がってくるように僕には感じられました。
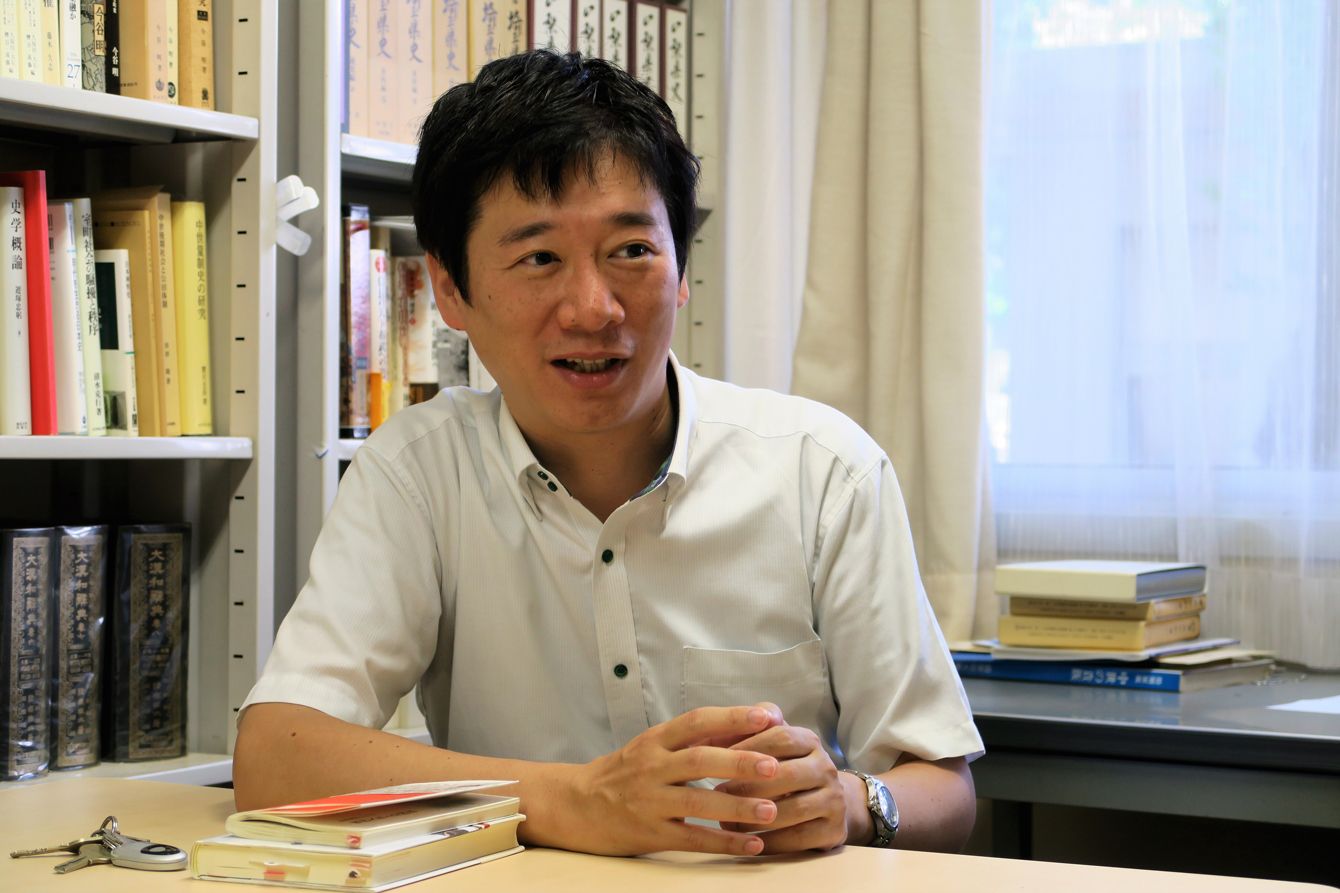
■「刀狩り」には「戦争に行きたくない」という民衆の思いがある
このように分国法を真正面から検証した日々は、僕にとって研究の面白さを再発見する営みでもありました。
僕が日本中世史の研究者を志す上で大きかったのは、『刀狩り』(岩波新書)の著者である歴史学者・藤木久志先生との出会いでした。
藤木先生は新潟の農村の生まれで、「ほとんどの日本人の先祖は農民だったのだから、戦国大名などよりも庶民の歴史をもっと明らかにすべきだ」というポリシーを貫いてきた研究者です。
それまでの庶民の歴史といえば、権力に追い詰められて一揆を起こし、結局は鎮圧されるというマルクス主義的な図式で描かれるものがほとんどでした。いわば「敗れ去る庶民」というイメージが一般的だったと思います。しかし、藤木先生はそれを屈折しているものと考え、実は権力に負けているように見えて、最後に大きな果実を得てきたのは民衆なのではないか、という視点で歴史を読み直したのです。
例えば教科書に載っている有名な刀狩りも、「百姓は農業に専念していればよく、戦争には行く必要はない」ということを秀吉が保証したと捉えると、「戦争に行きたくない」という民衆の思いを組み上げた法律となる。
戦争は武士たちが行ない、年貢は百姓が納める――「刀狩り」という従来は権力の圧制のように理解されてきたものを、権力と民衆のギブ&テイクの結果として捉え直す藤木先生の視点は、子供の頃からの歴史好き少年だった僕にとって衝撃的でした。
■普通の史料から、当時の人々の論理を引き出す
振り返ると、藤木先生から僕が学んだのは、歴史を研究する面白さと、研究者としてあるべき態度だったのだと思います。

既成概念に縛られないこと、そして、現代の常識から歴史を見ないこと――。
古文書を読みながらさっと流してしまうような箇所に、実は中世の人々の価値観や社会を理解する上で、とても大事なことが書かれている。われわれにとっては合理的に思えない条文であっても、彼がなぜそこにこだわったのかを一から考え、見方を変えると新たな世界が開けてくる。
ときおり誤解されるのですが、歴史研究における醍醐味とは新しい史料を見つけたり、天地がひっくり返るような新説を生み出したりすることではありません。むしろ自分の中にある既成概念を取り払い、これまで誰もが読んできた史料から、当時を生きた人々の論理を引き出してくることが、歴史研究の何よりの面白さだと僕は思っています。
歴史の研究をしていて最も心地良いのは、ああでもない、こうでもないと様々な可能性を検討しながら、史料を一からめくり直している時間です。大よそ考えつかないような可能性をも含めて検討し、一つひとつの可能性を取捨選択していく楽しさが、この分国法の研究には確かにあったと感じています。
----------
明治大学商学部 教授
1971年生まれ。立教大学文学部史学科卒業。早稲田大学大学院文学研究科博士後期課程単位取得退学。博士(文学)。専門は日本中世社会史。「室町ブームの火付け役」と称され、大学の授業は毎年400人超の受講生が殺到。2016年~17年読売新聞読書委員。著書に『喧嘩両成敗の誕生』、『日本神判史』、『耳鼻削ぎの日本史』などがある。
----------
(明治大学商学部 教授 清水 克行 構成=稲泉 連 撮影=プレジデントオンライン編集部)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
晩年の豊臣秀吉の狂気がよくわかる…一度は跡継ぎと認めた甥の秀次とその家族に対する酷すぎる仕打ち
プレジデントオンライン / 2024年7月14日 10時15分
-
だから『キングダム』の信は戦災孤児ながら「天下の大将軍」を目指せた…秦国にあった究極の軍功制の中身
プレジデントオンライン / 2024年7月12日 7時15分
-
北陸を制し勢いに乗る上杉謙信、逃げる織田軍は川に飛び込み溺死…謙信最強伝説を生んだ「手取川の戦い」
プレジデントオンライン / 2024年7月7日 8時15分
-
NHKブックス『「和歌所」の鎌倉時代 勅撰集はいかに編纂され、なぜ続いたか』が発売。謎に包まれた「和歌所」が明かす、中世日本の政治と文学とは?
PR TIMES / 2024年6月25日 12時15分
-
本能寺の変は決して無謀なクーデターではなかった…明智光秀の計画を狂わせた2人の武将の予想外の行動
プレジデントオンライン / 2024年6月25日 10時15分
ランキング
-
1ユニクロでブラジャーなど大量万引き 1200万円超す被害 ベトナム国籍の女3人を逮捕・送検
ABCニュース / 2024年7月19日 19時2分
-
2コロナ「第11波」、変異株KP・3が主流 流行期入りで夏に感染拡大か
産経ニュース / 2024年7月19日 21時4分
-
3ゆれる兵庫県庁 「解明が務め」と百条委、「自分も処分?」と疑心暗鬼になる職員も
産経ニュース / 2024年7月19日 20時1分
-
4防衛相、海自元隊員逮捕は「昨晩知った」 与野党から批判の声
毎日新聞 / 2024年7月19日 18時0分
-
5こども園の通園バスに置き去りにされた園児死亡 元園長ら控訴せず判決確定(静岡)
Daiichi-TV(静岡第一テレビ) / 2024年7月19日 9時31分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください











