なぜレクサスの営業は全員感じがいいのか
プレジデントオンライン / 2018年10月22日 9時15分
※本稿は、桑原晃弥『トヨタ式5W1H思考』(KADOKAWA)を再編集したものです。
■天才だけ集めて会社をやるのは無理
営業の世界は、今でこそいろいろな改革が進んでいますが、かつては根性主義が幅を利かせ、一握りの「営業の天才」とその他大勢に分けられる世界でした。優れた手腕で抜群の営業成績を上げる一握りの人間がいる一方で、それ以外の人間は「あいつは特別だから」というひと言で努力をあきらめていたものです。
あるビールメーカーの子会社A社は、スーパーなどのルートセールスを一手に請け負っていましたが、大勢いるマーケットスタッフの営業力にバラつきが多いことが悩みの種でした。
スタッフは1人あたり30~40店舗を担当して、在庫を確認したり、販売促進のアイデアを提案したりしていましたが、抜群の成績を上げるスタッフがいるかと思えば、機械的に各店を訪問するだけで、さしたる成果を上げられないスタッフもたくさんいました。
「そんなにバラつきがあるのならダメなスタッフをやめさせて、できるスタッフを雇えばいいじゃないか」という声もありましたが、そんな“天才”だけを集めて会社をやろうとすれば、毎月、たくさんの人を雇い、できる人間だけを残さなくてはいけません。それではブラック企業になってしまいます。
そうならないためには何が必要かを考えた結果、ひとつの問いが出てきました。
「なぜスタッフによってこれほどの成果の差が生まれてくるのだろうか?」
これは、営業には向き不向きがあって、その差はどうしようもないと思い込んでいたら、そもそも生まれもしなかった問いでしょう。この、最初のWHYを生むことが、何よりも重要です。「当たり前だ」「仕方がない」「どうしようもない」と思っている課題に改めてWHYを与えることで、解決の道筋が見えてきます。
■スタッフの間の違いを洗い出す
多くの職場でいえることでしょうが、できるスタッフができないスタッフの何倍もの時間働いているわけではありません。どちらも同じように働きながら、成果に差が出るものです。
とすれば、「能力」や「資質」以外の何かがあるのではないか。もしあるとすればそれを活かせば、「できない」といわれているスタッフの能力や成果も上げられるのではないか。そう考えるのが、トヨタ式5W1H思考です。
A社が「なぜ」の答えを見つけるために試みたのが、営業活動の「見える化」でした。本社のマネージャーが優秀なスタッフを100人選び、得意先に同行して「何をしているのか」「何がお客さまに喜ばれているのか」を調査したのです。
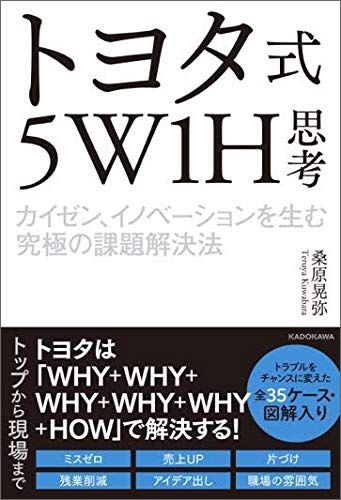
すると、できるスタッフが日頃からどのような活動を行い、得意先との親密度をいかにして高めているかがはっきりと浮かび上がってきました。そこでA社は、できるスタッフの活動をベースに「最低限の活動項目」のマニュアルを作成しました。
そこには、
(1)売り場フォロー
(2)他社動向を集めるための情報収集
(3)注文してもらうための促進活動
(4)販促企画の提案
(5)売り場の拡大
といった活動項目のほかに、たとえば「販促企画を提案できたか?」「販促企画を先方は検討してくれたか?」「ポスターなどを貼ってきたか?」といった質問票も付いていました。
スーパーマーケットなどを訪問したスタッフはこれらの項目について1つずつ「イエス」「ノー」を書き込んで本社へと送信します。その結果を集計すれば、1人ひとりのスタッフがどのレベルの活動を行い、どのように成果につなげているのかが一目でわかります。
■「ノー」をどう「イエス」に変えるのか
成果を上げているスタッフは圧倒的に「イエス」が多いのに対し、成果の上がらないスタッフはやはり「ノー」が多くなります。ただし、目的は「イエス」と「ノー」の数を競うことではありません。
こうした項目があれば、これまで成果が上がらなかったスタッフも「何をすれば成果につながるのか」を知ることができます。「ノー」が多ければ、どうすれば「イエス」にすることができるかを考え、行動すればいいのです。
■成績優秀者は「特別」ではなかった
できるスタッフは「特別だからできる」のではなく、「やるべきことをきちんとやっている」からこそできる人になるのです。それを知ったことで、ほかのスタッフも「自分もやるべきことをもっとしっかりやろう」と考えるようになったことが、何より大きな収穫でした。
営業の世界はどういうわけか、できる人を「特別な人」扱いする傾向があります。「あいつは特別だから」で済ませてしまえばそこから何も学ぶことはできません。しかし、「なぜ彼はこれほどの成果を上げることができるのだろう?」と、素直な気持ちで「なぜ」を問いかければ、そこからたくさんの学びや活動のヒントを得ることができるのです。
それは評価する側にもいえます。A社はこれまで営業スタッフを「できる」とか「できない」と評価することはあっても、「何ができるのか?」「なぜできるのか?」を問いかけることはありませんでした。
「できない」も同様です。何ができないのか、なぜできないのかを知ることなしに成績だけを見て、「あのスタッフはできる」「あのスタッフはできない」と評価していただけでした。
■「そういうもの」と諦めている課題を問い直す
A社は「なぜ成果にバラつきがあるのか?」という問いを立てたことで、できるスタッフの仕事を標準化・見える化に成功しました。そして標準化・見える化したことによって、スタッフ全体の営業力を引き上げることに成功したのです。
トヨタが「レクサス」の販売店を日本でゼロから立ち上げた際、目標にしたのは「1人のゼロもつくらない」でした。サービス業においては10人の社員のうち9人が素晴らしい仕事をしても、もし1人がゼロの仕事をしてしまえば、顧客の店への印象はゼロに近づいてしまいます。それではいけない、みんなが素晴らしい仕事をしてこそ「レクサス」というブランドを確立することができるのだ、というのがトヨタの考え方なのです。
営業において成果に差がつくのはしかたのないことですが、その差を「個人の能力差」に求めてしまうと何の改善もできません。これを改め、成果に差がつく理由を「活動のしかたや提案ポイント」などに求めれば、いくらでも改善ができるし、みんなを「できる」へと変えていくことも可能になるのです。
身の回りの「そういうものだ」と諦めている課題について、「なぜだろう?」と問いかけてみると、思いのほか解決可能なことがあるはずです。
----------
経済・経営ジャーナリスト
1956年、広島県生まれ。慶應義塾大学卒。業界紙記者などを経てフリージャーナリストとして独立。著書に『トヨタだけが知っている早く帰れる働き方』(文響社)、『トヨタ 最強の時間術』(PHP研究所)、『スティーブ・ジョブズ名語録』(PHP文庫)、『1分間バフェット』(SBクリエイティブ)、『伝説の7大投資家』(角川新書)など。
----------
(経済・経営ジャーナリスト 桑原 晃弥 写真=iStock.com)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
ひと晩で「高級車9台」盗難! トヨタ・レクサスやメルセデス等が被害も「72時間」で無事発見なぜ? 被害受けた民間駐車場が語る理由とは
くるまのニュース / 2024年7月16日 9時10分
-
就職氷河期世代の40代男性、転職先でも罵詈雑言から逃げられず…「一度郷里に戻ります」いまなお消えない〈パワハラ企業〉のイヤすぎる実情
THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年7月10日 11時15分
-
「桜蔭から2浪東大」彼女が"多浪"を決意した理由 桜蔭での生活、浪人時代に出会った運命の授業
東洋経済オンライン / 2024年7月7日 8時30分
-
「福島」からの問いにアナタは 【サヘル・ローズ ✕ リアルワールド】
OVO [オーヴォ] / 2024年7月7日 8時0分
-
だから厳しい仕事もやり遂げられる…2万人を面接した社長が見いだした「成果を生みだす人材」に共通する"ある能力"
プレジデントオンライン / 2024年6月28日 7時15分
ランキング
-
1大谷翔平の新居「晒すメディア」なぜ叩かれるのか スターや芸能人の個人情報への向き合い方の変遷
東洋経済オンライン / 2024年7月16日 20時40分
-
2申請を忘れると年金200万円の損…荻原博子「もらえるものはとことんもらう」ための賢者の知恵
プレジデントオンライン / 2024年7月17日 8時15分
-
3「再配達は有料に」 ドライバーの本音は
ITmedia ビジネスオンライン / 2024年7月17日 6時40分
-
4工学系出身者が「先進国最低レベル」日本の"暗雲" エンジニアを育てられない国が抱える大問題
東洋経済オンライン / 2024年7月16日 17時0分
-
5「380円のデザートを10人で分けて…」“ラーメン屋でラーメンを頼まない”ヤバい客の実態を店主のプロレスラーが赤裸々証言
文春オンライン / 2024年7月17日 11時0分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください











