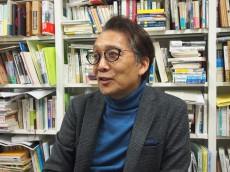"遺伝子操作"がダメなら、塾通いもズルか
プレジデントオンライン / 2018年12月30日 11時15分
■倫理的な問題と技術的・手続き的な問題は別
――中国・南方科技大学の研究者が「HIVに耐性を持つようにゲノム編集を施した受精卵から、双子を誕生させた」と発表し、物議を醸しています。岡本先生はこの件をどう見ていますか。
学会や政府系の委員会は「倫理的に問題がある」という形で反対意見を出しています。しかし私に言わせれば、何が「倫理的」かが明らかではないことが残念です。そもそも事実がよくわからないのに、それを明らかにする前に、「臭いものにはふたをする」で抹殺してしまうと、技術的な点を含め、大きな問題として解明できなくなってしまう。一気に反対・禁止をするよりも、具体的にどういう形でどこまで可能になったのかを明らかにすることが先だと思います。
中国がヒトの受精卵に対してゲノム編集を行った事例は、数年前から報告されていました。いずれ中国で母体に戻すことも行われるだろうと予想はしていました。だから私が驚いたのは、中国政府がこの研究者に対して、早々に活動停止処分を下したことです。事実関係すら明らかにならないまま闇に葬られてしまうのはとても残念ですね。
「安全性を確保すべき」という意見はもっともですし、リスクやメリットなど親に適切な情報を与えることも必要です。そうした意味での批判はよくわかります。しかし、仮にそうした手続きを踏んだ上で、今回のゲノム編集が行われたとすれば反対する理由は何なのでしょうか。これが問題です。
技術的な問題、手続き的な問題と、倫理的な問題はまったく別ものです。倫理的にはむしろ、「病気を治療してなにが問題なのか」という話になるかもしれません。
■病気治療のためならやってもいいのではないか
――今回の反対意見の大きさによって、今後ゲノム編集技術の進展には歯止めがかかるのでしょうか。
おそらくそうはならないと思います。今回の出来事は、体細胞クローン技術によってクローン人間が誕生するかもしれないと言われた時によく似ています。怪しげな宗教団体などが「クローン人間を作成した」と主張し、「クローン人間反対」を叫ぶ動きが世界的に起こりました。ただし、それに比べると今回はずっとニュアンスがやわらかい印象があります。
というのも、遺伝的な病気なら、受精卵の段階でゲノム編集をして、病気になる遺伝子を持っていない子供を生みだすことが一番の予防になります。他に治療法がないからです。体外受精して該当部分の遺伝子を組み替えることで、病気が発生しなくなるのだとすれば、そのことに対する社会的な拒否反応は少ないはずです。
「病気治療のために、問題となる遺伝子を変えてしまおう」という言い方で導入されれば、そんなに抵抗感は大きくないですよね。社会的には、クローン人間の場合は名前だけで拒否反応がありましたが、今回の中国の事例に対しては、「今回のやり方はまずかったかもしれないが、科学の発展と病気治療のためなら、きちんとした手続きと制度が整ったらやってもいいんじゃないか」という意見が結構あると思います。
■塾に通わせるのと遺伝子操作は何が違うのか
――先生の新著『答えのない世界に立ち向かう哲学講座』では、「病気治療のための遺伝子改変」より先の選択肢として、「身体的・精神的な能力増強(エンハンスメント)のための遺伝子改変」を取り上げています。人間はいずれエンハンスメントを行うのでしょうか。
まず、治療とエンハンスメントの線引きがそもそも難しいことがあります。たとえば知能の話。ある受精卵に対して遺伝子検査を行ったところ、生まれてくる子供(Aさん)のIQが70であると判明したとします。この受精卵に遺伝子操作を施した結果、AさんがIQ110になって生まれたとしましょう。ここで問題なのは、IQ95のBさんはどうなるのか、ということです。BさんのIQはAさんに越えられてしまうので、Bさんの親からすれば、「自分の子供にも受けさせたかった」と思うのは当然ですよね。

低身長症の人に対して成長ホルモンを投与するかどうかという話も同じです。中央値よりもかなり低い人に投与した結果、中央値よりも若干低い人の身長を超えてしまう可能性があります。そうするとやはり「うちの子は何で使えないのか」という話になってしまいます。「ここまでは治療だからいい」「ここからはエンハンスメントだからダメ」という線は非常に引きにくいのです。
社会的には、多くの人が治療・エンハンスメントを求めるだろうと思います。たとえば、子供の知的能力を高めるために、家庭教師をつけたり塾に通わせたりしますね。それを「一部の人だけがやるからダメだ」と言う人はさすがにいません。じゃあ、遺伝子を組み替えて頭を良くするのはなぜダメなのか。生まれてくる子供が知的能力を発揮できるように「初期設定」を高くしておきたいと親が望むのは、塾や家庭教師をつけるのとどこが違うのか。一番の「早期教育」としてゲノム編集を行う、そういう時代に今後なっていくのではないかと思います。
結局、スポーツにしても知的能力にしても、持って生まれた遺伝子の違いで生まれつき優秀な人はいるわけです。最初にその遺伝子を装着して子供を生むのがエンハンスメントですから、やってはいけない理由は私には見いだせません。
■「リベラル優生学」はナチスとは違う
親の立場から考えれば、健康な子供を産みたいとか、子供の能力はできるだけ高いほうがいいというのは、偽らざる希望だと思うんです。医学的に安全性が確認されれば、選択する可能性は高い。反対する理由があるかといわれると難しいでしょう。
ここで確認しておきたいのは、こうした遺伝子改良の話は、ナチスの話とは違うということです。遺伝子改変に対する批判としてよく聞かれるのが、「優生学や優生政策につながる」というものです。「命を人為的に選択するのは、ナチスが行った優生政策と同じではないか」というわけですね。
しかし、ナチスがやったのは、国家が個人の意思を無視した形で生命を抹殺したり隔離したりしたことです。現在の遺伝子検査や組み替えは、親の決定権が第一です。これは「リベラル優性学」といわれます。ナチスは、個人に対して国家が有無を言わさず生殖のあり方を強制した。一方、現在の議論は、国家ではなく個人、親となる人々が自由選択をするというものです。今は国家が「やってはならない」と反対意見を出し、親がそれを望むという構図になっていますよね。ナチスとは逆の状況です。
■「人間中心」の時代が終わる
――『サピエンス全史』『ホモ・デウス』著者の歴史学者ユヴァル・ノア・ハラリは、一握りのエリート層が生物学的な自己改変を行い自らを「ホモ・デウス(神の人)」にアップグレードする一方、そうでない人は人工知能に仕事を奪われた「無用者階級」として生きる未来を描いています。先生はこうした未来が訪れるとお考えですか。
世界中のすべての人が遺伝子を改変することはできないので、違いが生じるのは確かだと思います。ただし、今のレベルで遺伝子を組み替えても、どのぐらいの違いが出るのか、はっきりしません。この遺伝子をこう変えるとIQが高くなるというほど、特定されていないからです。今後どこまで厳密に解明されるかもわかりません。
単一の遺伝子が原因の病気は、遺伝病のなかでも極めてまれです。それなら治療はわりとやさしいですが、そうでない場合は遺伝子を少しいじったところで大差はないかもしれません。それなのに積極的にやるのかどうか。費用対効果の問題が出てくるでしょう。
とはいえ大きな方向性としては、バイオサイエンスが、人類の画期となるひとつの方向を示しているのは間違いありません。どこに向かっているかというと、「人間以後」の世界です。「ルネサンスが人間を発見した」と言われるように、近代社会が人間中心の時代だったとするならば、今訪れようとしているのは、「ポスト人間中心主義」の時代です。人間のDNAを読み取り、組み替えていけば、人間が生物として変わる。人間とは違う種、「ポストヒューマン」や「トランスヒューマン」が生まれる可能性があるわけです。
■「人間以後」の世界を生きる準備運動
『答えのない世界に立ち向かう哲学講座』では、バイオサイエンス以外にも「人工知能」と「資本主義社会のゆくえ」を大きなテーマとして取り上げました。その3つが示しているのはすべて「人間以後」の世界の到来なのです。
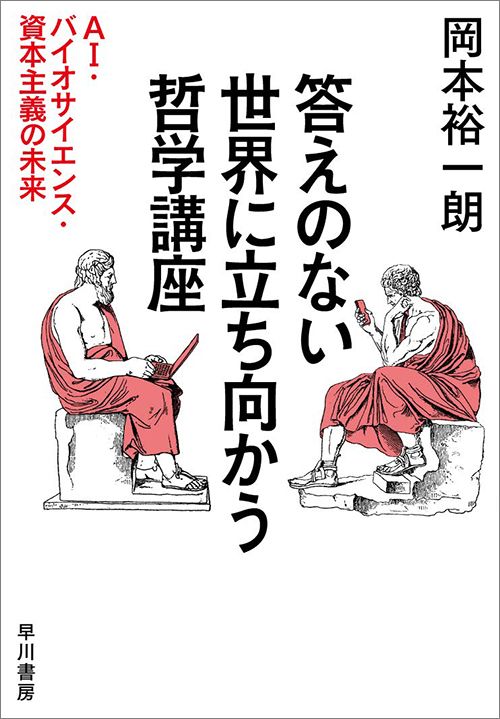
人工知能の登場で、機械、あるいはモノが人間と同じように考えることができるようになりました。シンギュラリティがどうのという以前に、人間だけが考える時代ではなくなったわけです。
資本主義についても、マルクスが考えていた産業資本主義とは、蒸気機関を中心にした大工場で人間が働いて利益を追求するものでしたが、今はIoTが発達して、人間が働かない工場が登場している。人間が働いて社会的生産をする社会とは違った社会に移行するかもしれない。そうなったときに人間はどうしたらいいのか、という問題は当然出てきます。
今までと違う人間になるかもしれないし、人間が不要になる社会を作り始めているし、人間よりも能率的に考える機械もうみだしている――これが「人間以後」の世界です。これまでの前提が根本からガラガラと崩れ始めるようなものを、自分たちで作りあげているのです。そこで立ち行かなくならないための準備運動として、さまざまな可能性を考えてみましょうというのが、『答えのない世界に立ち向かう哲学講座』のひとつの目論見でした。実際、中国の「ゲノム編集ベビー」のような事例が出てくると、そうしたことについて考えざるをえないわけです。
■「一般的にこう考えられている」を前提にしない
哲学の議論の進め方の重要な特徴は、「一般的にこう考えられている」ということを前提にしないということです。これが哲学の第一歩だと思います。それは果たして本当なのか、どこまでそう言えるのか、そうしたことを検討していく。技術的な問題や経済的な問題を消していって、それにもかかわらず反対するとしたら、理由には何があるのか。こうやって問うていくわけですね。
クローン技術が出てきたときに、イギリスの生物学者であるリチャード・ドーキンスは「私のクローンがいたら面白い」と言いました。こういう態度が哲学の一番の基本ではないかと思います。何か新しいものが出てきたときに、枠にはめて禁止するのではなく、それが一体どのような方向に私たちを導いていくのかを考える――この意味で、哲学は問題を根本から考える良い手立てになるだろうと思います。
----------
玉川大学文学部教授
1954年生まれ。九州大学大学院文学研究科哲学・倫理学専攻修了。九州大学文学部助手を経て現職。西洋の近現代思想を専門とするが興味関心は幅広く、哲学とテクノロジーの領域横断的な研究をしている。2016年に発表した『いま世界の哲学者が考えていること』は現代の哲学者の思考を明快にまとめあげベストセラーとなった。他の著書に『ポストモダンの思想的根拠』『フランス現代思想史』『人工知能に哲学を教えたら』など多数。
----------
(玉川大学文学部 教授 岡本 裕一朗 構成=早川書房編集部 撮影=プレジデントオンライン編集部 写真=iStock.com)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
テクノフィロソフィ!関西大学教授・植原亮さん『テクノロジーが哲学を変える』音声教養メディアVOOXにて、配信開始!
PR TIMES / 2024年8月16日 12時45分
-
イネコムギはイネのミトコンドリアを持つ新たなコムギであった!
共同通信PRワイヤー / 2024年8月7日 14時0分
-
初共演の堤真一&瀬戸康史が挑む二人舞台 「答えが出ない」問題を描く「A Number―数」【インタビュー】
エンタメOVO / 2024年8月6日 8時0分
-
メルク、パーキンソン病に対する遺伝子治療医薬品の製造促進に向け、遺伝子治療研究所と基本合意書を締結
PR TIMES / 2024年7月25日 16時40分
-
deCODE genetics:ゲノムの変異体はDNAメチル化に影響を与える
共同通信PRワイヤー / 2024年7月25日 9時58分
ランキング
-
1ハチに刺された男性が死亡 アナフィラキシーショックか 8日前に腕など複数刺され搬送 長野・伊那市
TBS NEWS DIG Powered by JNN / 2024年8月17日 18時56分
-
2台風離れ、Uターン本格化 災害警戒で予定変更の人も
共同通信 / 2024年8月17日 17時41分
-
3制限区域ではさみ紛失 新千歳空港で保安検査一時中断 帰省客で混雑
毎日新聞 / 2024年8月17日 14時19分
-
4尖閣・魚釣島にメキシコ国籍の男性が上陸、「カヌーで与那国島から漂流」…海保が救助
読売新聞 / 2024年8月17日 22時50分
-
5岩本前理事長、全役職を解任=不正支出疑惑―東京女子医大
時事通信 / 2024年8月17日 14時39分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください