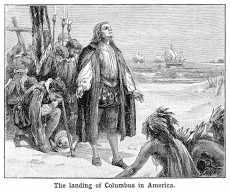「日本史と世界史」自虐的なのはどっち?
プレジデントオンライン / 2019年1月29日 9時15分
■見慣れた年表は何を書き落としているのか
日本史と世界史、どちらを学ぶのがよいのか? 歴史に興味をもつ人なら、一度は考えたことのある疑問だと思います。
日本人なら日本のことを知っておかなければならないから日本史、あるいは世界のことに目を向けるべきだから世界史――。いろいろな理由はあるでしょう。あるいは、受験のときに、「漢字が苦手だから世界史を選んだ」「どうしても横文字についていけなくて日本史を選んだ」とか。
本稿では、2つの視点から日本史と世界史を比較してみたいと思います。1つは、「日本史と世界史、どちらがより自虐的か」、もう1つは、「受験に有利なのはどちらか」。そして、まったく関係なく思えるこの2つのテーマは、じつは最終的には1つの論点に収斂されるのです。
前置きはこれくらいにして、本題です。まず、「世界史教科書風年表」を見てください。
1493年 ローマ教皇アレクサンドル6世、新大陸における紛争を解決すべく教皇子午線を設定。
1494年 トルデシリャス条約。教皇子午線に従い、東をポルトガル、西をスペインの勢力圏と決める。
気の利いた先生なら、「ポルトガルはアフリカに、スペインはアメリカ大陸に植民地をつくっていった」と解説してくれるでしょう。生真面目な生徒は、解説ごと丸暗記します。かくして、自虐的な子供が出来上がってしまいます。
なぜでしょうか。とくに自虐的な記述はありません。だから、問題なのです。世の中、何が書いてあるかよりも、何が書いていないかのほうが大事なのですから。人を騙すときには、嘘をつくよりも、大事なことを隠して教えないほうが、より効果的なのです。
世界史教科書風の年表に、その道の研究者ならば、誰でも知っている事実を足してみましょう。
1493年 ローマ教皇アレクサンドル6世、地図上に線を引き、「東はポルトガル、西はスペイン」と植民地獲得競争の縄張りを決める。もちろん、現地人の許可はとっていない。
1494年 トルデシリャス条約。教皇子午線の確認。地球は丸いので、日本(の明石市)が子午線の境界となる。ポルトガルもスペインも日本を植民地にすることはできず、最後は追い返される。
世界史教科書風の年表が、いかに罪深いか、おわかりでしょうか。客観的に事実を伝えているかのようで、じつは何も真実を何も伝えていないのです。
■書かれていないから「嘘」に気づかない
大航海時代の名前だけ聞くとロマンが溢れそうですが、やってこられた側にとっては侵略以外の何物でもありません。実際、フィリピンの名前の由来はフェリペ2世です。征服したスペインが記念に王様の名前を付けたので、国の名前になったのです。当時の日本人、つまり我々のご先祖様が、そんな連中に侵略をさせなかった事実の意味が、この記述では伝わってきません。
近代史における「日本の悪行」を並べている日本史教科書の嘘は、少し賢い受験生なら疑問に思うはずです。学界で通説になると、書かないわけにはいきませんから、嘘だと思っても書いておくのが教科書というものなのです。それでも、最近はインターネットの普及で、気になった用語を自分で気軽に調べることができます。教科書に書かれていることであっても、インターネットの検索結果には「捏造」の2文字がずらりと並びます。
しかし一方、「1492年 コロンブス、アメリカ大陸を発見」と書いてあるだけで、疑問に思う高校生はいないでしょう。大人だって知識がなければ、「あ、そうなの?」で終わりでしょう。日本の歴史と関係があるように思えませんし。
これが罪深い。以上、世界史教科書を学ぶと、自然と自虐的な日本人が出来上がります。
■世界史の教科書に「日本」はない
では、もう1つ。受験に有利なのはどちらか? 世界史です。
受験世界史を勉強する時のコツは、「広く浅く」です。フランス革命とか第2次世界大戦とか、受験問題として頻出の部分については、少しは深く勉強する必要はありますが、基本的には広く浅くです。どれくらい浅いかというと、「国の名前を覚えておけばよい」レベルです。
中国史でいうと、「三国時代の三国とは魏・呉・蜀」とか。三国志というとマニアが多い時代ですが、三国志に登場する人物を1000人覚えても、受験には1人も登場しないのです。
すべての時代のすべての国を取り上げることなど不可能なので、世界史では中心となるエリアが決まっています。西洋と東洋です。もっといえば、西洋とは、イギリスとフランスとドイツ、東洋とは中国です。日本の世界史教科書を読んでいると、西欧3国と中国が人類の曙から世界の中心であったかのように思えます。その4国が中心に描かれていて、記述量は圧倒的です。アメリカやロシアすら「成り上がり者」扱いです。さすがに20世紀になれば中心的記述になりますが。
世界史教科書は、いろんな分野の専門家が「自分の専門分野をぜひ盛り込んでほしい」と思っていて、ページの奪い合いなのです。東洋史では中国史、西洋史では英仏独史の専門家の発言力が強かったのですが、モンゴルやイスラム、アメリカやロシアの専門家が割って入っている、という状態が正確でしょう。日本史の専門家は、「日本史は別に教科書があるから、いいだろ!」で終わりです。
さて、この教科書のどこに日本が入り込む余地があるでしょうか。世界の片隅の島国だと思うしかありません。
ちなみにフランスには「世界史」という科目はなく、「歴史」です。人類の歴史など、「フランスとオマケ」です。1850年以降の近現代史だけを扱った教科書でも、そんな描き方なのです。
■何のために歴史を学ぶのか

そもそも歴史とは何のために学ぶのか。賢くなって自分の人生に生かすためです。世界のなかに自らを位置づけない世界史を学んでも、それは他人事にすぎません。
よく「自虐史観」という言葉がいわれますが、自分の国を意味もなく不当に貶める記述はよろしくないでしょう。しかし、さも客観的な事実を記しているだけのように見せて、何も知らない人をミスリードするのも問題ではないかと思います。
だからこそ、『並べて学べば面白すぎる 世界史と日本史』(KADOKAWA)では、外国(おもにヨーロッパ)の歴史と日本とを比較することで、そもそも日本人がどんな民族であるのかを考えるきっかけにしたいと私は思いました。よくも悪くも「ノンキ」な国、というのがその結論ですが、その特徴を理解しておくだけでも、客観的に見える「世界史」という教科が、まったく違ったふうに見えてくるはずです。
----------
憲政史家
1973年、香川県生まれ。中央大学大学院文学研究科日本史学専攻博士課程単位取得満期退学。在学中より国士舘大学に勤務、日本国憲法などを講じる。シンクタンク所長などをへて、現在に至る。『明治天皇の世界史 六人の皇帝たちの十九世紀』(PHP新書)、『日本史上最高の英雄 大久保利通』(徳間書店)、『国民が知らない 上皇の日本史』(祥伝社新書)、『嘘だらけの日独近現代史』(扶桑社新書)など、著書多数。
----------
(憲政史家 倉山 満 写真=iStock.com)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
ミセス「コロンブス」炎上を"初歩的"と笑えぬ理由 初歩的なミス?文化や歴史認識のギャップはこうして起こる
東洋経済オンライン / 2024年6月14日 23時40分
-
ミセスMVの話題を見てパラダイス銀河を思い出す人が続出→そういえば「しゃかりきコロンブス」ってなんなんだ?
おたくま経済新聞 / 2024年6月14日 13時25分
-
ミセスのMV炎上「コロンブス」が犯した恐ろしい罪 YouTubeは公開後に批判のコメントが相次いだ
東洋経済オンライン / 2024年6月13日 19時30分
-
「光も影もさらけ出す」…令和書籍の中学歴史教科書、検定初合格 竹田恒泰氏に聞く
産経ニュース / 2024年6月13日 12時17分
-
Mrs. GREEN APPLEの新曲MVが差別的であると非難殺到「最初から最後まで全部アウト。ちょっと酷すぎて」
オールアバウト / 2024年6月13日 10時45分
ランキング
-
1万博開幕まで300日前 一般向け前売り券販売伸び悩み、機運醸成が課題
産経ニュース / 2024年6月17日 20時12分
-
2アメリカ産の米「カルローズ」日本産との違いは?国産米の価格高騰で「低価格帯のコメは品薄」【Nスタ解説】
TBS NEWS DIG Powered by JNN / 2024年6月17日 21時34分
-
3作家も悲鳴、KADOKAWA「サイバー攻撃」の深刻度 ニコ動は復旧に1カ月、損失はどこまで膨らむ?
東洋経済オンライン / 2024年6月18日 8時40分
-
4キッコーマン「みぞれあん たっぷりおろし」1万9000本を自主回収…開栓時に噴き出すおそれ
読売新聞 / 2024年6月17日 17時30分
-
5吉野家 「シュクメルリ鍋」のグランプリ祝福に松屋感謝 “電撃訪問”のお礼返しにSNS「リスペクト精神すばらしい」「何このやさしい世界」と感動
iza(イザ!) / 2024年6月17日 15時28分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください