辞めるかもしれない社員を育て続ける理由
プレジデントオンライン / 2019年3月29日 11時15分
■いちばん難しくて大切なのは「人」
日々の経営には難しいことが多々あります。会社が大きくなり社員数が30人くらいになったとき、中小企業の経営で一番難しいのは「人」だ、と感じました。私は日々「人」について考え続けています。「人」こそが企業の財産だからです。
中小企業は中途採用がメインですから、社員の業務経歴は十人十色。仕事のやり方や考え方もさまざまです。
大手企業には、長年培われてきた企業固有の文化や慣習があり、それに合わせて仕事をすればうまくいくというやり方や、「これが正しい」と皆が思える共通認識がある。
しかし中小企業、ことさらベンチャーにはそれらがない。社員それぞれに異なる仕事のやり方、考え方、価値観があり、それが噛み合わないときにうまく落し所を見つけられない。こういうところが、中小企業の弱点でしょう。
■合理とはどういうことか?
たとえば、こんなことが起きます。同じ部署のAさんとBさんで、意見がぶつかる。それぞれの正義があって、どちらの意見も間違ってはいない。でも、どちらかを選ばないと仕事が先に進まない……。
そんなとき、解決策になるかどうかわからないですが、私は「合理性」についての話を社員によくします。
「『合理』というのはどういうことか考えてほしい。『合理』とは色んな理を合わせるという意味です。自分の側でも相手の側でもなく、間で折り合いがつくポイントを探す。それこそが『合理』であり、答えです。完全に納得できないかもしれないけれど、そこに皆の理が合わさる答えをつくらないと、1つの結果は出ない」
というような話です。

■社員間でのチューニングが必要
ですが合わせなければいけない理が、人数が増えるたびにどんどん増えてきます。合理のポイントは、メンバーの関係が深まるたびに合わせやすくなりますが、新しいメンバーが加わるたび、チューニングが必要になります。ベンチャーでは、この作業に追われるんです。
会社で1チームという単位はたいてい6~10人くらいだと思いますが、細かいチーム分けをしていない中小企業では、30~50人と、中途半端な人数なので、この人数を一気にチューニングしていく作業は本当に難しい。
IT企業は、「技術が一番」というイメージが強いかもしれません。でも実際は、IT企業の資産は人しかいないと私は思っています。弊社の売りは最新の技術ですが、それを作るのも、売るのもすべて人だからです。
近い将来、日本が深刻な人手不足に陥るのは間違いありません。だから業務のかなりの部分はAIなどに任せていくでしょうし、労働コストが低い海外に発注する流れも出てくるでしょう。ただ、企画、アイデア、デザイン、品質といった付加価値は生身の人間が担うしかない。IT企業の本質も、そこなんです。
■ドラえもんの世界を実現する技術
社員にどのように働いてもらうか、社員の能力を高まる環境をどうつくるか、魅力ある人を社に迎えるにはどうすればいいのか。
魅力のある人に来てもらうためには、普通の会社よりも面白いことをやり続けて、職場としての魅力を磨き続けるしかありません。弊社の最新技術は未来志向の多くの製品やサービスに活用されています。公共のディスプレイ画面に広告や販促情報、その他の様々な情報を表示するデジタルサイネージや、スマホ向けアプリを早く、安価に作れる自社プラットフォームサービスのapplicanもその範疇です。SF映画やドラえもんの世界のような近い未来を実現する技術を日々磨いています。「少し先のことにチャレンジする」というのがクリエイティブな人を集める上でも会社としての戦略ですね。
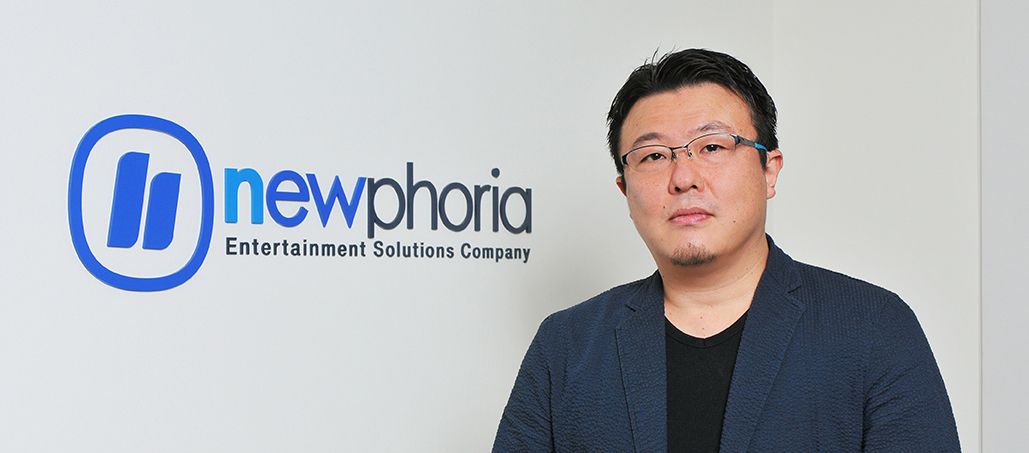
■「これからはインターネットの時代」
私は学生のときは「卒業したら探偵になるか、南米に金を掘りに行く」と荒唐無稽なことを言っていました。当時は就職氷河期真っ只中で「そんなこと言ってるとまっとうな人生をおくれないぞ」と周囲の友人に諭されて、やむなく就職活動を始めました。
入社試験を受けたのはNTTさんとバンダイさんの2社でした。バンダイは「おもちゃの会社だから面白そう」というシンプルな理由です。一方で、学生時代の「経営情報システム」ゼミでアメリカから帰国した教授が「これからはインターネットの時代になる」と言って、当時のブラウザのMosaicやEmacsを使わせてくれていました。1995年頃のことです。日本ではその存在がまだあまり知られていなかった時代にインターネットを学び、これは「面白そうだな」と思いました。NTTは当時インターネット、マルチメディアに力を入れていた数少ない企業でした。
最終的にはNTTから内定をいただき入社することになりました。就職氷河期に運がいいと言われますが、私は運は抜群に強いんですよ。マスカケ線という手相の強運な線が私は両手にあります(笑)。
■NTTの社長にはなれない
入社後は、企業や一般家庭を回ってインターネット回線の販売などをやりました。自らセミナー講師を務め、インターネットの普及活動もやっていました。電話がかかってきて「すみません、インターネットください」と言われたりしました。そんな時代でした。
「いつか起業する!」と明確に思っていたわけではありませんが、同期たちと将来の話になり、私は「どうせなら社長になりたいな」と言いました。「めざすなら社長でしょ」という軽い気持ちでした。しかし周囲から「それは無理だよ」と言われました。「NTTの社長は、基本的に東大か京大卒でないと」と。
確かに私立大学出身の自分では分が悪い。それなら何か考えなきゃな、とぼんやりと思いました。「社長が無理なら部長を目指す!」というのもおかしいでしょう。どうせならトップを狙いたい。このときから、起業を少しずつ意識していたかもしれません。
■30歳でNTTを辞める
入社5年目くらいで「ぷららネットワークス(現・NTTぷらら)」というインターネットプロバイダーに出向しました。いまの会社の仕事をしているのは、このときにネットビジネスの走りのような事業を自分が主体になって回した経験が大きいかもしれません。
仕事は、プロバイダー会員に対するEC(イーコマース)の提供で、物販だけでなく、映像配信やコンテンツ提供、ファンクラブ運営、オンラインチケット、キャンペーンプロモーションなどのインターネットビジネスに関わるあらゆることを経験させていただきました。トライ&エラーの連続で、完璧に仕上げたはずの企画書が机上の空論だったこともありました。物事はなかなか上手くいかない、ということを身をもって知りました。今から20年前はネットでモノを買う文化もまだ浸透しておらず、少し「早すぎた」のかもしれません。ただ、学びは多く、面白いビジネスでした。
当時から頑張っていた楽天やヤフーに加え、ゾゾタウンやアマゾンも参入してネットショッピング隆盛の今の時代はうらやましくもあります。
本格的な起業を見据え、NTTを辞めたのは30歳のときでした。ニューフォリアの前身の会社を友人と立ち上げました。私は取締役COOでした。ECの運営代行と、ホームページの制作受託を行う傍らで、映像や音楽をネット配信するサービスにチャレンジしましたが、Youtubeもない2004年当時、ビジネスモデルを作ることができませんでした。著作権管理を過剰に気にしすぎたりもして、映像配信事業の難しさを痛感しました。4年くらいやりましたが思うように成長せず、「このままではうまくいかない、次にシフトしよう」と考えました。
■起業はやりたくなったらやるべき
そして現在のニューフォリアをスタートさせました。35歳のときです。インターネットを軸にして新技術を取り入れた事業は今後さらに拡大していける、と思っていました。
「社長業はある程度経験値がないと難しいだろう」と漠然と思っていましたが、いざやってみると何もかもが初めてすぎて、これはいつ始めても変わらないな、と思いました。ですから、ベンチャーをやってみたい学生には「いつ始めてもいいと思うよ」とアドバイスしています。
私は大学で経営学を少しかじり、社会人経験も積みましたが、自分で経営を始めてみるとそれまでの知識はほとんど役に立ちませんでした。経営者になるのに、年齢や経験は関係ないと感じます。自分に足りないところは他人を入れて助けてもらえばいいですし、準備万端で始めればうまくいくわけでもない。
当時から他社さんより少し新しい技術を使い、少し先のこと、面白いことに会社としてチャレンジしていきたいと考えていました。この考えは今も変わりません。

■社員のアイデアが会社にチャンスをもたらす
うちは社員50人の小さな会社ですが、人材育成には力をいれています。NTTが原体験でした。NTTの人材育成は非常に手厚く、長期に渡ります。長い研修を経て、企業固有の文化・慣習が身についていきます。
社員にしっかり研修を受けさせる中小企業は少ないかもしれませんが、弊社では可能なかぎり研修を受けさせています。NTTには及びませんが、新卒は入社直後から4カ月、外部研修を受け、ビジネスマナーやプログラミングなどの基本を学びます。8月からようやく本配属となりますが、その後もたびたび研修を繰り返します。新卒だけでなく、中途採用の場合、タイムマネジメント、リスク対策、トラブル対策など、ビジネスのベース部分の研修には参加してもらっています。
IT企業はあらゆる業界との接点があって、新しい情報に触れる機会は多い。研修でしっかり基礎を身につけてから、新しいものに触れれば、仕事のアイデアがより浮かびやすい。社員の1つのアイデアが会社に大きなチャンスをもたらすことは、IT企業ではよくあることです。また、研修で身につけたスキルは社員個人にとってもプラスです。社員たちに「自分の市場価値、付加価値も意識するようにね」と言っています。
■いずれ辞める人に教育する意味
IT企業は、社員の流動性が高いので、「いつ辞めるかわからない社員に、なぜそれほどコストをかけるのか」と言われることがあります。もちろん、社員にはできるだけ長く一緒に働いてもらいたい。ただ、辞めてしまう人がいるのも事実です。
だから入社前の面接のときに、私は必ずその人のキャリアビジョンを聞きます。そのビジョンがうちの会社のビジョンとマッチするなら「共に成長できるから、一緒に働きませんか」と言っています。
採用でいい人が入ってくれるかどうかは給与の面も確かに大きいですが、特にエンジニアやクリエイターは働きやすい環境を重視している人も多いので、そこは整えるようには心がけています。毎年社員全員を対象にした面談をやっているのですが、そのときに職種によって重視する点が異なる傾向があるように感じました。営業職は「自分の仕事を認めてくれているか」を重視する。一方、エンジニアなどクリエイター系の人たちは成果への認識もありつつ、「どういう環境で仕事ができるか」ということを気にします。周りにどういう人がいて、どういう環境で働けるのか、に重きを置く傾向がありますね。

■フラットな組織がベストではなかった
働きやすさという点では組織の形態も重要です。最初は「組織はフラット型がいい」と思い、そうしていました。アメーバ経営のように自主的な組織もアリだな、と。フラットな環境のほうが働きやすいだろうと思ったからです。社員が10人くらいのときはそれでうまく回っていましたが、20人になった時点でうまくいかなくなりました。
中間層のポジションの人が増えてきたからです。20人を超えると私一人が全員をマネジメントするのは難しくなって、私以外にマネジメントを担当してくれる中間層の人が増えてきます。経営者と社員の間には金銭的な契約が成り立ちますが、中間層の人たちが他の社員をマネジメントするときにはそのインセンティブが効かない。フラットな組織では経営者以外のマネジャーのマネジメントコントロールが効きづらいんです。
■社長は、ただの役割
マネジメントする側もされる側も、自分の立ち位置や役割がつかめず、互いにどう振る舞うべきかが分かりにくくなって軋轢が生まれてしまう。そんな経験も踏まえて、今は組織を階層化しています。
企業組織の階層化には一定の合理性はあると感じています。ただ、各組織は階層化しつつ組織同士はフラットという構造にしています。これがどこまでうまくいくかは模索中。トライ&エラーです。
私自身の意識はフラットでいたいと思っています。あまり社長然としたくない。自分で始めた会社なので“言いだしっぺ”として多少はリスペクトしてね、という気持ちはありますが、基本的には社長というのはただの役割だと思っていますし、これからもそう思っていたいです。
インターネット自体がフラットでオープン、そしてフェアな存在です。インターネットのそういう部分に魅力を感じて関わってきたところもある。私も人としてそういったところは大切にしていきたいです。
(株式会社ニューフォリア 代表取締役社長 多田 周平 構成=山田由佳 撮影=石橋素幸)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
辞めない会社は何が違うのか?NEWONE『組織の未来は「従業員体験」で変わる』を共著書で出版
PR TIMES / 2024年6月24日 12時45分
-
リーダーはメンバーの夢を変えよ!「アップサイド」引き出すガイアックスの人材育成の流儀とは【インタビュー】
J-CASTニュース / 2024年6月20日 12時10分
-
「面接官や上司選べる」若手人材確保の"驚く手法" 人材不足が深刻、人に合わせる人事戦略が重要
東洋経済オンライン / 2024年6月20日 9時0分
-
入社1年目で上司の指示を拒否!「身勝手すぎる新入社員」を待ち受ける“2つの選択肢”
日刊SPA! / 2024年6月18日 15時51分
-
部長、どうか私を管理職にしないでください。 出世したくない会社員が激増する3つの理由
東洋経済オンライン / 2024年6月11日 7時20分
ランキング
-
1ソニー宮城拠点、250人削減=ブルーレイ、生産縮小
時事通信 / 2024年6月29日 15時49分
-
2「クレカタッチ」は交通系ICカードを駆逐するのか 熊本で「全国相互利用」離脱、一方で逆の動きも
東洋経済オンライン / 2024年6月29日 7時30分
-
3「押しボタン式信号」なぜ“押してすぐ青”にならないケースが? 納得の理由があった!
乗りものニュース / 2024年6月29日 16時42分
-
4作文は「理系だと苦手」「文系が得意」という大誤解 算数が得意な子は大概「作文もうまい」納得理由
東洋経済オンライン / 2024年6月29日 10時0分
-
5池袋西武とヨドバシ「売り場折半」の波紋と懐事情 北側にヨドバシ出店、西武の集客力に影響は?
東洋経済オンライン / 2024年6月29日 10時30分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください












