1000億円企業をつくったシンプルな問い
プレジデントオンライン / 2019年3月28日 15時15分
※本稿は、野々村健一『0→1の発想を生み出す「問いかけ」の力』(KADOKAWA)を再編集したものです。
■AIにもできない自由研究のテーマ設定
「最近の子どもたちはなんでもググれるから、私たちが子どもだった頃より頭が悪くなっているよね」
ある日、カフェで仕事をしているときに聞こえてきた、ママ友同士の会話です。
「そうそう、なんでも簡単に答えがわかっちゃうから、娘の夏休みの自由研究のテーマが決まらないのよ」
確かに、今や大抵のことはネット検索をすれば数分以内に調べることができ、「答え」の相対的価値は下がっています。AI時代が到来し、子どもたちの宿題にも影響を及ぼしていますが、このママ友たちの言うように、その結果、「人間は頭を使わなくなる」のでしょうか?
私はむしろ、逆だと思います。例えば、他の人とかぶらず、ユニークで、AIに聞いてもすぐわかる類のものではない、夏休みの自由研究のテーマ設定。これは、与えられた課題に対して「答え」を探すことよりも、はるかにクリエイティブで、難しい作業ではないでしょうか。
こうした「問い」を立てることは、今のところまだAIにはできません。
この自由研究のテーマ設定の話は、実は、今大人たちが直面している課題にも通ずるところがあります。
■「答えのない課題」と向き合う時代
私が勤めるIDEO(アイディオ)は、アップルの初代マウスをデザインしたことで知られていますが、その後領域を広げて今ではデザインを通じて様々な組織のイノベーションを促すコンサルティング会社であり、世界に9拠点を構えています。青山にオフィスを置くIDEO Tokyoには、日本の各業界をリードする多くの企業の方々が相談に来られます。問い合わせの件数は年々増え、昨年は年間120社を超えましたが、その相談内容の多くは、
「新規事業部が立ち上がったが、何をしたらいいかわからない」
「この事業の未来を考えたい」
「発想を変えたい」
といった、前例も正解もない「問い(課題)」ばかりです。
目まぐるしく変化する社会で生きる我々は、日々「答えのない課題」と向き合っています。そもそも課題自体が何であるかすら、わからないことが多いかもしれません。この予測不能で不確実な時代に自ら未来を切り拓いていくためには、これまでにない新たな価値を生み出すことが求められています。
「イノベーション」がバズワードのように飛び交い、多くの企業が焦燥感を感じていることは、こうした変化の象徴なのかもしれません。
■ロジカルシンキングの限界
ハーバードビジネススクールのロザベス・カンター教授が2006年に発表した論文によると、「イノベーション」という言葉は概ね6年周期で流行し、様々な企業の注力分野として戦略の中に現れるようです。この周期の理由は様々ですが、主に経営層の入れ替えや、ビジネスを「創る→回す」の新陳代謝が挙げられます。
そして、そのサイクルは年々加速しています。
この一役を担っているのがデジタルの浸透ですが、イノベーション、もしくは新たにビジネスを生んでいくという行為は、「数年おきに取り組むもの」ではなく、「カイゼン」のように組織の基本動作にしていくことが求められるようになっているのです。
そんななか、今でも日本(そして多くの海外)のビジネスの現場では、連続的な論理構築、もしくは「ロジカルシンキング」が全盛です。ロジカルシンキングの有用性を否定する気はまったくありませんが、これは「論理的な選択」をするためのツールであり、選択肢の中から答えを導き出すものです。
誰もが同じ方向を見ながら論理的に導き出される答えは重複しますし、模倣可能です。それでも皆で分け合える巨大な市場があるときはやっていけますし、既存の事業を効率化していくうえでは効果的でしょう。
■「次世代の通勤電車」はどうすれば考えられるか
しかし、今求められているのは、「新しい選択肢を創造」することです。「他と違うこと」「これまでにないもの」を創らなければならないのであれば、求めるべきものは「答え」ではなく、多くの可能性を生み出す、良質でクリエイティブな「問いかけ」なのです。
例えば、鉄道会社の方が「次世代の通勤電車」について相談に来たとしましょう。どんな問いかけから始めてみたら、面白い発想が湧きそうだと思いますか?
例えば次の3つだとどうでしょう?
(1)どうすれば新しい電車体験を、0からつくることができるだろうか?
(2)どうすれば今より20%多くの人が乗れる電車を作ることができるだろうか?
(3)どうすれば東京で毎日通勤する人々がより自由な働き方ができるような移動体験をつくることができるだろうか?
これらの中に、間違った問いはありません。(1)のような大局的な問いで「電車のあり方」を問いかけていくのもいいでしょう。(2)のように具体的な目標値を掲げて物理的な電車のあり方を改善していくのも方向性としてあると思います。
私のオススメは、(3)です。もしかしたら電車以外の移動手段も発想できる余白を残しつつ、どんな人たちのために発想をしているかも思い描けます。
■問いを立てる力は筋肉のように鍛えられる
実際にはどの問いかけに取り組んだとしてもなんらかの「答え」には到達するかもしれません。また、その企業の存在意義や戦略とも関係するでしょう。しかし(3)のような問いかけからスタートすると、新しいものが生まれる機会が増えるのではないかと考えます。
人間は幼いときほど好奇心旺盛で、きっと皆さんも子どもの頃は親を質問攻めにして困らせた時期があるでしょう。先入観やバイアスがない子どもたちの質問は実にクリエイティブで、そこにたくさんの可能性や想像力を感じさせます。
ところがその後の教育では、より速く正確に「答え」を導くことに重きが置かれているため、従来の常識や正論にとらわれない行動や思考をもとに「問い」をつくることに難しさを感じる人は多いかもしれません。
しかし、少し視点を変えたり工夫をすることで、面白い問いを考えていくことを練習することができます。これは筋肉のようなものなので、意識して鍛えることによって強化できるのです。
■日常の「当たり前」を疑う
「変化をもたらす問い」などと言うと、なにやら革新的で大それたものを考え出さないといけないように聞こえるかもしれませんが、必ずしもそうとは限りません。多くの場合、それは日常に潜んでいる一見なんの変哲もない疑問や気付きから始まることがあります。最近もそんなストーリーを目の当たりにする機会があったのでご紹介します。
薬ケース、もしくはピルケースというものを見たことがあるでしょうか? 毎日薬を飲まないといけない人にとって、飲み忘れは一大事です。それを防ぐために、多くの患者は毎週自分で、曜日別に蓋の分かれたピルケースに薬を詰めるのです。そのような努力をもってしても、実際には、定常的に薬を飲まないといけないアメリカ人の半分以上は何度も薬を飲み忘れているそうです。
2代目薬剤師だったT・J・パーカーはそんな「当たり前」に疑問を投げかけました。
「どうすればたくさんある薬を毎週手作業でピルケースに詰めないで済むようにできるだろう?」
ヘルスケア業界は巨大な市場規模があるにもかかわらず「当たり前」や「そういうものだから」というものが多く残っている業界です。そこで彼が考えたのは、オンライン薬局とも言えるようなサービス「ピルパック」です(実際ピルパックは実店舗を持ちませんが薬局として認可されています)。
■次々に気付きを得る
医師に処方された薬は自動的にピルパックと呼ばれる小袋に1回分ごとに仕分けられ、ロールとなって家に届きます。複数の薬を飲んでいる人の場合は、ひとつの小袋にそれらの薬がすべて入っています。仕分けはロボットによって自動的にされ、各パックにはその薬を飲む曜日と時間が印字され、患者はそれに従ってパックをロールからちぎり取って飲んだり出かけたりするだけです。
ビジネスモデルとしてはサブスクリプションで、ロールは自動的に届いていきます。小袋には華美な装飾もなく、印刷されている情報も必要最低限です。
プロジェクトを進める過程で、ヘルスケア業界にある「当たり前」の問題は、飲み忘れ以外にもあることがわかりました。
実は20~30%の患者はそもそも処方箋すら取りにいっておらず、さらには心臓発作のような体験をした患者でさえ4分の1の人は薬を取りに行っていないという状況も見えてきました。こういった人たちにとっても、まさに生活を一変させるようなサービスとなったのです(IDEOはこのケースで、ブランディングや戦略、そしてパックのデザインなどを担当。最初は奇抜さを狙っていたパックのデザインも、あくまで使いやすさを考えたものに変更し、登録作業も10ステップから3ステップに短縮するといった工夫をしました)。
■1兆円のインパクトを生んだ問いかけ
2013年に立ち上がったサービスは約5年でユーザー数3000万人以上、50州中49州で展開され、100億円の売上を出すまで成長しました。そして2018年夏、約10億ドル(約1000億円)でAmazon.comに買収されました。おそらくこれからさらに拡大することになるでしょう。
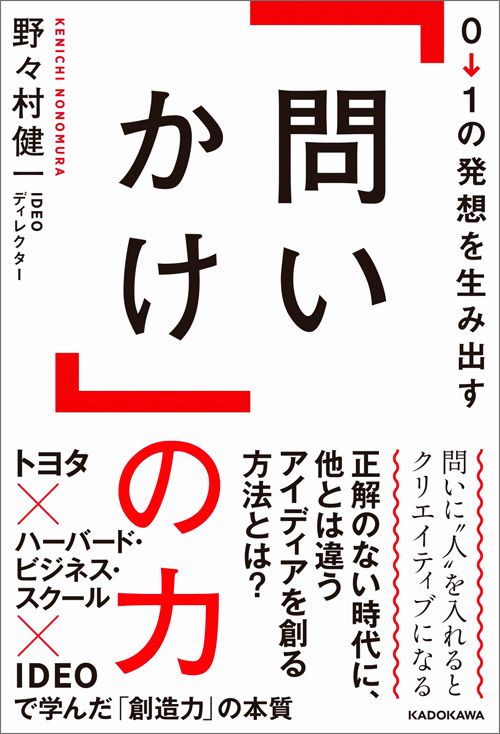
参考までに、このニュースが公開されたとき、米国の薬局御三家とも言えるCVS Health、Rite Aid、Walgreens Boots Allianceの株価は8~10%下落しました。薬局セクターのマーケットキャップ(株式の時価総額)にすると約130億ドル(約1.3兆円)が一瞬にして消滅したことになります。
規制上のハードルもあるかもしれませんが、是非日本にも入ってきてほしいサービスです。
もともとは「飲み忘れ」という、ヘルスケアのシステムの上に長らく「当たり前」のこと、しょうがないこととして放置されていた問題をどうにかしようと投げかけた問いかけは、ピルパックが育つ過程のなかで、様々な問いかけに変わっていき、「飲み忘れ」以外の部分にも射程を広げていきました。
数年後に、ディスラプション(破壊的なインパクトをもたらす変革)と言うにふさわしい大きな変化を起こすだけでなく、薬を飲まなければいけない患者やその家族の生活をより良いものに変えたのではないでしょうか。
(IDEOディレクター 野々村 健一 写真=iStock.com)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
日本調剤の「お薬手帳プラス」、厚生労働省が公表した「ガイドラインに沿った電子版お薬手帳サービスリスト」に掲載
PR TIMES / 2024年6月7日 17時40分
-
学校法人 洛陽総合高等学校 創立100周年企画
PR TIMES / 2024年6月6日 17時15分
-
日本でも普及する"低用量ピル"そのワケとは - 少子化が加速する、性感染症が増えるってホントなの?
マイナビニュース / 2024年6月3日 18時30分
-
「つながる薬局」導入薬局が5000店舗、LINE公式アカウント友だち登録者数が111万人を突破!
PR TIMES / 2024年6月3日 17時15分
-
〈フランスでは約800円なのに…〉日本のアフターピルはなぜ高額なの? 意外と知らない「経口中絶薬との違い」
CREA WEB / 2024年6月1日 11時0分
ランキング
-
1「押しボタン式信号」なぜ“押してすぐ青”にならないケースが? 納得の理由があった!
乗りものニュース / 2024年6月29日 16時42分
-
2ソニー宮城拠点、250人削減=ブルーレイ、生産縮小
時事通信 / 2024年6月29日 15時49分
-
3作文は「理系だと苦手」「文系が得意」という大誤解 算数が得意な子は大概「作文もうまい」納得理由
東洋経済オンライン / 2024年6月29日 10時0分
-
4あおり運転被害72.5%に増加…チューリッヒ保険調査
レスポンス / 2024年6月29日 16時0分
-
5「稼げればなんでもOKでしょ」は大間違い…1億円を貯めてFIREした経験から伝えたい「おススメできない副業」とは
THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年6月29日 10時45分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください












