「安い服を買わない」が誰も救わない理由
プレジデントオンライン / 2019年5月8日 9時15分
※本稿は、仲村和代・藤田さつき『大量廃棄社会』(光文社新書)の一部を再編集したものです。
■「ものが豊富ではない時代」は美化できない
東北地方の農村では古くから、「刺し子」と呼ばれる民芸がさかんだった。一針ひとはり、丁寧に施された刺繡は素朴で愛らしく、今でも手芸の一つとして親しまれている。だが、元はといえば、古くなった布を何枚も重ね合わせ、丈夫にするための工夫だった。
かつて、布は貴重品。庶民たちは、着物がすり切れて着られなくなっても、継ぎ合わせて別のものに生まれ変わらせ、ボロボロになるまで使い続けていた。為政者の側が、農民に貴重な木綿の使用を禁じ、麻しか身につけることができなかったため、繊維の荒い麻を一針ひとはり埋めることで、なんとか温かさを確保していた、という事情もあるようだ。
ものが豊富ではなかった時代は、そんな風に、服も、食べ物も、自分たちの手で作り、消費されていた。無駄にする余裕はなく、ものの寿命を全うするまで丁寧に使われた。
それは美化するにはあまりにも厳しい暮らしでもあった。天候不順による凶作や災害などの事態がひとたび起きれば、暮らしはたちまち立ちゆかなくなり、命を落とす人も少なくなかった。
■分業化で失われていった「作り手の顔」
産業化が進むと、自給自足の生活は少しずつ形を変え、服や食べ物の製造の過程は大規模になり、分業化されていった。その恩恵は非常に大きい、と私は思う。先進国では、文字どおり有り余るほどの食べ物が流通している。万が一、天候不順などの問題が起きても、グローバルな枠組みの中で補うことが可能になった。高価だった衣料品の価格もどんどん下がり、安くて丈夫でおしゃれな商品が当たり前のように手に入るようになった。
一方で、私たちの手に届く商品からは、作り手の「顔」が失われていった。自分たちの衣食住に関わるものが、どこで、誰の手で、どのように作られているのかがわからなくなってきた。さらに発展が進むと、製造の場は外国にも広がり、世界規模の分業体制が作り上げられた。作り手の姿はますます見えなくなっていった。消費しきれないほどの商品が作られ、捨てられていくが、私たちはどこで、どのくらいのものが、どのように捨てられているかについて、ほとんど目にすることなしに、暮らしていくことができる。
この世界規模の分業体制は、多様な選択肢の中から「買う」という行為を通して「選ぶことができる側」と、安い製品を作るために安い賃金しか支払われず、それでもその労働をすることでしか生活が成り立たないという、「選ぶことができない側」が、対になることで成り立っている。先進国の人が「安い」と思える価格で、たくさんの選択肢を用意するためには、誰かが安い労働力を提供する必要があるからだ。
■「素朴な暮らしは、とても危ういもの」
2012年末、取材でバングラデシュの農村を訪れたことがある。日本企業が手がけるソーシャルビジネス(社会的事業)を取材するためだった。
村では、日本から新聞記者が来たということで大騒ぎになり、村中といっても過言ではないほどの人たちが出迎えてくれた。やぎや鶏が我が物顔で村を歩き、子どもたちが裸足でかけ回る。私の頭に浮かんだのは、先進国ではなかなか目にすることのできなくなったその素朴さに対する、率直な賛辞だった。
「すごくのどかで、いいところですね」
そんな感想を口にした私に、事業を手がけてきた日本人の男性はこう返した。
「本当にその通りです。でも、災害だったり、病気だったり、ちょっとしたことが起きただけで、彼らの暮らしはたちまち、立ちゆかなくなる。この素朴な暮らしは、とても危ういものなんです」
私は、新しい出会いの高揚感だけにとらわれ、安易な言葉を口にしてしまったことを恥じた。
その時はそこまで頭が回らなかったが、当時の写真を改めて見返してみると、集まっていたのは男性ばかりだ。今回、バングラデシュの事情について改めて調べなおしてみて、これは女性が1人で買い物にすら出られないというバングラデシュならではの事情も絡んでいたのだろうと思う。
■「メイド・イン・バングラデシュ」の洋服
2013年4月、バングラデシュの首都ダッカ近郊で、縫製工場が入った8階建てのビル「ラナプラザ」が崩壊し、1000人以上が命を落とした。ここで犠牲になった人たちは、こうした農村から都市部の工場に働きに出ていた人たちだ。農村では、現金収入を得る機会はとても少ない。「次の世代の教育のために」。そんな思いが、彼女たちの支えになっている。
「Made in Bangladesh」。最近そんなタグが着いた洋服を、よく見かけるようになった。観光国ではないバングラデシュについて、日本ではイメージできる人は少ないだろうし、足を運んだことがあるという人も少ないだろう。この洋服を作った人が、どこで、どんな暮らしをしているのか。想像することが難しい世界に、私たちは生きている。
大量生産の商品は、顔の見える誰かが作った服に比べれば、価値が低いもののように扱われている。もしかしたら、生産に関わっている本人も、何万もある工程の一つを担っただけの商品に対する愛着は薄いのかもしれない。生産にかかわる人たちも、消費する側も、「簡単に捨ててよい」という感覚になってしまう。
移り変わる流行に合わせて、服を簡単に取りかえられる生活は、私たちを豊かにしたのだろうか。
■「いいものを、安く」の先は、不毛な価格競争だった
最近、たくさんのものに囲まれた暮らしに対して、疲弊しはじめたという声も聞くようになった。「買う」という行為は、人をハイにしてくれる。「ほしいものが手に入った」だけではなく、「他より安く手に入った」「お得感がある」「他の人と差別化できる」「とりあえず在庫を確保して安心する」など、理由はいろいろとある。
だが、家に帰ってその蓄積と向き合うと、「なぜこんなに買ってしまったのだろう」と罪悪感が募り、捨てきれずにあふれたものを前に、げんなりする。そんな経験を持つ人は少なくないだろう。
いいものを、安く。それが、これまでの賢い消費者だった。
だが、その先にあったのは、不毛な価格競争だ。同じ品質で、同じ技術で作られる製品の価格を下げるには、働く人の賃金を削っていくしかない。同じ国内での競争が一定の水準に達すれば、次はより賃金の安い国へと発注される。ある国では仕事が失われ、別の国では過酷な労働環境に耐えながら働き続ける人たちがいる。
地球環境への負荷も大きい。資源には限りがあり、いつまでも潤沢に使えるわけではない。また、大量に捨てられるものをどう処理し、コストをどう負担するかも大きな問題だ。こうしたことから目を背けていれば、そのまま、私たち自身の住環境や、健康問題として跳ね返ってくる可能性がある。
■「不買は幸福をもたらさない」
いま、世界中でグローバル化に「NO!」を突きつける人が増えているのは、経済が発展し、ものが売れて数字の上は「豊か」になったといわれていても、暮らしの中で実感できなくなり、こうしたシステムを続けていくことの限界を肌で感じているからだろう。
では、消費者として、私たちはどうしていけばいいのだろう。「買わない」という選択をすれば、それで解決するのだろうか。
バングラデシュのアパレル産業とそこで働く女性について詳しい茨城大学人文社会科学部の長田華子准教授は、「不買は幸福をもたらさない」と訴える。たしかに、バングラデシュの縫製工場には多くの問題がある。だが、だからといって私たちがそこで作られた服を買うことをやめてしまえば、彼女たちの労働環境が改善するどころか、工場への注文が減り、彼女たちの給与が下がるだけでなく、最悪の場合は仕事を失ってしまう可能性もあるからだ。
「私たちに問われているのは、これまで990円で売られていたジーンズの価格を、5円でもいいから値上げすることを受け入れられるかどうかなのです」
その5円を、現地の人たちの給与や労働環境の改善に使うよう、企業に対して声をあげていくことも、もちろん必要だ。
■「バングラデシュ アパレル」と検索してみると……
グローバル化が進んだ時代のメリットの一つは、情報も手に入れやすくなったことだ。インターネットに言葉を打ち込むだけで、これまで知らなかった国々の現実のことも、知ることができる。
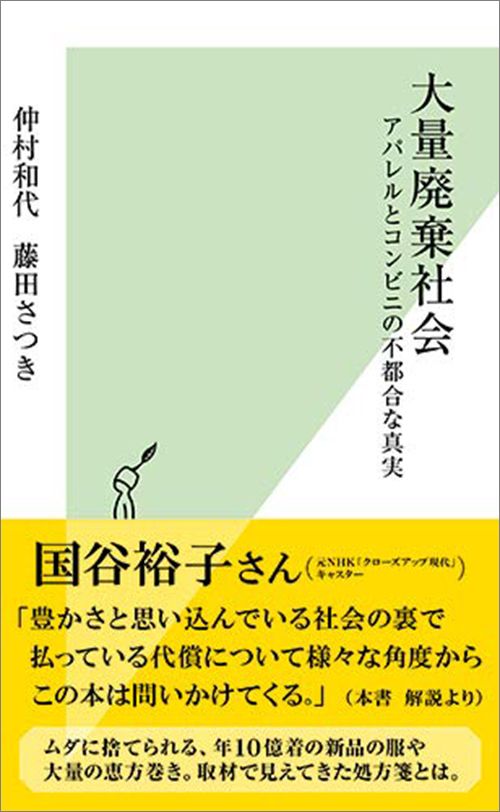
試しに、「バングラデシュ アパレル」とグーグル検索してみると、NGOなどのサイトで、現地の人の暮らしのことや、労働環境について知ることができる。もう少し詳しく知りたいと思えば、スタディツアーなどの形で現地に行くこともできるだろう。さらに、私たちがどう向き合えばいいかについても、様々な提案がなされ、議論がされている。
技術の革新を人類にとってプラスのものにするか、マイナスのものにするかは、使う側の意識に左右される。一度に大量にものを作ることができる技術。作ったものを運ぶ輸送力。人やものをつなげるインターネットの力。人類の知恵によって生み出された技術をどう生かすかも、人類の知恵次第だ。
そのための一歩が、知ることだ。目の前にある「安い服」は、どうやって生み出されているのか。買われることもなく捨てられてしまう服は、その後どうなるのか。自分が知った後は、誰かに伝えてみてもいい。そこから、一緒に何かできることはないかと考えてみてもいい。
知ろうとする人が一人増え、さらに変えようと一歩踏み出す。それが少しずつ増えれば、いまの方向性は変えられる、と信じることは、あまりに楽観的すぎるだろうか。
でも、そうすることでしか、変えることはできない。大量廃棄社会の現実を変えられるのは、私たち一人ひとりなのだ。
「いいものを、安く」ではなく、「いいものを、適正な価格で」。それが、これからの賢い消費者の姿だ。
----------
朝日新聞 社会部記者
1979年、広島市生まれ。沖縄ルーツの転勤族で、これまで暮らした都市は10以上。2002年、朝日新聞社入社。長崎総局、西部報道センターなどを経て2010年から東京本社社会部。著書に『ルポ コールセンター』、取材班の出版物に『孤族の国』(ともに朝日新聞出版)がある。
藤田さつき(ふじた・さつき)
朝日新聞 オピニオン編集部記者
1976年、東京都生まれ。2000年、朝日新聞社入社。奈良総局、大阪社会部、東京本社文化くらし報道部などを経て、2018年からオピニオン編集部。近年は、消費社会や家族のあり方などを取材。取材班の出版物に『平成家族』(朝日新聞出版)など。
----------
(朝日新聞 社会部記者 仲村 和代、朝日新聞 オピニオン編集部記者 藤田 さつき 写真=iStock.com)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
次々に辞めていく公立学校の教師たち…本当に「残業代なし」が離職の原因なのか?【〈ノンフィクション新刊〉よろず帳】
集英社オンライン / 2024年6月2日 19時0分
-
マンションは「ちょっと狭い」より「かなり狭い」がベスト…「良い物件を掴めば3000万円儲かる時代」の必須スキル
プレジデントオンライン / 2024年6月1日 9時15分
-
40年ぶりの新型不動産バブル到来…これからの勝ち筋の買い方と"負け組物件"に転落するマンションの特徴
プレジデントオンライン / 2024年5月30日 9時15分
-
「毎日ヘトヘトの年収1000万円より余裕のある600万円社員を増やせ」日本で子どもを増やすための必須改革
プレジデントオンライン / 2024年5月29日 16時15分
-
大失敗!5月に後悔した「気合いを入れた新生活」の悲惨な結末…
美人百花デジタル / 2024年5月22日 20時0分
ランキング
-
1「実質強制だ」 健康保険証廃止まで半年、SNSに投稿相次ぐ
毎日新聞 / 2024年6月16日 21時2分
-
250万円台の激安ベンツが「実はお買い得といえる」ワケ。“壊れそうなイメージ”の実体とは
日刊SPA! / 2024年6月16日 15時53分
-
391歳女性ひき逃げ疑いで送迎業の男(72)を逮捕 「人間だとは思わなかった」と否認 兵庫・姫路市
ABCニュース / 2024年6月17日 0時2分
-
4高校生、店員に助け求める 容疑者ら「取り合うな」 旭川17歳殺害
毎日新聞 / 2024年6月17日 12時21分
-
5教員の裁判で傍聴席が満員「動員されているのでは…」尾行、質問状、記者会見。取材を重ねて組織の不祥事を明らかにした2か月半
47NEWS / 2024年6月17日 11時0分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください












