橋下徹「上流の氾濫で下流が助かる治水の現実」
プレジデントオンライン / 2019年10月23日 11時15分
(略)
■八ッ場ダムは本当にきっちりと機能したのか?
政府与党は、利根川水系につくられた八ッ場ダムに関して、台風19号の豪雨に対してきっちりと機能していたと言い張った。2009年の政権交代時に八ッ場ダムの建設を中止にすると宣言した旧民主党系の野党各党は、歯切れが悪い。野党各党は、八ッ場ダムがたまたま試験湛水で水を抜いていた状態で、水を貯める能力が通常よりも過大だった可能性を指摘すればよかったのに、それをしない。勉強不足なのかなんなのか。
今回、満水に至って緊急放流したダムが6カ所あり、その他のダムでも緊急放流にまでは至らなかったが満水の恐れがあったものが多数あったと聞く。これらのダムは事前放流(水を抜く)が十分にできずに、水を貯める力の限界に達していたということだ。
八ッ場ダムも、通常運用時で水がある程度貯まっている状態であれば、今回の豪雨の水をどこまで貯めることができたのか、つまり通常運用時において今回の台風19号に対してまったく問題なく対応ができたのかの検証が必要であって、そのことは本メルメガ前号(Vol.171【「大豪雨」時代の治水行政(1)】台風19号豪雨被害で考えたい――未来世代の安全・安心のためには「ダムに頼る治水」でいいのか?)で論じた。
それで、そのオンライン版(橋下徹「八ッ場ダムは本当に機能するのか」 /再考・大豪雨時代の治水行政)における八ッ場ダムに疑問を呈したかたちの記事がネットで流れると、橋下はダムの否定者だ! ダムは必要だ! というネットの声が沸き起こった。
まずね、こういうネットの連中に言いたいのは、オンライン版だけを読んで済ますなよ、ということ。オンライン版は無料だから、当然、簡略版になっている。だから文中は(略)のオンパレードだ(笑)
(略)
■僕はダム建設をすべて否定しているわけではない
お金を出して僕のメルマガの全文を読んで下さっている有料購読者の皆さんは理解して下さっていると思いますが、僕はダムを全否定していません。そうそう、僕は原発の全否定者とも思われているらしいが、そうじゃない。僕の主張はちょっと複雑なところがあって、なかなか伝わりにくいところがあると思う。だから、それはこの有料メルマガでガンガン論じていきたいと思う(笑)
話を元に戻すと、僕は、どうしてもやむを得ない場合に限ってダムを建設すべきであって、今は安易にダムが選択されており、それは最終的に住民の生命・安全を守ることにはつながらないというのが持論だ。
(略)
治水対策としては、河川の弱点部分を克服し水をきちんと流すことが基本。他方、ダムはそれとは逆に水を貯めることを基本としているので、河川の弱点部分に焦点が当たりにくいという最大の欠点があることを前号で指摘した。
さらにダムは、水を貯める限界を超えた時の危険性が、甚大になることも指摘した。
(略)
それと近日の報道でだんだん明らかになってきたけど、雨の降り方が予想外なものになってきている。ダムによる治水は、雨の降り方や山間部に降った雨がどのように川の源流に集まってくるか、そして源流以外に降った雨はどのように川に入ってくるかなど、緻密な計算で予測を立てて、それを基に治水計画を作っている。この計算による予測がでたらめなものだと言うつもりはないが、それでもあくまでも机上の論。
当然、予測を超えた自然災害などはいくらでも発生する。そもそも自然災害が、人間が計算し予測した通りに発生して推移するなんてこと自体がおかしいことなんだ。今回だって、当然予想外の雨の降り方や、川の源流への水の流れ方が多発した。
こういうときに、威力を発揮する治水対策というのは、水を貯めるダムではなくて、できる限り水が流れる河川の整備なんだよね。
(略)
■上流が氾濫すれば下流が助かるという厳然たる事実
僕は大阪府知事のときに、大阪府内だけでなく、関西全体の治水行政に携わってきた。特に関西は淀川水系や大和川水系という大水系を抱え、淀川と大和川の河口域にある大阪平野は日本でも有数の大都市を形成している。
淀川と大和川という大河川に囲まれた低地の大阪平野は、いずれかの河川が氾濫し、ましてや堤防決壊にでもなれば、その都市機能は壊滅状態になる。だから、大阪において特に治水行政は重要だった。
このときに色々と学び、経験したことを基に、10月13日にフジテレビ系の番組「Mr.サンデー」に出演した際、
「治水行政にはシビアなところがある。上流で氾濫させて下流を守るという考えもある」と発言したんだ。
同じく出演していた元国土交通省官僚の布村明彦さんは、「行政は平等だから……」と建前として僕の考えを否定したけどね。
そうしたら、番組終了後、色んな意見が殺到したね。
「橋下が言うような話はあり得ない!」
「橋下がたわけたことを言っている!」
「そんな話があるなら、それは治水行政の闇だ!」
(略)
歴史を振り返れば、上流で氾濫すれば下流が助かるという事実が厳然として存在する。それが河川の自然な姿だ。もし、上流の氾濫を無理矢理抑え込めば、その分下流に水が来る。何も手立てを講じなければ、下流が氾濫するのは当然だ。
だから治水行政というのは、上流を氾濫させないように河川改修をする場合には、必ず下流の方からしっかりと河川改修をして下流で水が流れるようにしてから、上流を河川改修するというのが鉄則だ。
(略)
■なぜ千曲川の「つっかえ」はそのままなのか
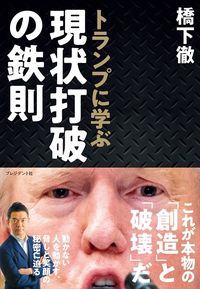
今回堤防が決壊した、千曲川の長野市穂保付近。どうもこの決壊場所の下流先は、いっきに川幅が狭くなっているらしい。水量が増えれば、ここで水がつかえるのは誰でも分かる。にもかかわらず、なぜそのつっかえを取らないのか。
そのつっかえを取ってしまったら、下流域に多くの水が流れてしまい、つっかえがあることを前提している千曲川下流域が耐えられなくなるからだ。
もしこのつっかえを取る河川改修をするなら、河川改修の原則である、「まずは下流から」を徹底しなければならない。下流部の河川改修ができるまでは、このつっかえを取ることができないんだ。まさに下流部を守るために、上流部の河川改修が棚上げにされるということ。
下流部の河川改修は困難なので、千曲川のこの決壊した箇所は、堤防強化の対策を講じる予定だった。それが間に合わない中での堤防決壊だった。
(略)
(ここまでリード文を除き約2600字、メールマガジン全文は約1万2100字です)
※本稿は、公式メールマガジン《橋下徹の「問題解決の授業」》vol.172(10月22日配信)を一部抜粋し、加筆修正したものです。もっと読みたい方はメールマガジンで! 今号は《【「大豪雨」時代の治水行政(2)】なぜ千曲川はあの地点で決壊したか……知事を経験したからわかる利害調整の現実》特集です。
----------
元大阪市長・元大阪府知事
1969年東京都生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業後、大阪弁護士会に弁護士登録。98年「橋下綜合法律事務所」を設立。TV番組などに出演して有名に。2008年大阪府知事に就任し、3年9カ月務める。11年12月、大阪市長。
----------
(元大阪市長・元大阪府知事 橋下 徹)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
洪水被害の減災を目的に大規模な「堤防決壊」実験を十勝川で実施 押し寄せる大量の水に“決壊しにくい堤防”はどこまで耐えるかなど検証 北海道幕別町
北海道放送 / 2024年6月27日 19時36分
-
中国各地で洪水被害、気候変動よりも直接的な理由があった―仏メディア
Record China / 2024年6月27日 7時0分
-
「大雨に備える」“関東最大級”宮ヶ瀬ダム 杉野アナ・佐藤アナ・市來アナが取材
日テレNEWS NNN / 2024年6月22日 9時45分
-
田んぼダムで浸水被害を防げ 低コストで効果 東日本豪雨で被害の茨城・常総市で研修会
産経ニュース / 2024年6月17日 15時55分
-
本格雨季前に気象庁は「線状降水帯」情報の新運用開始…2年連続堤防決壊「敷地川」流域住民は(静岡・磐田市)
Daiichi-TV(静岡第一テレビ) / 2024年6月6日 17時20分
ランキング
-
1ソニー宮城拠点、250人削減=ブルーレイ、生産縮小
時事通信 / 2024年6月29日 15時49分
-
2「クレカタッチ」は交通系ICカードを駆逐するのか 熊本で「全国相互利用」離脱、一方で逆の動きも
東洋経済オンライン / 2024年6月29日 7時30分
-
3「押しボタン式信号」なぜ“押してすぐ青”にならないケースが? 納得の理由があった!
乗りものニュース / 2024年6月29日 16時42分
-
4作文は「理系だと苦手」「文系が得意」という大誤解 算数が得意な子は大概「作文もうまい」納得理由
東洋経済オンライン / 2024年6月29日 10時0分
-
5池袋西武とヨドバシ「売り場折半」の波紋と懐事情 北側にヨドバシ出店、西武の集客力に影響は?
東洋経済オンライン / 2024年6月29日 10時30分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください












