30代で身を置くと"ムダ"に終わる会社の共通点
プレジデントオンライン / 2019年10月24日 15時15分
■とりあえず一回会社を辞めたらいい
【冨山】僕がお手伝いしている東京電力とかパナソニックみたいな大企業が変わるのは大変。理由はかんたんで、新卒一括採用・終身雇用という既存システムで長年やってきた人がたくさんいるから。彼らからすると、遠くからやってきた新たな知によって、長年築き上げてきた地位がなくなったら困るわけです。今までは野球をやってきたのに「今日からラグビーをやりましょう」と言われても、対応できないでしょう。
だから20代、30代の若手社員がどんなに知の探索をして、本気で会社と戦っても報われません。じゃあどうすればいいかというと、とりあえず一回会社を辞めたらいい。どの会社も建前としては変わらないといけないというものの、実践できているのはごくわずか。
変わることができない会社にいる若手社員は時間のムダ。今の会社でやりたいことがあるとしても、一回辞めて、違うところで修行する。会社の仕組みが変わった頃、50歳くらいでまた戻って来るのがちょうどいい。

■「大企業病」はどうしたら克服できるのか
【馬場】僕もアグリーで。日本的な会社は、どんなに若手が戦っても途中でストップする仕組みになっています。この仕組みを変えずして知の探索をしても時間がもったいない。
以前、「大企業病」はどうしたら克服できるのかということに取り組んでいた時期があって。
その時にわかったことは、ふつうの人が、MBAとかハーバードのやり方を企業に取り入れれば取り入れるほど悪化するということです。つまり「知の深化」ばかりをやってしまう。
悪化しすぎてしまった場合の処方箋は西洋医学しかなくて、解体するのみ。でも自らの力で再生能力がある場合は東洋医学が使えます。整えれば自然治癒で回復するということで、僕は今パナソニックでこっちをやっています。結局のところ、イノベーションをストップさせるのは人間じゃなくて、会社の仕組み。

■ゼロイチという青い鳥探しはムダ
【安田】多くの会社がイノベーションを生み出せていない本質的な原因は、何か新しいことをしなければと、外にばかり目を向けているからだと思います。しかし、若手社員を中心に、社内のどこかにイノベーションの芽になるものやアイデアは湧き出ているはず。くみ取りをせき止める“何か”をなくすだけで一気に動き始めると思います。だからまずは社内の仕組みやルールを変えたほうがいい。新しいルールを作ってしまえば、役員や上司が(任期を終えて)変わったとしても、継続できるでしょう。日本企業は、一度決めたルールは変えにくいですから。
でも実際は、イノベーションというと、社内の人間ではダメだから、外から優秀な人を呼ぼうっていう発想になりがち。それって、新しいことをはじめるにはゼロイチでやらなきゃいけないっていう先入観があるからだと思います。その発想は危険。

【冨山】大企業でイノベーションとなると、ゼロイチの青い鳥を探し始めてしまう。ゼロイチなんて一生懸命やっている暇があったら周りのビジネスを観察しなさいと。知を組み合わせて新結合させるなんていうのは高尚な言い方で、イノベーションって要はパクリですよ。ヤフーやグーグルにしろ、フェイスブックにしろ、既存のビジネスモデルを進化させることで競争に勝っているわけですから。あのヘンリー・フォードだってそうでしょう。食肉処理場を見て、自動車の大量生産を思いついたそうですから。昔からゼロイチなんてないわけです。
渋谷や六本木のITベンチャー系の若い人たちはこのあたりがうまい。でも経営はできなかったりする。
彼らの中には、ずっと“ガキでいたい”っていうシリアルアントレプレナー(連続起業家)もいるから、それはそれでいい。だって、事業として成熟させていくのは“おとな”の仕事ですから。
大企業の人はおとなになりすぎているから、これ以上おとなになっても仕方ない。どっちがいい悪いじゃなくてガキとおとなの両方が必要です。
■見習うべきはラグビー日本代表
【冨山】今いる会社の仕組みがダメだったとしても、“変人”が上に抜擢されていれば、まだ報われる可能性がある。パナソニックなんかは面白くて。(シリコンバレーを拠点にしている)馬場さんもそうですし、ナンバー2の樋口(泰行)さんに至っては、出戻りですから。樋口さんはパナソニックの新人の頃、会社のお金でハーバードに行ったと思ったら、その後に辞めちゃって。60歳くらいになってまた戻って来た。考えてみるととんでもない社員ですよ(笑)。
会社としては、やっぱりエース級の社員が辞めると、いよいよ危機感を持つ。とりあえずハーバードに行かせればいいとか、小手先ではダメなんだって気づく。だから会場のみなさんは自分がエース人材だと思ったら辞めてあげたらいい。そしたら会社も変わりますから。で、変わった頃に戻ってくると。
【馬場】転職経験がない人はシリコンバレーに行ったら変人です。1つの会社に10年もいたら能力的に問題があると思われる。日本は変人と普通人がひっくり返っていかないといけない。
【冨山】その通り。でもそのような起用がメインストリームになるのを嫌だと思っている人は大勢います。今までずっと同じ会社にいてポジションを守ってきた人からすると、とんでもない話と感じるのはもっともですから、そこを変えていかなければなりません。
たとえば、AIの分野で世界トップレベルの人材を雇うとすると新卒でも年収2000万くらいを支払うことになります。でもその上司は年収800万だったりするでしょう。日本の既存組織でやってきた年収800万の人が年収2000万の人材を使うことができるのか? っていう話ですよ。ストレスでしかないから当然無理で、結局は年収500万の優秀な新卒をつかまえて、AIを教えるっていう選択肢を取ってしまう。それではダメだということ。
まさに今のラグビー日本代表と真逆の状態です、日本の会社は。日本のラグビーチームって多国籍でしょう。多様性を受けいれている。会社もそうなっていかないと。
■サッカーW杯の成功をパナソニックでも実践
【入山】サッカーも、Jリーグとプレミアリーグはほぼ同時期に創設され、当時は売り上げが同じくらいだった。でもプレミアムリーグの売り上げは今、その頃から10倍以上伸びてJリーグを引き離しています(※1)。それは超グローバルコンテンツになったから。イングランドのマンチェスターには、イギリス人の選手が1人もいませんが、それでもイギリス人が応援するという仕組みができている。これが日本でも必要です。
※1 売上高:Jリーグは約1257億円(2018年度、出所:Jリーグ)。プレミアリーグは約6620億円(2018年度、出所:デロイト)

【馬場】僕はJリーグの社外理事もやっていまして。サッカーやラグビーのやり方を事業にも取り入れています。30年くらい停滞している日本企業を尻目に、スポーツ界はどんどん進化している。サッカー界の最大の発明は、100年くらい前にワールドカップ(W杯)をはじめたこと(編集部注:1回目のワールドカップは1930年)。FIFAのトップが「国別対抗をやるぞ」って言い出して、当時はみんな「はっ?」ってなった。今までクラブで敵だった人同士が仲間になって、別の監督を立て、別の環境で戦う新しいチームを作る。これってすごいイノベーションですよね。この仕組みを取り入れようとしているのが、僕が今取り組んでいる「Panasonic β(パナソニック・ベータ)(※2)」です。
※2 Panasonic β……パナソニックが米シリコンバレーに置く戦略拠点。企業文化の変革を担う。製品・サービスごとの縦割りの現状を「タテパナ」とし、クロスバリューが生まれる「ヨコパナ」の実現を目指す。

■人間に対してどれだけ“沸騰”できるか
【馬場】何がイノベーションかというと、クラブ制と国別対抗という仕組みを両立させているということ。どんなにW杯が盛り上がっても、サッカー界はクラブをやめていないわけですよ。選手はクラブに所属しながら、W杯での優勝を目指している。この両立がビジネスでも重要。これをやらないと組織は変わりません。
だからどんなにみなさんが理解しても、上の人たちが理解しないとダメ。「ONE JAPAN」は若手社員中心で、今この会場には若い人が多いけど、おじさんたちを連れて来られるイベントにしたほうがいい。「こんなすごい人たちが集まっちゃった」って話題になるくらいの。日本企業の社長なんて探索好きだから来てくれますよ。でも社長だけが応援してくれても変わらなくて。役員とか部長とかも連れてこないと。そうでもして理解させた方が会社のためにもなります。
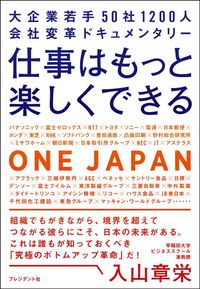
【冨山】最後に問われるのは、みなさん自身が、人間に対してどれだけ“沸騰”できるかということ。ものごとを大きく変えていく時は、いろんな人の人生や生活に光と影をつくることになるでしょう。
人は影が多いと思ったら必死で抵抗するし、大企業の場合は多くの人生がかかっている。経営者はそういうことも眺めながらどうしようかと考えています。だからこそ、最終的にはみなさん一人ひとりが、自分の人生も含めて、人間というものに対して深い洞察力を持って、理解して、思いを持てるかどうかが大事になってくる。
それが面倒な人は“こども”のままでいればいいし、他人の人生に関わっていくことに本気で喜びを感じられる人は、“おとな”のマネジメントをすればいい。
人間的な情熱や無邪気さと深い洞察力によって「両利きマインド」を身につけたら、結構イケてる50代になれるんじゃないかな。期待しています。
----------
経営共創基盤CEO
1960年生まれ。東京大学法学部卒、在学中に司法試験合格。スタンフォード大学でMBA取得。2003年から4年間、産業再生機構COOとして三井鉱山やカネボウなどの再生に取り組む。07年に経営共創基盤を設立し現職。パナソニック社外取締役、東京電力ホールディングス社外取締役。
----------
----------
パナソニック 執行役員/ビジネスイノベーション本部長兼パナソニックノースアメリカ副社長
1977年新潟県生まれ。2000年中央大学経済学部卒業。01年SAPジャパン入社。15年欧州SAP SEのバイスプレジデントを経て17年4月よりパナソニック。ビジネスイノベーション本部副本部長。18年同本部長。Jリーグ特任理事。
----------
----------
経済学者/大阪大学大学院経済学研究科 准教授
1980年東京都生まれ。2002年東京大学経済学部卒業。政策研究大学院大学助教授を経て、14年4月から現職。専門は戦略的な状況を分析するゲーム理論。主な研究テーマは、現実の市場や制度を設計するマーケットデザイン。学術研究の傍らマスメディアを通した一般向けの情報発信や、政府での委員活動にも積極的に取り組んでいる。
----------
----------
早稲田大学大学院経営管理研究科教授
専門は経営戦略、グローバル経営。慶應義塾大学を卒業後、ピッツバーグ大学経営大学院博士課程修了(Ph.D.)。三菱総合研究所研究員、ニューヨーク州立大学バッファロー校助教授、マクロミル社外取締役などを務める。
----------
(経営共創基盤CEO 冨山 和彦、パナソニック 執行役員/ビジネスイノベーション本部長兼パナソニックノースアメリカ副社長 馬場 渉、経済学者/大阪大学大学院経済学研究科 准教授 安田 洋祐、早稲田大学大学院経営管理研究科教授 入山 章栄 構成=小林 こず恵)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
早稲田大学大学院 入山 章栄教授が 世界の経営学からみるAI経営の視座を語るオンラインセミナー『DX・AI時代のグローバル経営とは』
PR TIMES / 2024年6月26日 13時45分
-
協力のメリット!経済学者・安田洋祐さん『安田洋祐の戦略思考入門|第7話. 協力ゲーム――競合するラーメン屋はどうコラボするか――』音声教養メディアVOOXにて、配信開始!
PR TIMES / 2024年6月14日 14時15分
-
キャディ、入山章栄氏と大東精機 執行役員の松本氏をゲストに迎え、オンラインイベント「製造業における管理職のジレンマ 『現場意識改革』で8割解決できる」の開催を決定
PR TIMES / 2024年6月11日 10時45分
-
協力できるか?経済学者・安田洋祐さん『安田洋祐の戦略思考入門|第6話. 非協力ゲーム:繰り返し囚人のジレンマゲーム』音声教養メディアVOOXにて、配信開始!
PR TIMES / 2024年6月7日 13時15分
-
リーグワン王者・BL東京に根付く、タレントを発掘し強化するサイクル。リーグ全勝・埼玉の人を育てる風土と仕組み
REAL SPORTS / 2024年6月3日 2時55分
ランキング
-
1関東「気動車王国」の離れ小島路線が面白い! 不思議な“右ハンドル”車両 3駅の路線に“スゴイ密度”であるものとは?
乗りものニュース / 2024年6月29日 15時12分
-
2意外な面倒さも? 財布いらずの「スマート支払い」、店側はどう思っているのか
ITmedia ビジネスオンライン / 2024年6月30日 8時10分
-
3ウイスキーが「おじさんのお酒」から激変したワケ 市場復活に導いたサントリーのハイボール秘話
東洋経済オンライン / 2024年6月30日 8時20分
-
4「押しボタン式信号」なぜ“押してすぐ青”にならないケースが? 納得の理由があった!
乗りものニュース / 2024年6月29日 16時42分
-
5障害者雇用未達で「社名公表」寸前からの挽回劇 法定雇用率クリアへの3年で見えた成果と課題
東洋経済オンライン / 2024年6月30日 9時0分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください












