希望を最大化する「投資家的生き方」で生き残れ
プレジデントオンライン / 2019年11月27日 9時15分
※本稿は藤野英人『投資家みたいに生きろ 将来の不安を打ち破る人生戦略』(ダイヤモンド社)の一部を再編集したものです。
■リスクと「向き合う」ということ
平成が終わりました。日本経済を長らく停滞させてきたもの。それは、保守や忖度(そんたく)を重んじ、リスクを避ける体質でした。
特に、日本では高齢化問題が重しになっています。どの組織でも上の世代がいつまでも重要なポストに居座り、新陳代謝が起きにくくなっている。その結果、若い人たちが力を発揮する場所が増えず、社会に新しい価値観が根付かない。時代が変化しつつあるのに、旧来型の発想から抜け出せず、成長の芽が摘(つ)まれてしまうのです。
その一方で、新しいことにチャレンジする若い人たちが増えています。ベンチャー企業を立ち上げて30代で役員になって高収入を得たり、専業ブロガーやYouTuberとしてコンテンツを作って稼いだり、副業やダブルワークも当たり前になり、会社員にとらわれない働き方をする人はどんどん増えています。
彼らに共通するのは、“リスクをとることで大きなリターン(成果)を得ている”ということです。変化することを恐れずにお金や時間を自分や会社に投じて、さらに大きな収入や多くの自分の時間を得ています。日本経済全体が停滞する中で、一部の人たちは確実に「成長」をし続けています。
この「リスクをとる」という考え方は、まさに「投資」の考え方です。投資の世界におけるリスクとは、「得られるリターンの不確実性の度合い(振れ幅)」のことを指します。リスクをとらないとリターンが得られない。すなわち、大きなリターンを得たいのであれば、不確実性(リスク)を受け入れなくてはいけません。
■「日本人はリスクをとれない」という思い込み
多くの日本人は、変化や変動を嫌います。できるだけリスクをとることを避けて、現状維持を好みます。だから、何かに挑戦することができずにいるのです。
「日本人とリスク」の問題を考えるとき、私はよく日本史にヒントがあるという話をします。誰もが学校で学んだことですが、奈良・平安時代に日本は遣唐使を中国に派遣しました。当時の船は20メートル程度の大きさで、航海の技術は未熟なものだったそうです。なんと、中国へ渡る船の約半分は沈没してしまいました。50%の確率でしか中国に渡れなかったのです。
それでも、1隻の船には100人ほどの遣唐使が乗りました。彼らは、当時の高官や留学生で、いわば「超エリート」の人たちです。遣唐使のときは4隻の船を出しました。なぜなら、行きの船で2隻が沈み、帰りの船では1隻が沈む計算になるからです。
300人ものエリートや財産を海の底に沈めてでも、中国の政治体制や文字、文化、宗教を取り入れようとしたのです。かつての日本人はこうした「リスクテイク」をして、貪欲に外の世界から学びました。日本人は決してリスクをとれない民族ではありません。
新しい価値を生み出すには、リスクが必ず伴います。私自身もリスクを常に考え、リスクをとる人たちを応援し、彼らの成長を近くで見てきました。そして、たどり着いた1つの結論があります。
これからの時代を生き抜くには、「投資の思考」が必要不可欠だということです。
■投資家ほど「成長」を近くで見続ける人はいない
みなさんは、私の職業である「ファンドマネジャー」の仕事はご存じでしょうか。ファンドマネジャーとは、投資家からお金を預かり、そのお金を使って投資をする担当者のことです。主に投資先の選定や、売買タイミングの決定をおこない、預かったお金を運用しています。私自身が専門としている投資先は、日本の企業、特に「成長」が見込める中小企業です。
この仕事を夢中で続けてきて、かれこれ約30年になります。中堅企業や急成長するベンチャー企業の経営者たちと毎日のように会い、ダイレクトに自分の仕事への情熱を語ってもらったり、地方にある世界の産業を支える部品をつくっている企業に出会ったり、工場見学で誇りを持って働く従業員たちに感動したり……。そうして働くうちに気づいたことがあります。
それは、私たちが手がけている企業への投資とは、株価への投資ではなく、「人への投資」だということです。
投資先を決めるときには、長期的に成長するか、利益を上げていける会社かということを見極めていくわけですが、そこで要になるのは、「人」です。働く人を率いる経営者の考えは何より重要ですし、機械を動かすのも技術を磨くのも、すべては人です。実際に、経営者や社員がいきいき働いている企業に投資したほうが、そうでない企業に投資するよりも成果が上がります。これは、過去に延べ7000人以上の経営者にインタビューをおこなってきた経験上、明らかにいえることです。
■「成長のにおい」を嗅ぎ分けろ
投資家というと、どんなイメージがありますか。
「パソコンの前で、数字のデータとグラフを分析している」「ギャンブルのように株式やFXを売買する」――。そのような「デイトレーダー」の印象が強いかもしれませんし、マンションなどの不動産投資をする人を想像するかもしれません。
しかし、実際は先ほど語ったように、人間的で泥臭いものなのです。
特に、私のように主な投資先が中小企業の場合、地方まで足を運び、実際にその土地を歩き回り、人に会い、直接お話をして、成長するかどうかを見極めています。よく例に出すのは、富山県にある東証二部上場の朝日印刷という会社です。全国的にはあまり知られていないかもしれませんが、医薬品や化粧品の箱の印刷をしている会社で、この分野ではトップとなる約4割のシェアを誇っています。
なぜ大手を差し置いてシェアを獲得できているのでしょう。医薬品には、いわゆる薬事法という法律があり、パッケージの印刷をするのにも面倒な手続きが多くなります。そのため、大手印刷会社はわざわざ力を入れない分野なのです。そこに朝日印刷は勝機を見出し、リスクをとって設備投資をしています。現在も2020年春に大規模な工場が完成予定です。
投資家的な見方をすると、成長のにおいを嗅ぎ分けられるようになるのです。「印刷=斜陽産業」という先入観にとらわれると、こうした成長に目がいきません。常識や固定観念から逃れるためにも、投資家的なものの見方は必要なのです。
■リスクとの向き合い方が「二極化」を生む
私は今、日本人は2つのグループに分けられると思っています。
・希望を最大化する人たち
まず、圧倒的に多数派なのが、「失望を最小化する人たち」です。彼らは、「将来には、どうせ失望が待っている……」という考え方をし、なるべく失望を少なくとどめようと、行動原理もリスクを最小化する傾向があります。
「今いる会社は好きではないけれど、転職したらもっとブラックなところにいくかもしれないから、我慢して会社にしがみつく」
「友人が多いと傷つくことがあるかもしれないから増やさないし、フェイスブックやツイッターなどのSNSもしないでおく」
そんなマインドを持った人たちです。お金についても、「貯めておけば何とかなるかもしれない」と、不安に取り憑(つ)かれて節約ばかりするのです。
一方で、少数派なのが、「希望を最大化する人たち」です。彼らは、「将来は明るいし、挑戦したほうが喜びは大きくなる」と前向きに考えられるグループです。自分を成長させるため、そして社会に貢献するために、「自分にできることは、積極的に取り組もう」と考えます。変化を望み、自ら進んで動き、希望を最大化するべく行動します。このグループの人は、「何もしないこともリスクだ」ということがわかっているので、消費や投資行動にも前向きです。
私が投資家として投資先に選ぶ企業の経営者や従業員のほとんどは、「希望を最大化する」側の人たちです。さて、あなた自身はどちら側のタイプでしょうか。
ここで別のテストをしてみましょう。次の質問について考えてみてください。
いかがでしょう。おそらく、この条件では、「しない」と答えた人も多いのではないでしょうか。でも安心してください。実際にこの条件でゲームにチャレンジする人は、かなり少数です。なぜならば、人間は本能的に「損失を回避したい」という気持ちのほうが「何かを得られる」という気持ちよりも大きくなるからです。これは、行動経済学でノーベル経済学賞を受賞したダニエル・カーネマンらの「プロスペクト理論」としても実証されています。
けれど、合理的に考えると、期待値はプラスになるので、チャレンジしたほうがトクです。ちなみに、外国と比べて、日本人のほうがチャレンジしない割合が大きいそうです。国民的に「損失を回避したい」という傾向が強く表れるのです。
私は投資家として、日本に損したくない気持ちが必要以上に蔓延(まんえん)しすぎていることに対して、少し残念な気持ちがあります。だから、この本を手にとったみなさんには、ぜひチャレンジする戦略を選択していってほしいのです。損するリスクを冷静に直視した上で、貯め込んだお金や、自由な自分の時間を、少しでも未来のために投じるのです。
これからの日本では、「希望を最大化する人たち」と「失望を最小化する人たち」、つまり「動く人」と「動かない人」の格差が、さらに広がっていきます。ところが、前者の考え方を持つ人たちに対して、「イタい人」だとか「意識高い系」と揶揄(やゆ)する人も多いのが今の日本です。
「失望を最小化する人たち」は、嫉妬の感情が大きいため、自分の水準まで他人を引きずり下ろそうとしてくるでしょう。嫉妬などの負のエネルギーは連鎖していくので、「チャレンジするのが怖い」「恥ずかしい」などと、社会全体の不活性化につながっていってしまうのです。
■何もしないことのリスクも考えよう
「希望を最大化する人になりましょう」。そうはいっても、安易に起業や株式投資をすすめたいわけではありません。
「リスクをとる」ということは、目を閉じてやみくもに飛び込むことではありません。目を見開いて直視し、ちゃんと考えて決断をしてチャレンジすることです。
これからの時代、一生サラリーマンのままで過ごすこともハイリスクな決断です。近年、会社や事業の寿命は短くなっています。会社に運命を預けっぱなしにすると、会社が潰れた途端に人生が詰んでしまいます。なぜなら、同じ会社で働き続け、「その会社でしか通用しないスキル」しか身につけていないからです。そのスキルだけのままで年をとると、他の会社に再雇用される可能性は限りなく低くなります。再就職できたとしても、少なくとも前の会社と同じ給料は稼げないでしょう。
■自分自身の人生への投資家になろう
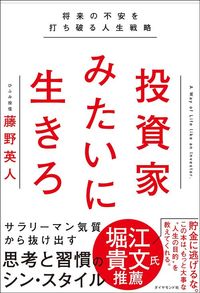
「動くリスク」がある一方、「何もしないリスク」が見えるかどうか。先ほどの質問では、「サラリーマンとして働きながら、いつでも動けるように準備しておく」という中間に答えがあります。リスクがゼロになるのを待つのではなく、リスクを下げる努力をしつつ、よきタイミングで挑戦をする。そういう賢い投資家的マインドを、『投資家みたいに生きろ』という本を通じて手にしていただきたいのです。
投資家のように考えることができれば、リスクをコントロールして日々の行動を決めることができますし、自分の市場価値を念頭に置いて生きることができます。
負のエネルギーに絡めとられずに、いきいきと働き、人生を楽しく生きていくには、自分の人生に「投資」の考え方を取り入れることです。あなた自身が、自分の人生の投資家になる方法をお伝えしていくのが、『投資家みたいに生きろ』という本の狙いなのです。
----------
レオス・キャピタルワークス社長
1966年、富山県生まれ。90年早稲田大学法学部を卒業後、野村投資顧問(現野村アセットマネジメント)に入社。ジャーディンフレミング投資顧問(現JPモルガン・アセット・マネジメント)、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントを経て、03年レオス・キャピタルワークスを創業。以来、CIO(最高投資責任者)を務めている。中小型株の運用に長け、東証アカデミーフェロー、明治大学非常勤講師なども兼務する。
----------
(レオス・キャピタルワークス社長 藤野 英人)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
レオスが協賛 中高生向けアプリ開発コンテスト「第14回アプリ甲子園」次世代を担う若手クリエイターの発掘と育成
PR TIMES / 2024年6月25日 18時15分
-
次世代の起業家を支援!「NIKKEI THE PITCH SOCIALBUSINESS SCHOOL」に協賛
PR TIMES / 2024年6月20日 13時40分
-
リスクは限りなくゼロで、リターンは無限に近い…お金の専門家が「もっとも手堅い」と太鼓判を押す投資先
プレジデントオンライン / 2024年6月15日 10時15分
-
中高生による小学生のための金融教育動画制作「FESコンテスト」に金融機関としてレオスが初協賛
PR TIMES / 2024年6月10日 21時40分
-
日本を担う若者のリアル起業体験を応援「リアビズ 高校生模擬起業グランプリ」第5回 応募受付開始!
PR TIMES / 2024年6月3日 12時15分
ランキング
-
1ソニー宮城拠点、250人削減=ブルーレイ、生産縮小
時事通信 / 2024年6月29日 15時49分
-
2「クレカタッチ」は交通系ICカードを駆逐するのか 熊本で「全国相互利用」離脱、一方で逆の動きも
東洋経済オンライン / 2024年6月29日 7時30分
-
3「押しボタン式信号」なぜ“押してすぐ青”にならないケースが? 納得の理由があった!
乗りものニュース / 2024年6月29日 16時42分
-
4作文は「理系だと苦手」「文系が得意」という大誤解 算数が得意な子は大概「作文もうまい」納得理由
東洋経済オンライン / 2024年6月29日 10時0分
-
5池袋西武とヨドバシ「売り場折半」の波紋と懐事情 北側にヨドバシ出店、西武の集客力に影響は?
東洋経済オンライン / 2024年6月29日 10時30分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください












