「社会のバックボーンになる」量子技術とは何か
プレジデントオンライン / 2019年12月27日 9時15分
■そもそも「量子」って何ですか?
【田原】僕は中学・高校で原子や電子を習ったけど、量子は習わなかった。だから基礎から聞きたい。いったい何ですか、量子って?
【山城】量子は物理の分野のすごく小さいミクロの単位です。田原さんが習った原子や、それよりもう少し小さい電子などを総称して、量子と呼んでいます。
【田原】総称ですか。どうして総称が必要なの?
【山城】僕たちが普段生活しているときに感じている物理学は、ニュートン以来の古典力学。一方、すごく小さくて冷たい世界では、僕らが普段感じている物理現象とは違う現象が起きています。そのことを説明するのに、量子が必要でした。
【田原】違う物理現象って?
■1番有名なのは、量子重ね合わせ状態
【山城】1番有名なのは、量子重ね合わせ状態ですね。「シュレーディンガーの猫」という話があります。僕らの世界では、猫って生きているか死んでいるのかのどちらか。だけど、すごく冷たい量子の世界だと、猫は生きてもいるし死んでもいます。

【田原】どういうこと? 全然わからない。
【山城】僕たちは猫は生きてるか死んでいるかのどちらかで、必ず確定していると思っています。しかし、本当はそうではなくて、観測されるまでは生きてもいるし死んでもいるという状態が許されています。
【田原】たとえば山城さんはいま生きてるでしょ。本当は山城さん、死んでいるともいえるってこと?
【山城】いや、田原さんはいま僕のことを見ていますよね。見ているのでダメです。重ね合わせ状態は、観測していない場合なので。
【田原】見えてない猫の生死がわからないなんて、あたりまえじゃない?
【山城】そういう意味ではないんです。もともと生きてもいるし死んでもいるという状態が許されていて、観測されると、どちらかになると。
【田原】さっぱりわからない。なんで許されているの?
【山城】自然がそうなっているとしかいいようがないです。えーと、量子コンピュータで説明すると……。
【田原】待った。量子がわからないのに量子コンピュータなんてわかるわけない! 量子、もう1度説明してください。そもそも量子が登場したのはいつなんですか?
【山城】産業革命のころです。当時は鉄を溶かして機械をつくっていました。鉄を熱してうまく変形させるには、鉄の温度を測る必要があります。ただ、当時は高温を測る温度計がなく、職人が鉄の色を見て温度を推定していました。いわば勘と経験の世界です。当てずっぽうではなく正確に温度を知りたければ、鉄の色と温度を結びつける理論、数式が必要。当時の物理学ではその数式をつくれなかった。ところが、マックス・プランクという物理学者がプランク定数という概念を取り入れたところ、色と温度に対応する数式ができました。その理論を説明するために導入されたのが、量子力学の考え方でした。
【田原】重ね合わせがよくわからないんだよね。どういうことだろう。
【山城】猫ではなく、電気回路で説明してみましょうか。丸い電気回路をつくって電気を流せば、僕たちは電気が右に流れているか左に流れているかを計測することができます。ただ、小さくて絶対零度に近い温度の回路をつくって電気を流すと、右にも流れているし左にも流れているという現象をつくることができる。
【田原】なんで小さいと相反することが同時に起きるんですか?
【山城】実は量子は、右に回っている可能性が何%、左に回っている可能性が何%というように確率的な振る舞いをしています。大きくなると、この確率がどちらかに偏る。逆にいうと、小さいときは偏りが小さく同時に存在できるんです。
■量子コンピュータは量子力学の現象を使った計算機。
【田原】おかしいよ! クルマだって、右に曲がりながら同時に左に曲がるなんてできない。
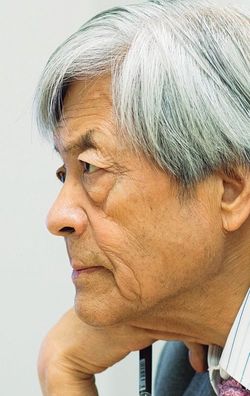
【山城】クルマもごくわずかな確率で左右同時に曲がる現象が起きていいんです。ただ、クルマは大きいのでその確率がものすごく小さい。
【田原】そんなのありえない! 同時に曲がるなんて、ごまかしだ!
【山城】きちんと数式でも説明されていますし、実験も、それを支持しています。
【田原】実験で証明されている?
【山城】というか、まず実験で、それまでの物理学では説明できない現象がたくさん確認されました。現実に起きたことを説明するには新しい理論が必要で、それが量子だったと。
【田原】たとえば?
【山城】そうですね……。田原さん、中学のときに「電子は原子核の周りを回る」と習わなかったでしょうか。実はあれ、古典力学では説明できません。電子は回ると光を放ちます。光ればエネルギーを失うので、古典力学に基づけば原子核に吸い込まれることになります。でも、実際には電子は原子核の周りを回り続けている。つまり古典力学は間違っていたわけです。では、なぜ回り続けるのか。物理学者らは「電子が波だから」と説明しました。僕が電子で波だとしたら、ここにもいるし、同時に少し横にも存在確率がある。そういう重ね合わせ状態を仮定すると、現実の現象を説明できたのです。
【田原】波ってどういうことですか。動いてるってこと?
【山城】そうです、僕も波で動いているし、田原さんもそう。ただ、観測できないくらい小さな幅でしか揺れていないので、見てもわかりません。なぜ大きいサイズだと波の性質が見えなくなるのかというのは、環境との相互作用が主な理由ですが、イメージするとしたら、大きくても小さくても波の幅は同じで、小さいと相対的に揺れが大きくなるんです。
【田原】つまりニュートンなんかの力学は波を認めないで、量子力学は波を認めるわけね。まだ信じがたいですが、少しイメージできたところで本題に入ります。山城さんが研究する量子コンピュータって、何ですか。スーパーコンピュータと何が違う?
【山城】量子コンピュータは量子力学の現象を使った計算機。スーパーコンピュータの上位互換だと勘違いされますが、そもそも仕組みが違います。普通のコンピュータが0と1の足し算しかできないとしましょう。それに対して、量子コンピュータは0と1の重ね合わせによる足し算が許されます。具体的にいうと、普通のコンピュータが0と1を足すのに対して、0と0、0と1、1と0、1と1を同時に計算できる。パターンは2のn乗で、nは量子ビット(量子コンピュータを構成する最小単位)。2量子ビットなら、4パターンを並行的に処理できる。
【田原】なるほど。だから速いのか。
■波と波が打ち消し合ってゼロになる
【山城】普通のコンピュータは、パターンをぜんぶ試して正解を選びます。一方、量子コンピュータは並行的に処理して、波と波が打ち消し合ってゼロになる「干渉」という現象を使って、選びたいものを選びます。
【田原】重ね合わせとか波とか、それをどうやってコンピュータの中でやるんですか?
【山城】すごく冷たくするんです。小さくて冷たい世界だと、量子的揺らぎが大きくなるので。
【田原】いまはどこまで進んだんですか? 資料によると、1998年に東京工業大学の西森秀稔さんが提唱したと。これが最初ですか。
【山城】西森さんはすごく小さい世界を制御できると仮定して、そこで何か計算したら、新しいことが生まれるんじゃないかと考えて、試しに理論をつくりました。それが量子力学を使った計算手法(アルゴリズム)の1つである量子アニーリング。西森さんの論文をもとにカナダのベンチャーであるディーウェーブが計算機をつくったのが2011年でした。
【田原】99年に東京大学の中村泰信さんも世界初の発見をした。これは何をやったの?
【山城】西森さんの話とは別に、量子を使った計算は昔から研究されていて、量子ゲートと呼ばれています。その回路をつくるための最初の1量子ビットを中村さんが世界で初めてつくりました。
【田原】それから?
【山城】大きかったのは、カリフォルニア大学のジョン・マルティネスが開発したデバイスです。ディーウェーブがつくったのはアニーリングという計算に特化した計算機ですが、マルティネスは14年、いろいろなタスクができる超高性能の量子ビットをつくった。おそらくこれが、世界が変わった瞬間ですね。これほど高精度の量子をつくることができるとは、みんな信じていませんでしたから。
【田原】西森さんや中村さんはいち早く量子コンピュータ開発で成果を出した。でも、それ以降、結果を出したのはカナダや米国。どうして日本でできなかったんだろう。
【山城】お金にならないと思って、資金を注ぎ込まなかったんでしょうね。当時、量子コンピュータは途方もないものだと思われていましたから。マルティネスが成功したのは、ある種の狂気があったから。量子コンピュータをつくるときの選択肢はいくつかありますが、ひとつに賭けてほかが成功したら、注ぎ込んだ資金が無駄になります。でもマルティネスは選択肢の中から超伝導に賭けて、執念でつくった。日本の企業は、ギャンブルしてまで挑戦しようとは考えなかった。
【田原】そんな賭けの世界に山城さんも身を置いて起業した。そもそもどうして物理に興味を持ったの?
【山城】僕は沖縄出身です。高校生のころ、琉球大学の前野昌弘先生が出張講義に来てくれて、さっきの波の話をしてくれました。それで物理に興味を持ち始め、大学では「この宇宙は何でできているのか」という素粒子理論の研究をしていました。
【田原】それがなぜ量子コンピュータに?
■タイムマシンをつくって未来を見たかった
【山城】最初はタイムマシンをつくって未来を見たかったんですよね。でも宇宙の研究をしているうちにできないとわかった。未来が見られないなら、自分で未来をつくろうと発想を転換。機械学習や人工知能よりもっと先で、でも自分が生きているうちに実現しそうなテクノロジーがいいと思って、量子コンピュータの研究を始めました。
【田原】それがいつ頃ですか?
【山城】大学4年のときなので、15年頃ですね。
【田原】具体的にはいま何を開発しているのですか?
【山城】ハードウェアではなく、アプリケーションの開発をしています。80年代、日本は国家プロジェクトとして第5世代コンピュータの開発を始めましたが、結局は頓挫した。原因は、つくった後に産業にどう応用するかという部分が足りなかったから。量子コンピュータ業界はそのことを学ばないといけません。僕自身、研究者として全然わからない現象を制御するハードウェア開発にすごく惹かれますが、同時にその技術ができた後に社会にどう役立てるのかを考えないといけない。僕はそちらにフォーカスしようかなと。
【田原】実際、量子コンピュータができると、何ができるようになるんですか?
【山城】いくつか分けて話さないといけません。僕がやっている量子アニーリングは最適化計算が得意です。たとえば、物流の配送計画。どの経路が一番コストが安いのかという問題を解けます。量子コンピュータで有名なのは、ショアのアルゴリズム、つまり暗号破壊です。ただ、暗号破壊はすごく遠い未来。期待できるのは創薬シミュレーションですね。いまスーパーコンピュータでやっている創薬シミュレーションは近似法で、厳密解ではありません。量子コンピュータなら本物の創薬と同じものをシミュレーションできます。
【田原】グーグルが19年10月、量子コンピュータを発表しましたね。あれでシミュレーションできますか?
【山城】まだできないです。
【田原】実現するのはどれくらい先?
【山城】10年くらいじゃないでしょうか。僕は業界の中だと楽観主義者。30年は必要と悲観的な見方をしている研究者もいます。
【田原】10年後、楽しみですね。
【山城】量子技術は社会のバックボーンになっていて、僕たちが気づかないところで恩恵を受けている世界になると思います。そのバックボーンを支えられるように研究を続けていきたいですね。
山城さんへのメッセージ:日本発で世界で勝てるソフトウェアをつくれ!
----------
ジャーナリスト
1934年、滋賀県生まれ。早稲田大学文学部卒業後、岩波映画製作所へ入社。テレビ東京を経て、77年よりフリーのジャーナリストに。著書に『起業家のように考える。』ほか。
----------
----------
Jij 代表取締役
1994年、沖縄県生まれ。沖縄県立具志川高校、琉球大学卒。東京工業大学理学院物理学系西森研究室で研究を行い、2018年11月にJijを創業。量子アニーリングマシン向けソフトウェア開発、コンサルティング事業を行っている。
----------
(ジャーナリスト 田原 総一朗、Jij 代表取締役 山城 悠 構成=村上 敬 撮影=枦木 功)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
【予約開始直後にAmazonランキング第1位!】カルフォルニア大学バークレー校教授野村泰紀氏の最新刊『なぜ重力は存在するのか』を発売!
PR TIMES / 2024年6月28日 17時40分
-
2つの新展示を2025年春に公開
PR TIMES / 2024年6月27日 17時15分
-
物理学の「2024年問題」タイムトラベル論争も時間の問題?その1
Japan In-depth / 2024年6月24日 15時25分
-
「原始ブラックホール」は生成されない? Kavli IPMUが矛盾点を発見
マイナビニュース / 2024年6月3日 13時3分
-
なぜ現在の宇宙は単純な姿で観測されるのか?、東大などが理由の一端を解明
マイナビニュース / 2024年5月31日 15時52分
ランキング
-
1「クレカタッチ」は交通系ICカードを駆逐するのか 熊本で「全国相互利用」離脱、一方で逆の動きも
東洋経済オンライン / 2024年6月29日 7時30分
-
2バナナは「太くてまっすぐ」が大当たり…フルーツ研究家が教える「バナナの正しい保存方法」
プレジデントオンライン / 2024年6月28日 9時15分
-
3「東京チカラめし」が東京で再始動 今度はどう売っていくのか
ITmedia ビジネスオンライン / 2024年6月28日 6時5分
-
4LINE、分離26年3月に完了 情報流出、システムの計画前倒し
共同通信 / 2024年6月28日 17時29分
-
5【速報】「いまになって何を言い始めているんだ」「小林製薬だけに任せておくわけにはいかない」と厚労相が怒りをあらわに “紅麹サプリ”問題で「摂取後に死亡疑い」76事例が調査中と小林製薬が明らかに 27日まで報告せず
ABCニュース / 2024年6月28日 16時14分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください












