人材会社の「転職で収入増」を疑わない人の末路
プレジデントオンライン / 2019年12月20日 11時15分
※本稿は、郡山史郎『転職の「やってはいけない」』(青春新書)の一部を再編集したものです。
■「転職回数は1回まで」の企業もある
求人サイトや人材紹介会社などのCMでは、転職でステップアップしようとあおっているが、転職の経験が多いことは明らかに採用選考においてマイナスポイントになる。転職回数は今や転職活動において、年齢の次に大事なファクターだ。
転職回数は少ないに越したことはない。では、何回までならOKなのだろうか。これまでさまざまな企業からの求人案件を見てきたところ、「転職回数は2回まで」を条件にしている企業が多い。なかには「1回まで」という厳しい条件を挙げる企業もある。
会社の売上げに直接貢献する営業職やエンジニアは、成績がよければより高い待遇を求めて転職回数を重ねてしまうことが考えられるので、まだ許される。しかし、経理や財務や人事などバックオフィスの仕事で転職回数が多い人は、徹底的に嫌われる。こうした職種においては、実績はあるが転職経験の多いAさんと、実績は劣るが転職回数ゼロのBさんがいたとしたら、Bさんが選ばれる可能性が高い。
つまり、転職はすればするほど不利な条件になり、3回以上経験していると転職が非常に困難になる。
■転職回数が多いと人格的に問題ありと思われる
では、なぜ転職回数が多い人は企業から敬遠されてしまうのだろうか。その理由はいくつか考えられるが、まずは「辞めグセがあるのではないか」と思われてしまうことがある。
例えば、30歳で転職経験3回だとすると、今勤務している会社で4社目ということになる。つまり、大学を卒業してから今まで3年も経たずに辞めている会社があるということだ。そのため採用担当者は「うちに入社してもすぐに辞めてしまうんじゃないか」と危惧してしまう。
また、人格的に問題があると思われるという理由もある。どの会社も長続きしないということは、「この人にはどこか欠点があるんじゃないか」「会社員として、チームの一員として欠陥があるんじゃないか」と見なされてしまう。これは辞めた理由が自己都合であれ会社都合であれ、関係なくそう判断される。
採用担当者は「安全第一主義」。採用にはコストがかかるので、採用した社員に短期のうちに辞められてしまうのは生産性が低い。「離職するリスクが高い候補者は、最初から排除しておこう」というのが採用担当者の本音なのだ。私個人としては、社員が離職しないようにするには、「辞めない人を採用する」のではなくて、「人が辞めない会社にする」「会社をよくする」以外に方法はないと思っている。
■本当は会社が離職原因のケースが多いが…
多くの転職希望者と面談した経験からいえるのは、社員が離職するのは会社が悪いケースが少なくとも6割。本当にいい会社なら、社員は辞める必要がないはずである。会社をよくするには、基本的なことだがセクシャルハラスメントやパワーハラスメントを許さないなど、社員が気持ちよく働けるよう、まずは幹部社員教育を徹底することだ。
しかし、企業はこうした本質には気づかずに「辞めない社員を採用する」という方針を貫いており、この現実を変えることは難しい。退職に至る事情はさまざまだと思うが、これまで2回転職してきた人は次が最後だと考えたほうがよい。3回以上転職してきた人はエントリーしても弾かれる可能性が高いと心得て、転職活動に臨むべきだろう。
■転職回数を問わない企業もあるにはある
転職を重ねる人を敬遠する会社が多い一方で、転職回数を問わない企業もある。そのような企業はだいたい3つのタイプに分かれる。
1つは年功序列型ではない、完全成果主義の会社である。こういう会社は、採用の際には特に転職経験は問わないことが多い。ベンチャーもその傾向が強い。その半面、転職回数以外の条件が非常に厳しい。
例えば、TOEICが900点以上でないとどんな職種であっても書類審査にも通らない。筆記試験も難易度が高いものが出題されるのはもちろん、企業によってはすぐに答えの出せない難問を出題する「ケース面接」がおこなわれたりする。
「ケース面接」とは、これは妥当と思われる仮説を立てて論理的に質問の回答を導き出すというもの。応募者の考察力や問題解決能力、固定観念にとわれない自由な発想などが試される。もちろん、入社したらしたで生存競争も激しい。成果を出さなければ昇給や昇進を望むべくもなく、年下の上司の下で働かないといけない場合もある。
■営業は「使い捨て」として採用されるケースも
2つ目は営業など離職率の高い職種の人材を大量に必要としている企業である。それまでの転職回数は問われない代わりに、営業経験や前職での実績が重視される。
給与は成果や能力に関係なく支払われる固定給制ではなく、完全に出来高で支払われるフルコミッション制や、売上げ成績に応じて支払われる報酬が変わるインセンティブ制であることが多い。そのため成果が上がらない人は結果的に安い報酬で働くことになり、それが離職率の高さを招いている。いい方は悪いが「使い捨て」として採用される可能性もあるので、注意が必要だ。
3つ目は外資系である。私の会社でも外資系企業の求人案件を扱っているが、転職回数をとやかくいってくるところはほとんどない。3回以上転職してしまった人も外資系企業だったら受け入れてくれるかもしれないが、当然のことながら高い語学力が求められる。
こちらも入社したら厳しい競争社会が待っている。外資系は欠員が出た際に人材を募集するので、そのポジションの役割や与えられるミッションが明確なのが特徴だ。チームではなく個人として、会社とコミットした目標をクリアできたかどうかですべてが評価される。クリアできなければ当然、リストラの対象となる。
以上のように転職回数不問という会社もあるにはある。しかし、そこはいずれも生き残りが大変な世界であることは間違いない。
■企業が転職回数の条件を厳しくした背景
企業が転職回数や年齢の条件を設定することは以前からあったのかもしれないが、このように厳格化、表面化してきたのはここ10年くらいだろうか。年齢制限を求人票に載せることは雇用対策法により禁じられているが、転職回数に関しては「2回まで」「1回まで」とハッキリ書いてある求人票を見かけることがある。
転職回数や年齢の条件が厳しくなってきた背景には、昨今の転職ブームの影響が考えられる。実際、ここ数年で転職者数および転職者比率は上昇し続けている。転職者比率とは一定の期間内での労働者全体に占める転職者の割合のことで、転職者数を総労働者数で割って100をかけた計算式で求められる。
総務省統計局の「労働力調査」によると、リーマン・ショックと東北大震災のダブルショックで日本経済が大きく落ち込んだ2011年では転職者の数は284万人、転職者比率は4.5%である。2018年では転職者数が329万人、転職者比率は4.9%。実に20人に1人が転職する時代になっている。
厚生労働省による2015年の「転職者実態調査」では転職回数の平均は2.8回。もっともこれはその年に転職を経験した人に聞いた転職回数で、一度も転職したことがない人、それ以前に転職を経験した人の回答は含まれていないので、全体の平均ではない。が、その年に転職した人のなかですでに3回近く転職を経験しているというのは、やはり人材の流動性が高くなっているといえるだろう。
■人材の流動化で逆説的な現象が起こっている
人材紹介業界が転職することをあおり、これだけ人材が流動的になると、逆説的ではあるが、今度は企業側が「辞めない人材」「転職ブームに浮かれないような堅実な人材」が欲しくなってくるのではないだろうか。
また、中途採用が多くなると、転職回数が多い人を雇用した際にマッチングがうまくいかなかったケースも、当然ながら増えてくる。そういうことが1度でもあると「やっぱり転職回数が多いヤツはダメだな。今後はやめよう」という偏見ができてしまう。たとえ転職経験が多い人が何人もその会社で実績を上げていたとしても、失敗例や悪い例のほうが印象に強く残ってしまうものである。
書類選考がコンピュータによっておこなわれるようになったことも、転職回数や年齢の条件が厳しくなっている背景にあるだろう。今は転職ブームゆえ、人気企業・有名企業は転職希望者が殺到してしまう。そのため書類選考の際になんらかの条件でフィルターにかけなくてはならない。その条件のなかに転職回数と年齢が入ってくるというわけだ。
■転職ブームが起こると転職しにくくなる
私が聞いたところでは、ある企業が有名人材紹介会社に、あるポストの求人を頼んだところ、そこの若手社員が100人以上の候補者の履歴書を送ってきたという話がある。そもそも企業が採用を人材紹介会社にアウトソーシングするのは、自分たちが採用にかける手間や時間を省力化したいためなのに、これでは自社で新聞広告を出して募集するのと変わらない。
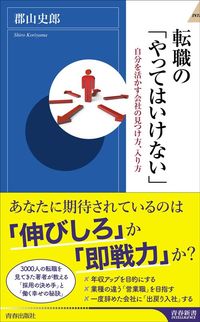
大量の履歴書を受け取った採用担当者は、選考が大変なので、「学歴はGMARCH(学習院大学、明治大学、青山学院大学、立教大学、中央大学、法政大学)以上」とか「国立じゃないとダメ」などの条件でふるいにかける。人材紹介会社ではコンピュータが大学や学部をグレード分けし、ボタン1つで一定以上のグレードの大学を卒業した者だけが選別される仕組みになってしまう。
それでも候補者が絞れないと、そのうちに「2回以上転職した人は不可」といった条件で足切りをするのだ。
以上のように、人材紹介業界は「転職しよう」とあおるが、その結果、ますます採用条件が厳しくなり、転職しにくくなっているという皮肉な現象が起きている。
----------
CEAFOM社長
1935年生まれ。一橋大学経済学部卒業後、伊藤忠商事を経て、1959年ソニー入社。73年米国のシンガー社に転職後、81年ソニーに再入社、85年取締役、90年常務、95年ソニーPCL社長、2000年同社会長、02年ソニー顧問を歴任。04年、プロ経営幹部の紹介をおこなう株式会社CEAFOMを設立し、社長に就任。著書に『定年前後の「やってはいけない」』『定年前後「これだけ」やればいい』(ともに青春新書)。
----------
(CEAFOM社長 郡山 史郎)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
こんな人を絶対入社させてはいけない…採用面接で「モンスター社員」を見極めるキラー質問
プレジデントオンライン / 2024年6月21日 8時15分
-
「ストレス耐性はありますか?」と聞いてはいけない…転職面接で応募者の打たれ強さを見抜くワザあり質問
プレジデントオンライン / 2024年6月20日 8時15分
-
4月入社の新卒社員が、1ヶ月で「退職代行」を利用して退職しました。私は「最低3年は働くべき」という考えなのですが、今の時代もう古いのでしょうか…?
ファイナンシャルフィールド / 2024年6月19日 3時0分
-
年収750万円・42歳のサラリーマン「先輩、またお世話になります!」と戻ってきた〈出戻り社員〉に憤りのワケ
THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年6月18日 5時15分
-
労働⼈⼝激減の時代だからこそ究極の属⼈化 第1回 なぜ、「究極の属人化」が必要だと考えるのか
マイナビニュース / 2024年6月13日 7時0分
ランキング
-
1関東「気動車王国」の離れ小島路線が面白い! 不思議な“右ハンドル”車両 3駅の路線に“スゴイ密度”であるものとは?
乗りものニュース / 2024年6月29日 15時12分
-
2意外な面倒さも? 財布いらずの「スマート支払い」、店側はどう思っているのか
ITmedia ビジネスオンライン / 2024年6月30日 8時10分
-
3ウイスキーが「おじさんのお酒」から激変したワケ 市場復活に導いたサントリーのハイボール秘話
東洋経済オンライン / 2024年6月30日 8時20分
-
4「押しボタン式信号」なぜ“押してすぐ青”にならないケースが? 納得の理由があった!
乗りものニュース / 2024年6月29日 16時42分
-
5障害者雇用未達で「社名公表」寸前からの挽回劇 法定雇用率クリアへの3年で見えた成果と課題
東洋経済オンライン / 2024年6月30日 9時0分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください












