私が、「人を育てる必要はない」と考える理由
プレジデントオンライン / 2019年12月20日 11時15分
■これからは経営の道を歩むかもしれない
岡山県倉敷市にある水島製鉄所(現JFEスチール西日本製鉄所)の企画部長になったのは1992年4月のことで、私は51歳でした。
企画部長というのは部長の中でも経営にいちばん近い要のポジションです。私は入社以来ずっと技術畑を歩んできたわけですが、その職に就いたことで、技術畑から離れ、これから、もしかしたら経営の道を歩むことになるかもしれない、という意識が少し芽生えたのです。
当時の川崎製鉄の定年は60歳でした。しかし、私は定年後も65歳や70歳まで働くつもりでいました。
日本の製鉄技術は世界最先端ですから、発展途上国に行けば、鉄関係のエンジニアは年齢に関係なく、雇ってくれる場合が多い。とはいっても、少しでも意に沿った仕事に就くためには、私の能力を証明してくれる客観的材料が必要です。
そのために、若手のときからずっと技術論文を書き、特許も取得してきていました。当時、国内、海外含めて論文は25編ほど、特許は3、4名のチームで書いたものが100件を超えていました。
技術畑の人間として日々の仕事に向き合いつつも、60歳で定年を迎えたあと、海外でエンジニアとして雇ってもらえるための準備もしていたのです。
■人の上に立つための勉強とは
しかし、論文や特許はエンジニアとしては大きな財産ですが、経営者になるとしたら、大して役立ちません。人の上に立つためには、別の勉強が必要です。そこで、これまで学んだこともない新しい五つの分野の勉強をすることにしました。具体的には、人事、営業、財務、会計ならびに原価計算、システムです。
私にとって一番の勉強法は本を読むことです。さっそく大きな本屋に出かけ、200ページ足らずの概説書を各分野で3冊、合計15冊、購入しました。
このようなとき、心がけていることが、ふたつあります。
ひとつめは、難しい本ではなく、手軽に読める本を選ぶことです。勉強するぞと張り切って、何とか原論といった分厚い本を買ってきても、往々にして途中で挫折してしまうものです。そうではなく、意外と思われるかもしれませんが、最初は全体を簡単に解説した概説書を選ぶようにします。

ふたつめは、一冊の本を最低でも三度読むということです。最初は流して目を通し、二度目はよく噛(か)み締めながら読む。三度目になるとさすがに内容が頭に刻み込まれてきます。200ページ足らずの本なら、2カ月で一分野、つまり3冊を三回読むことができます。
実際、10カ月ほどで、全五分野すべてを読み終えることができました。もちろん、ごく基本的な範囲の内容です。
私にとって、このときの勉強は、のちに経営者となってからだけではなく、国内外のさまざまな分野のビジネスパーソンと仕事の話をするときにも、大いに役に立ちました。
■中国の春秋戦国時代における思考
同時に、私はいまより、ひとつかふたつ高いポジションに就いたとき、どのようにするかを常に考え、行動することを心がけるようにしました。
その際、もうひとつ気にかけたのは、横のポジションです。すなわち、水島製鉄所の企画部長だったときであれば、同じ川崎製鉄でも千葉製鉄所の企画部長なら何を考えどういう手を打つだろうか、新日鉄大分製鉄所の企画部長だったらどうだろうか、と。
では、私がトップ・オブ・トップ、すなわち、川崎製鉄の社長になったときはどうしたか。そのときには、今度は社外に思考を移すことを意識しました。同じ業界でも新日鐵の社長は何を考えているのだろうか、世界最大の鉄鋼メーカーであるアルセロール・ミッタルの代表はどう考えているだろうか。日本の通産省は何を思っているだろうか。そんなことばかり、日々考えていました。
しかし、思えば中国の春秋戦国時代にも、同じような「戦い」や「思考」が行われていたのではないでしょうか。周の王室が次第に衰えてその権威が失墜し、十を超す諸国が領土の併呑、拡張を目指して互いに侵攻し合い、弱肉強食の様相を呈した時代で、まさに現在の企業社会そのものです。
中国の古典を読みあさっていましたから、私も常に「心は春秋戦国時代」です。そして幸いなことに、当時の春秋戦国時代といまの企業社会でいちばん違うのは、戦いとはいっても、命までは狙われないことです。
現在に生きるリーダーで、こうした状況をおもしろく感じない人がいるのでしょうか。いや、いないはずはないと思います。
■ピックアップに優る人材育成なし
「頭の中でのチームビルディング」もまた、常に心がけてきたことのひとつです。ようは、私が役員や社長になった場合、誰を直下のスタッフに抜擢(ばってき)するかを考えておくのです。
特に重要なのは自分の専門外の分野に秀でており、人の上に立つ能力のある人物です。具体的には先の五分野を念頭におき、人事、営業、財務、会計、システム、技術、研究等に長けた人間です。そのためには、社内によく目配りし、社内をあちこち歩き回り、どこにできる奴がいるか、鵜(う)の目鷹の目で探しておきました。
ある日突然、役員に指名されてあたふたするなど、みっともないことでしかありません。100分の1、10分の1の低い確率であっても、自分が上に行く可能性があったら、ともに仕事をしたい、すなわちピックアップの候補を決め、頭の中でチームビルディングをやっておく。
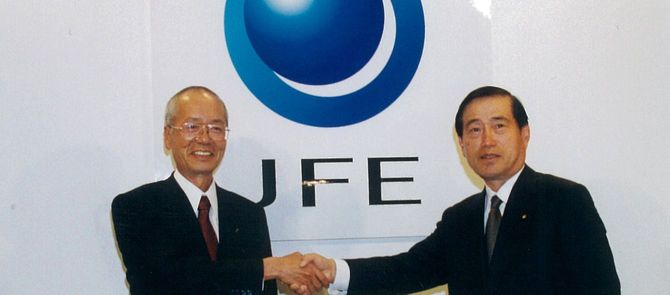
それから、もうひとつ。「想定外」という言葉を簡単に口にする人がいますが、上に立つ人ほど、想定外というのは口にしないほうがいい。想定外に陥ってしまったら、それは自分の能力が足りなかったせいです。
そして、ここからが肝心なのですが、じつはこのピックアップこそが人を育てるのです。考えてみてください。曹操がいつ人材を育てたでしょうか。織田信長が、豊臣秀吉がいつ、部下を育成したでしょうか。
曹操や信長がやったのは、適時適切な人材のピックアップです。むしろ、ピックアップ以外はやっていないといっていい。これぞという人間を抜擢し、仕事を任せる。それが、人間の能力を発揮させる最良の方法です。
そればかりではありません。抜擢を目の当たりにした周囲の人間は、自分も抜擢されたいと思い、そのための力をつけようとします。それぞれが切磋琢磨(せっさたくま)することで、能力ある強い人材が勝手に育つのです。
ピックアップに敵う人材育成なし。そういったこともまた、中国古典は教えてくれます。
■「うちの有利子負債はいくらだ?」
では、ピックアップのための人材は、どのように見つけるのか?
私の体験で、このようなことがありました。のちに電力会社の会長を務めたときのことです。財務担当者を呼び、「うちの現在の有利子負債はいくらだ?」と尋ねたところ、「約8兆円です」と。
私は言いました。「約8兆円とは何だ。何億何千万円の単位まで言ってもらいたい」。
当時の担当者は優秀なのですが、言えなかった。私はこう続けました。「それを削ろうと四苦八苦しているのが君の仕事じゃないか。正確な数字を記憶しておかずに、どうしてそれができるのだ」。
さらに「その金利はいくらなんだ」と畳みかけると、「約○.○%です」と、小数点以下一桁までの概数しか言わない。
私はその数字を、小数点以下三桁まで正確に記憶していました。
「下三桁までちゃんと覚えておくんだ。その数字を何とか下げてもらおうと、君の部下が銀行や融資先に頭を下げているのだろう。その部下を統括する君が、正確な数字を把握していなかったらどうするんだ」
財務担当者はぐうの音も出ません。「会長、いつの間に、そんなに財務に詳しくなられたんですか」と聞くものですから、こう言ってやりました。
「君はどうしてそんなに詳しくないんだ?」
もし、このとき財務担当者が正確な数字を答えていたら、何が起きたか。逆に、ピックアップの候補者として、目に留まったのではないでしょうか。たとえばの話です。
組織のなかで身を立て、いずれリーダーとなるための知恵を得る。その意味でも、古典や歴史には大きな価値があります。
----------
JFEホールディングス 名誉顧問
1941年富山市生まれ。64年北海道大学工学部卒業後、川崎製鉄入社。常務、副社長を経て、2001年代表取締役社長。最後の川崎製鉄社長として、NKK(日本鋼管)との経営統合によるJFEスチール設立を進め、03年初代代表取締役社長(CEO)就任。05年JFEホールディングス代表取締役社長(CEO)。10年相談役。豪腕の経営者として、11年日本放送協会経営委員会委員長、12年東京電力ホールディングス社外取締役、14年より同会長の要職も歴任。川崎製鉄では冶金技術者として多くの論文執筆と特許出願でも貢献したほか、中国古典に造詣が深いことでも知られる。19年旭日大綬賞受賞。
----------
(JFEホールディングス 名誉顧問 數土 文夫 文=荻野 進介 撮影=小川 聡)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
本能寺の変は決して無謀なクーデターではなかった…明智光秀の計画を狂わせた2人の武将の予想外の行動
プレジデントオンライン / 2024年6月25日 10時15分
-
投資判断を左右する「経営者メッセージ」、響く伝え方は? オリックス、塩野義製薬の統合報告書に見る
ITmedia ビジネスオンライン / 2024年6月24日 8時15分
-
エネオスHD新社長はナルシスト?初の東燃ゼネラル出身“下剋上”トップ人事に日石組からは不満が(小林佳樹)
日刊ゲンダイDIGITAL / 2024年6月15日 9時26分
-
モンスター客が怖くて手が震えた…ココイチの泣き虫アルバイト22歳が社長就任後もよく涙を流す別の理由
プレジデントオンライン / 2024年6月10日 10時15分
-
骨太の方針への新視点。元テレビ朝日ワシントン支局長が解説する『日本企業のための経済安全保障』6/18発売。
@Press / 2024年6月7日 10時0分
ランキング
-
1関東「気動車王国」の離れ小島路線が面白い! 不思議な“右ハンドル”車両 3駅の路線に“スゴイ密度”であるものとは?
乗りものニュース / 2024年6月29日 15時12分
-
2意外な面倒さも? 財布いらずの「スマート支払い」、店側はどう思っているのか
ITmedia ビジネスオンライン / 2024年6月30日 8時10分
-
3ウイスキーが「おじさんのお酒」から激変したワケ 市場復活に導いたサントリーのハイボール秘話
東洋経済オンライン / 2024年6月30日 8時20分
-
4「押しボタン式信号」なぜ“押してすぐ青”にならないケースが? 納得の理由があった!
乗りものニュース / 2024年6月29日 16時42分
-
5障害者雇用未達で「社名公表」寸前からの挽回劇 法定雇用率クリアへの3年で見えた成果と課題
東洋経済オンライン / 2024年6月30日 9時0分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください












