日本人が「質的ワンチーム」を目指すべき理由
プレジデントオンライン / 2019年12月20日 17時15分
■流行語大賞からみる「不易流行」
2019年の流行語大賞が決まりました。ラグビー・ワールドカップの日本代表の活躍から広まった「ONE TEAM(ワンチーム)」でした。「みんなでひとつになる」というイメージが想起されるこの言葉は、そもそも日本代表を率いたジェイミー・ジョセフ・ヘッドコーチが掲げたチームのスローガンです。
同時期に決まった「今年を表す漢字一字」が「令」でした。これは「令和」の令でもありますが、ふだん使いする多さからすると、「指令」の令のほうが一般的でもありましょう。しかも日本代表のヘッドコーチは「指令」を出してチームを勝利に導く立場です。温故知新に則(のっと)って「不易流行」を、そして「令とワンチーム」から今年の日本の流行を、そして流行から不易についてを、今回展開してみたいと思います。
余談ですが、ラグビー日本代表のユニフォームの胸に輝くエンブレムは「桜」でしたし、「桜を見る会」もかなり話題になりました。さらにはそこに招かれた人たちが実は「サクラ」だったのではないかというオチもありましたので、てっきり今年の漢字一字は「桜」ではないかと私は思っていました(笑)。
■日本はずっと「ワンチーム」だった
ここで仮説を述べてみたいと思います。
「ワンチームという流行語が今年流行(はや)ったのではなく、日本という国がそもそもワンチームではなかったのか」と。
すべて難局を「ワンチーム」で乗り切ってきたのがこの国なのかもしれません。天変地異が毎年発生する国に生きているとワンチームにならざるを得なかったのが本音でしょう。まして稲作が中心の農業国でもあります。そもそもの用水路を作るにあたってはワンチームで協力し合うのが前提ですし、いざ田んぼが整ったら草取りからはじまり、田植え、稲刈りと一人ひとりの力を合わせてゆくのに慣れた国民性だったはずです。
江戸時代までのかような精神性は一気に工業化を促すことになった明治維新以降にも威力を発揮します。国を挙げてのワンチーム化は、軍国化にも役立ちました。旗さえ振れば脇目も振らずに一心不乱についてくるのですから、為政者側としてはある意味ワンチームというのは扱いやすさをも意味します。政治家としては処理しやすい対象のはずだったのでしょう。
師匠の談志は生前よくいっていました。「四方が海で囲まれた国の統治なんて、地続きでのべつ領土問題で揉(も)めている国に比べたら屁みたいなもんだ。極論すれば、政治とか外交は無視しても経済のみに明け暮れていればいいのだから」と。
幾分皮肉めきますがかような地勢上の特性が、政治家を世襲制に落ち着かせ、その反動も含めて経営者サイドは競争力を磨いてゆくことになったのかもしれません。政治よりも経済、かつて「エコノミックアニマル」といわれた所以(ゆえん)がそこにあります。
■そだねー、忖度の意外な共通点
結果としてその踏ん張りが、明治維新から100年しか経たない1968年に、敗戦という憂き目を食らいながらも世界第3位の工業生産国にまで日本を押し上げたのでしょう。
有史以来のワンチームだったのが日本の実体で、それをラグビーというスポーツがたまたま象徴し、さらにはブームとともに具現化したのが今年の流行語大賞になったのではと推察します。影だった存在が光を当てられ表に出てきたような格好でしょうか。
そう考えると、もしかしたら、毎年行われる「流行語大賞」とは、もともと日本人があたり前のように持っていた精神性をその年の流行りとともに記号化させたものなのかもしれません。「不易流行」はここにあったのです。
ちなみに昨年2018年の流行語大賞は、「そだねー」でした。ご存じのとおり2018年平昌オリンピックで大活躍したカーリング女子日本代表チームの選手の会話から広まった言葉でした。そしてさらに、2017年の流行語大賞はと思い調べてみましたら、「インスタ映え」と「忖度(そんたく)」でした。
ワンチーム、そだねー、インスタ映え、忖度。
おお、いま気づきました!
ここ3年の流行語大賞に通底するものから、日本人の普遍性という不易の部分を抽出するならば、「他者への気遣い」ではないでしょうか。
■流行語を通して「日本人の感受性」を再認識
「ワンチーム」は、まず「他者への気遣い」を前提として組織を一体化させるために機能する言葉です。「そだねー」は、そもそも相手への同意、つまり「他者への気遣い」そのもの。「インスタ映え」は「他者への気遣い」の可視化ですし、そこでの「いいね!」の数が「他者への気遣い」の数値化になります。「忖度」に至っては「他者への気遣い」とほぼ同義語だと辞典にも書かれていそうなことであります。
もしかしたら日本人は、流行語を通して「他者への気遣い」という先祖代々受け継いできた大切な感受性を、再認識したいと願っている国民なのかもしれません。他者のことを「他人様」とか「世間様」とか「様」という敬称まで施してリスペクトしている国は他に果たしてあるのでしょうか。
理想は、いままでのような経済成長などを前提とした「量的なワンチーム」ではなく、LGBTをはじめとした多様な価値観の存在を認める「質的なワンチーム」ではないでしょうか。
無論メダルの数が多いほうに越したことはありませんが、数値目標ではなく、より感動を目指す——日本に期待されるポジションはそんなところだと確信します。
そして、そんな「他者への気遣い」が応酬される空間こそが落語会の会場ではないかと確信しています。
落語は登場人物の会話とその表情だけで成り立つ芸能です。正直余白だらけ。そこの余白部分に観客各位が「想像力」をフルに働かせてはじめて完成する世界です。つまり、演者も観客も同じ場に立つ共感力こそが肝となります。落語会の会場全体がいわば「ワンチーム」なのです。
■自分を知らない人は、他者への気遣いもできない
このワンチームはある意味集団催眠の場でもあります。だからこそ落語の最中に鳴る携帯電話はそんな儚(はかな)い夢のひとときから目を覚ましてしまう凶器にすらなってしまうのです。
今よりもずっと人間同士の密度の濃かったはずの江戸時代に花が咲いたのが落語です。そんな落語家と観客との「ワンチーム」を会場を愛でつつ、観客は落語家に同意の意志表示で「そだねー」と笑いで反応し、「瓦版」という「江戸版インスタ映え」で情報を共有化しながら、みんなで上手に「忖度」し合ってきたからこそ、300年近くにもわたるあの長年の平和が保たれてきたのでしょう。
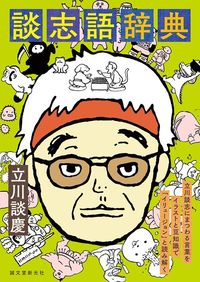
こうしてみると流行語大賞とは「長年日本人は変わってきていないこと」を証明する儀式にすら思えてさえきますなあ。
そして、「他者への気遣い」とはまず「自分の客観化」からはじまるのではないかと私は考えます。「自分というもの」がどういう存在なのかが客観的に見える人こそ「他者への気遣い」ができるものです。「自分というものは、こういう時に怒るのだ」ということがわかる人は、少なくとも他人を怒らせるような振る舞いはしなくなるはずです。「自分はこういうことをされたら嬉(うれ)しい」とわかる人は、それを率先してやれば人は喜ぶということを知っているはずです。
■3キロのダンベルを100回上げるとわかること
では、「自分を客観化してくれるもの」とは一体なんでしょうか。

私は、筋トレを提案します。
筋トレは自分のレベルを残酷にも客観化させます。どんなにネットで「俺は昔ベンチプレス100キロ上げていた」といっても、目の前に器具を用意してやらせてみたらわかることです。
嘘(うそ)やハッタリはまったく効きません。「一生懸命トレーニングしています!」と訴えても、「じゃあスクワットで担いでみて」といわれれば一目瞭然です。そんな客観化とのせめぎ合いを毎日続けてゆくことで、自分というものがおぼろげながら見えてきます。
そこで浮かんできた自分をコアにする訓練を積み重ねてゆけば、「他者への気遣い」も同じように明確化されてゆくのではと、私は手ごたえを感じています。3キロのダンベルでも100回上げれば、腕がパンパンになります。
そんな気持ちをつなげてゆくと、町で出会ったご年配の方が駅の階段などでつらそうに抱える荷物をさりげなく持ってあげることなどたやすいことです。
----------
立川流真打・落語家
1965年、長野県生まれ。慶應義塾大学経済学部卒業。ワコール勤務を経て、91年立川談志に入門。2000年二つ目昇進。05年真打昇進。著書に『大事なことはすべて立川談志に教わった』など。
----------
(立川流真打・落語家 立川 談慶)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
立川志らく、弟弟子の代わりに謝罪 石丸氏に関する過激投稿で「不愉快にさせた事を深く陳謝」
スポニチアネックス / 2024年7月16日 20時38分
-
『ブラックペアン シーズン2』第3話ゲスト発表 大御所俳優&人気落語家が登場
ORICON NEWS / 2024年7月14日 12時0分
-
東生亭世楽&立川キウイ ガーシーカウンターイベントを開催「落語愛あるなら筋を通すべき」
東スポWEB / 2024年7月12日 23時15分
-
言いたい放題ざこばさん 女性蔑視? 発言のウラを読売テレビ女子アナ明かす
日刊スポーツ / 2024年7月7日 21時51分
-
今年の流行語大賞は朝ドラ『虎に翼』の“必殺フレーズ”か。日本社会の風通しを良くするワードとは
女子SPA! / 2024年6月22日 8時46分
ランキング
-
1大谷翔平の新居「晒すメディア」なぜ叩かれるのか スターや芸能人の個人情報への向き合い方の変遷
東洋経済オンライン / 2024年7月16日 20時40分
-
2工学系出身者が「先進国最低レベル」日本の"暗雲" エンジニアを育てられない国が抱える大問題
東洋経済オンライン / 2024年7月16日 17時0分
-
3申請を忘れると年金200万円の損…荻原博子「もらえるものはとことんもらう」ための賢者の知恵
プレジデントオンライン / 2024年7月17日 8時15分
-
4「再配達は有料に」 ドライバーの本音は
ITmedia ビジネスオンライン / 2024年7月17日 6時40分
-
5旅客機用の燃料不足で緊急対策 輸送船を増強、運転手確保へ
共同通信 / 2024年7月16日 23時42分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください











