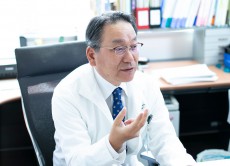医師が「神の手よりロボット手術」と断言する訳
プレジデントオンライン / 2020年1月20日 15時15分
武中 篤(たけなか・あつし)/1986年山口大学医学部医学科卒業。1991年神戸大学大学院研究科(外科系、泌尿器科学専攻)修了。医学博士。神戸大学医学部附属病院、川崎医科大学医学部、米国コーネル大学医学部客員教授などを経て、2010年より現職。2013年~2017年に低侵襲外科センター長、2017年4月より副病院長を兼任。専門は泌尿器悪性腫瘍学、低侵襲手術、骨盤外科解剖 - 撮影=中村 治
※本稿は、鳥取大学医学部附属病院広報誌『カニジル 3杯目』の一部を再編集したものです。
■私の記憶から消えた母親と、残った決心
武中篤が医学の道を志したのは、小学3年生のときだった。母親が慢性腎不全で亡くなったのだ。
「慢性腎不全ってね、今は血液透析を行えば命を落とすことはないですよね。その当時は、まさに日本にその技術が導入されたばかり、当然、健康保険は利用できません。私の父親は学校教師、普通の家庭です。慢性腎不全に血液透析という治療選択肢は一般的ではなかった」
父親が医師と血液透析をするかどうか、相談をしていたことをはっきり覚えている。
当然無理ですよね、と医師は冷静な口調で言った。そのやりとりを聞きながら、死刑宣告を受け入れるとはこういうことなのだと思った。母親が亡くなったのはその数日後のことだ。その前後の記憶はほとんどない。
「母親が寝込んでいる姿しか覚えていない。あとは夏休みに母親の調子がよくなって、家族旅行に数回行ったことぐらい」
その理由は分かっている。その数年後に父親が再婚したのだ。
「新しい母親は素晴らしい人だった。今でも血縁のある親子以上に信頼もしているし、仲もいい。だから前の母親には申し訳ないけれど、私の記憶から消さざるを得なかったのだろう。生体防御反応です」
ただ、医者になろうという決心だけは、彼の頭に残ることになった。
■唯一無二の存在になりたかった
武中は1961年5月に兵庫県加東市で生まれた。最初の挫折は高校に進学した後、野球部を覗いたときのことだ。小学生から投手だった武中は高校でも野球部に入り、甲子園を目指すつもりだった。しかし、自分の力量ではとても歯が立たないと悟ったのだ。
そこから3年間、勉強に集中することになった。私は身の程を知れる人間なんです、と武中は自己分析する。
「世の中に頭の切れる人はいっぱいいます。そういう人は、すべてが一瞬に頭の中に入ってくる。凡人はどうしたらよいのか、どうしたらその差を埋めることができるのか。時間を掛けるしかないんです」
頭の切れる人が1時間でやるなら、自分は2時間でやればよい、そう武中は思いながら机に向かった。そして現役で山口大学医学部に合格している。
入学後は医学部の準硬式野球部に入った。大学6年間は、ほんと野球漬け、勉強は試験直前以外はほとんどしていない、試験はいつもカツカツ、と笑った。
大学卒業が近づき、専門科目を決める時期になった。5年次、頭に浮かべていたのは消化器内科だった。
「ある分野で、抜けた存在になりたかった。内視鏡に興味があったんです。でも1年間迷って、なぜか決めきれなかった。消化器内科に進もうか、別の科に進もうかと。そのとき、ふと頭をよぎったんです、俺、どうして医者の道を選んだのかって」
そこで母親が亡くなった、あの3月の寒い日が突然浮かび上がってきたのだ。
「1日で泌尿器科に決めました。消化器内科って最もメジャーな診療科で、多くの医師が在籍している。そこで頭抜けるって大変じゃないですか。当時、泌尿器科っていうのは、どちらかというとマイナー診療科で他の診療科と比べたら歴史が浅い。少し頑張ったら、唯一無二の存在になれるのでは、という考えもあった」
■大手商社入社1年目、同じ年のがん患者に出会って
1986年、武中は神戸大学医学部附属病院で研修医として働きはじめた。神戸大学を選んだのは癌治療を得意としていたからだ。その直後、一人の患者に出会っている。
「有名大学を出て、大手商社に入社1年目の患者だった。私と全く同じ年。秋の定期検診で胸部レントゲンを撮ったら、肺に巨大な多発陰影が発見された。肝臓やリンパ節にも同様の陰影がある。精巣癌多発転移で、進行度は最も進んだステージⅢCだったんです」
精巣癌とは男性の精巣にできる癌である。若年者に多く発症し、進行スピードが極めて速いことが特徴だ。彼の場合、入社前の健康診断では異変は見つからなかった。一気に癌が広がっていたのだ。
「多臓器転移で、腫瘍も巨大。研修医の自分としては、予後はよく持って1年以内と思った。一般的な固形癌なら、百パーセント根治は無理。彼の場合、超大量の抗がん剤で腫瘍を縮小させ、残存した肺、肝、リンパ節転移巣は切除した。難しいのは薬剤の量。副作用を考えて減量すると効果は不十分。しかし、増量しすぎると、副作用で命を落とす。本当に紙一重。泌尿器科は、抗がん剤投与も腫瘍切除も両方自科で行う。治療に時間のロスがない。彼の場合はすべて上手くいった」
同時期、精巣癌で亡くなった患者もいた。医師の判断は人の命に直接関わることなのだ、と自分の仕事の重みをつくづく思い知った。そして母親のことが頭に浮かんできたのだ。
「どうして命を落としたのか、あのときにもう少し何かやっておけば延命できたのでは、って。私には記憶もないし、父親も覚えていないから治療が適切であったかどうかの判断材料はないのですが」
だからこそ、と武中は語気を強める。
「あの時こうしたらよかったとか、妥協は1ミリもしたくない。それが私のポリシーです。もちろん手を尽くしても結果がよくなるとは限らない。でも、自分の気持ちのなかに妥協は一切残したくないんです」
■海外留学を断り“出世”の本筋から外れる
大学院では分子病理学を専攻し、精巣癌の進展メカニズムについて研究を行なった。大学の指導教員から、大学に残るため海外留学し基礎研究を継続してはどうか、と薦められたこともある。しかし、自分がやりたいのは臨床――患者を診ることであると断った。自然と彼は“出世”の本筋から離れることになった。

その後、大学病院を離れて兵庫県内の基幹病院に勤務することになった。そして、ほぼ毎月、札幌の医学部解剖学研究室に通っている。
「とにかく手術が上手くなりたかった。その研究室に、当時珍しかった新鮮凍結遺体という献体があったんです。通常、ご遺体はホルマリン固定後、保管される。人体解剖って実は分かっていない部分がたくさんある。ホルマリンで固定されると、手術時に展開する剥離層や末梢自律神経の詳細な走行は分からない。それを明らかにするために、特殊なご献体がある解剖学研究室に通いました。また、そういうご献体が日本以上に豊富にある韓国の解剖学教室に行ったこともあります」
大学院時代、武中は病理学教室に所属していた。その経験もあって、人体を形態学的に解明したいという思いが強かったのだ。
■外科解剖は車のナビゲーション
2003年4月、武中は川崎医科大学の泌尿器科学講座の講師となっている。約10年ぶりの大学病院への復帰だった。川崎医科大学の教授となった先輩から強く誘われたのだ。武中は何度か断ったが、人は誘われるうちが花だと思い直した。
大学では臨床以外に研究の時間や論文を書く時間が与えられる。武中はこれまで行なってきた外科解剖学研究を文章にしたためることにした。論文は『ザ・ジャーナル・オブ・ウロロジー』の2004年9月号に掲載された。すると武中が戸惑うほど、世界中から反応があった。その背景には医学界の新しい動き――手術支援ロボットの存在があった。
「喩えるならば、解剖は車のナビゲーションなんです。運転技術が適当な間は、緩いナビでも大丈夫。ところがロボット手術は運転技術が完璧。ロボット手術をやろうとしたら、実はナビが20年前の旧製品だって話になったんです。これまで使っていた地図というのは古典的でロボット手術の役に立たなかった」
武中は人体解剖学研究を続けるうちに、これまで知られていなかった人体の暗闇である、微細構造に光を当てていたのだ。
■“神の手”に興味はない。ロボット手術が必ず世界を席巻する
2006年1月、武中は泌尿器科の“ビッグスリー”の一つ、アメリカのコーネル大学から客員教授として招聘された。外科解剖を指導し、ロボット手術のナビゲーション役を務めてほしいという依頼だった。そこで日本にはまだ導入されていなかったロボット手術を経験する。

「それまで自分なりに日本でトップレベルの手術を行なってきた自負があった。しかし、ロボット手術を見たとき、黒船襲来、これには敵わない、この手術が必ず世界を席巻する、と確信した」
そして武中はこう頼んだ。外科解剖を教える代わりに、私にロボット手術を教えてくれ、と。
2007年5月、神戸大学大学院医学研究科の准教授として日本に戻った。そして2010年7月に、鳥取大学医学部泌尿器学教授となっている。同年8月、鳥取大学医学部附属病院は山陰地方で初めて手術支援ロボット「ダビンチ」を導入。最初の手術は武中に任された。
「極論すればダビンチは誰でも使えるんですよ。車の運転もナビが発達して、自動運転に向かっている。手術も同じです。これからは技術は器械がアシストしてくれる。大切なのは常にアップデートされたナビ、つまり外科解剖学を勉強することなんです」
医療の世界には“神の手”と呼ばれる外科医がいる。ロボット手術が普及すれば、神の手はいらなくなりますね、と訊ねると、武中は頷いた。
「私は神の手には興味がありません。神の手の手術は、その人しかできない。ロボットを使えば、誰でも高品質で再現性の高い手術ができる。いいナビと自動運転の車を作れば、誰でもハイクオリティの運転ができる。私はそちらを求めたい」
多くの患者に、妥協ない高度医療を提供する――自分が小学3年生のときに感じた、哀しみを他の人には味あわせたくないと考えているのだ。
----------
ノンフィクション作家
1968年3月13日、京都市生まれ。早稲田大学法学部卒業後、小学館に入社。『週刊ポスト』編集部などを経て、1999年末に退社。スポーツを中心に人物ノンフィクションを手掛け、各メディアで幅広く活躍する。著書に『W杯に群がる男たち―巨大サッカービジネスの闇―』(新潮文庫)、『偶然完全 勝新太郎伝』(講談社)、『維新漂流 中田宏は何を見たのか』(集英社インターナショナル)、『ザ・キングファーザー』(カンゼン)、『球童 伊良部秀輝伝』(講談社 ミズノスポーツライター賞優秀賞)、『真説・長州力 1951-2015』(集英社インターナショナル)『電通とFIFA サッカーに群がる男たち』(光文社新書)など。
----------
(ノンフィクション作家 田崎 健太)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
「高い知性と教養を有し、人間力に満ちた実践能力あるグローバルな人材育成に努めて参ります」 鳥取大学次期学長に原田省副学長が選考 鳥取県
日本海テレビ / 2024年9月20日 18時28分
-
手術室には産婦の絶叫が響き…麻酔が効かないままの「切腹カイザー」はなぜ繰り返されたのか
文春オンライン / 2024年9月19日 6時0分
-
徹底解説・第6弾 男性更年期 患者はどうやって克服したか 頻尿を改善する新しい体操、骨盤底筋群鍛える「110度スクワット」 テストステロンの低下で膀胱を収縮する筋肉も衰える
zakzak by夕刊フジ / 2024年9月13日 6時30分
-
大阪大学公式クラウドファンディング(大阪大学×近畿大学 コラボプロジェクト) 腹部大動脈瘤の治療薬創出を目指して! ―「腹部大動脈瘤患者に対する世界初のトリカプリン投与試験」にご支援を ―
Digital PR Platform / 2024年9月10日 14時5分
-
“磨き上げた匠の技で婦人科がんの患者を救え!パッションを胸に走り続ける命の守護者”金尾祐之氏を特集 DOCTOR'S MAGAZINE ドクターズマガジン9月号発刊
PR TIMES / 2024年8月27日 10時15分
ランキング
-
1ペーパードライバーの “迷惑運転行為”に、走行距離30万km超のゴールド免許所持者が怒りの告発
日刊SPA! / 2024年9月15日 15時52分
-
2ダウンタウン浜田雅功の“くちびる寿司”を食べてみた ユニークな見た目に笑ってしまう
オトナンサー / 2024年9月20日 23時10分
-
3東京都、018サポートで新たに134人への重複支給発覚 マイナ申請の照合設定に誤り
産経ニュース / 2024年9月20日 19時47分
-
4メルカリで「マイナス評価」が1つでもあったら売れなくなる? 購入を敬遠される可能性も……
オールアバウト / 2024年9月20日 20時40分
-
5超一流パティシエも"満場一致"の大絶賛。「完璧」「これは本物」ローソンで食べるべき絶品スイーツとは。
東京バーゲンマニア / 2024年9月17日 18時46分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください