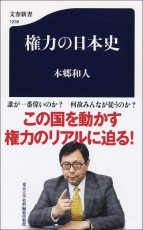日本が昔から「競争より身分を重んじる」価値観であるワケ
プレジデントオンライン / 2020年3月1日 11時15分
■女性天皇はいても、女系の天皇が輩出されなかった理由
平成から令和への代替わりの年にあって、皇室報道や平成回顧が様々な媒体に掲載されている。ただ、皇室を敬愛している人が多いことは伝わっても、意外に皇室をめぐる情報は少ないし、皇室をめぐる言論はどうも貧しい。
それは、近年の皇室をめぐる言論が、「男系男子」vs「女系・女性容認」という皇位継承のあり方や、嫁姑問題などの口さがないゴシップに集中してしまっているからではないだろうか。もっと豊かな歴史を学びたい、と思う人にこそ本書を手に取ってほしい。
日本人はそもそも天皇という存在をよく知っているのだろうか。本書は、日本における身分制が何を守ろうとしてきたのかを明らかにしつつ、権力の実像を伝えている。
本書で投げかけられる問いはどれも面白い。天皇と上皇はどちらが偉いのか、なぜ兄弟間での平等な相続ではなく中継ぎの女性天皇を即位させてまで直系相続が一般的になっていったのか、女性天皇はいてもなぜ女系の天皇が輩出されなかったのか。
そして、天皇だけでなく、貴族の立身出世のパターンを解説することで、ある共通項が浮かび上がる。それこそ、家柄を重んじ、土地持ちの「家」の継承を最優先する考え方だ。いわば、現代の日本政界のあり様にも通ずるような秩序観である。
面白いのは、日本人が「家」の継承と系譜を重んじつつも、その中身に関しては割と最近まで無頓着だったというくだりである。遺伝子だ、Y染色体だ、という男系男子の皇統に重きを置く論者が重視してきたいわゆる「血」の要素に関しては、昔の貴族社会に、あまり強いこだわりは見られない。むしろ、その点に関しては女性の性交渉を含めておおらかであると言ってもいい。
■日本における「家」へのこだわりはすさまじい
その一方で、日本における「家」へのこだわりはすさまじい。こうした一本すっと通ったロジックに基づいて、院政の勃興や女性天皇の出現が語られていくので、読者は随所で思わずなるほどと膝を打つことだろう。
本書から浮かび上がってくるのは、歴史が偶然性の連続の上にあるという事実と、そのなかでもやはり日本人が大事にした価値観がいまのあり方を形作っているということの2つだ。日本人が大事にしてきた価値観とは、秩序安定のための長幼の序であり、家格である。
競争よりも身分を、新しいものよりも古いものを重んじてきたのが日本だとすれば、それは著者が言うように秩序を維持しようとする意識的な決断であったのだろう。だからこそ、近代日本が激動の国際情勢のなかで「家」よりも能力を、平穏よりも変革を優先する過程で、ただ1つ変わらないものの象徴として、万世一系の天皇という継続性を前面に押し出さざるをえなかったことがよくわかるのだ。
----------
国際政治学者
神奈川県生まれ。東京大学卒業。同大学院法学政治学研究科修了。博士(法学)。『21世紀の戦争と平和:徴兵制はなぜ再び必要とされているのか』、『政治を選ぶ力』(橋下徹氏との共著)など著書多数。討論番組、ワイドショーなどテレビでも活躍。
----------
(国際政治学者 三浦 瑠麗)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
沖縄会派、女系天皇容認を 衆参議長の意見聴取
共同通信 / 2024年7月18日 18時46分
-
旧宮家の子孫たちが皇族になる現実味は… 77年前に離脱、復帰案に賛否渦巻く
共同通信 / 2024年7月16日 7時1分
-
安倍晋三元首相 三回忌 八木秀次麗澤大学教授 「夫婦別姓」「LGBT法」「皇位継承」…安倍元首相は自民党の「左傾化」を憂い、胸に秘めていた〝決意〟
zakzak by夕刊フジ / 2024年7月12日 11時0分
-
佳子さまのOL姿もあとわずか?眞子さんのように“皇室から出たい”が本音も結婚には高い障壁
日刊ゲンダイDIGITAL / 2024年7月11日 9時26分
-
国会の議論はあっという間に行き詰まった…皇位継承問題の解決をこじらせている最大の阻害要因
プレジデントオンライン / 2024年6月28日 8時15分
ランキング
-
1システム障害、世界で余波続く=欠航、1400便超
時事通信 / 2024年7月21日 22時45分
-
2円安は終わり?円高反転4つの理由。どうなる日経平均?
トウシル / 2024年7月22日 8時0分
-
3なぜユニクロは「着なくなった服」を集めるのか…「服屋として何ができるのか」柳井正氏がたどり着いた答え
プレジデントオンライン / 2024年7月22日 9時15分
-
4イタリア人が営む「老舗ラーメン店」の人生ドラマ 西武柳沢「一八亭」ジャンニさんと愛妻のこれまで
東洋経済オンライン / 2024年7月22日 11時30分
-
5コメが品薄、価格が高騰 米穀店や飲食店直撃「ここまでとは」
産経ニュース / 2024年7月21日 17時41分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください