日本に「建国記念日」が存在しない本当の理由
プレジデントオンライン / 2020年2月11日 9時15分
※本稿は、本郷和人『空白の日本史』(扶桑社新書)の一部を再編集したものです。
■「の」から紐解く“空白の日本史”
2月11日の「建国記念の日」。この日は、日本の建国を祝う祭日として、明治6年の1873年に定められました。当時は「紀元節」といっていました。世界各国で「建国記念日」は存在しますが、なぜ現在の日本では「建国記念“の”日」と称されるのか。
その背景にある「皇紀の虚偽」を紐(ひも)解くことで、新たな「歴史史料の空白」を検証してみたいと思います。
まず、この「建国記念の日」ができた当時、明治政府は日本が万世一系(ばんせいいっけい)の天皇を頂点にした統治国家であることを、強烈にアピ―ルをしようと考えていました。当時の日本は、近代国家として誕生したばかり。
そのため、明治政府は、国内外に向けて、海外にはない日本のオリジナリティや存在感を示すため、日本という国が、長年に渡って天皇家というひとつの系譜に連なる血筋が治めていることを、最大限利用しようとしたのです。
■「エンペラー」の称号を得た明治政府の猛アピール
こうした明治政府の活動が功を奏し、現在でも日本の天皇は、海外では「皇帝(Emperor)」という称号を得ています。たとえば、英国王室のエリザベス女王の称号でさえも「女王(Queen)」であって、「皇后(Empress)」ではない。世界有数の伝統を誇る王室でさえも、「King/Queen」と呼ばれるなか、日本の皇室は「Emperor/Empress」という特別な称号を使用することが認められています。
明治時代には、エチオピア王室も「Emperor/Empress」の呼称が使われていたそうですが、現時点では世界中でこの呼称が使われているのは、日本の皇室だけ。これは、明治政府が世界中に「日本の天皇家は万世一系である」と訴えた主張が、見事に影響していると言えるのでしょう。
諸説ありますが、少なくとも26代の継体天皇(450?-531年)以降は、天皇家は一つの血筋でつながっているのだと考えられています。それだけとってみても、世界一古い王家であることは、間違いありません。英国王室以外のヨーロッパ王室の血統は、古くとも18~19世紀前後のナポレオン戦争くらいから始まったものが大半です。
■国内外で利用された皇室の“伝統”
欧州の王室は、1800年代ごろに外国から来た人が、王となるケースが多い。そう考えると、日本の皇室がいかに古く、歴史と伝統を持っているかという話は、外国に向けて発信してもたいへんに誇らしいものです。また、この主張は、国外だけではなく、国内に向けても、明治政府が中央集権国家を作る上での大きな武器になりました。
「天皇家は世界でも類を見ないほどに、古く、伝統がある。長い間、日本を見守ってきた天皇のために、国民が力を集めて頑張ろう」
こうした、非常にわかりやすいスローガンがうまく作用し、明治政府によって、日本という国はひとつの国へとまとめられていきました。この例を見てもわかるように、「我が国には長い歴史がある」と主張することは、国内外に強い影響力をもたらします。
■紀元前660年が「元年」になったワケ
現在の日本では、元号や西暦が使われていますが、明治時代に正式に採用されたのが、「皇紀」という暦(こよみ)でした。
「皇紀」とは、神武天皇が最初に即位した年を元年とした暦のこと。紀元前660年を元年として数えられており、東京五輪が開催される2020年は皇紀2680年にあたります。なぜ、紀元前660年が神武天皇即位の年になったのかというと、そこには少し複雑な経緯があります。
まず、古来から日本の暦は「甲(こう)・乙(おつ)・丙(へい)・丁(てい)・戊(ぼ)・己(き)・庚(こう)・辛(しん)・壬(じん)・癸(き)」を表す十干(じっかん)、「子(ね)・丑(うし)・寅(とら)・卯(う)・辰(たつ)・巳(み)・午(うま)・未(ひつじ)・申(さる)・酉(とり)・戌(いぬ)・亥(い)」を表す十二支を組み合わせた、十干十二支で表していました。
そして、両者を組み合わせた数字である60(10×12÷2)が、一つの周期になります。60歳を「還暦」と称するのは、60年という周期が一度巡ることで、また「暦が還る」から。そして、還暦の人に真っ赤なちゃんちゃんこを贈るのは、「赤子に戻って、もう一度人生を生まれ直すから」だと言われています。
■中国由来の「十干十二支」
さて、十干十二支には様々な組み合わせがありますが、その中の58番目の組み合わせである「辛酉(かのととり)」は革命の年とされています。これは、中国由来の考え方で、漢の時代に生まれた儒教の考え方をまとめた書物『緯書(いしょ)』で唱えられた予言「讖緯(しんい)説」に由来するものです。
「讖緯説」によれば、60年に1回の辛酉の年には、何かしら革命が起こる。さらに、60年が21回続いたときの辛酉の年には、ただの革命ではなく、とてつもない大革命が起こると言われていた。60年×21回ということは、1260年に1回のペースで大革命が起こるという計算になります。
その説に基づき、明治初頭の歴史学者たちは「前回、大革命が起こった辛酉の年はいつだったのか」を検証します。そして、「聖徳太子がいた頃に起きた辛酉が、大革命の年だろう」と結論づけたのです。なぜ、聖徳太子がいた頃に、大革命が起きたとされたのか。その理由は、当時の日本では、日本の基礎を作ったのは聖徳太子だと考えられていたからです。
近年の研究では「聖徳太子は本当にいたのか?」という論争もある上、日本という国の基礎ができたのは、天智天皇や天武天皇の時代だと考えられています。ただ、明治当初、彼は、十七カ条の憲法や官位十二階の制定、遣隋使の派遣、仏教の普及などに貢献し、日本の基礎を作った人物として、非常に重要視されていました。
■「皇紀」を生んだ辛酉大革命という思想
だからこそ、「聖徳太子がいた時代こそ、日本という国ができた年である。日本ができた年こそ、辛酉の大革命が起こった年である。では、そのもう一つ前の辛酉の大革命の年とは何だ? 聖徳太子クラスの人物の関与ということであれば、こここそが、神武天皇が即位した年次であるに違いない」と、明治の歴史学者たちは考えた。
わかりやすく言うと、1回目の辛酉の大革命では神武天皇の即位があり、その1260年後となる2回目の辛酉の大革命で、聖徳太子が国を作った。そう当時の研究者たちが結論づけた結果、神武天皇即位を原点とした「皇紀」が誕生しました。逆に言えば、この辛酉大革命という思想を受け入れていなかったら、皇紀というものは生まれなかったとも言えます。
その結果、紀元前660年1月1日こそが日本建国の日になりました。ただ、これは太陰暦の日付なので、太陽暦に直すと2月11日です。そこで、明治6年となる1873年に、2月11日を「紀元節」とし、日本の建国記念日として定めました。
■「この日を本当に日本の建国記念日としてよいのか」
戦前は紀元節に盛大なお祝いをしていたのですが、戦後になると、より冷静な考えが広まり、「この日を本当に日本の建国記念日としてよいのか」という疑問が浮かんできます。先に挙げたように、文献史料は何もないので、当然立証できない。GHQの意向もあり、戦後しばらくの間、建国記念日は日本から消えました。
ところが、1950年代初頭、日本の国力が勢いを増したことで、日本に再び建国記念日を復活させようという動きが始まります。アメリカの独立記念日(7月4日)や、韓国が日本の統治から離脱した日を祝う光復節(8月15日)のように、世界各国にその国の誕生日があり、それなりにお祝いをしている。ならば、日本にも国の誕生日があっていいだろう、と。
ただ、いざ日にちを決めるとなると、右派と左派の間で、かなり大きな論争が繰り広げられることになります。右派としては、「紀元節」に則(のっと)って、以前と同じ2月11日を推薦する。でも、左派側は、「2月11日が建国記念日である科学的根拠がない」として猛反対する。
たしかに、紀元前660年に神武天皇が存在したという話自体が、まったくの神話世界の中の話であるため、何の根拠もない。こうした主張については、右派側も認めざるを得ません。
■「の」は大人の配慮の結晶だった
神話の世界の話を「これぞ、日本の歴史」だと主張することは、さすがに近代国家では通用しません。そこで、苦肉の策として生まれたのが「建国記念の日」です。つまり、「建国記念日」とは言わず、「建国記念“の”日」とすることで、日本の建国をお祝いする日にしよう。それならみんなが納得できるのではないか。そんな事情で、「建国記念日」の間に、「の」という一文字が入ります。この「の」はいわば、大人の配慮の結晶だったと言えるでしょう。
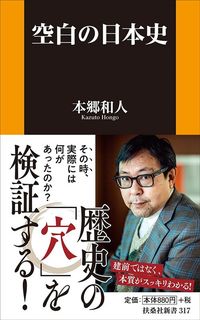
そして、こうした苦心の末、1966年、安倍晋三首相の祖父・岸信介の弟である佐藤栄作内閣の下で、「建国記念の日」が制定されました。
時に「日本は神の国だ」と言い出す政治家がいますが、日本の皇室が、神の子孫だというのはあくまで神話の中のお話で、科学的根拠はまったくありません。ただ、26代の継体天皇以降は、現代に至るまで血がつながっていることは、間違いない。紀元前660年ではないにせよ、それでも世界的に見たら群を抜いて古い王家であることは、きちんと僕たち日本人は踏まえておいたほうがよいのではないでしょうか。
もちろん「古いものが優れているわけではない」という議論も当然上がってきますが、長ければ長いほど伝統は育まれますし、時の積み重ねは重いものです。皇室に関する新たな議論が出るたびに、そこは冷静に話し合っていくべきではないかと僕は考えます。
----------
1960年、東京都生まれ。東京大学史料編纂所教授。専門は、日本中世政治史、古文書学。『大日本史料 第五編』の編纂を担当。著書に『日本史のツボ』『承久の乱』(文春新書)、『軍事の日本史』(朝日新書)、『乱と変の日本史』(祥伝社新書)、『考える日本史』(河出新書)。監修に『東大教授がおしえる やばい日本史』(ダイヤモンド社)など多数。
----------
(東京大学史料編纂所教授 本郷 和人)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
【逆説の日本史】米騒動は「天皇制支配に対する労働者・農民の反抗」にあらず
NEWSポストセブン / 2025年1月30日 16時15分
-
天皇家の先祖が南九州から近畿へ大移動…『古事記』『日本書紀』から読み解く「神武東征」のルート
プレジデントオンライン / 2025年1月19日 17時15分
-
「変革」多い巳年 脱皮繰り返すことから「生命力」「再生」新しい事象への「起点」象徴
日刊スポーツ / 2025年1月18日 7時45分
-
【新刊】世界最古の国・日本の2700年を31人の偉人で紐解く、新感覚歴史書がここに誕生『歴史がもっと面白く、神社やお寺がもっと楽しくなる!日本の真・偉人伝』
PR TIMES / 2025年1月14日 12時15分
-
65歳の自分にとっては「聖徳太子」がお札の顔だけど、娘に両替を頼んだら「初めて見た!」とのこと。今の若い人には通じない? お札が市場に出回らなくなる仕組みも解説
ファイナンシャルフィールド / 2025年1月4日 4時10分
ランキング
-
1令和の米騒動で外食の「お代わり無料」が危機に? 対応分かれる各社の現状
ITmedia ビジネスオンライン / 2025年1月31日 10時48分
-
2スタバ、東京23区・大阪市などで「立地別価格」導入&豆乳変更は無料に ネットでは「横浜は含まれませんよね?」「マックも取り入れてる」
iza(イザ!) / 2025年1月31日 16時47分
-
3フジ・日枝相談役について取締役の1人「退任を求めるのは難しい」 中居氏と女性をめぐる一連の対応のなかで進退注目
TBS NEWS DIG Powered by JNN / 2025年1月31日 13時35分
-
4「間違った断熱」で電気代がかさむバカらしさ…職人社長が「一戸建てはエアコン1台で十分温まる」と断言する理由
プレジデントオンライン / 2025年1月30日 7時15分
-
5「まどか26歳」9時5時勤務の研修医が見た"葛藤" 「労働時間が短い=良い」は思い込みなのか
東洋経済オンライン / 2025年1月31日 8時50分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください










