村上ファンドを退けた名門アパレルがたちまち消滅した理由
プレジデントオンライン / 2020年2月20日 9時15分
■「会社は誰のものか」を問いかけた大騒動
かつて東京スタイルという名門婦人服メーカーがあった。デザインの華やかさは今一つだったが、しっかりした縫製など、ものづくりの技術に定評があった。東証1部上場で、約9割という驚異的な自己資本比率を誇っていたが、あまり目立たず、業界上位のオンワード樫山に追いつくことを目標にしていた。そんな同社が、2002年、突如世間の注目を集めた。村上ファンドが株を買い占め、高配当や役員の派遣を求めからだ。
22年間にわたって社長として君臨していた高野義雄氏は村上ファンドの要求を全面拒否。日本では珍しいプロキシー・ファイト(委任状争奪戦)に突入し、「会社は誰のものか」という根本的な問いかけとともに、日本中を巻き込む大騒動に発展した。当時、筆者は同社の株主総会に出席したり、村上氏に会ったりして取材をした。株主総会はガチンコ対決で、結果としては、東京スタイルが村上ファンドの要求を退けた。村上ファンドを支持していた外国人投資家が、総会前に高値で売り抜けたことが要因だった。
高野社長は勝つには勝ったが、この騒動で寿命を10年縮めたと言われた。その後、2006年に村上氏が証券取引法違反で逮捕されると、大いに留飲を下げたが、3年後に食道がんで急死。後任の社長の下で、2011年に同業のサンエー・インターナショナル(東証1部上場)と経営統合をして、TSIホールディングスが発足したが、翌年、東京スタイル出身の社長が突如解任され、経営権は完全にサンエー側に移った。あまりの激動のドラマに筆者は唖然とし、今般上梓した『アパレル興亡』(岩波書店)の執筆を思い立った。
■「つぶし屋」から百貨店アパレルへ
『アパレル興亡』では、婦人服メーカーを舞台に、戦前から現在に至るまで、85年間にわたる日本のアパレル産業の変遷を描いた。

日本で本格的な洋装化が始まったのは戦後である。戦争中、高級織物禁止令によって綿のモンペ姿を強いられていた日本の女性たちは、進駐軍の米国人女性たちのファッションに触発された。しかし、極度の物不足の時代だったので、着物や羽織の裏地を利用したり、男物のコートを上着に作り替える「更生服」が主流で、色合いも黒っぽく地味なものが大半だった。既成服業者は、別の衣料品を「つぶして」製品を作っていたので「つぶし屋」という蔑称で呼ばれた。東京スタイルの創業者、住本保吉氏も、戦前、山梨県甲府市の洋服店での丁稚奉公を経て、「つぶし屋」としてスタートした。
人々の洋装化が急速に進んだのは高度成長時代(一般に1954年~73年)である。「つぶし屋」から出発した日本のアパレル各社は、百貨店の隆盛と歩調を合わせ、百貨店を主な販路とする「百貨店アパレル」へと変貌を遂げた。
1965年(昭和40年)の大手アパレル・メーカーの売上げランキングは次の通りである。①レナウン162億円、②樫山(現・オンワード樫山)85億円、③イトキン43億円、④三陽商会39億円、⑤東京スタイル24億円。
■デザインより営業重視だった日本の大手アパレル
日本の大手アパレル・メーカーの特徴は、営業中心のビジネス・モデルである。
BIGI、コムデギャルソン、ハナエモリといったDC(デザイナーズ&キャラクターズ)ブランド、あるいはクリスチャン・ディオールやラルフローレンのような海外の有名ブランドは、デザイナーがこんなものを着たい、作りたいという創造欲から出発した。
これに対し、レナウンや東京スタイルなど、日本の大手アパレル・メーカーは、戦後の衣料の西洋化という社会的変化に押されて業容を拡大し、クリエイティビティ(創造性)より営業に重点が置かれた。西洋化の波のおかげで、作れば売れたからだ。そのため婦人服メーカーであっても、社内に女性デザイナーくらいはいたが、経営トップは高野義雄氏のような営業出身の男性で、マーチャンダイザ―(商品開発・販促を行う重要職種)も皆男性、営業も全員男性だった。そして百貨店もほとんどのバイヤーが男性だった。
取材をしてみて驚いたのは、アパレル業界の体育会的体質だ。その筆頭が東京スタイルである。営業マンは全員黒か紺の地味なスーツにネクタイ着用、仕事中の私語は一切禁止、終電間際まで連日の残業、上司が部下にびんたを食らわすのは当たり前という世界だった。
メーカー同士の争いも熾烈で、それが如実に表れるのが、百貨店で季節やテーマごとに行われる模様替えの際の場所取り合戦だ。各社がどこに商品を置くかは、百貨店の売り場責任者が事前に決めているが、模様替えが始まると、ハンガーラック(支柱に20~30のハンガーがぶら下がった陳列用具)を肩に担いだ各社の営業マンたちが一斉に平場に突入し、怒声が飛び交う中、少しでも広く、少しでもエレベーターに近い場所を獲ろうと血眼の争いを繰り広げたという。
■部下を蹴飛ばした伊勢丹のカリスマ・バイヤー
そうしたエピソードの中で一番強烈だったのが、アパレルの売り場としては国内のリーダーである伊勢丹新宿店を担当したある営業マンの話だ。
当時、社会人一年生だったが、前任者が違法カジノにはまって、自社の高級コートを質屋に横流しして懲戒免職になったため、急遽伊勢丹を担当することになった。最初に「鬼」の異名をとる伊勢丹の辣腕バイヤーに挨拶に行くと、何度名刺を渡しても「商品を横流しするような腐った会社の名刺は要らん」と床に放り投げられた。

師走近くになって、前任者が数千万円のコートの注文を受けていたのを鬼バイヤーから「あれどうなった? 早く納品しろ」と知らされ、何の引き継ぎも受けていなかったので、本社に問い合わせると、生地不良で少し前に生産中止になったと告げられ、顔面蒼白になった。鬼バイヤーからは毎日「早く納品しろ」と急かされ、「生産中止になりました」と言えずごまかしていたが、ついに打ち明けざるを得なくなった。バイヤーは激怒し、その営業マンを殴る代わりに、そばにいた自分の部下のアシスタント・バイヤーを思い切り蹴り飛ばしたという(さすがに他社の人間には手を出せないと思ったようだ)。
「お前の会社は冬物が終わり次第、口座抹消、取引停止!」と宣告され、上司に辞表を提出し、2月末まで針の筵の上で仕事をした。しかし、懸命に知恵を絞った末、ある方法で数千万円の売上げを穴埋めし(具体的な方法は『アパレル興亡』に詳述した)、鬼バイヤーの信頼を取り戻し、2月の終わりに退職の挨拶に行くと、「なんで辞めるんだ? 辞めるなよ。これやるから、お前の好きに書いて、春物立ち上げろ」と、印鑑だけが捺(お)してある白地の注文書を一冊くれたという。
こうした人々が婦人服を含む洋服を作り、売っていたのである。利幅はメーカー、百貨店ともに3割程度と大きく、バブル崩壊まで濡れ手に粟のビジネスを謳歌した。
■平成不況で日本人のお金の使い方が変わった
ところが、平成の不況期に入ると、人々は服装に金をかけなくなり、衣料の「カジュアル化」が進んだ。2000年前後から携帯電話やインターネットが普及すると、その流れに拍車がかかり、日本人のライフスタイル自体が大きく変化した。嗜好や趣味が多様化し、人々は、携帯電話、ゲーム、SNS、食事、趣味に金を使うようになり、服はファストファッションやアウトレットの商品、インターネット・オークションの古着で間に合わせるようになった。さらにZARA(西)、ギャップ(米)、H&M(スウェーデン)といった海外のファストファッションの日本上陸が競争を激化させた。
■大手アパレルにとって代わった「カテゴリーキラー」
しかし、作れば売れるというワンパターンのビジネスに30年以上もどっぷり漬かっていたアパレル・メーカーと百貨店の男たちは、時代の変化を読む感性が磨滅していた。その結果、かつて業界の王者と自他ともに認めたレナウンは2010年に中国山東省の民間大手繊維メーカー、山東如意科技集団の傘下に入り、2015年に虎の子のバーバリーのライセンス契約を失った三陽商会はリストラに次ぐリストラという荊の道を歩み、東京スタイルは姿を消した。
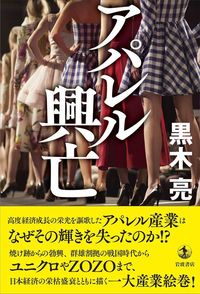
彼らが頼っていた百貨店も、カテゴリーキラー、ネット通販、ショッピング・モールなどの登場で、単独で生き残ることが難しくなり、2003年にそごうと西武百貨店が統合し、ミレニアムリテイリングが発足したのを皮切りに、続々と経営統合に走ったが、いまだに業績改善の兆しは見えない。
大手アパレルにとって代わったのが、ユニクロ、しまむら、青山商事といった「カテゴリーキラー」だ。特定分野(カテゴリー)の商品を大量に揃え、低価格で販売する小売業者(および製造小売業者)のことである。
かつてレナウン、樫山、三陽商会といった「百貨店アパレル」が上位を占めた業界の売上げランキングは、直近の決算では次の通り激変した。
①ファーストリテイリング(ユニクロ)2兆2905億円
②しまむら5460億円
③青山商事2503億円
④ワールド2499億円
⑤オンワードホールディングス2407億円
ユニクロの勝因と既存大手アパレル・メーカーの敗因は何だったのか? それを知るためには、「平成の怪物」であるユニクロのビジネスモデルを解明しなければならない。(後編に続く)
----------
作家
1957年、北海道生まれ。早稲田大学法学部卒、カイロ・アメリカン大学大学院(中東研究科)修士。銀行、証券会社、総合商社に23年あまり勤務し、国際協調融資、プロジェクト・ファイナンス、貿易金融、航空機ファイナンスなどを手がける。2000年、『トップ・レフト』でデビュー。主な作品に『巨大投資銀行』、『法服の王国』、『国家とハイエナ』など。ロンドン在住。
----------
(作家 黒木 亮)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
池袋西武の全面改装で危ぶまれる25年夏の開業 複雑な構造の建物に対応できず工事に大幅な遅れ
東洋経済オンライン / 2025年1月24日 10時0分
-
ユニクロ最新コラボ「2990円とは思えない質感」「カットソーなのに上品な印象」絶対に買い逃してはいけない5アイテム
日刊SPA! / 2025年1月22日 19時8分
-
「つぶれる百貨店」「生き残る百貨店」の明確な違い インバウンド需要の恩恵があるのはごく少数
東洋経済オンライン / 2025年1月20日 8時30分
-
繊細な彫金加工が魅力!厳選された中古クロムハーツを集めた期間限定POPUPが原宿で開催中
IGNITE / 2025年1月17日 17時45分
-
2025年、アパレル5大予測!激安EC隆盛がむしろユニクロ一強を促す理由
ダイヤモンド・チェーンストア オンライン / 2025年1月6日 20時59分
ランキング
-
1「間違った断熱」で電気代がかさむバカらしさ…職人社長が「一戸建てはエアコン1台で十分温まる」と断言する理由
プレジデントオンライン / 2025年1月30日 7時15分
-
22月電気料金、8社値上げ=21~54円、燃料高反映
時事通信 / 2025年1月30日 18時50分
-
3《笑福亭鶴瓶の冠番組が放送休止》「このタイミングでなぜ…」疑問にテレビ局広報が回答した“意外な理由”「一連の報道とは関係がありません」
NEWSポストセブン / 2025年1月30日 19時45分
-
4ロピア上陸「あおりを受けるのは、あそこだろう」…北海道のスーパー勢力図に荒波
読売新聞 / 2025年1月30日 10時26分
-
5中国AI「DeepSeek」、究極の後追い戦略の破壊力 世界最先端に匹敵する性能を低コストで実現
東洋経済オンライン / 2025年1月30日 9時20分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください










