中国はなぜ他国の目を気にせず外交ができるのか
プレジデントオンライン / 2020年3月2日 11時15分
※本稿は、ペドロ・バーニョス『国際社会を支配する 地政学の思考法』(講談社)の一部を再編集したものです。
■リーダー、取り巻き、一匹狼
世界中のどんな学校にも、小さな集団を仕切る生徒が存在する。その子は、クラスの、あるいは学年全体の支配者としてよく知られ、学校中の生徒から敬われ、恐れられている。
特別な影響力を持つ子どもは、その集団にできるだけ高潔な振る舞いをするよう促し、思いやりのある行動をとるように導くこともできるはずだ。だが往々にしてリーダーとなる子どもは、乱暴な行動を扇動しがちで、教師の知らないところで校則を破るようほかの子に強要することも多い。ひどい場合は、身体的に弱かったり、能力や魅力に欠けると判断されたりした子どもを、精神的に、ときには身体的に攻撃することもある。
通常、そういうリーダーの周りには取り巻きがいる。リーダーの近くにいることで、自分は守られたい、認められたいと考える子どもたちだ。彼らは、自分に欠けている能力や強さを求めてリーダーに近寄っていく。たとえ自我の一部を失ったとしても、自分になんらかの地位が与えられて特別扱いしてもらえるおべっか使いの随行団の一員になるほうを選ぶのである。
一方、リーダーの影響力やグループ全体のプレッシャーに抵抗しながら、まずまずの学校生活を送る子どもたちもいる。ある程度の力を持っていても、派閥はつくりたくないとか、影響力ある立場にはなりたくないと思うタイプの子たちだ。彼らは自分を大切にし、自分らしく生活できれば満足であり、仲間に対する不適切な行動にはかかわりたくないと考える。状況によってはそのとき力を持っている者と一時的に手を組むこともあるが、基本的にはどこにも属さずマイペースでいたいと願う。
■さまざまな共同体に共通する図式
さらに、ここまでに挙げた類型に当てはまらないタイプの生徒もいる。どんな集団とも距離を置き、好ましいものであれそうでないものであれ、どんな活動にも参加しないと決めている子どもたちだ。かたくなな態度をくずさず、誰かに馬鹿にされようものなら過剰に反応する。
こういう図式が見られるのは学校に限らない。たとえば軍隊、刑務所、職場など、構成メンバーが多くの時間をともに過ごさなければならない共同体であれば、どこにでも当てはまる。世界的な意思決定において、大小さまざまな影響力を持つ強国がせめぎあう国際社会においても、まさに同じことがいえるのではないだろうか。
■地政学の大原則は「偽善」である
国際政治ほど偽善的で残酷なものはない。各国は自国の利益だけを考えて政策を練り、それを実施する。だが、利害関係はうつろいやすく、つねに変化する。しかも、ある国にとっての利益は、他の国々にとってはほとんど、いやまったくといっていいほど関係がないものだ。
国内に目を向けてみると、国内政治もまた無慈悲で近親憎悪的であり、政治的ライバルに対してはまったく敬意が払われない。政治家たちは、相手の力を削(そ)ぎ、相手を権力の座から追い落として自分がそのポストに就くためであれば、どんな手でも使おうとする。それでもなお、どんなに異なる主張を唱えようが、政治家集団というものが追い求めるのは、共通の目的、共通の利益、すなわち“国民と国家の幸福rdquo;であるはずだ。違うのは、集団の利益や幸福を解釈する際のアプローチだけである。
ところが地政学の舞台である国際領域においては、野蛮な行為を思いとどまらせることができる共通目的など存在しない。少なくとも永続的な共通目的はなく、国同士を結びつけるわずかな絆を保つのは難しい。利害が共通すると思われたとしても、それはあくまで一時的なものだ。同盟や友好関係はもとより、敵対関係ですらつねに矛盾をはらみ、驚くほどの速さで関係が変わっていく。つねに競争が存在し、各国は、あちらこちらに働きかけては自己の利益を最優先させるための突破口を開こうと躍起になっている。
気候変動のように、どんな国にも共通する問題への取り組みですら、現実には、各国の関係を深めるのに役立ってはいない。なぜなら、現代の特異な環境においてさえ、各国は自己の利益しか見ていないからだ。
■大国ほど他国の要求に無頓着
さらにいうと、国家が強大であればあるほど、他国の要求については配慮しなくなる。馬鹿馬鹿しいと思われるかもしれないが、地球外生物の侵略といった脅威でもなければ、各国が手に手をとって人類全体の利益のために行動することはできないのかもしれない。これまでどの国も、直接的にせよ間接的にせよ他国に害をおよぼすかもしれないとはっきりわかっているときでさえ、自国だけを見て、自国の利益のために行動してきた。そういう状況はこれからも続くだろう。
強者が支配し、方向づけ、ルールを決めてきた国際関係とは、“高度の偽善”にもとづくものである。軍事史を専門とする歴史家マイケル・ハワードはこの偽善を次のように表現している。「平和維持について最大の関心を示す国こそが、往々にしてもっとも多くの兵器を備えている」
■多くの国が進んで大国の庇護を求める理由
「強者は望むことを行い、弱者は強者の横暴に苦しむ」
古代アテネの歴史家トゥーキュディデースはこう述べた。世界にはいくつもの強国が存在するが、世界の意思決定における影響力は国家によって異なる。国家は、基本的に2つの種類に分けられる。支配者国家と被支配者国家だ。
支配国は、地域規模、または世界規模でその支配力を行使する。被支配国はおおむね直接的に支配され、さまざまな形(軍事、経済、文化、科学技術等)で服従し、否応なしに、ときにはあきらめをもってその状態を受け入れる。必要であれば、相手は重要国だから、または手ごわい国だからという理由で、より強大な権力を持つ国の属国となることもある。
理由はどうあれ、自身が強大であると感じていない国々――核兵器を備えているかどうかが、そのはっきりとした分かれ目となる――は、少なくとも理論上は安全と特権を保障してくれる強大国の傘下に入ろうとする。核の力がそうさせるのであり、純粋な戦略的手段ということでいえば、国連安全保障理事会(UNSC)の常任理事国も国際的制裁の対象と仮定された国を支配下に置いている。
例として挙げられるのが、中国が、スーダンおよび同国のオマル・アル=バシール大統領に対してとった行動だ。ダルフールで起きた暴力事件の結果、2009年3月に人道に対する罪と戦争犯罪で国際刑事裁判所から逮捕命令が出されたにもかかわらず、バシールは大統領の地位にとどまっている。彼は、中国の庇護のもとにいるうちは自分の地位が安泰であることをわかっているのだ。
■大国が持ちかけるウィンウィンの「サービス」
中国政府は他の国々とさまざまな交渉をする際にも、このように自分も得をしながら相手の立場を守るというウィンウィンの「サービス」を持ちかける。たとえばスーダンとの関係では、このサービスと引き換えに同国の原油と耕作可能地を手に入れた。中国は、これまで植民地政策をとってきた強国ではなかっただけに、とくにアフリカでは、他の競合国のような不信感を抱かれにくい。
力の弱い国が好戦的な国の攻撃を受け、頼れる第三国の支援を受けざるをえなくなった例として、シリアが挙げられる。シリアのバッシャール・アル=アサド大統領は、米国とその地域的・国際的な同盟国の支援を受けた反乱軍に押されてその勢力が不安定になり、政権を失わないためにロシアの支援を受け入れざるをえなかった。ロシアはロシアで、自国の利益を追求していた。
そもそも自らは地域的・国際的に十分な影響力や支配力を備えていないと考えている国は、地政学的影響力を得るために他国と連携する。その理由については、プロイセン首相(1862年~1873年)とドイツ首相(1871年~1890年)を歴任したオットー・フォン・ビスマルクの次の言葉が端的に表している。「自分たちだけで祖国も利益も守れると考えて完全に孤立する民族はやがて、他国の影響力に圧倒されて消滅するだろう」。
■従属国家の悲哀とリスク
そうした連携が行われると、従属する立場にある国家は、たとえ世界的に見れば中程度の勢力があったとしても、連携した巨大勢力によって自国の利益とはまったく関係のない戦闘行為に引き入れられてしまう恐れもある。その結果、守るべき自国の利益など何もない遠隔地に自国の軍隊を派遣しなければならなくなる。
一方、目下の統治者に気に入られることばかり考えている理論家はつねにいるもので、そういった連中が後付けで、その戦闘は“先制防衛”だったとか、世界規模の危機には孤立無援で取り組めないとか、(あたかもその地域だけが人権侵害されているかのように)人権擁護のためだったとか、あるいは民主主義を普及させるためだったなどといって、軍隊派遣を正当化してくれる。
結局、こうした“傭兵派遣国家”が手に入れたのはまったく必然性のない新たな敵だけだったということも少なくない。たとえば、自国の領土がテロに襲撃される──遠方の派遣先で、戦術にテロリズムを含むような集団と対立したり、そうした集団になんらかのダメージを与えたりした場合にはよく起こることだ──というシナリオから、目的が曖昧な軍事遠征を行ったことに対して自国民の支持が得られず社会騒乱となり、ひいては軍隊派遣の責任者であった政府の転覆につながるシナリオまでが考えられる。
■支配を拒めば「反逆者」か「無責任」
数は少ないが、前述の分類のいずれにも当てはまらない国家もある。そのなかには、支配者になるほどの力はないものの、どんな形でも支配されたくないためにあえてどちらの側にもならない国々もある。
そういう国は既存の国際システムにとっては“反逆者”となる。2015年月日に発表された米国の「国家安全保障戦略」〔訳注:歴代の米政権が安全保障政策を連邦議会に向けて説明するための公式文書〕では、それまで“反逆者”と形容されていた国々が“無責任”と呼ばれるようになった。今日ではこのカテゴリーに北朝鮮も含まれている。
だが、学校の支配者グループから離れて過ごしたがる子どもと同じように、国家間の権力ゲームに参加することを拒んで独自の政治・社会システムを適用しようと考える国家が危機にさらされているのは間違いなく、そういった国は孤立無援で自国を存続させていかなければならない。
サウジアラビア、トルコ、エジプト、イランといった国々は、また別の少数派グループに属する。すでにそれぞれの地域のリーダー格であり、自国の経済発展と他者への影響力の行使は続けたいと望んでいるものの、曖昧な関係を保っている超強大国の感情を害さないために、いまよりグローバルな権力を持つことは賢明ではないと考える国々だ。もちろん彼らは、地政学的に従属する側のグループに追いやられるつもりもない。
■「戦略的プレーヤー」と「地政学的回転軸」
米国の政治学者で大統領の顧問や補佐官を務めたズビグニュー・ブレジンスキーも同じような区分をしている。彼は地球上には「戦略的プレーヤー」と「地政学的回転軸」が存在するとした。
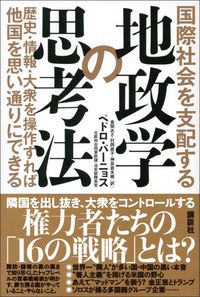
前者には、国境を越えて権力や影響力を行使し、地政学的問題の現状を変えるための能力と国家的意図を持つ国々がある。「戦略的プレーヤー」」はつねに力を持っている重要な国々だが、このような特徴を持つ国がすべて戦略的プレーヤーであるとは限らない。権力ゲームに参加するもしないも、支配者層の意思次第だからだ。
一方、「地政学的回転軸」の国家としてはウクライナ、アゼルバイジャン、韓国、トルコ、イランなどが挙げられる。地理的に重要な位置にあるおかげで、他国が自国の資源や特定の場所に接近しようとしても、それを制限することができるのである。
----------
1960年生まれ。スペイン・サラゴサの陸軍参謀学校、および陸軍士官学校卒。マドリード・コンプルテンセ大学で安全保障学の修士号を取得。スペイン各地で部隊指揮官としての経験を積んだ後、陸軍参謀本部の分析官、ストラスブールの欧州合同軍における防諜部門のリーダー、スペイン国防省参謀本部の地政学分析主任などを歴任。現在も地政学、戦略、防衛、セキュリティ、インテリジェンス、テロリズム、国際関係のアナリストおよび講師として活躍。
----------
(スペイン陸軍予備役大佐 ペドロ・バーニョス)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
中国の「言いなりになることは…」大国の間で揺れる南の島・フィジー ランブカ首相が語る“中国との距離感”
TBS NEWS DIG Powered by JNN / 2024年7月21日 6時30分
-
廃墟タワマンが立ち並び経済苦境は深刻に…追い詰められた習近平政権が世界を敵に回す"禁じ手"とは
プレジデントオンライン / 2024年7月20日 9時15分
-
英で欧州政治共同体首脳会議 スターマー英首相、安保などテコに「欧州回帰」打ち出す
産経ニュース / 2024年7月18日 20時1分
-
訪朝しても、金正恩と「ブロマンス」しても、プーチンの活路は開けない
ニューズウィーク日本版 / 2024年6月27日 16時14分
-
米国が中国から学べること―米国際政治学者
Record China / 2024年6月26日 5時0分
ランキング
-
1システム障害、世界で余波続く=欠航、1400便超
時事通信 / 2024年7月21日 22時45分
-
2コメが品薄、価格が高騰 米穀店や飲食店直撃「ここまでとは」
産経ニュース / 2024年7月21日 17時41分
-
3円安は終わり?円高反転4つの理由。どうなる日経平均?
トウシル / 2024年7月22日 8時0分
-
4なぜユニクロは「着なくなった服」を集めるのか…「服屋として何ができるのか」柳井正氏がたどり着いた答え
プレジデントオンライン / 2024年7月22日 9時15分
-
5ウィンドウズ障害、便乗したフィッシング詐欺のリスク高まる…復旧名目に偽メール・偽ホームページ
読売新聞 / 2024年7月22日 0時0分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください











