私財20億円を研究者に与えて消えた「戦前の富豪」の生き様
プレジデントオンライン / 2020年3月1日 11時15分
与那原恵(よなはら・けい)/1958年東京都生まれ。96年、『諸君!』掲載のルポで編集者が選ぶ雑誌ジャーナリズム賞作品賞を受賞。2014年、『首里城への坂道 鎌倉芳太郎と近代沖縄の群像』で第2回河合隼雄学芸賞、第14回石橋湛山記念早稲田ジャーナリズム大賞を受賞 - 撮影=プレジデントオンライン編集部
■武器商人の父から巨万の富を継いだ「戦前の富豪」
「赤星(あかぼし)鉄馬(てつま)」という名前を聞いて、「ああ、あの人か」とすぐに分かる読者は多くないだろう。
赤星鉄馬——明治15年生まれ。薩摩出身の父親の弥之助は武器商人として日清戦争の頃に巨万の富を稼いだ。鉄馬はその富を継いだ人物で、知る人ぞ知る「戦前の富豪」だ。
鉄馬は吉田茂や白洲正子の父でもある実業家の樺山愛輔、三菱財閥の4代目・岩崎小弥太といった重鎮と深い親交を持ち、日本初の学術財団「啓明会(けいめいかい)」を設立している。また、釣りを生涯の趣味とした彼は、大正末期に芦ノ湖にブラックバスをアメリカから移入したというエピソードも持つ。
だが、赤星鉄馬の存在は、これまで日本の近現代史の中でほとんど知られてこなかった。なぜなら、赤星は趣味から派生したブラックバスの研究書を除いて、日記や回想録といった文章を一切書き残さず、インタビューにも応じなかったからである。
謎に包まれた生涯を6年にわたって追い、昨年11月に評伝『赤星鉄馬 消えた富豪』を上梓した与那原恵さんは、この「消えた富豪」にどこで出会い、どうやって実像に迫ったのだろうか。
■焼失した首里城の「かつての姿」を記録していた在野研究者
与那原さんが赤星鉄馬という名前を知ったのは、河合隼雄学芸賞などを受賞した前著『首里城への坂道 鎌倉芳太郎と近代沖縄の群像』(中公文庫)を執筆中のことだった。
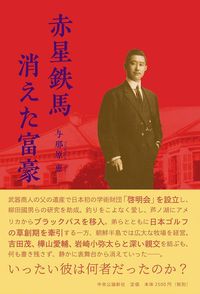
鎌倉芳太郎は大正末期から昭和にかけて琉球芸術の調査を行い、琉球文化全般の膨大な史料を残した人物だ。彼はカメラとガラス乾板を携えて大正期から沖縄本島・離島、奄美大島各地を巡り、風景や建造物、工芸品など千数百点の写真を撮影した。それはいまも当時の沖縄を記録した貴重な画像となっている。
とともに旧琉球王家を中心に貴重な古文書を収集、筆写したり、衰退しつつあった「紅型」型紙を収集したりした。鎌倉が登場した時期の沖縄ではのちに「沖縄学」と名付けられる研究が始まっていたが、本土では注目されておらず、彼の仕事は現在に至るまで総体的な「琉球文化研究」の最も重要な仕事であり続けているわけだ。
例えば、昨年10月末に火事で焼失した首里城は、大正末、取り壊しが決定していたが、それを阻止できたのは鎌倉の働きかけもあったからだ。国宝指定されたものの沖縄戦で失われ、戦後は琉球大学の建設によって、城壁などの一部がかろうじて残されているだけだった。
■無名の在野の研究者に2000万円を出した富豪がいた
その首里城が復元されたのは鎌倉没後の1992年。以後、首里城は四半世紀をかけて沖縄を象徴する文化遺産として受け入れられていったが、復元作業、とりわけ「色」と「かたち」の再現は鎌倉の遺した史料がなければ不可能だったと言われる。今後、首里城の再建が進められるとすれば、彼の史料は再び欠かせないものとなるはずだ。
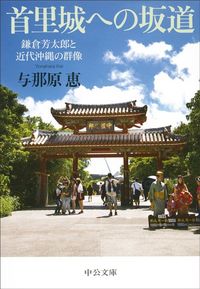
およそ10年前、その鎌倉の足跡を取材していた与那原さんは、彼が大正12年に「啓明会」という学術財団から多額の資金提供を受けている資料を発見した。
「香川で生まれた鎌倉芳太郎は、東京美術学校で学んだ後に沖縄に美術教師として赴任しました。その時に見た風景とともに琉球の歴史と文化に衝撃を受け、沖縄の人たちの協力を得ながら研究に着手しました。内地に戻ってから美校の研究生をする中で、さらなる研究を志しました。よって、その頃の彼は全くの無名の青年、まだ実績のない在野の研究者にすぎなかったんです」
「『啓明会』という学術財団は、その彼が行おうしていた「琉球芸術調査」に対して、今のお金に換算して3回にわたり総額約2000万円もの調査費を支給していた。大正12年というのは琉球芸術に注目する本土の人は皆無で、柳田国男が2年前に沖縄に来ましたが、『海南小記』発表以前という時期です。民俗学的な関心は向けられ始めていても、琉球を芸術として捉える人はいませんでした。そのような時代に、無名の在野の研究者に2000万円を出した富豪がいた、ということがすごく不思議だったんです」
■国内の全研究助成費の五分の一を占めるほど大きな存在感
啓明会は基礎的な文献や資料の収集、研究に重きを置いて助成活動を行っており、学術界の重鎮のほか無名の研究者や女性研究者も支援するなど、当時においてかなり先進的な取り組みをしていた。〈近代日本の学術研究の基礎を築いたといってよく、設立当時は国内の全研究助成費の五分の一を占めるほど大きな存在感を示した〉という。
その啓明会の記録を調べてたどり着いたのが、同会は赤星から100万円(現在の約20億円に相当)の提供を受けて設立された財団という事実だった。だが、彼は財団の名に「赤星」の名を使用させず、運営にも親族を一切かかわらせなかったため、すぐには名前が出てこなかったのである。

「私はフリーランスの書き手としてずっと仕事をしてきたので、在野の研究者にこれだけの調査費を出してくれる存在の有り難さを身に染みて知っています。でも、気になって調べても鎌倉に資金を提供した赤星鉄馬という人物は謎のままで、資料には具体的なことが何も書かれていない。いったいこの人は何者なんだろう、とがぜん興味が湧いてきたんです」
では、与那原さんはそんな赤星の生涯をどのように描いたのだろうか。
■「明治人」樺山愛輔、吉田茂、野口英世との邂逅
本書は赤星鉄馬をめぐる「明治人」たちの群像劇としても知的好奇心をくすぐられる一冊だが、一方で自らは何も語り残さなかった一人の男の実像に、与那原さんが徐々に迫っていく手法そのものにも読み応えがある。
前述の通り、赤星鉄馬は明治15年に東京で生まれた。明治34年に中学を卒業後、アメリカにわたってニュージャージー州の名門校へ。その最中に父・弥之助が死去したがペンシルベニア大学に進学している。8年間の留学生活を終え帰国すると、家督を継いで銀行の設立や朝鮮での大規模農場「成歓牧場」などの事業を興した。啓明会の設立は大正7年、父親の遺した国宝級のものも含む大量の美術品を売却して得たうちの5分の1を財団設立のために提供したという。

与那原さんは赤星が青春時代を過ごしたカリフォルニアや朝鮮半島の農場跡などを歩き、膨大な資料によって彼の過ごした「時代」を描いていく。
樺山愛輔や吉田茂、フィラデルフィアに同じころにいた野口英世、大倉喜八郎や渋沢栄一ら財界の大物たち――。
■自らは何も書き残さなかった彼自身の「輪郭」
同時代を生きた多くの人々の視点を借り、赤星の見ていただろう風景を再現することを通して、自らは何も書き残さなかった彼自身の「輪郭」を浮かび上がらせていくのである。
「例えば、鉄馬は孫文や野口英世とも交流があったのかもしれないという勘が働きましたが、実際に赤星の名前を見つけ出すためには、孫文の会った日本人名簿や野口の書簡集などを丁寧に読んでいく必要がありました。当時の電話帳から邸宅のあった麻布鳥居坂の近所に住んでいた著名人を割り出したり、『この時代なら革命家の宮崎滔天(とうてん)とも接点があったのでは』と思って滔天の方から調べていくと、タイ・バンコクで滔天と交流し、当地で写真館を開いた初の日本人磯長海洲が鉄馬の従兄であった事実を見つけ出したり。評伝を書きあげるまでに6年の歳月がかかりましたが、昔の資料や写真、新聞などを読みながら、自分でいくつか仮説を組み立てて、それを一つひとつ自分でつぶしていく作業の繰り返しでした」
また、アメリカやヨーロッパ、農場を経営した韓国など、彼の旅を追いかけて行く際も、クック社の資料と世界地図を照らし合わせながら、「この頃には鉄道があったんだな」という具合に当時の風景を忠実に再現することを心がけた。
「それは鉄馬の精神がアメリカへの留学や世界一周の旅の中で、どんなふうに変化していったかを想像する上で欠かせない作業でした」
■高額の寄付には世間から厳しい声が上がることもあった
赤星鉄馬が自らについて語らなかったのは、父親が武器の取引で巨万の富を得たこと、その財産を無条件に継ぐ立場にいたことなどが理由としてあげられる。
例えば、大正3年に日本海軍高官への贈賄が発覚し、薩摩閥と海軍の関係が問題視された「シーメンス事件」で、鉄馬は当時の新聞や世論から大きな非難を浴びた。事件の先例として弥之助の事例が取り沙汰され、その資産を継いだ鉄馬に批判の矛先が向いた形だった。
「鉄馬は父親から継いだ資産を守りながら、欧米で身につけた寄付文化を日本でも実践したかったのでしょう。しかし、高額の寄付には世間から厳しい声が上がることもあった。そのなかで『良かれと思って寄付しただけでは、日本社会には受け入れられない』ということを知ったのだと思います。そうして自らの姿を消し、活動の痕跡を残さないように生きるようになっていく彼のふるまいには、富豪であったが故の孤独や寂しさ、社会の荒波を超えていくつらさを感じました」
そうして与那原さんは赤星鉄馬という「消えた富豪」について、取材の過程で次のような理解を得ていく。
〈赤星鉄馬は一代目が築いた財産を放蕩(ほうとう)した典型的な「二代目」だったという見方もあるかもしれない。けれど私には、父弥之助が築いた資産を少しずつ失っていくことが、彼の一生を懸けた「事業」だったように思えてならない。そうして自分の姿を消していく――、意識的にそれを選んだのではないだろうか〉
■欧米の学術財団から「基礎研究」の大切さを深く理解した
そして、鉄馬の「事業」の一つであった学術財団「啓明会」の功績を書き残しておきたいと思うようになったと話す。

「明治以前の学問というものは、藩がお抱えの学者を重用するという世界でした。鉄馬のルーツも薩摩藩で活躍した天文学者家系です。アメリカに留学した鉄馬は、親戚であり兄のように慕った樺山愛輔もアメリカとドイツに留学しているので、欧米の学術財団の動向を実際に現地で目の当たりにしたのでしょう。そのなかで『基礎研究』というものの大切さを深く理解していったのだと思います。そうした啓明会の価値観と功績を知れば知るほど、『ブラックバスを日本に持ち込んだ人』としてだけしか知られていない鉄馬のイメージを、どうにかして変えたいという気持ちが芽生えてきました」
啓明会は在野の研究者も含む多くのテーマを助成したが、その中の一人であった鎌倉が当時の調査を約1000枚に及ぶ論文と写真集(『沖縄文化の遺宝』)として結実させたのは、啓明会の助成から約60年後の1982年だった。
■すぐに成果が出なくても、重要な研究はある
「啓明会はせっつくこともなく、鎌倉芳太郎の仕事を待ち続けたわけです。それが現在の首里城の再建に欠かせない基礎史料を生んだ。調査や研究において、彼のような在野の人間が成す力の大きさを表す一例でしょう。最近は研究費といえばすぐに成果の出るもの、あるいはビジネスにつながるものばかりが重視される風潮がありますが、彼の仕事のように長い時間をかけて結実したり、次の世代になって花開いたりする重要な研究もある」
「本来、研究費の助成とは、そういう分野にもきちんと目を向けるべきですし、そうした助成の考え方が新しいものを生み出していく面もあるはずです。その意味で、鉄馬の作った日本最初の財団である啓明会が、そのような姿勢を強く持つ団体であったことの意義は大きいと思うのです」
「もう一つ付け加えれば、鉄馬は転居した吉祥寺にアントニン・レーモンド設計の邸宅を1934年に竣工させましたが、この建物が現存しており、昨今武蔵野市が購入・活用する方向で検討されています。建築から86年を経て、再び赤星鉄馬の存在が注目されているのが本書の刊行と重なったのは偶然ではないのかもしれません」
与那原さんはその啓明会の功績と歴史的な意味を、これまで日本近現代史にほとんど登場しなかった「消えた富豪」の名前ともに記録した。想像力を駆使したその粘り強い取材・調査を結実させた本書からは、「人物評伝を書く・読む」ということの醍醐味が伝わってくるはずだ。
----------
ノンフィクション作家
1979年生まれ。2002年早稲田大学第二文学部卒業。2005年『ぼくもいくさに征くのだけれど 竹内浩三の詩と死』(中公文庫)で第36回大宅壮一ノンフィクション賞受賞。著書に『こんな家に住んできた 17人の越境者たち』(文藝春秋)、『豊田章男が愛したテストドライバー』(小学館)、『ドキュメント 豪雨災害』(岩波新書)などがある。
----------
(ノンフィクション作家 稲泉 連 聞き手・構成=稲泉 連)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
琉球瓦、文化財保存技術に 八幡昇さんと琉球瓦葺技術保存会 文化審議会が答申
沖縄タイムス+プラス / 2024年7月19日 17時0分
-
【(一財)沖縄美ら島財団】沖縄未来コンサバターズ~高校生が学ぶ琉球漆器修理の技~
PR TIMES / 2024年7月18日 16時45分
-
沖縄発スキンケアブランドSuiSavon-首里石鹸-が2024年7月20日(土)に東京・町田市 グランベリーパークに直営店をオープン
PR TIMES / 2024年7月16日 18時15分
-
【首里城公園】親子で楽しめる「夏休み体験イベント 2024」開催!!
PR TIMES / 2024年7月3日 14時15分
-
沖縄発祥ブランドによるコラボレーション“記憶に残る香り”を創造する『株式会社いいにおい』×沖縄発スキンケアブランド『SuiSavon-首里石鹸-』オリジナルの香りによる店舗空間演出を開始
PR TIMES / 2024年6月26日 16時15分
ランキング
-
1システム障害、世界で余波続く=欠航、1400便超
時事通信 / 2024年7月21日 22時45分
-
2円安は終わり?円高反転4つの理由。どうなる日経平均?
トウシル / 2024年7月22日 8時0分
-
3なぜユニクロは「着なくなった服」を集めるのか…「服屋として何ができるのか」柳井正氏がたどり着いた答え
プレジデントオンライン / 2024年7月22日 9時15分
-
4イタリア人が営む「老舗ラーメン店」の人生ドラマ 西武柳沢「一八亭」ジャンニさんと愛妻のこれまで
東洋経済オンライン / 2024年7月22日 11時30分
-
5コメが品薄、価格が高騰 米穀店や飲食店直撃「ここまでとは」
産経ニュース / 2024年7月21日 17時41分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください











