「東宝」vs「Netflix」vs「Amazonプライム」最後に勝つのは誰だ!
プレジデントオンライン / 2020年3月16日 15時15分
■監督は母、プロデューサーは父
映画のプロデューサーとは、才能に奉仕する仕事です。
たとえば、北野武さんが監督デビューを飾った『その男、凶暴につき』。この企画はもともと、深作欣二監督が撮る作品に武さんが出演する、という話から始まっていたんです。ところが、打ち合わせを進めるうちに深作監督と武さんの間で、どうしても折り合いがつかない部分が出てきてしまった。深作監督が「自分が降りるか、武さんが降りるかだ」と言い出すまでに事態が深刻になったときに、武さんが「俺が監督をやりますよ」と宣言したんです。
当時、武さんは芸人としてはとても有名だったけれど、監督は未経験。だから、僕は内心とても驚いたんだけど、武さんにどう撮るのか具体的に聞いてみると、本を読んだ段階で画が浮かんだ、と言うんです。話を聞くにつれ彼の本気度が伝わってきて、私も、武さんの構想に惚れ込んでいった。とはいえ、出資元は「監督が変わるならお金は出せない」となるわけです。
プロデューサーが重要になるのは、こういうタイミングです。僕としてはもう武さんに可能性を感じていて、なんとか彼の監督作品を世に送り出したいと思っている。情熱に突き動かされながら、なんとか人々に作品が届くところまでの道をつくっていくことが、プロデューサーの仕事の醍醐味なんです。
作品が子どもだとすると、監督は母親で、プロデューサーは父親のようなもの。作品を可愛がるのは監督もプロデューサーも同じ。でも、対社会の態度が違うわけです。「あばたもえくぼ」という言葉があるように、監督は作品を無条件に溺愛し、常に寄り添っていていい。
■「世界のキタノ」の誕生の瞬間
しかしプロデューサーは、社会と作品の間に立って、あばただとわかっていながらも、「これはえくぼです」と言わなくてはいけない。作品が社会に存在できるように矢面に立って戦っていくのが、プロデューサーの仕事。あのとき僕は、武さんの監督としての可能性にすべてをかけて、資金集めに奔走した。大変だったけれども、それが「世界のキタノ」の誕生の瞬間だったわけです。

このように奇跡のような結果を出せる人というのは、最後まで自分の価値観を信じきれる人だと僕は思っています。プロデューサーはその価値観に常に寄り添いながら、その目的に向かって最短距離で直線を引くしかない。大切なのは、作品に対して深い愛情が持てるかどうか。それが「才能に奉仕する」ということなんです。
才能に奉仕できるプロデューサーというのが何人も現れてくれば、映画業界が盛り上がっていくはずなんです。映画というのは、たくさんの人間が集まって、最も人間くさいところで1つの商品を作り上げるということだから、とにかく情熱が必要になってくる。前のめりでパッションを持って作業できるか、それとも萎縮してしまうか、そこが大きな差となります。
ところが昨今では、すでにベストセラーになっている作品を原作にしたり、スーパーアイドルによる映画化という組み立てをしたりするプロデューサーも目につきます。それでは、監督や作品が発掘される機会が減り、日本の映画業界は衰退に向かってしまいます。
■柔軟性と責任感で業界の閉塞感を打破
ほかにも、日本映画界は複数の課題を抱えていると言われています。
そのひとつに「NetflixやAmazonプライムなど、新しい動画閲覧プラットフォームが台頭する今、映画業界は大丈夫なのか?」という声がある。動画配信が始まったことで業界が様変わりするのは当然のことです。いろいろな側面があるけれども、まずは競争力。2019年話題になった『全裸監督』にしても、ボタン1つで全世界に配信されていく。海外進出への垣根が低くなっている分だけ、作品としての競争力を上げないとダメだということです。
同時に、ボタン1つで全世界に発信されていく利点もあります。なぜなら、今、映画には、見るべき人のところにちゃんと届いていかないようなハンディキャップが存在してしまっている。はじめに、配給会社の経済力。次に、マーケット力、宣伝力と繋がっていく。その一連の流れにおいて、日本映画界は全体的に勢いを失ってしまっています。いい作品さえ作ればちゃんと届くんだなんていうことは、今やもう、夢のまた夢。だからこそ、一瞬で世界に広がっていく動画配信は、いい作品が見るべき人に届くための“方舟(はこぶね)”のような価値があると思います。
■『カメラを止めるな!』の大ヒット
近年の事例で注目しているのは、『カメラを止めるな!』の大ヒットです。この作品は予算300万円からスタートし、2017年11月から都内で単独劇場公開したところ、話題が話題を呼んで世に広まった。いち早く可能性を見出した東宝が『カメラを止めるな!』をグループの映画館で上映し、圧倒的な興行収入を挙げ、18年を代表する話題作となった。
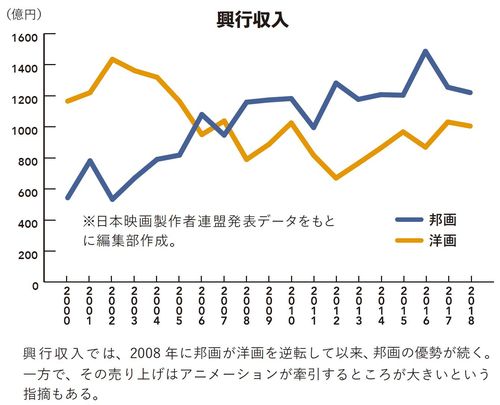
重要なのは東宝という企業に「自分たちが変わらないと業界がダメになる」という意識があったことと、結果を出せたことだと私は考えます。現場の意見を理解し「やってみろ」と言えるトップがいた。そして、やる以上は当たるように持っていく。この成功は、作品自体の実力というよりも、小さなインディーズ映画の可能性を信じて、東宝がマーケットに出して数字を上げてみようとしたことにあると見ています。1つの映画の番狂わせ的な奇跡というものに対しての面白味を、映画業界に対する危機感と愛情を持って煽ったということです。
この大ヒットを契機に、日本の映画業界全体に、マイナーな映画でもいいものは届けていこうよ、というムーブメントが生まれ始めた。伝統のある業界や大企業ではトップに対する忖度が働いて閉塞感が出がちですが、今の日本映画界には柔軟性が重要なんです。
『カメラを止めるな!』に限らず、東宝のシネコンではその融通性を最大活用し、マイナーな映画でもどんどん上映するようになっています。入場料金を取っても失礼ではないというクオリティを持っていれば、東宝は受け入れますという姿勢を取っている。松竹も、グループの映画館であるピカデリーで独自の推薦映画を選ぶブランドをつくってみたり、マイナーな映画を上映するなど、柔軟になってきていますよね。
配給会社が責任感というものを持ち、その中にマイナーな映画だって育ててみせるという思いを持ってくれるのであれば、日本映画界の将来は明るいんじゃないかと僕は思っています。
----------
映画プロデューサー
1954年生まれ、『ハチ公物語』『遠き落日』『226』などヒット作多数。『うなぎ』(今村昌平監督)で第50回カンヌ国際映画祭パルム・ドール受賞。94年『RAMPO』を初監督。現在は、京都国際映画祭などのプロデュースも行う。
----------
(映画プロデューサー 奥山 和由 構成=吉田彩乃 撮影=熊谷武二 写真=京都国際映画祭)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
池松壮亮、“母校”で未来の映画界を担う学生たちにエール!「ルールに縛られずに、新しい時代を作ってほしい」
映画.com / 2024年7月25日 21時0分
-
齊藤京子、TikTokと東宝による縦型映画祭グランプリ受賞記念作主演に! 審査員は三吉彩花、しんのすけら
クランクイン! / 2024年7月23日 12時0分
-
「ぼくのお日さま」奥山大史監督×池松壮亮×越山敬達×中西希亜良がカンヌで語った、忘れ得ぬ体験【オフショット多数】
映画.com / 2024年7月22日 12時0分
-
「アニメ頼りの日本映画」がアジアで直面した現実 アジア最大規模のジャンル映画祭で見えた課題
東洋経済オンライン / 2024年7月19日 13時0分
-
「NN4444」が10以上の国際映画祭に選出。8月9日(金)より下北沢K2含め3都市にて順次再上映決定。
PR TIMES / 2024年7月16日 16時15分
ランキング
-
1パリ五輪〝初老ジャパン〟活躍でわく疑問「40歳って初老なの?」 皆がイメージする年齢は...
Jタウンネット / 2024年7月30日 21時0分
-
2スーパーの大胆な節電方法が話題 猛暑の中、飲料の冷蔵ショーケースを丸ごとオフに… ネットでは賛否の声
よろず~ニュース / 2024年7月31日 7時20分
-
3水道水はそのまま飲めない…令和の子育て世代、煮沸して飲む人増加 その背景には「水道管の劣化に対する不安も」
まいどなニュース / 2024年7月31日 7時20分
-
4藤原マキさん「私の絵日記」に米アイズナー賞…つげ義春さんの妻
読売新聞 / 2024年7月30日 18時55分
-
5夏は「ぽっこりお腹」に要注意!? その原因とケア方法を専門家が解説
ハルメク365 / 2024年7月30日 22時50分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください











