こんなときは「どうすれば遊べるか」を考えたほうがいい
プレジデントオンライン / 2020年4月9日 9時15分
※本稿は、為末大『新装版 「遊ぶ」が勝ち』(中公新書ラクレ)の一部を再編集したものです。
■スポーツの本質は「遊ぶ」ことにある
僕のツイッターにオリンピック強化選手とおぼしきアスリートから、心境を吐露するようなメッセージがときどき届く。そのメッセージを読むと、どれも苦しそうだ。「もう(重圧に)耐えられません」というような内容もある。
僕自身にも同じような経験があるので、その思いは痛いほどわかる。もし僕に言えることがあるとすれば、「難しいかもしれないけれど、問題をあまり真正面からとらえず、視点を変えるといいのではないか」という提案だ。たとえば「いま自分がこだわっている問題ってそんな大切なのか?」ということを問い直してみるのだ。
スポーツというと、険しい表情で練習を積み重ねるイメージが強いかもしれない。しかし、「陸上競技場」を英語で言えば、“playground”であるし、「スポーツをする」も英語ならば、“play tennis”“play baseball”と、“play”が使われることが多い。元をただせば、スポーツの本質は「遊ぶ」ことにあるのだ。スポーツを原点に返ってとらえ直すことで、見えてくる景色や気分が変わって、肩の力がスッと抜けるのではないかと思っている。少なくとも僕はそうだった。
■新しいことを生み出す人が持つ「余白」
遊びが必要なのは、スポーツだけではない。ビジネスにおいても、遊びを採り入れたほうが、時代の変化にうまく対応できるのではないだろうか。
仕事で経営者と会う機会が多いが、新しいことを生みだす人は、「余白」を持っているような気がする。余白とは何かと言えば、「遊び」である。
ビジネスだから効率を求められる部分は当然ある。そこは徹底するのだが、効率一辺倒ではないのだ。イメージとしては2割ぐらいは、“面白そう”とか“これがあったら楽しそうだな”と思ったことに着目してサーチしたり、体験したりしている。それが将来的に仕事になるかどうかはあまり重視しない。楽しそうだからやるという、本能的な動機だ。たとえて言えば、子どもが積み木をしていて、この上にもう一つ積み木を載せたら、どんな形になるだろうとワクワクしながら遊んでいる。そんな感覚に似ているだろうか。
■「夢中」になるとブレイクスルーが起きる
不確実性の面白さ。失敗したっていい。試行錯誤すること自体が楽しい。
遊びは、日常の仕事に追われて、固まりそうになっている発想を柔らかくして、新しいものが生まれる環境をつくってくれる。遊ぶことが、人の可能性を広げてくれるのである。遊びの何がすごいかと言えば、人を夢中にしてくれたり、我を忘れて没頭させてくれるからである。
陸上選手の頃を振り返っても、夢中で競技に取り組めているときに、それまでいくら努力してもできなかったことが、できてしまった経験がある。夢中というのは、立ちはだかっていた壁を一瞬にして突破できる力を与えてくれるのだ。しかも、そのとき競技の本質、深い部分に触れることができる。アスリートとして一つ上のステージに行けるのである。
「努力」よりも、「夢中」が勝るのだ。
仕事の世界でも同じではないか。遊びで夢中になることに身を置く中で、ずっと解決できなかった問題をブレイクスルーできるかもしれない。遊びを採り入れることは、じつに賢明な生き方であるということが、この本『新装版 「遊ぶ」が勝ち』を通して伝わるとしたら本望だ。
■苦しかった時、「楽しさ」を思い出させてくれた本
この本は、『ホモ・ルーデンス』(ヨハン・ホイジンガ)という、遊びを哲学的に考察した名著の内容を引きながら書いた。陸上選手として行き詰まった僕に、遊ぶことの大切さを教えてくれた愛読書なのだが、意外だったのは、茶の湯をはじめ日本人は遊び上手だったという記述である。そんな日本人の姿は、近代化する過程で薄れていく。
初めて『ホモ・ルーデンス』を僕が読んだのは20代中盤の頃だったろうか。日本代表というポジションがようやく定着した頃で、少しずつその重責を感じはじめていた。自分の陸上競技が自分だけのものではなくなり、みんなの夢と期待を背負って走っている。それはアスリートとしては誇らしくて、夢に描いていたことだけれど、でも実際に体験するとその責任が息苦しくもあった。
『ホモ・ルーデンス』に書いてある遊びの世界。それはまさに僕が競技を始めた頃感じていた世界で、そして現役の間中ずっと自分の内なるモチベーションを支えてくれたものだった。楽しいから走っている。走りたいから走っている。久しぶりにその感覚を、僕に蘇(よみがえ)らせてくれたのが『ホモ・ルーデンス』だった。
■ノルマに追われる社会で、いかに「遊ぶ」か
「遊び」と聞くと、大方の日本人は、真面目の対極だと感じてしまうけれど、実際には遊びは真面目と共存しうる。一所懸命に子どもは遊ぶし、大人も大真面目に休日の趣味の時間を過ごす。遊びは決してふざけることではなく、むしろ我を忘れて何かに熱中することだと僕は思っている。
大人の仕事が遊び化しにくいのは、目的があり、組織の都合があり、期限とノルマがあり、クオリティをある一定以上保たなければならないからだと思う。それは仕方のないことだろう。そしてこれまでの社会であれば、ある程度人が淡々と作業をこなすことで産業は成り立ってきた。
でも、イノベーションやクリエイティビティというのが大事だと言われる時代に入り、この「遊び感」がそれらに大きく影響しているのではないかと僕は感じている。生真面目にこれまでの文脈の延長線上に何かを積み上げていくだけでは、どうしてもイノベーションは起きにくいし、クリエイティビティも生まれにくい。
人間にしかできないことがこれから先の社会に求められているとしたら、僕は遊びの中にヒントがあると思っている。遊びで磨かれた五感的な直感、遊びを入れる感覚、楽しいという気持ち。
大人が遊び続けるのはとても難しい。社会から役割を与えられ、常に目的を問われ、ノルマに追われる社会の中で遊び続けることはとても難しい。でも、その中でどう遊ぶかというのが人間の知恵であり、また人間にしかできないことなのではないだろうか。
■人間は「何かを表現したい生き物」だ
僕の競技人生は30歳以降下り坂で、競技では思うような結果が出なかった。それでも自分自身の身体の仕組みを探る旅はとても興味深くて、終盤になればなるほど理解は深まった。そして何より、それは面白かったのである。
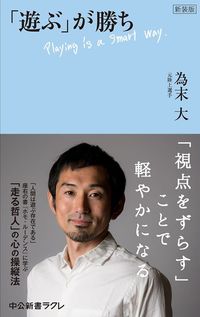
奇しくもさまざまなテクノロジーの発達で、人間にしかできなかった領域が少なくなってきている。この先に一体何が待っているのか。そして、そもそも人間とは何だろうか。人間らしいとはどういうことだろうか。
英語で遊びとは“play”と書く。演奏することも、演ずることも、競技をすることも、すべて“play”で表現される。おおよそ人が何かを表現することは“play”という言葉で括(くく)られている。
人間のありようそのものが問われる今、僕は遊びの領域にこそ人間らしいものを見ている。私たちは本来的に、何かを表現したい生き物で、そしてまた誰かの表現を受け取ることで、新たな表現が生まれる。
人間とは遊びたいもので、そして遊ぶことにより、人間はより人間らしくなるのだと僕は思っている。
----------
DEPORTARE PARTNERS 代表
男子400メートルハードル走の日本記録保持者、元プロ陸上選手。現在は各種媒体でコメンテーターとしても活躍中。
----------
(DEPORTARE PARTNERS 代表 為末 大)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
“パラ陸上界の顔”山本篤が現役引退、トップであることにこだわり続けた競技生活
パラサポWEB / 2024年5月31日 19時32分
-
「野球少年がメジャーリーガーになりたいと思うように東京パラに出よう!と思ったんですが」酒浸りの生活からアジア新記録を叩き出した義足のスプリンターのパリ〈パラ陸上 井谷俊介 〉
集英社オンライン / 2024年5月29日 11時0分
-
6万168歩を歩いた関東インカレ 減りゆく体力と握力…初めて撮影した陸上の夢中になった4日間【フォトコラム】
THE ANSWER / 2024年5月28日 10時33分
-
『ひゃくえむ。』劇場アニメ化で来年公開 100メートル走の人間ドラマ 『チ。』作者の連載デビュー作
ORICON NEWS / 2024年5月24日 17時0分
-
「周りのことを考えなさい」と言われて育った日本人…「どうぞご自由に」と言われフリーズする理由とその末路
プレジデントオンライン / 2024年5月21日 18時15分
ランキング
-
1ダウン症児を虐待、私の愚行から考える偏見の真因 不寛容な日本社会の根底にあるのは「無知」
東洋経済オンライン / 2024年6月16日 12時0分
-
2自転車「逆走」が招く重大事故 ドライバーには「一時停止無視のママチャリ」も恐怖
NEWSポストセブン / 2024年6月16日 16時15分
-
3ヤンキー座りできない人、急増中…腰痛、むくみ、血行不良…足首が硬いと起きる見過ごせない不調とは
集英社オンライン / 2024年6月16日 10時0分
-
4BMWが誇る「M」を冠するスーパーバイクの実力 雨の「もてぎ」で元GPライダー先導で試乗した
東洋経済オンライン / 2024年6月16日 8時20分
-
5日産「新型“高級”ノート」初公開! 「オシャブルー」内装&斬新グリル採用! 史上初の超豪華仕様「オーラ“AUTECH”」24年7月に発売へ
くるまのニュース / 2024年6月13日 15時10分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください












