仕事にあぶれた弁護士がむらがる「第三者委員会」という欺瞞
プレジデントオンライン / 2020年4月13日 9時15分
※本稿は、八田進二『「第三者委員会」の欺瞞 報告書が示す不祥事の呆れた後始末』(中公新書ラクレ)の一部を再編集したものです。
■輸入ではなく、「国産」の仕組み
組織の不祥事が発覚するたびに発足される「第三者員会」。これはもはや慣行といってもいいのではないか。
なぜそうした組織がこれほど幅を利かすことになったのだろうか? 第三者委員会の問題点とその原因をあらためて整理するとともに、この疑問に答えていきたいと思う。
まずは、その出自から話を始めることにしよう。この仕組みは、いつどこで生まれたのだろう? 「問題を起こした組織や団体を、それと無関係の外部の人間が厳しく調査し、再発防止策も含めたレポートを提出する」というと、いかにも「欧米的」に感じられるのではないだろうか。第三者委員会の報告書には、「組織のコンプライアンス欠如」を指摘するものが少なくない。そうした概念を普及、徹底させる仕組みとして、それらと同時に「輸入」されたように感じても無理はないのだが、実際は、そうではないのである。第三者委員会は、純然たる“メイド・イン・ジャパン”のスキームなのである。
■山一證券に置かれた「社内調査委員会」が第一号
その原点ともいえる「組織」が産声を上げたのは、1997年12月のことだ。97年というのは、一定以上の年齢の日本人にとって、忘れられない(あまり思い出したくない)1年かもしれない。90年代初頭にバブル経済が弾け、くすぶり始めていた企業の不良債権問題は、この年の11月、三洋証券に始まり、北海道拓殖銀行、そして山一證券と続いた大手金融機関の破綻ドミノという想定外の事態で、一気に「見える化」された。まさか大企業や金融機関が倒れるようなことはないだろうと思っていた人々は、日本経済がいかに深刻なところに追い込まれているのかを、初めて思い知らされたのである。国際的にも「暗黒の11月」と称された変事の中でも最も衝撃的だったのが、旧4大証券の一角を成す山一證券の自主廃業の発表だったと言えるだろう(結果的には自己破産)。
のちに「隆盛」を誇るようになる第三者委員会のルーツは、ほかならぬこのとき山一證券に設置された「社内調査委員会」だったのである。設置の主目的は、新聞報道などで2000億円とも言われた、「簿外債務」すなわち損失隠しの実態究明だ。これが山一を倒した最大の病巣だった。
■当時の第三者委員会は、その役割を果たしていた
この社内調査委員会が、例によってお手盛りの報告でお茶を濁すだけの組織だったかといえば、そうではなかった。同委員会は、翌98年4月に「社内調査報告書―いわゆる簿外債務を中心として―」を公表する。この調査に携わった弁護士の一人國廣正氏は、著書『修羅場の経営責任』(文春新書)で、
「一つは、山一の破綻に至る事実関係を、第三者的観点から、詳細かつ徹底的に調査、検証し、これを『社内調査報告書』という形で対外的に公表したということである。これは当時としては前例のない試みだった。
社内調査報告書の公表は、リスク管理不在、先送り、隠蔽、責任回避、官との癒着という巨大証券会社の経営実態を白日の下に明らかにした。加えて、本業そっちのけで財テクに走り、損失が発生すれば自分が『被害者』だとして損失補填を求める自己責任意識の欠如した顧客企業、『見て見ぬふり』をしながら最後には梯子をはずして引導を渡す『官』の実態も明らかにした。社内調査報告書は、うわさや評論としてではなく『事実』として、これらのことを明らかにした点に意味がある」
と自ら評価した。これには私も同感だ。
危機に瀕したというよりも、すでに死を宣告された組織を調べる現場に、「第三者の目を入れる」という知恵が生まれたのは、皮肉なことだった。ともあれ、この画期的な仕事が、その後第三者委員会という実務に発展していったのは、紛れもない事実なのである。
「とにかく真実を明らかにしたい」という思いから立ち上がった当時の第三者委員会は、十分社会的な意義を持っていた。それを認めるのに、やぶさかではない。
■「第三者委員会」の看板が独り歩きを始めた
21世紀に入り、「暗黒の11月」が「序章」に過ぎなかったことを、我々は痛感した。バブル崩壊の後遺症もあって、数多くの企業不祥事も明るみに出た。そして、前世紀末に産み落とされた「問題の原因追及などを外部の第三者の手に委ねる」という手法も、多用されるようになっていく。
だが、数が増えるにつれ、「第三者委員会」という看板が独り歩きを始めるようになる。第三者委員会とは名ばかりの、信頼性に疑いを持たざるを得ない「調査報告書」が目立ち始めたのである(詳細は、拙著『「第三者委員会」の欺瞞』(中公新書ラクレ、2020年4月刊))。
■経営者の罪を隠す「有害な報告書」
2009年、彼らがいかにデタラメな仕事をしているのかを白日の下にさらす、ある「事件」が起こる。08年10月、自動車部品メーカー、フタバ産業に過年度決算の不正会計処理が発覚し、事実の解明などを目的とする「第三者委員会」が設置される。ここまでは普通なのだが、この事案では、委員会が報告書を出すものの、次から次に新たな疑惑が浮上して、結局短期間に3つの委員会が設置され、それぞれ異なる結論を語るというドタバタぶりを露呈してしまったのだ。
当初、発足した「社外調査委員会」はおおむね会社を擁護するような内容の報告書を出している。
この事件では、その後、元社長らが刑事責任を問われ逮捕されたものの、元社長は嫌疑不十分で不起訴処分となった。しかし、一部の元執行役員には業務上横領と有印私文書偽造・同行使の罪で実刑判決が言い渡されている。
委員会の結論が徐々に先鋭化したのは、処分の見極めに関わる証券取引等監視委員会が一連の報告書の信頼性の無さに懸念を抱くこととなったからだとも言われている。いずれにしても、少なくとも最初の社外調査委員会(報告書)は、無用の長物であるばかりでなく、逮捕までされた経営者たちの罪を、結果的に覆い隠す役割を担ったという点で、有害でさえあった。
■不祥事を起こした企業の株主が「二重のダメージ」を受ける
ところで、第三者委員会は、“手弁当”で仕事をするわけではない。公的機関として、公から報酬が支払われるのでもない。それを負担するのは、依頼した企業、団体である。では、いったいいくらのコストをかけて調査を行ったのだろうか? 依頼した企業などがそれを明らかにしたことも、報告書にその金額が明示されたことも、私の知る限りこれまではない。
これは、実は重大な問題で、不祥事を起こした企業の株主は、その発覚による株価下落で損害を受けたうえに、第三者委員会への支出による会社の損失=企業価値の棄損という形で、二重のダメージを受けていることになるのだ。そんな支出など大したことはないのだろう、と言うなかれ。ある重大事案で設立された第三者委員会に対して、数十億円の対価が支払われたという話を、耳にしたことがある。
「日弁連ガイドライン」にあるように、弁護士報酬は「時間制」でカウントされるのが普通だ。その報酬は、例えば同じ「士業」の公認会計士や税理士よりも、割高な水準にある。加えて、仕事をするのは、通常、報告書に名前の出ている人たちだけではない。資料の読み込みや分析、さらには関係者へのヒアリングといった実務に、所属する法律事務所の弁護士やスタッフが多数関わる。その体制で3カ月、4カ月と任務を遂行するのだから、人件費だけで金額が相当嵩むのは、想像に難くない。
そうしたコストをかけて、当該企業が再生を果たすことのできる中身のある報告書が出るのなら、まだいい。そうでなければ、単なる無駄遣いだ。その意味でも、第三者委員会の報告書の作成・公表に関する一連のコストに無関心でいるわけにはいかないのである。
■「過払い金請求」と並ぶビッグビジネス
このコストに関しては、別の視点からも重要な問題を指摘しておかなくてはならない。誤解を恐れずに言えば、第三者委員会の委員を引き受けることが、「弁護士業界」にとって格好のビジネスになっている、という現実があるのだ。
税理士法人ファーサイトが運営する「第三者委員会ドットコム」という情報サイトによれば、19年度に設置された上場企業の第三者委員会(内部調査委員会なども含む)は、73件に上る。ちょうど5日に1件のペースでつくられている計算で、請け負う側にとっては、十分魅力ある市場だと言えるだろう。事実、第三者委員会専門の事務所も生まれている。
第三者委員会が揺籃期から成長期に入った2000年代初めは、奇しくもわが国で司法制度改革が推進された時期と合致する。04年には法科大学院ができ、司法試験合格者が大幅に増加した。ところが、改革の意図に反して、それにより生じたのは、「弁護士余り」の現実だった。まったくの偶然ながら、そんな業界にとって、第三者委員会ビジネスは、「過払い金請求」と並ぶビッグビジネス・チャンスをもたらす救世主ともなったのである。
■ビジネス化が進むと、本来の役割を果たせなくなる
もちろん、法律事務所が第三者委員会で稼ぐのはけしからん、などとは言わない。ただ、「事業」という切り口からそこにアプローチすると、次のような問題が生じることになるだろう。
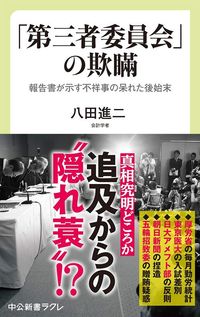
例えば、ここに、温かく迎え入れてくれて、抱えた問題は私たちがきれいさっぱり処理してあげましょう、というお寺と、まずあなた自身が心から反省しなさい、と性根を叩き直されるお寺があったとして、「法務部同士が連絡を取り合う」ユーザーは、どちらに駆け込むだろうか? 第三者委員会をビジネスと考えるのだったら、そのニーズに応えるサービスを提供するのが、「成功」の道だ。逆に言えば、「真因の追究」や「厳格な再発防止策の提起」は、ビジネスの拡大にとってマイナス要因になる危険性がある。その結果、当たり障りのない調査報告書が乱発されるという事態も、あり得ないことではない。
ここでも、第三者委員会を請け負う事務所が軒並みそれを単なるビジネスにしている、などとは言うまい。しかし、客観的には、不正の追及をかわして幕引きを図りたい依頼主と、そこでの仕事を拡大したい法律事務所があったら、その利害が見事に一致するのである。その構図を疑う、私のような人間もいる。
----------
会計学者
1949年生まれ。慶應義塾大学経済学部卒業、早稲田大学大学院商学研究科修士課程修了、慶應義塾大学大学院商学研究科博士課程単位取得満期退学、博士(プロフェッショナル会計学;青山学院大学)。現在、金融庁企業会計審議会委員、金融庁「会計監査の在り方に関する懇談会」メンバー、文部科学省「学校法人のガバナンスに関する有識者会議」委員、第三者委員会報告書格付け委員会委員、日本公認会計士協会「監査基準委員会有識者懇談会」委員等を兼任。著書に『不正-最前線』『開示不正』『会計・監査・ガバナンスの基本課題』『これだけは知っておきたい内部統制の考え方と実務』など多数。
----------
(会計学者 八田 進二)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
『新版 お金の減らし方』【書籍紹介】
トウシル / 2024年7月14日 11時0分
-
「経営体質が変わらない限り、再発する可能性が極めて高い」生徒4人死傷のBBQ事故 報告書受け理事長が辞職表明
RKB毎日放送 / 2024年7月4日 14時7分
-
前理事長が異なる事実を周知 移植ネット第三者委が報告書
共同通信 / 2024年7月1日 21時41分
-
「こんなに長い期間、彼女を苦しめていた」いじめで自殺と認定 旭川中2女子自殺 流出受け報告書は概要版
HTB北海道ニュース / 2024年7月1日 20時9分
-
なぜ豊田章男氏は「不正撲滅は無理だと思う」と語ったのか…「組織不正」の研究者が見た認証不正問題の根本原因
プレジデントオンライン / 2024年6月25日 8時15分
ランキング
-
1今回のシステム障害、補償はどうなる?…「保険上の大惨事」「経済的損害は数百億ドル」
読売新聞 / 2024年7月20日 21時24分
-
2「みんなの意見は正しい」はウソである…ダメな会社がやめられない「残念な会議」のシンプルな共通点
プレジデントオンライン / 2024年7月20日 16時15分
-
3AI利用で6割が「脅威感じる」 規則・体制整備に遅れも
共同通信 / 2024年7月20日 16時50分
-
4次はコメで家計大打撃!? 昨年の猛暑の影響で不足が懸念、約11年ぶりの高値水準に 銘柄によっては品薄や欠品も
zakzak by夕刊フジ / 2024年7月20日 10時0分
-
5苦境の書店、無人店舗が救う? 店内で感じた新たな可能性
ITmedia ビジネスオンライン / 2024年7月20日 7時35分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください











