なぜ昭和の親たちは「たくさんの子供」を平気で育てられたのか
プレジデントオンライン / 2020年6月19日 15時15分
※本稿は、熊代亨『健康的で清潔で、道徳的な秩序ある社会の不自由さについて』(イースト・プレス)の一部を再編集したものです。
■生きていること自体が「リスク」だ
新型コロナウイルス感染症が最も警戒された2020年の3月から5月にかけて、日本人の大半は感染症という健康リスクに敏感に反応した。人々は争うようにマスクを着用し、ロックダウンが宣言されたわけでもないのに外出を自粛した。
この場合、日本人の健康リスクに対する意識の高さは感染予防に寄与したことだろう。だが、リスクに対する意識の高さが必ず良い結果をもたらすとは限らない。新しい命を生むこと・育むことに関しては、まさにそのリスクに対する敏感さが仇(あだ)になっている側面もあるのではないだろうか。
仏教では「生・老・病・死」を四苦と呼び、これらが苦の源であるとしている。老・病・死がリスクであるとするなら、そもそも生きていること、生まれてくること自体もリスクと言わざるを得ない。実際、これから述べていくように、生は現代社会におけるリスクとして、合理性をもって回避されようとしている。
■子どもは生まれる前から「リスク」の塊だ
なかでも子どもはリスクの塊だ。子どもは生まれる前からリスクを孕んでいる。
妊娠・出産にまつわるトラブルは尽きない。昨今は高齢出産が増加しているため、流産や早産などのリスクも高まっている。子どもがどのような遺伝形質を持って生まれてくるのかは生まれてみなければわからない。そうした予測不能性に生殖テクノロジーが貢献するとしても完璧にはほど遠いし、また優生学への反省を経た現在においては完璧でさえあれば良いとも考えられない。
無事に子どもが生まれても、乳幼児期には事故のリスクがついてまわる。異物を飲み込まないように、アレルギーにならないようにと、親は子育てに細心の注意を払う。学校に通うようになれば登下校中に事件や事故に巻き込まれないように心配し、身体が大きくなればよその誰かの迷惑にならないか気を揉むことにもなる。
不登校。引きこもり。不純異性交遊。思春期以降も安心はできない。子育てに親の金銭や情熱を傾ければ傾けるほど子育ての“賭金”は高くなり、それに伴って、子育てについてまわるリスクはますますマネジメントされなければならないものとなる。かといって、“賭金”をリスクマネジメントしようと神経質になりすぎれば、その神経質さ、その親の不安が子育てのメンタルヘルスに難しい影を投げかけることになる。
■子どもは「よく生まれ、よく死ぬ」ものだった
親自身もリスクに曝される。母親は産前から妊娠糖尿病や早期胎盤剥離などの健康リスクを冒し、医療によって死亡リスクが大幅に減らされているとはいえ、出産はいまだ命懸けの行為である。産後うつ病にはじまり、子育てに伴うメンタルヘルスの問題は引きも切らない。虐待やネグレクトに誰もが敏感になっている昨今は、自分の子育てが適切なものなのか、とりわけ注意しなければならない。
日本に限らず、近代以前の社会はたくさん産んでたくさん死ぬ、多産多死の世代再生産によって成り立っていた。後に、人口ボーナスによって経済成長を導いてゆく戦後ベビーブーム期の親たちも、現代では考えられないほど子どもを産み育てていた。今日の、子どもがリスクそのものと言うべき状況に基づいて考えると、昔の人々は途方もないリスクを背負って子育てをしてきたように思えるかもしれない。
だが、実際にはそうではなかった。子どもも大人ももっとリスクに鈍感ななかで子育てが行われ、それで世の中は回っていたのだ。そもそも本書の第3章でも触れたように、リスクに基づいて物事を判断する発想自体、きわめて現代的なものである。
子どもはよく産まれ、よく死ぬこともあり、子育ては親にとってここまで負担のかかるものではないと同時に、生死の責任の曖昧なものでもあった。子どもは安全ではなかったが、ある部分では今日の子どもよりも自由で、実際、子どもが自由の象徴とみなされていたところもある。
■少子化が進む国ほど、子どもに手をかけている
対して現代社会の子育てにまつわる通念や習慣は、私たちの先祖に比べて神経質で、先祖から見れば、子どもをあまりにも大切にしているだけでなく、子どもをあまりにも不自由に閉じ込めていると映るだろう。
日本をはじめ、多くの先進国では少子化が進行しており、そのような国々では子育ては大きなリスクと表裏一体の営みと捉えられている。つまり、少子化が進行している国では必ず、親は子どもに細心の注意を払って当然とみなされ、虐待やネグレクトに対して社会も親自身も注意深くなければならない。と同時に、多くの家庭はますます子どもの教育に大きな投資を心がけるようになり、その投資に見あった成果を期待する視線を浴びながら子どもは育てられている。
本書で触れるように、過去の子育ては危険で野放図な、現代の基準では許容できないものだったが、現代社会の子育てもこれはこれで、リスクや費用対効果のロジックによって歪んでいるのではないだろうか。
そのような歪みは、現代社会では歪みと呼ばれるよりも、正しさや必要性として認識されるものではあろう。だとしても、ホモ・サピエンスの子育ての歴史を振り返る限り、現代社会の子育てのほうが人類史のなかでは異質であり、その異質さは親子を利するばかりでなく、子育てを始める人々をためらわせ、子育てに携わる当事者の負担を大きくするハードルともなっている。
■子どもは“動物”として生まれてくる
現代社会の子どもを考える際、まず思い出していただきたいのは、子どもははじめから現代人として生まれてくるのでなく、子どもは“動物”として生まれてくる、ということだ。
ここで言う現代人とは、現代社会が個人に対して期待するとおりの機能を持ち、権利や責任の主体者たりうる人間、社会の通念や習慣がインストール済みで、社会のルールや法制度を理解し、資本主義や個人主義や社会契約に則った行動がとれる人間のことを指す。これらの機能や主体性を持ち合わせない状態で子どもは生まれてくる。
生まれたばかりの赤ちゃんは言葉すら知らない。赤ちゃんは本能のままに泣き、本能のままに世話される。赤ちゃんを育てる際、親は現代社会の通念や習慣のとおりにでなく、赤ちゃんの本能に沿って世話をしなければならない。
赤ちゃんは母乳を吸うことは本能的に知っていても、「街中で大きな声で泣くと、周囲の人に迷惑がられる」といった現代社会の通念など知らない。「不快な臭いは迷惑」という理由で大小便を我慢することもない。このため、社会の通念や習慣を内面化した親が赤ちゃんを街で連れ歩く際には、赤ちゃんの行動が周囲の人々の迷惑にならないか気を揉むことになる。
■小学生ですら「現代人」としては未完成
たとえば新幹線のなかで赤ちゃんが大声で泣きだした際には、親は申し訳なさそうな顔をしてデッキに移動し、赤ちゃんをあやしはじめる。親だけでなく、赤ちゃんの側にも苦労はあるだろう。たとえば幸運にも、年収2000万円の東京都内の落ち着いた家庭に生まれたとしても、秩序の行き届いた安全なメガロポリスに生まれてきたことを赤ちゃんは知りようがない。あるいは電車のなかにベビーカーごと連れてこられた赤ちゃんから見て、見知らぬ男性に囲まれ、母親が緊張した顔をしている状況はどのように見えているだろうか。またあるいは、子ども部屋に一人で置き去りにされた時間を、赤ちゃんはどのように感じているだろうか。
幼児~小学生になったあたりでも、子どもはまだまだ動物的で、現代人として完成の域には遠い。歩行者は歩道を歩くよう定められていることも、赤信号で横断歩道を渡ってはいけないことも、座学の時間には行儀良く座っていなければならないことも、ホモ・サピエンスが生まれながらに身に付けていることではない。それらは現代社会の制度や習慣に基づいたものだから、いちいち教わり、身に付けていかなければならない。
多くの子どもは、やがてそれらを身に付けていくだろう。とはいえ年少の段階ではそれらはしっかりと身に付いていないから、たとえば子どもが車道近くにいるのを発見した自動車ドライバーは、リスクを感じながらその脇を通り抜けなければならない。
思春期を迎える頃にもなると、ほとんどの子どもは現代の通念や習慣をおおよそ身に付け、それらに沿って行動できるようになる。それでも大人に比べれば身に付けている度合いは完璧とは言えず、親や教師や世間をハラハラさせたりもする。
■子どもにつける「ハーネス」が持つ2つの意味
こんな具合に、秩序の行き届いた現代社会において子どもはリスクを想起させる存在であり続ける。放し飼いの動物が、いつ道路に飛び出してきたり他人に迷惑をかけたりするかわからないのと同じように、まだ秩序を知らない子どもや学習途上の子どもも、いつ道路に飛び出して他人に迷惑をかけたりするかわかったものではない。
その延長線上として、子ども、とりわけ小さな子どもが一人で街にいるだけで私たちは不安になるようにもなっている。子どもが迷惑なことをするかもしれないから不安というだけではなく、その子に何かあったら不安という部分でも、“放し飼いの子ども”はリスクを想起させる存在だ。
最近の親が、子ども、とりわけ小さな子どもを連れ歩く際には絶対に離れようとせず、時にはハーネスをつけることもあるのは、そういった観点からも理解しやすい。子どもにつけたハーネスは、子どもの安全を守り、親の安心を守ると同時に、子どもが想起させるリスク、不安、迷惑といったものを最小化することを他者に示すシグナルとしても機能している。
■「リスク回避」で自縄自縛になっていないか
現代の親は、子どもの安全を守るだけでなく、街の大人たちにできるだけ迷惑をかけず、できるだけリスクを想起させないよう注意しながら子育てをやり遂げなければならない。現代社会の通念や習慣は、そうするよう親に強いてやまない。
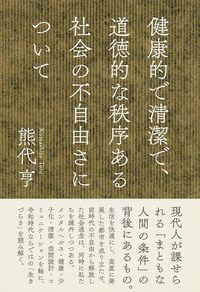
私たちにとって“リスクは回避しなければならない”という考えは当たり前のものになっているし、それはそれで必要な考え方には違いない。しかし、こと子育てに関しては、リスクという考え方のゆえに親も子どもも、いやそれ以外の人々も神経質にならざるを得なくなっている。
リスクを回避するという考え方によって私たちは多くの危険を回避できるようになったが、その一方で、まさにその考え方によって自縄自縛に陥っている側面も、あるのではないだろうか。
----------
精神科医
1975年生まれ。信州大学医学部卒業。精神科医。専攻は思春期/青年期の精神医学、特に適応障害領域。ブログ『シロクマの屑籠』にて現代人の社会適応やサブカルチャーについて発信し続けている。著書に『ロスジェネ心理学』『融解するオタク・サブカル・ヤンキー』(ともに花伝社)、『「若作りうつ」社会』(講談社現代新書)、『認められたい』(ヴィレッジブックス)、『「若者」をやめて、「大人」を始める』(イースト・プレス)がある。
----------
(精神科医 熊代 亨)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
競泳・池江璃花子「暑いのにお疲れさまです」会場入りの際に警備員に必ず声をかけた理由…母親が重要視した「あいさつの習慣」
集英社オンライン / 2024年7月27日 12時0分
-
「相続税100%」を導入しなければ超高齢社会を乗り切れない…世代間対立を避け不況を解決する最強策
プレジデントオンライン / 2024年7月12日 15時15分
-
40歳前後で結婚する夫婦の「子供のリスク」5つ
KOIGAKU / 2024年7月9日 18時23分
-
"お利口な"子が多い保育施設に潜む「不適切保育」 「しつけ」や「指導」の意味を履き違えていないか
東洋経済オンライン / 2024年7月9日 16時0分
-
動物の赤ちゃんの顔「可愛さ」を感じる黄金比とは 赤ちゃんの「愛くるしい姿」は立派な生存戦略だ
東洋経済オンライン / 2024年7月7日 16時0分
ランキング
-
1「コロナで頭がアホになった」のツイートが話題。コロナ後遺症“ブレインフォグ”の恐ろしすぎる実態「集中力が続かない」「家事の途中で何をしていたか忘れる」対策と最近注目の治療法とは…
集英社オンライン / 2024年8月2日 8時0分
-
2やってはいけないお米の保存方法とは? 正しい保存場所や賞味期限を詳しく解説!
オールアバウト / 2024年8月3日 20時45分
-
3【ケンタッキー】1060円もお得な「お盆バーレル」発売! オリジナルチキン10ピース&選べるサイドメニュー5個で“大容量”
オトナンサー / 2024年8月2日 23時10分
-
4【セブンで買える】"神商品"?"草の味"?賛否両論のレモングラスティー、飲んでみた。想像以上の高クオリティーだけど...?《編集部レビュー》
東京バーゲンマニア / 2024年8月3日 19時11分
-
5「あ~、気持ちよかった」女性オペレーターを謝罪させて楽しむ男性クレーマーの“恥ずかしすぎる顛末”
日刊SPA! / 2024年8月4日 8時52分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください











