「熱心な10人」を集められないイベントは絶対に長続きしない
プレジデントオンライン / 2020年8月14日 11時15分
■「イベントに人が集まらない」
「イベントを開催したいのだけれど、なかなか参加者が集まらない」——。
私は普段、コミュニティ・アクセラレーターという肩書きで、企業や自治体のコミュニティづくりを支援するような仕事をしています。そのため普段から、コミュニティやイベントについて相談を受けることがよくあります。中でも6月に、初の著書『ファンをはぐくみ事業を成長させる「コミュニティ」づくりの教科書』(河原あず・藤田祐司著、ダイヤモンド社)を発売してからは、相談数がさらに増えていきました。
新型コロナウイルスの感染拡大後、オンラインイベントは急増しています。初めてコミュニティをつくったり、イベントを開催したりするビジネスパーソンが増えているのでしょう。中でも最も多いのが冒頭のような相談です。
「コミュニティをつくりたいので、まずはイベントを開催したいのだけれど、思うように人が集まらない」
こう頭を抱える人が増えているのです。
しかし、まず集客について悩む前に、考えてほしいことがあります。それは、あなたが「何のために人を集めるのか」というイベントの目的です。
今回は、「集客人数」をテーマにコミュニティづくりにおいて重要なポイントを整理します。
■人手も予算もないのに「初回で100人集める」のは困難
企業がコミュニティを立ち上げる場合、多くの担当者がいきなり、イベントの企画について考え始めます。
例えば、ある医療器具メーカーのヤマダさんが、体重計や血圧計などの自社製品のコミュニティづくりを上司から命じられたとします。
いろいろとネットで調べるものの、コミュニティのつくり方がよく分かりません。
そこでSNSなどで調べてみると、競合他社が有名なゲストを招いて、オンライン健康相談会を、毎月1回開催していることが分かりました。
イベントを企画することに、間違いはありません。しかし無理は禁物です。
コミュニティの運営を任されると、成果を焦るあまり、ついイベントの数や動員数を増やそうとしがちです。しかし、人手も予算もないのに頑張りすぎると途中で息切れしてしまうし、当初、思い描いていたようなコミュニティがつくれなくなってしまいます。
■まずは「コアとなる10人」を集めることが大切だ
ヤマダさんの例では、こんな事態に陥りました。
3回目は集客力のある有名なゲストに声をかけよう。ゲストに支払う講演謝礼が予算よりもオーバーしているけれど、隔週のペースでイベントを開くと上司に宣言したし、仕方ない。今回は承認してもらおう。そうこうしている間に、4回目のゲストも決めなくては。もう、誰でもいいから100人集まる人をゲストに呼べばいいや!」
結局ヤマダさんは、焦って有名なゲストを続々とブッキングし、本来のイベントのテーマからは、どんどんとズレていきました。
こういった事態は、ビジネスコミュニティを運営していると、本当によく起こります。
要するに「隔週で集客力のあるイベントを開催すること」が目的化しているのです。
ヤマダさん本人も頭を抱え、コミュニティづくりに長けた専門家に相談しました。すると、こんなアドバイスを受けるはずです。
「あなたのコミュニティの目的は、イベントを続けることでしょうか。それとも、ファンをつくり、中長期的に成長することでしょうか。イベントは手段の一つでしかありません。まずはコミュニティのコアとなる10人を集めてください。たった10人でいいんです」
■最初の10人を「選ぶ条件」
「たった10人でいいのか」と驚くかもしれません。
しかし、コミュニティづくりでは最初は10人も集めれば十分なのです。しかし、この10人には2つの条件があります。そのどちらかに当てはまる人を、集めましょう。
【コミュニティ最初の10人の条件】
①既にあなたの会社の製品やサービスを使ったことがあり、愛着を持っている人
②あなたの製品やサービスに興味を持ち、熱心なファンになりそうな、ターゲットど真ん中の人
最初の一歩は、コミュニティに興味を示しそうな熱心なファンに「弊社の製品○○について、カジュアルな意見交換会を開催します」といったように声をかけるところから始めます。
例えば、消費者向け製品やサービスのコミュニティの場合、自社サイトやメールマガジン、SNSの公式アカウントなどで、参加者を募集しましょう。あなたの会社の製品やサービスを愛用する人を中心に声をかければいいのです。こういった声がけに応募してくる人は、かなり熱心なファンである可能性が高いでしょう。
企業向け製品やサービスのコミュニティの場合、既に付き合いがあり、コミュニティ活動をおもしろがってくれそうな顧客企業の担当者が有望です。営業担当などにヒアリングをして、勘どころがありそうな人を招待するといいでしょう。
10人に声をかけた結果、最初の会合に訪れるのが5人でも全く問題ありません。大切なのは、会場に来てくれた参加者が、製品やサービスに対して興味や思い入れを持っていることです。
■まずはコミュニティの「ビジョン」を決める
熱心な10人との会話を通じて、まずはコミュニティの方向性、つまりはビジョンを決めていきます。
ビジョンという言葉に少し面食らうかもしれませんが、そこまで大仰なものでなくて構いません。自分たちの会社が実現したいことと参加者のメリットが合致する部分を言語化すればいいのです。
コミュニティづくりは、「そもそも何のためにやるのか」という方向性を決めることから始まります。誰を相手に、何を達成しようとしているのかという目的を明確にしましょう。
参考までに、ビジョンづくりのきっかけになりそうな、参加者への問いを列挙します。コミュニティを立ち上げるときには、次のような問いを集まってくれた10人の参加者に投げてヒントを見つけましょう。
【10人の熱心なファンにこう聞いてみよう】
・なぜ自社(あなたの会社)の製品やサービスを使っているのか
・その製品やサービスにどんなメリットを感じているのか、何を評価しているのか
・その製品やサービスを通して生活がどう変わったのか
・どんな人たちにその製品やサービスを薦めたいか
コミュニティづくりにおいて、最初につくるビジョンは大切な意味を持ちます。あらゆる意思決定の判断基準になるものだと理解してください。
ビジョンなしにコミュニティをスタートさせると、事業に関係が薄くても目立った施策に終始したり、目先の利益にとらわれた活動に陥りがちです。これは、コミュニティ運営においては、「手段が目的化している状態」で、とても危険です。そうならないためにも、コミュニティのビジョンづくりにはじっくりと時間を掛けましょう。
■「購入者ヒアリング」×「社内議論」でビジョンを見いだす
先ほどの医療器具メーカーのヤマダさんは、コミュニティの目的を明確にするため、通販サイトで自社の体重計を購入した10人を呼んで、ヒアリングを実施することにしました。
話を聞くと、「医療器具メーカーならではの安心感がある」など、企業に対する信頼感が高いことが分かりました。また「ダイエットアプリのように人と励まし合える機能がほしい」「定期的に体重を測る仕掛けがほしい」といった意見も出てきました。
こうしたヒアリングから「信頼」「楽しさ」といったキーワードが浮かび上がりました。
さらに社内で議論を重ね、「自社の信頼感を武器に、楽しく健康な体づくりのできるコミュニティをつくろう」というビジョンが見えてきました。これを言葉にして、再び調査を実施し、コミュニティのビジョンは次のようになりました。
「健康づくりを100倍楽しくする」
健康管理はまじめに実践すると味気なく、長続きはしません。
しかしこのコミュニティに参加すれば、楽しく健康的な生活が送れます。参加者にコミュニティに加わるメリットが伝わり、共感を得ることのできるビジョンです。
■10~20人規模のミートアップから、常連が増えていった
ビジョンを決めた後で、ようやく具体的な企画を立てていくのです。ビジョンがクリアであれば、コミュニティのターゲットも明確に定まり、企画はすんなりと決まるはずです。
ヤマダさんは、コミュニティのターゲットを「不健康な生活を送るビジネスパーソン」と設定しました。
そしてイベントの企画を、多くの謝礼を支払って著名人を招いて、多くの参加者を集めるようなスタイルから、健康な生活を送りたいけれど、運動やダイエットが長続きしないビジネスパーソンを10~20人集めたミートアップに変更しました。
楽しくできる運動をするための講師などをイベントのゲストに招いたところ、徐々にコミュニティの常連参加者が増えていきました。
そして、この常連参加者が友達を誘うようになり、少しずつ「コミュニティが楽しくて、御社の体重計を買いました」という参加者が増えてきたのです。
「ダイエットアプリをつくるベンチャー企業のエンジニアなのですが、アプリ連携に興味はありませんか」といった商談も生まれるようになりました。ヤマダさんは、SNSを駆使してコミュニティ参加者と積極的に交流し、ファンの数も増えていきました。
■「熱心な10人」と一緒にビジョンを決めるのが大切
コミュニティの参加者は、次のような手順で進めるといいでしょう。
① 最初は10人に声をかける
② 5人〜10人規模のミートアップを開く
③ ミートアップで製品やサービスの長所と短所をヒアリングする
④ 友達や仕事上付き合いのある人など少しずつ輪を広げる
⑤ SNSで参加者とつながり、コミュニケーションを続ける
繰り返しますが、コミュニティを立ち上げる際に特に大切なのは、最初に熱心な10人のファンを集めて、一緒にビジョンを決めること。ビジョンづくりをないがしろにしてはいけません。
「何のためにやっているのか」を忘れると、コミュニティそのものがぼんやりとしてしまいます。そうしたコミュニティは大抵の場合、参加者や関係者のモチベーションが高まらず、結果的に活動が停滞します。
・何のためにコミュニティを立ち上げるのか
・コミュニティを通して何を実現したいのか
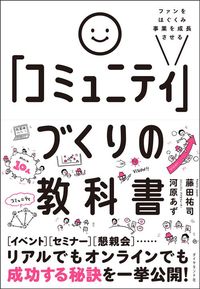
まずはこれを明確に決めること。いざコミュニティを立ち上げる段になると、イベントの数を増やしたり、動員数を伸ばしたりすることに意識が向きがちになるので、くれぐれも注意しましょう。
新型コロナウイルスの感染拡大後、多くのビジネスパーソンがコミュニティの重要性に気づきました。しかし、実際にコミュニティやオンラインイベントを立ち上げようとして、戸惑う人も実に多いようです。
そんなビジネスパーソン向けに、コミュニティづくりのポイントをゼロからまとめた新刊『ファンをはぐくみ事業を成長させる「コミュニティ」づくりの教科書』を発売しました。急速に増えているオンラインイベントのノウハウなども盛り込んでいます。ぜひ参考にしてください。
----------
Potage コミュニティ・アクセラレーター
富士通を経て、2008年からニフティが運営する(当時)イベントハウス型飲食店「東京カルチャーカルチャー」イベントコーディネーター就任。年間200本以上のイベント運営に携わる。2013~2016年、サンフランシスコに駐在。帰国後、伊藤園、コクヨ、オムロンヘルスケア、サントリー、東急などと数多くのビジネスコミュニティをプロデュース。2020年春に独立し、ギルド制のチーム「Potage」を立ち上げ、コミュニティ・アクセラレーターとしてイベント企画、企業のコミュニケーションデザインなどを手掛ける。
----------
(Potage コミュニティ・アクセラレーター 河原 あず)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
【期間限定で無料配信】320人の限界集落に年間3万人が訪れる農村起業ノウハウ13選を伝授。農村の「在る」を生かして地域活性を目指す。
PR TIMES / 2024年7月19日 16時40分
-
【オンライン交流会】第三者承継コミュニティ「relays(リレイズ)」、事業承継について気軽に話せるイベント「relays MONTHLY MEETUP vol.4」開催決定!7月25日(木)開催。
PR TIMES / 2024年7月16日 12時45分
-
くれまぐ「TGC 松山 2024」出演決定 連動イベントで岡⽥蓮&みとゆなトークショーも開催
モデルプレス / 2024年7月4日 15時0分
-
JACK IT.、「第11回LIVeNT 2024 イベント総合 EXPO」にブースを出展!【αコミュニティ×eスポーツ×イベント】を掛け合わせ新たな事業創出の可能性を提案。
PR TIMES / 2024年6月26日 16時45分
-
仲間と学びで、未来を拓く...「仲間」を重視する、人事のための「人事図書館」が話題を集める理由とは?
ニューズウィーク日本版 / 2024年6月20日 19時24分
ランキング
-
1マクドナルド 約3割の店舗が営業停止 レジに障害
日テレNEWS NNN / 2024年7月19日 11時46分
-
2【速報】ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)でレジや店のシステムにトラブル 閉店する店も… JR西日本はHPやアプリで不具合
MBSニュース / 2024年7月19日 16時15分
-
3世界的にシステム障害、米航空は運航停止 問題特定し修復へ
ロイター / 2024年7月19日 19時54分
-
4TBS退職→Netflixと5年契約「50代P」選んだ道 「不適切にもほどがある」「俺の家の話」手掛けた
東洋経済オンライン / 2024年7月18日 12時30分
-
516時に仕事が終わり、会社から人がいなくなる…フィンランドが「世界一幸せな国」であり続ける納得の理由
プレジデントオンライン / 2024年7月19日 9時15分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください











