立花隆「文明のベクトルは速度を上げながら破局に向かっている」
プレジデントオンライン / 2020年9月3日 9時15分
※本稿は、立花隆『新装版 思考の技術』(中公新書ラクレ)の一部を再編集したものです。
■自然は「数量化できない要素」に満ち満ちている
自然は、われわれがとらえたと思っているものより、常により広く、より深い。――私はここで“自然”ということばを、自然科学が対象とする自然よりも広い意味で使っている。自然というよりは、現実のすべてとでもいったほうがよいかもしれない。
自然をとらえようとするとき、われわれはどんな操作をほどこすだろうか。それは、抽象化、単純化、数量化などである。そのそれぞれの操作のたびごとに、とらえようとした現実の自然はのがれ去り、ゆがめられた自然のモデルが残る。
現実の自然は常に具体的で、無限に複雑かつ多様で、そこには測定不能のもの、つまり数量化できない要素が満ち満ちているのである。人間が直観的に理解できるのは、三次元の空間までである。これを、関数のグラフ化ということと結びつけて考えてみると、人間は三つの座標軸を持った空間の中にある関数しか直観的に把握できないということになる――むろん、直観的な把握ということを抜きにすれば、次元がいくらでも高い位相空間を考えることができるし、それを扱う数学もある。
そこで、自然科学の実験では、多くの因子がかかわる事象でも、他の条件は一定の状態を保ったままで、変量はいつも一つか二つにとどめる。
自然科学だけではない。人間が現実を考察するときは、たいてい可変量を一つか二つにとどめ、残りについては判断中止しておくものである。
■小説の恋愛と現実の恋愛が「どこかちがう」理由
恋愛心理小説に登場する人物は、いつも恋愛者として登場してくる。現実の恋愛における登場人物は、生活者である。だから、小説の恋愛における葛藤は、現実の恋愛における葛藤とはどこかちがう。現実の恋人たちの間に起きる葛藤には、二人の生活者としてのすべての背景がからんでいる。
もし、そのすべてを描ききろうと思うなら、一つのできごとを描くためにも、百科事典ほどの紙数が必要になろうし、また、時間的にも空間的にも現実には一点において起きたことを、文章の上では継時的に書いていくという操作を加えなければならないため、結局、支離滅裂のこととなり、読む者には、著者が何を書きたいのかわからないことになってしまうだろう。
だから、どんなに複雑なからみ合いを描いた小説でも、それは数学的にいってみれば、位相空間の事象を三次空間に投影してみたようなものでしかない。また、それでなければ、読者に理解できなくなってしまうのである。――現代小説における“意識の流れ”手法は、文学における位相数学のようなものだが、この手法の追求の果ては、ちょうど純粋数学が、純粋数学者の間にしか理解者を獲得できないところにきてしまったのと同じように、文学マニアの間にしか読者を得られないところまできてしまっているようだ。
■人間は、現実を恐れることを忘れてしまった
結局、小説がフィクションでしかありえないのは、それが現実を読者に理解可能な次元にまで投影しなければならないというところにある。
自然科学も、自然のモデル化という投影操作を抜きにできない以上、いかにそれが科学的に見えようとも、現実に対しては、一種のフィクションでしかないのである。
科学の上にたてられた技術も、技術の上にたてられた文明も、同じような意味で壮大なフィクションなのである。文明の中に生きる人間は、いつのまにかフィクションの中に生きることに慣れきってしまって、現実を畏怖することを忘れてしまっている。そして、フィクションと現実との間で、価値観を転倒させてしまっている。
“不純物”ということばがある。かなり悪いイメージを起こさせることばである。しかし、考えてみればすぐにわかることだが、現実の自然界に存在するのは不純物なのである。現実にあるものを、現実にあるがままには理解できず、かつそのままでは利用するだけの技術を持つことができなかった人間が、自分に理解できかつ操作できるような形に現実のものを変えた結果としてでてきたのが、純粋なものなのである。
理論は常に純粋なものを扱うが、技術はものを現実に操作する必要上、かなり純度の低いものまで扱う。ここで現われてくるギャップが、いわゆる理論と実践のギャップであり、技術の面でいえば、工業化、企業化にともなう公害などの問題である。
純粋な人間の代名詞のごとく使われている『白痴』のムイシュキン公爵はついに狂気に取りつかれざるをえなかった。純粋さの上にたてられてきた文明も、発狂寸前の段階にきている。われわれはもっと不純になり、不純なものの扱い方を学ばねばならない。
■「ムダ」を「ムダ」としか見ない人間の恥ずかしさ
悪いイメージのことばとして、“ムダ”、“ムラ”ということばがある。企業での生産性向上運動というと、すぐにこの二つの追放がスローガンにかかげられる。
これまた、身の回りどんな現実でもながめてみればすぐにわかることだが、現実はムダとムラに満ち満ちている。これに対して、人間の作ったものは、ムラなくムダなく、実にスッキリと、合理的にできている。まるで、自然の作るものよりは、人間の作ったもののほうが、はるかに上等なものであるかのように見える。だが、これまた人間の価値観の狂いにほかならない。
生態学がいくつかの面で解き明かしたように、現実の自然においては、ムダなものは一つもない。ムラと見えるものも、そのムラさ加減は現実の要請に従ったムラさ加減であるという意味で、逆に現実的には最も整然としたものであるといえるのである。
人間はむしろ、ムダがムダとしか見えず、ムラがムラとしか見えない自分を恥ずべきなのである。逆に、一見ムダなしと見えた人工システムが実は恐るべきムダをはらんでいるということを知るべきである。人工システムの合理性は、そのシステムの内部だけでの一面的な合理性である。トータルシステムとのかかわりの中で検討してみると、それがとんでもなく非合理であることがしばしばある。
■「数量化できないもの」へのチエを忘れている
公害企業は、企業の合理性の追求によって公害を生む。その結果は、人類全体にとって、むしばまれた健康、自然環境の破壊、ひいては人類の生存基盤の危機という恐るべきムダを与えている。もっと視点をしぼって、その企業の得失だけを考えてみても、企業イメージの悪化、それによる労働市場での不人気、社内のモラルの低下、公害防止のための予期せぬ出費などで、はじめから公害防止の経費をかけていた場合よりも多くの損失を出しているはずである。
なぜ、小さなムダは見えても、大きなムダが見えなかったのか?
それは合理性の追求が一面的だったからである。公害産業の場合には、経済主義的な合理性の追求がそれに当たる。しかし、より根源的には、現代文明の根幹にアルゴリズムがあるからではなかろうか? どうもわれわれは数えられる合理性しか知らないできたようだ。
数量化できないものを恐れることと、数量化できないものに対処するチエを忘れていたようだ。
われわれがいま学ばねばならないのは、プロローグで紹介した包丁の刀さばきのように、自然の骨と肉のスジにそって文明という刀を走らせることである。アルゴリズム合理主義の砦による陣地戦ではなく、自然という“敵”の動きに応じて動く、ゲリラ戦術である。そして、合理主義を根底から検討し直す必要である。
■「進歩」は破局に向かい、速度をはやめている
同じように、進歩という概念についても、われわれはもう一度考え直さなければならない。
進歩とは、目的論的な方向性をもった変化のはずである。人間が進歩ということばを用いるケースをいくつか検討してみよう。漢字の読み書き能力の進歩、料理の腕前の進歩、よりこわれにくい時計を作る技術の進歩……こういった目的が明確に設定されている進歩はよい。だが、こうした日常的な、ミクロの進歩のベクトルの総和がどちらを向いているのか、その到達地点であるマクロの目的についての構想はあるのか――誰もそれを考えていないようである。
どうやら、人間はこの点に関しては予定調和の幻想に酔っているらしいのだが、現実には文明のベクトルは予定破局に向かっているような気がしてならない。そしてなお憂うべきことは、このベクトルの長さ、つまり速度がますますはやまりつつあることである。
■進歩が「善」になるのは、方向と速度が正しい時
生態学の観察する自然界での変化の速度は正常な変化であるかぎり緩慢である。生物は、あるスピード以上の変化には、メタボリズム機能の限界によってついていけなくなるからである。
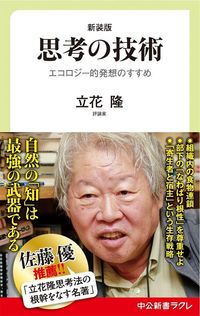
進歩という概念を考え直すに当たって、生態学の遷移という概念が参考になるにちがいない。遷移のベクトルを考えてみる。その方向は系がより安定である方向に、そして、エネルギー収支と物質収支のバランスの成立の方向に向けられている。その速度は目に見えないほどのろい。なぜなら、系の変化に当たって、それを構成する一つ一つのサブシステムが恒常状態(ホメオスタシス)を維持しながら変化していくからである。自然界には、生物個体にも、生物群集にも、そして生態系全体にも、目に見えないホメオスタシス維持機構が働いている。
文明にいちばん欠けているのはこれである。それは進歩という概念を、盲目的に信仰してきたがゆえに生まれた欠陥である。進歩は即自的な善ではない。それはあくまでも一つのベクトルであり、方向と速度が正しいときにのみ善となりうる。
いま、われわれがなにをさしおいてもなさねばならないことは、このベクトルの正しい方向と速度を構想し、それに合わせて文明を再構築することである。
----------
評論家
1940年長崎県生まれ。64年、東京大学仏文科卒業後、文藝春秋に入社。66年に退社し、東京大学哲学科に学士入学。その後、評論家、ジャーナリストとして活躍。83年、「徹底した取材と卓越した分析力により幅広いニュージャーナリズムを確立した」として、菊池寛賞受賞。98年、第1回司馬遼太郎賞受賞。著書に『田中角栄研究 全記録』『日本共産党の研究』(講談社文庫)、『宇宙からの帰還』『脳死』(中公文庫)、『脳を鍛える』(新潮社)、『臨死体験』『天皇と東大』(文春文庫)など多数。
----------
(評論家 立花 隆)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
ワームホールやワープドライブの科学的可能性 タイムトラベルから見る「時間」とは?
東洋経済オンライン / 2024年7月10日 17時30分
-
40年は1つの秩序に綻びが生じるに十分な長さ...高坂正堯「粗野な正義観と力の時代」より
ニューズウィーク日本版 / 2024年7月10日 11時5分
-
【7/1〜7/7の運勢】7月1週目の運勢はどうなる?SUGARさんが贈る12星座占いをチェック!
isuta / 2024年6月30日 22時5分
-
AI時代にこそ必要となる「IQ以外の知性」って何? チャットGTPの答えを「正しくわかる」ための技
東洋経済オンライン / 2024年6月28日 21時0分
-
時代と場所を超越する幻想風刺コミック『怪奇古物商マヨイギ』、第1巻発売
マイナビニュース / 2024年6月26日 12時0分
ランキング
-
1トヨタの新型「ランドク“ルーミー”」初公開!? 全長3.7m級「ハイトワゴン」を“ランクル化”!? まさかの「顔面刷新モデル」2025年登場へ
くるまのニュース / 2024年7月23日 11時50分
-
2ダニ繁殖シーズン到来…アレルギー持ちや痒くてたまらない人はカーペットと畳に注意
日刊ゲンダイDIGITAL / 2024年7月24日 9時26分
-
3父親と“彼女の母親”がまさかの…両家顔合わせの食事会で二人が「固まった」ワケ
日刊SPA! / 2024年7月24日 15時54分
-
4いい加減にして!何でももらってくる“自称・節約上手”の母のせいで衝撃の事件が…
女子SPA! / 2024年7月24日 8時47分
-
5【520円お得】ケンタッキー「観戦バーレル」本日7月24日から期間限定発売! SNS「絶対に買う」の声
オトナンサー / 2024年7月24日 12時40分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください











