呪いの手紙を送ってくる母親を、50歳女性が許せるようになったきっかけ
プレジデントオンライン / 2020年9月21日 11時15分
※本稿は、菅野久美子『家族遺棄社会 孤立、無縁、放置の果てに。』(角川新書)の一部を再編集したものです。
■介護を皮切りに家族の「面倒くさいこと」が始まる
かつて親に苦しめられた人の中には、親を捨てることを選択する人がいる一方、自分なりに向き合うことを決めた子供もいる。戸田幸子(仮名・50歳)も母親との関係で葛藤を抱えていた一人だった。
取材を通じて感じるのは、親が元気なうちはあまり問題は起きないということだ。親は子供と疎遠ながらも自立的に自分の人生を送っているし、それなりにおう歌しているかもしれない。
しかし、認知症やケガなどで親や兄弟の介護が始まったときから、五月雨式に様々な「面倒くさい」ことが発生し、そこには大きな葛藤が生じる。親族は、身内として突如ありとあらゆる決断を迫られることになるからだ。それは、親と物理的な距離があっても、たとえ親を介護施設に入れていたとしても変わらない。
「毎月、介護施設の請求書と一緒に母親からの手紙が送られてくる。私はそれを『呪いの手紙』と呼んでいたんです。介護施設に入れていても、この手紙が来ると気持ちがガクンと落ち込んで、ざわざわする。辛すぎる。親がおかしいのか、自分がおかしいのか、時たまわからなくなっていました。私の中で、何かが欠落してるのはわかる。私がおかしいのか。でもどこでおかしくなったのか、わからなかった」
関東の介護施設に看護師として勤めている幸子は、そう言って一通の手紙を差し出した。幸子が「呪いの手紙」と呼ぶその封書には、84円切手が貼られていて、文面を見るとボールペンでびっしりとつづられた呪詛のような言葉が並んでいた。
『こんな犬も猫も着ない服なんか送ってきて。自分のことを乞食かと思うこともあります』
幸子は、封筒の中に入っていた一枚の写真を取り出した。
■妄想にとりつかれ家中のコードを抜く母親
写真の中に写っている高齢の女性は、紫色の花柄のタートルネックを着てベージュのソファーに座ってわずかながら、ほほ笑んでいる。やせ形で白髪が目立つが、ボブの髪型と目元が幸子にそっくりだ。背後には、介護施設の木製の手すりが見える。これが、母の恵子(仮名・78歳)である。写真の中の恵子は、一見穏やかに見える。しかし幸子にとっては、かつてはまとわりついて離れない蠅のような存在だった。
恵子が毎月送ってくる手紙──そこには毎回、自分が欲しいものが書かれている。パジャマやインナー、靴下。しかし、実際に手紙に書いてきたものを送ると、その度にケチをつけられる。母の終わりのない要望、いくらそれを叶えてあげても、尽きることはない。それだけでなく、母は施設でトラブルを起こし、数えきれないほど施設を転々としていた。そのトラウマが、幸子の中で恐怖心として焼きついている。
母の居住地は秋田のため、会うことはないし積極的に会いにいくつもりもない。しかし、何かある度に問題を起こす母親に、幸子はほとほと疲れていた。
「他人から見たら、『かわいそうに、お母さんはあんなに年取ってるのになんでキッとなってるんだろうね』と見られると思う。だけど、抑えられない導火線が自分の中にはあるの。手紙とか介護施設からの電話連絡がくると、それにポッと火がついて、腹が立ってた」
幸子は医療従事者の父親と、専業主婦の母親・恵子との間に生まれた。父親が37歳の時の子供で、当時では遅く生まれた一人っ子ということもあり、父親は幸子をとてもかわいがった。
しかし、今思いかえしてみても、母親からはまともな愛情を受けた記憶はなく、ネグレクトされて育った。それが、幸子にとっては大きな傷となっていた。物心ついた時から、母親は強迫神経症を患っていた。
火事になるかもしれないという妄想を抱き、家中のコードを抜いたり、突然怒鳴り声をあげることもあった。そんな異常な行動を取る母親が、子供心に怖かった。
■「かわいがられたい」と言われた母は鬼のような形相に…
幸子には、忘れられない辛い思い出がある。小学四年のときに、自家中毒で入院をしたときのことだ。背中に人の腕ほどの大きい注射をすることになった。子供心にあんなに大きい注射は、怖くてたまらなかった。隣のベッドの女の子は、「注射我慢したよ」と母親に自慢すると、頭を撫でてもらい、「よく頑張ったね」と折り紙を折ってもらっていた。それが羨ましかった。
私もあの女の子みたいに、お母さんにかわいがられたい──。そう母親に伝えた。しかし、母親からは鬼のような形相で、「あなたには十分やってる。私は私で一生懸命やってるの! 今までで十分だから」と突き放された。
普通の子供のように甘えられる母親、それが心底羨ましかった。恵子は感情が欠落したロボットのようだった。
「小さいころ、あなたが泣き止まないから、足をつねってたのよ」と笑顔で言われたこともある。私のこと、愛してなかったんだ。ずっとそう思っていたため、地元の秋田を離れてからは母とも自然と距離ができるようになった。
「母がやってきたことは本人にとっては何の悪気もないと思うの。特に手を上げられたわけでもない。だけど、私にとっては殴ったり蹴ったりと同じだったと思ってる」
幼少期の辛い思いは、大人になった今でも幸子の中にひっそりと影を落としていた。
■社会通念や模範的な娘像を押しつける世間が辛い
それでも離れて生活していたうちはまだ良かった。父親が70歳で亡くなってから10年間、恵子は一人で生活していた。しかし、11年目の春に突然様子がおかしくなった。
「私の家の井戸水が石油臭い」
そんな妄想に取りつかれて家を出て、賃貸マンションに引っ越したのだ。しかし、その引っ越し先でも「水が石油臭い」という妄想にかられ近所の住民を騒がせるようになる。役所のケアマネージャーから「お母さんの様子がおかしい」と幸子に電話がきたのは、5年前だ。
恵子の行動は異常だが、精神科へ入院が必要なほどではない。それがケアマネの見立てだった。そのため、グループホームへ入居することになった。しかし、そこも「ベッドが固い、変な臭いがする」と二日で飛び出してしまう。移った施設でも、「なんでここはトイレが少ないの」「自殺する!」と施設の職員を怒鳴りつけ、度々トラブルを起こした。そして問題を起こす度に、施設を点々とせざるをえなかった。恵子は施設をたらいまわしにされ、その度に次の施設を探さなければならなかった。幸子は、次第に介護施設からの電話におびえ、不安に襲われるようになっていく。
辛かったのは、担当のケアマネにこれまでの経緯を相談したときだ。ケアマネは、幸子に同情を示しつつも、「でもこれだけは覚えておいてください。お母さん、娘さんが自慢なんですよ」とにべもなく返してきた。そして、母が要求している新しいパジャマを贈るように促してきた。
社会通念や模範的な娘像を押しつける世間、それが当たり前で回っている社会──幸子にとっては何よりも辛かったものの一つだ。
ある日、施設から届いた書類の中にインフルエンザの予防接種の請求書が入っていた。
このまま母がインフルに罹って、死んでくれたらいいのに──、そう願っている自分がいた。
母が亡くなったら、まずホッと胸を撫でおろすはず、幸子はそう感じている。最後までわかり合えなくて残念だったと思うかもしれない。でも、それだけだ。母親は、今この瞬間もグループホームで手厚い介護を受けている。しかし、毎月来る母からの手紙や今後に悩み苦しむ幸子に心の底から寄り添う人はいない。ぽっかりと空いた空虚な穴は、ただただ深まるばかりだ。だから、苦しい。
■お正月が終わっても帰ってこなかった80代の男性
転機となったのは、職場の施設で、ある事件が起きたことがきっかけだった。
幸子が勤務する施設には、いつもニコニコと笑顔で接してくれる心の優しい車いすの80代の男性がいた。男性は、息子夫婦の家にお正月に一時帰宅することをずっと心待ちにしていた。
しかし、お正月の帰宅期間が終わっても、男性は帰ってこなかった。いざ息子のもとに帰宅すると、男性は家族にその存在を完全に放置されていたらしい。男性は施設で常用していた薬を家族に飲ませてもらえず病状が悪化し、命を落としてしまったのだ。
幸子は男性の最後の後ろ姿を思い出し、胸にキリキリと突き刺さるような痛みを感じた。
男性は息子の家に帰らなければ助かっていたかもしれない。家族っていったいなんなんだろう──。
■「家族とは決して一枚岩ではない」と悟った
よく見渡すと幸子の職場では、「今日は孫の面倒を見るんだよ」「家に帰って、子供のためにご飯を作らなきゃ」と嬉しそうに語る利用者もいる。その一方で家族からお荷物扱いされたり、身寄りがない高齢者もいる。男性の死は、親とは何かということを考えるきっかけを与えてくれた。
家族の形は人それぞれだ。他人のような家族もいるし、家族がいても孤独な人もいる。家族とは決して一枚岩ではない。そして、その関わり方に正解なんて、ない。正解を求めたり、常識に縛られるから、辛い。家族にはコインのように裏と表があって、自分だけでなく、みんなどこかしら歪んでいる。そんな当たり前の事実に気がついた時に、ふっと肩の力が抜けた。
数日前、母の入居する施設の職員から電話があった。母親が施設でトラブルを起こし、ここから出たいと言っている──。またか、と思った。しかし、かつての自分のように動揺することはなかった。
「好きにさせてあげてください。母は母の人生だから」
気がつくと、そう返答している自分がいた。親は親の人生だ。だから、好きにすればいい。母に自分が振り回されることはない。そんな自分を受け入れた時に、途端に気持ちが楽になった。母親としてではなく、一人の人間、違う命として客観的に見ること──。母親という呪縛を何よりも自分の心の中から、消し去るということ。母を他者として切り離して俯瞰で見ると、そこには生きづらそうにしている一人の高齢の女性がただ、立ちすくんでいただけだった。
「これからの時代、私みたいに親と関わりたくないという考え方の人が増えてくると思う。だけど現実問題として、親子の縁はなかなか切れない。でもやりたくないことは親子でも、やらないほうがいい。無理なんだもん。鬼とか酷いとか言われても、自分の気持ちに正直なほうがいい。母は母の人生で私の人生ではないから」
そう思うようになってから、母のことを一歩引いた目線で見られるようになった。擦り切れるほどにボロボロだった精神の安定も、少しずつ取り戻している。
■自分なりの距離の取り方を見つければいい
「私の家族は何かが欠落していたと思うの。母親のことを見るのは子供の私しかいない。だけど会わなくて済むなら、二度と会わなくていい。それで私は後悔しないと思う。母が亡くなったら、最低限のことはやる。
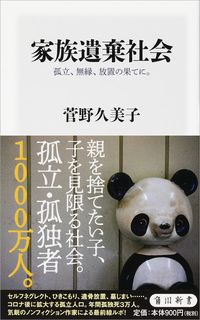
だけど、やっと逝ってくれたかと思って死んでも泣かないと思うね。何もしてあげられなくてごめんね。でも、近づくと傷つくから近づけなかったんだよ。すごく傷つくから嫌で近寄りたくなかったけど、今は感謝してるよ。この世に出してくれてありがとねって」
ヤマアラシのジレンマという寓話がある。鋭い針を持ったヤマアラシは、たがいに寄り添おうとすると自分の針毛で相手を傷つけてしまうため、近づけない。だから離れていなければならない。近づくと傷つくなら、自分なりの距離の取り方を見つければいい。世間の常識に縛られて、これまではそれが難しかった。だけど、今はそうじゃない。
幸子は、長年ヤマアラシのジレンマに苛まれながら、ようやくその適切な距離を見つけたのだった。幸子は、これまで押し殺してきた本音を今は大切にすることにしている。そして何より自分の人生を最優先に置くことで、一人の人間として、一人の老いた大人として、母親と向き合うことにしたのだった。
----------
ノンフィクション作家
1982年、宮崎県生まれ。大阪芸術大学芸術学部映像学科卒。出版社で編集者を経てフリーライターに。著書に、『超孤独死社会 特殊清掃の現場をたどる』(毎日新聞出版)、『孤独死大国 予備軍1000万人時代のリアル』(双葉社)、『大島てるが案内人 事故物件めぐりをしてきました』(彩図社)などがある。また、東洋経済オンラインや現代ビジネスなどのweb媒体で、生きづらさや男女の性に関する記事を多数執筆している。
----------
(ノンフィクション作家 菅野 久美子)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
“ブラック企業勤務”で豹変した父から逃げ出し20年…娘がケアマネからの手紙で知る「驚きの現状」
Finasee / 2024年11月15日 17時0分
-
「会ってもらえなくて当然」絶縁した父から娘に届いたビデオレター、最期にどうしても伝えたかった言葉とは
Finasee / 2024年11月15日 17時0分
-
義実家に行って「“2階の女性”に向けた手紙に絶句」…義父母が認知症を患った51歳女性の選択
日刊SPA! / 2024年11月9日 15時54分
-
「一体、なにがしたかったのか」母の想いを無視した施設入所、葬式、遺産分割の末、家族に残されたものは?
Finasee / 2024年11月8日 17時0分
-
母さんに寄生したくせに。…老母の介護を背負わされ、別居の姉・弟に「使い込み」を疑われた50歳バツイチ女性、号泣。母の貯金「2,000万円」が減り続けた本当の理由【弁護士が解説】
THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年10月18日 11時15分
ランキング
-
1<独自>衆院選自民運動員2人に計7万円支払い買収 公選法違反容疑で大阪・太子町議逮捕
産経ニュース / 2024年11月15日 21時45分
-
2厚労省「106万円の壁」見直し、保険料の会社負担増やす特例案…「従業員51人以上」も撤廃へ
読売新聞 / 2024年11月15日 23時47分
-
3「生活苦で、母殺して死のうと」85歳母絞殺、容疑で出頭した息子逮捕 大阪・岸和田
産経ニュース / 2024年11月15日 17時51分
-
411月も中旬なのに青々としたモミジ、10月の高温で紅葉の見頃が遅れる…観光客は半袖姿も目立つ
読売新聞 / 2024年11月16日 7時40分
-
5「死に方考えてほしかった」=元妻、3回目の被告人質問―「紀州のドン・ファン」・和歌山地裁
時事通信 / 2024年11月15日 19時26分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください










