日本企業が学ぶべきなのはアメリカより中国である5つの理由
プレジデントオンライン / 2020年10月30日 9時15分
■「世界トップの経済力=アメリカ」と思っているのは3カ国だけ
いま、中国ビジネスに注目するのは、世界のマーケターの常識といっても過言ではない。「中国に注目すべき」というよりも、「注目して当然」で、それをできていない日本が異常といった方が適切だろう。
2020年10月、アメリカのピュー研究所が発表した報告書(※1)によれば、「世界トップの経済力を持つ国はどこか」という質問を14カ国(※2)で行ったところ、じつに11カ国で「中国」が最多回答になった。「アメリカ」が最多回答になったのは、アメリカ自身と、韓国、そして日本のわずか3カ国である。カナダやオーストラリア、欧州各国では、大差をつけてアメリカよりも中国が回答されており、中国ビジネスが世界をリードする存在としてすでに認識されている結果が明るみに出た。
※1:Silver et al. 2020/『Unfavorable Views of China Reach Historic Highs in Many Countries』
※2:カナダ、アメリカ、イタリア、ドイツ、ベルギー、オランダ、スペイン、フランス、スウェーデン、イギリス、デンマーク、オーストラリア、日本、韓国の14カ国。
2019年春、アメリカのハーバード・ビジネススクールが発行する研究誌に掲載された論文(※3)では、次のような主張が展開されている。
「これまで欧米のマーケティングは万能で、世界中のあらゆるビジネスに当てはめられると考えられてきた。しかし、中国のマーケティングは、それが誤りだと確信させるものである。中国は、欧米のマーケティングよりも速く、安く、そして効果的な独自のマーケティングを生みだしている。固定概念に染まった欧米のマーケターは、中国のマーケティングからもっと学ぶ必要がある」
※3:Whitler 2019/「What Western Marketers Can Learn from China」『Harvard Business Review 2019 May-June』
■日本人の中国イメージは古いままだ
アメリカのマーケターの間では、中国のマーケティングを分析し、長所を学ぶ動きが始まっている。それはちょうど1980年代の日本のバブル期に、アメリカが日本企業から学ぼうとした構図そのままだ。当時、日本の自動車や家電のメーカーは「ジャパン・アズ・ナンバー1」と称され、注目を集めた。その対象は、2020年代から本格的に中国のITベンチャーになる。
中国はもはや、安価な労働力を提供するだけの「世界の工場」ではない。キャッシュレス、モバイルオーダー、AIによる画像識別・顔認証、IoT家電、スマートシティ、ドローン、無人運転、遠隔医療、ニューリテールなど、世界最先端のデジタル・イノベーションを次々に生みだすベンチャー大国。これが中国の現在地である。アメリカはいち早く中国に対する評価を更新し、中国ベンチャーから学ぼうとしている。
しかし、多くの日本企業と日本人は、安かろう悪かろうの「メイド・イン・チャイナ」で、中国はモノもサービスも日本から数十年遅れている、という時代遅れの固定概念に支配されたままだ。中国ビジネスの飛躍を耳にしても、「中国は特殊だから」「どうせすぐに終わる」と、もう20年近く目をそらしつづけてきた。世界でもっとも中国に注目できていないのが、過去のイメージにとらわれた日本である。
アメリカが中国から学び、中国のマーケティングの長所を取り入れる姿を見て、「アメリカに認められたなら本物だ」と観念し、数年遅れで中国から学ぼうとするのではあまりに遅すぎる。
■中国ベンチャーはライバルであり、パートナー
世界から注目を集める中国ビジネスの成長を牽引しているのは、デジタル・イノベーションを生みだす中国ITベンチャーたちだ。「BATH」と呼ばれる、バイドゥ、アリババ、テンセント、ファーウェイはもちろんのこと、TikTokを世界で展開させるバイトダンス、ドローンの世界シェア70%を握るDJI、スマホ生産台数で世界第4位のシャオミ、世界最大規模のフードデリバリー事業を展開する美団点評などが飛躍を遂げている。そして、その下にも200社以上のユニコーン(※4)が続々と控えている。
※4:創業から10年未満に10億ドル(約1,100億円)以上の企業価値へ飛躍した未上場企業の呼び名。
こうした中国ベンチャーたちは、日本にとって、学ぶべきライバルであり、手を組むべきパートナーでもある。すでに手を組んでいる資生堂とアリババ、トヨタと小馬智行(Pony.ai)や奇点汽車(Singulato)、ホンダとセンスタイム、任天堂とテンセント、ソニーとビリビリのように、日本企業と中国ベンチャーはいまならまだ「Win-Win」の関係を築いていくことができる。

■ハードに強い日本、ソフトに強い中国
【日本と中国は正反対】その1:得意分野
日本企業と中国ベンチャーは、対照的な得意分野を持っている。日本企業は、お家芸として積み重ねてきたハードのモノづくりが強い。自動車、家電、住宅、設備機器、生活用品、化粧品など、安心・安全・信頼のモノづくりは、いまでも世界屈指の高水準を誇る。高性能で壊れにくく、優れた人的サービスやメンテナンス・サービスも競争優位だ。
その反面、日本はソフトのデジタル分野に関して弱く、世界的に見ても大きく出遅れている。2020年9月、マッキンゼーが発表した緊急提言レポート(※5)によると、コロナ禍におけるデジタル化の普及拡大に関して、日本は調査対象12カ国のなかで最下位となった。
対人接触を減らすためにデジタルサービスの需要が高まっているにもかかわらず、オンラインのエンターテインメント、フードデリバリー、リモートワーク、オンライン学習、遠隔医療などの各項目で、日本における利用増加率は10%未満にとどまった。これはアメリカや中国は言うまでもなく、欧州各国、韓国、インドと比べても、突出して低い結果である。
※5:マッキンゼー・デジタル・日本オフィス/『デジタル革命の本質:日本のリーダーへのメッセージ』
一方、中国は、日本と対照的に、ソフトに強くてハードに弱い。デジタル分野に関しては世界最先端を進むほどに強いが、モノづくりやサービスに関しては改善してきているものの依然として弱い。だからこそ、日本の得意分野を中国がまだ苦手にしている現状なら、中国ベンチャーにとって日本企業と手を組むメリットが存在しているのである。中国が苦手を克服してしまえば、もう「Win-Win」の関係になることはできなくなる。
■中国ベンチャーは手を組むのに最適な相手だ
中国ベンチャーたちは、コロナ禍を、デジタル・イノベーションを進展させるチャンスに変えている。屋内外の配送・消毒作業にはドローンや無人運転車が活用され、AIを用いた医療画像診断やチャットボット(自動応答システム)の利用が進み、遠隔の医療・勤務・学習が当たり前になるなど、得意のデジタル分野の強さをさらに際立たせていっている。
そして、中国政府の進める「新インフラ整備」の政策で、5GやAIなどのデジタル・インフラ産業が新たな重点領域に指定されたことによって、中国のデジタル分野はますます世界をリードしていくだろう。
日本の得意分野を、中国は苦手にしている。中国の得意分野を、日本は苦手にしている。これほど手を組むのに適したパートナーは他にいないといっても過言ではない。そして2020年は、日本が得意分野の強みを発揮できて、中国の得意分野はさらに進化していく、連携にちょうどいいタイミングでもある。日本企業はいますぐ中国ベンチャーを学び、深く理解し、利用し合える関係になるべきである。

■「人にだまされるな」と教える中国、「人に迷惑をかけるな」の日本
中国ベンチャーを学ぶときには、表面のビジネス・戦略の分析だけでなく、そのビジネス・戦略に取り組む組織と人まで深く分析してこそ、真の理解ができるようになる。戦略は、戦略を実行できる組織と人がいて初めて十分な効果を発揮するものであるからだ。
日本人は、中国ベンチャーの組織と人の特徴について、ライバルとしても、パートナーとしても、よく知っておくべきである。日本と中国は、地理的に近く、文化的に通じる部分があるが、ビジネスにおける考え方や戦略は真逆といっていいほどかけ離れている点に注意しなければならない。
【日本と中国は正反対】その2:教え
例えば、教えについて、日本と中国は正反対だ。親が子に、目上の者が下に教える根本的な価値観として、日本では「人に迷惑をかけるな」と教えられる。「他人様に迷惑をかけないように」「言われたとおりに」「ルール通りに」「ちゃんとしなさい」。自分の好きな方法よりも、他者・周り・環境にフィットできる方法が重要視されやすい。
一方、中国では「人にだまされるな」と教えられる。「本当にそうだろうか」「もっとうまい方法があるのではないか」「他人はそう言うけれど、自分はこう考える」。他者の言うことを鵜呑みにするのは危険で、自分・身内の適切な判断が重要視されやすい。
■「足るを知る」の日本、「もっと上へ」の中国
【日本と中国は正反対】その3:美徳
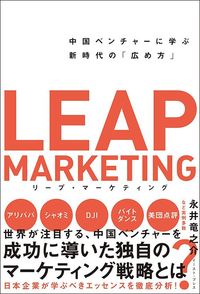
美徳についてもじつに対照的だ。日本では「足るを知る」が美徳とされる傾向にある。「自分にはこれでじゅうぶん」「私にはもったいない」「もう現状で満足だ」。現状のよさに気づき、分相応の現状に満足するのがよしとされやすい。
反対に、中国では「足るを知らず」の上昇志向こそが大切にされている。「もっと上へ」「もっと豊かに、便利に」「より良い暮らしを」。現状に甘んじず、1つの目標をクリアしたら今度はさらに上の目標に向けて走り出す。足るを知らないために、身の程知らずや、根拠のない自信にあふれた中国人も少なくない。しかし、だからこそ、成り上がっていく成功者が出てくる。どちらがベンチャーやイノベーションを生みだしやすいか、一目瞭然である。
【日本と中国は正反対】その4:マーケティング
こうした教えや美徳は、人の価値観を形成し、人が主体かつ対象となるマーケティングにも大きな影響を与えていく。日本のマーケティングは、前例主義の積み上げ型といえる。アイデア出しも意思決定も、開発もプロモーションも、前例にのっとったうえで積み上げられる。よほどの理由と確信を持てない限りは、これまでの前例から逸脱した、リスクが高く冒険的な手は打たない。
対照的に、中国のマーケティングは、前例更新主義の飛躍型だ。「前例・通例ではこうしている」という情報を踏まえたうえで、より速く新しい方法を試していく。リスクが高く、外れも大きいが、その分当たりも大きい。
■アメリカと比較するより、中国と比較したほうがいい
【日本と中国は正反対】その5:イノベーション
こうしたマーケティングの傾向は、成果であるイノベーションを特徴づけていく。前例に基づき積み上げ型のマーケティングを行う日本では、既存プロダクトの延長線上で、コツコツと改善・改良が重ねられる。時間をかけて、よりよいプロダクトを目指す「持続的イノベーション」が生みだされやすい。
対して、中国では飛躍型のマーケティングに基づき、既存の延長線上から外れた、新しく挑戦的なプロダクトがつくられる。リリース当初は、「品質は最低限だが、新しくておもしろい」プロダクトが、市場の反応を受けて、一気に性能を向上させ、既存ライバルを倒していく「破壊的イノベーション」が生みだされやすい。
これまで、ビジネスをはじめ多くの面で、日本はアメリカを比較対象としてきた。しかし、中国と比較することによってこそ日本の価値と課題はより鮮明に浮かび上がってくる(図参照)。日本と中国は、対照的で極端な特徴を持っているからこそ、比較することで両者の価値と課題が際立つし、補完関係を築いて共存共栄していく未来を目指すことができる。

----------
1986年生まれ。早稲田大学政治経済学部経済学科卒業、同大学大学院商学研究科修士課程修了の後、博士後期課程へ進学。同大学商学学術院総合研究所助手、高千穂大学商学部助教を経て2018年より現職。専門はマーケティング戦略、消費者行動、イノベーション。日本と中国を生活拠点として、両国のビジネス、ライフスタイル、教育等に精通し、日中の比較分析を専門的に進めている。主な著書に、『リープ・マーケティング―中国ベンチャーに学ぶ新時代の「広め方」』(イースト・プレス)がある。
----------
(高千穂大学商学部准教授 永井 竜之介)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
台湾、第2のTSMC目指すベンチャーが群雄割拠 激変した資本・技術・市場の今を投資家が語る
東洋経済オンライン / 2024年9月25日 9時0分
-
ザ・グレート・カブキ誕生前夜 1973年3月8日「日プロ最後のUN王者」高千穂明久
東スポWEB / 2024年9月22日 10時4分
-
「有名すぎない人」のほうが効果的…インスタで3COINS商品をコツコツ広めている"インフルエンサー"の正体
プレジデントオンライン / 2024年9月11日 16時15分
-
マイティキューブ、新型RFIDリーダライタ RW-X01を発売
PR TIMES / 2024年9月10日 15時45分
-
新たな棚田の体験コンテンツを提供!高千穂の棚田で観賞する夜神楽講演を初開催
IGNITE / 2024年9月6日 19時45分
ランキング
-
1悲惨すぎて笑えます…〈勤続46年・月収30万円〉のサラリーマン、65歳で手にした「年金額」に唖然「たったこれだけ」
THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年9月26日 5時15分
-
2吉野家がカレーをリニューアル 牛丼チェーンの“カレー商戦”激化
TBS NEWS DIG Powered by JNN / 2024年9月26日 12時2分
-
3各社が進める「小型店舗」 コンビニと飲食チェーンで明暗が分かれそうなワケ
ITmedia ビジネスオンライン / 2024年9月26日 6時15分
-
420代社員の文章にストレスを感じる人が84.5%…「頭が悪いな」と思われる報告書に共通するパターン
プレジデントオンライン / 2024年9月26日 8時15分
-
5東京株、一時1000円超高=円安好感、買い優勢
時事通信 / 2024年9月26日 13時5分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください










